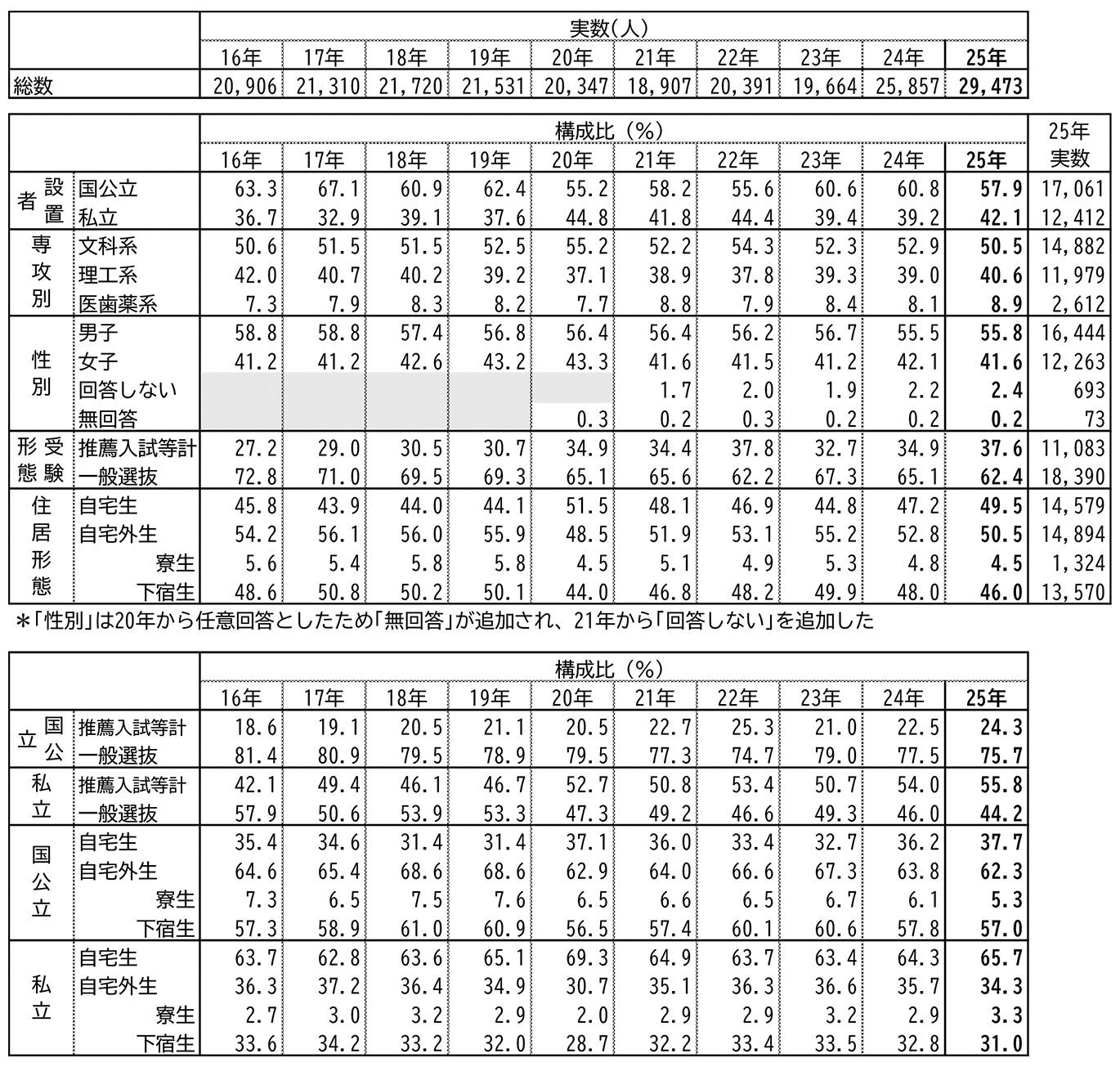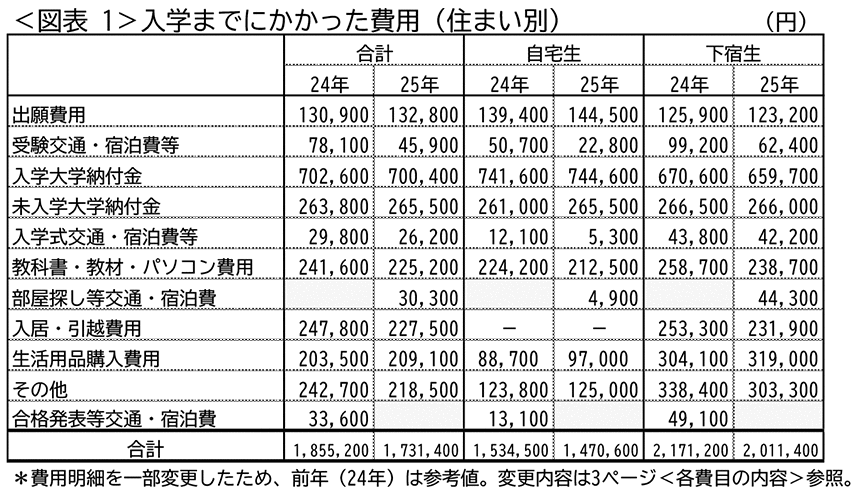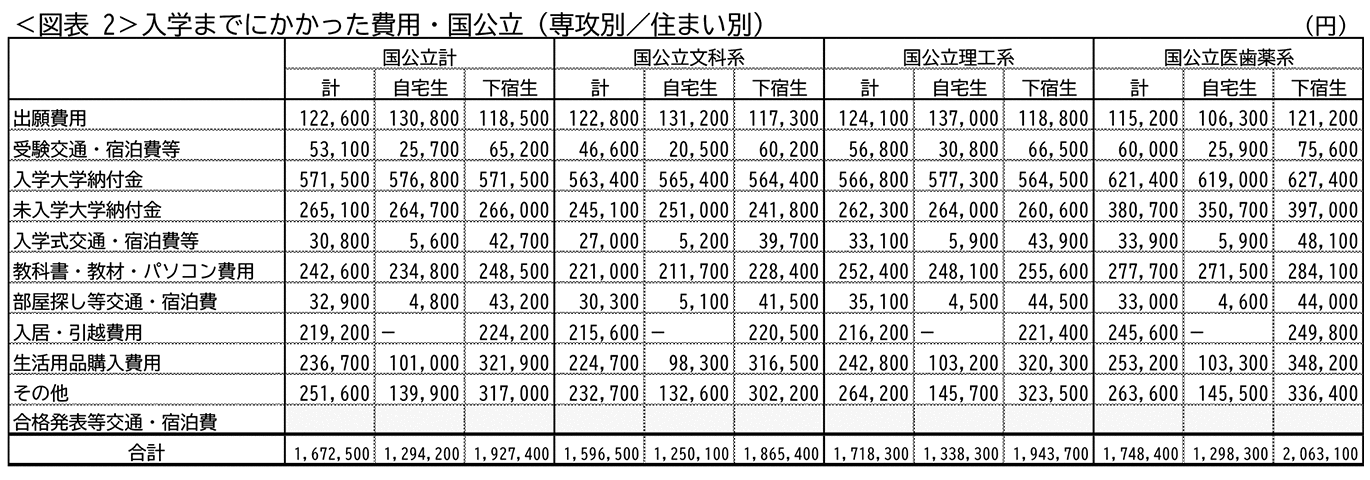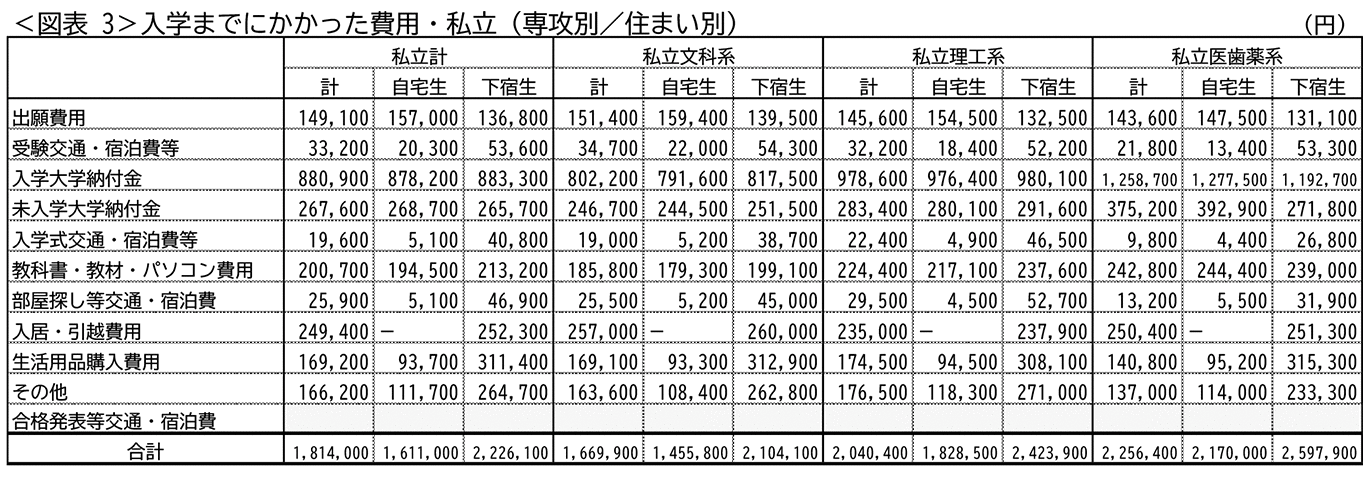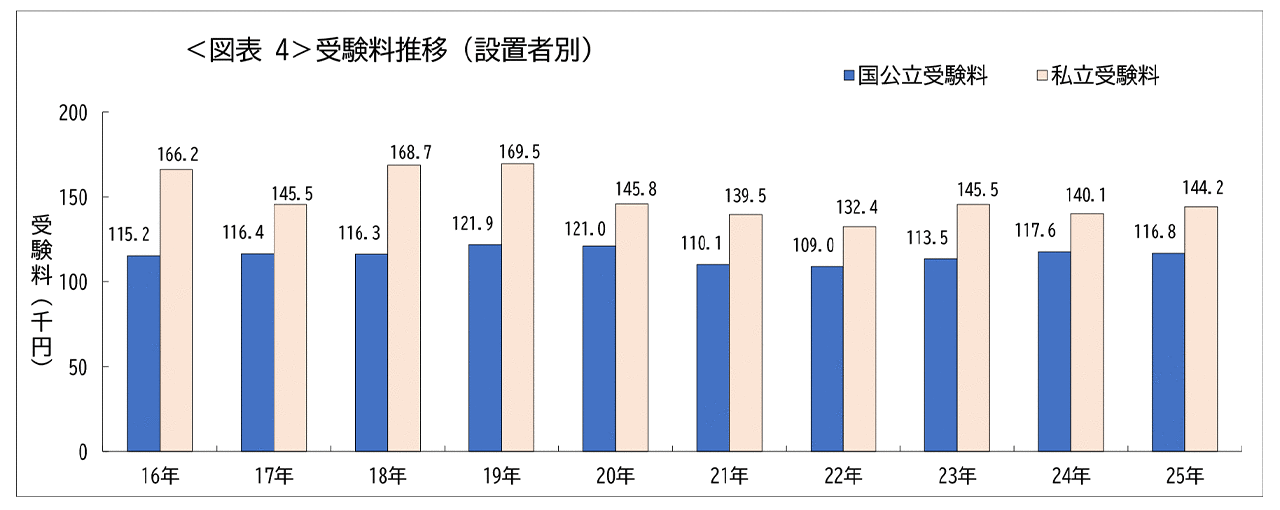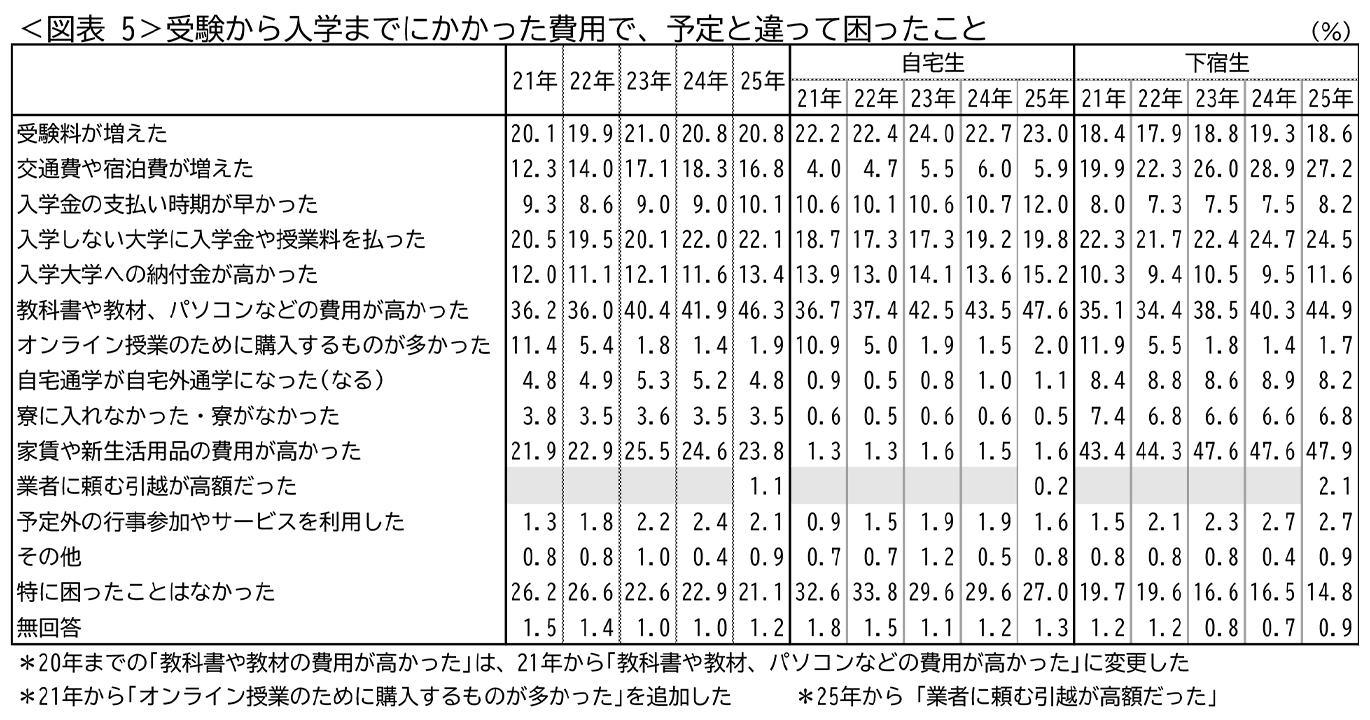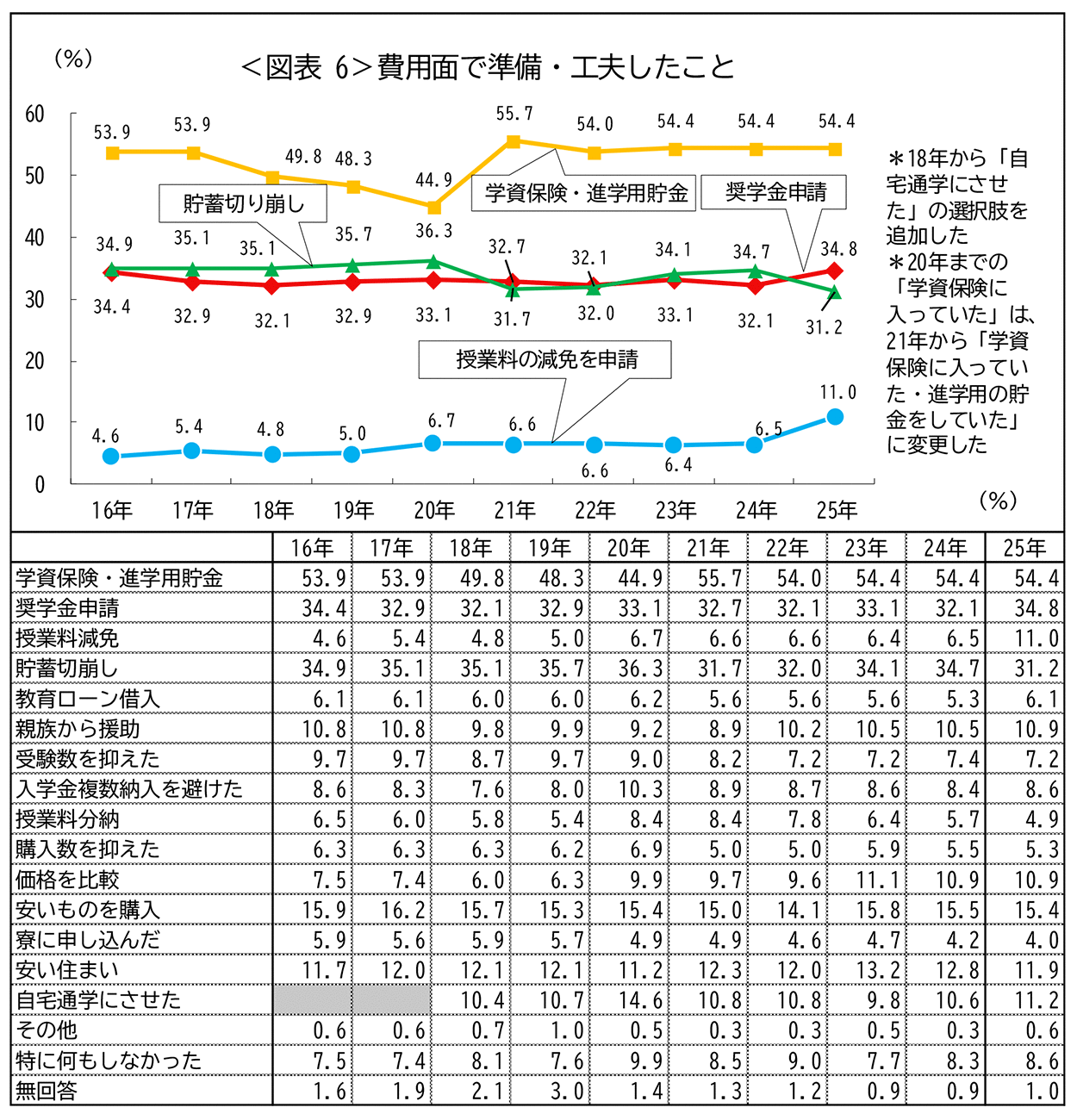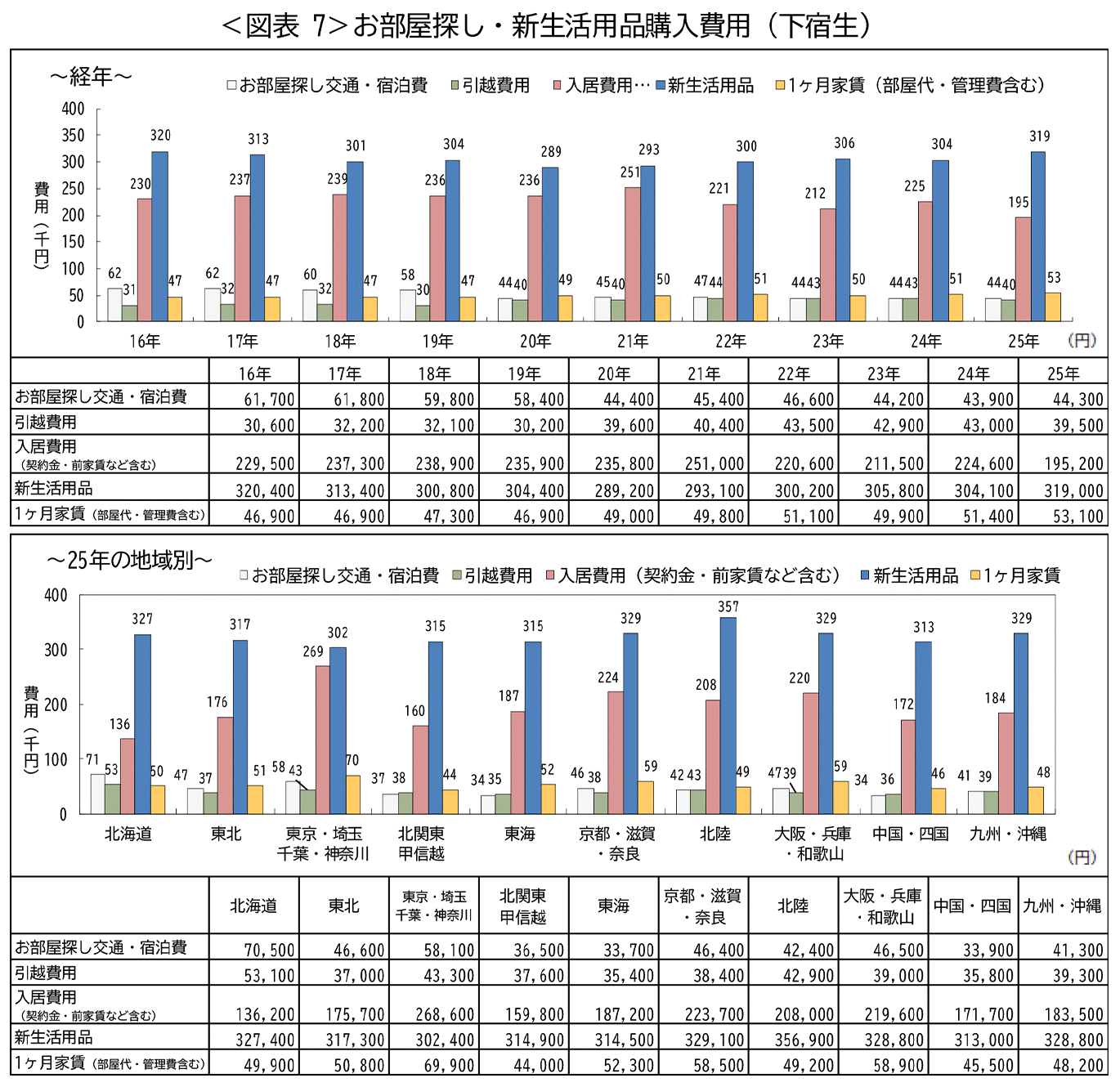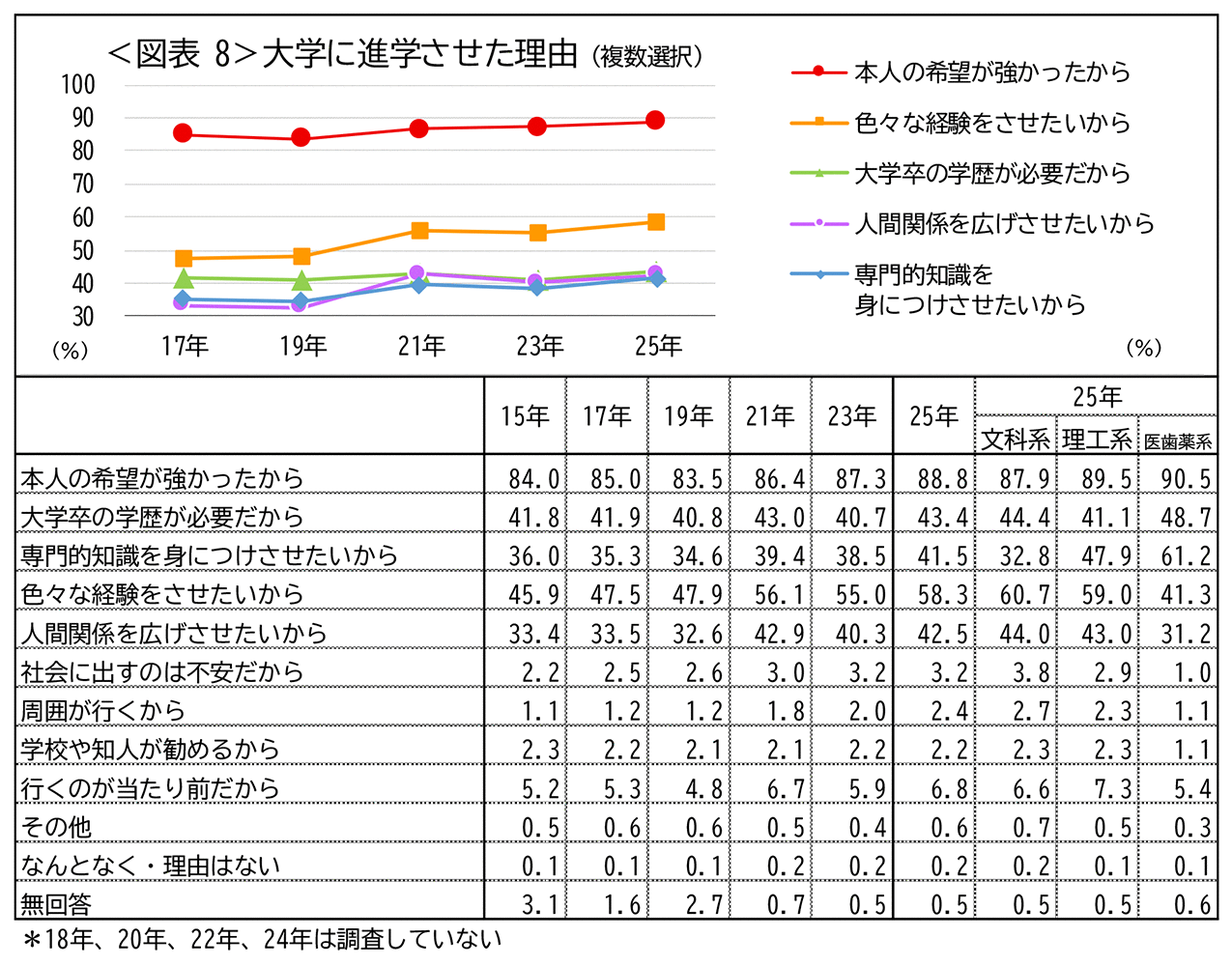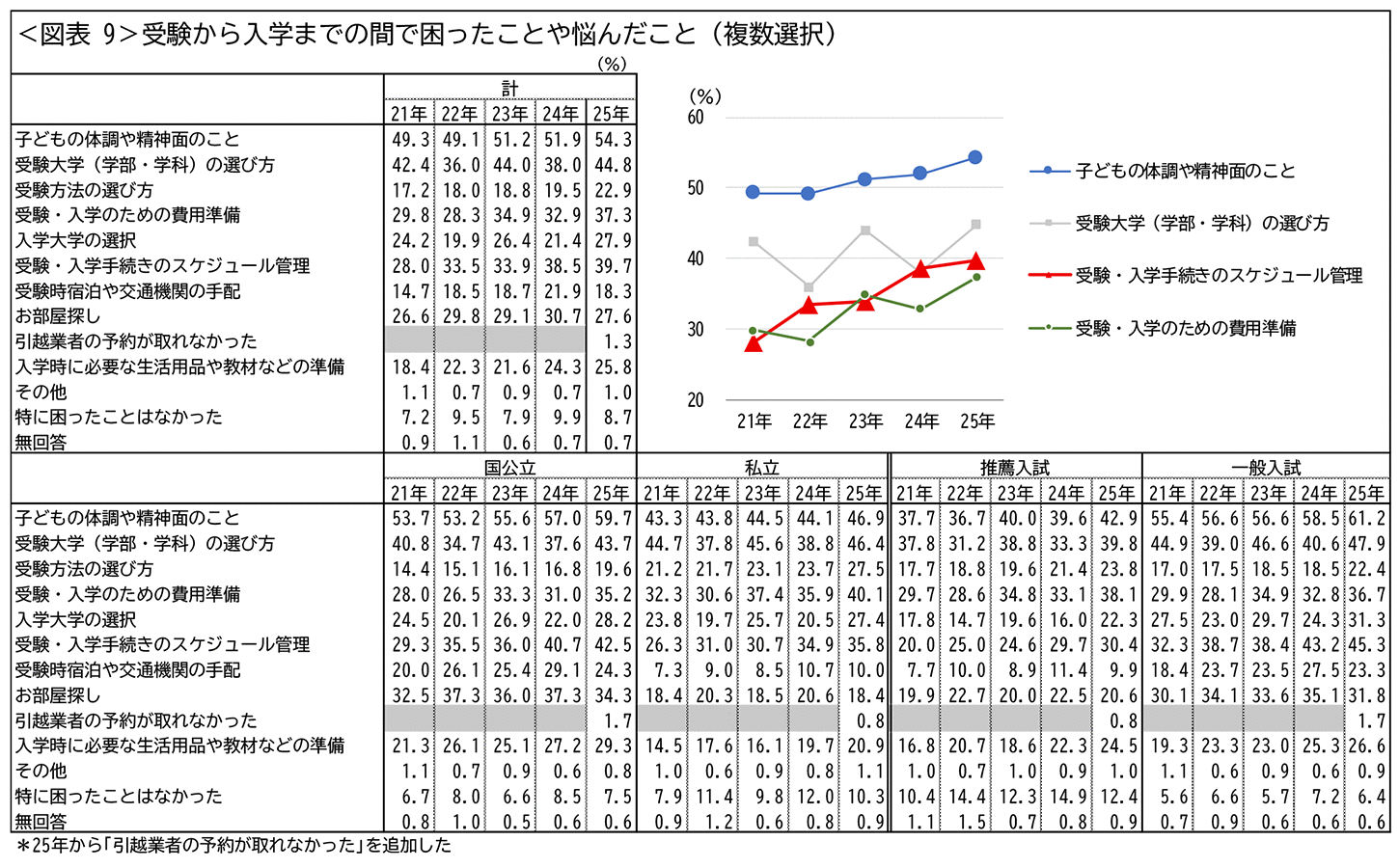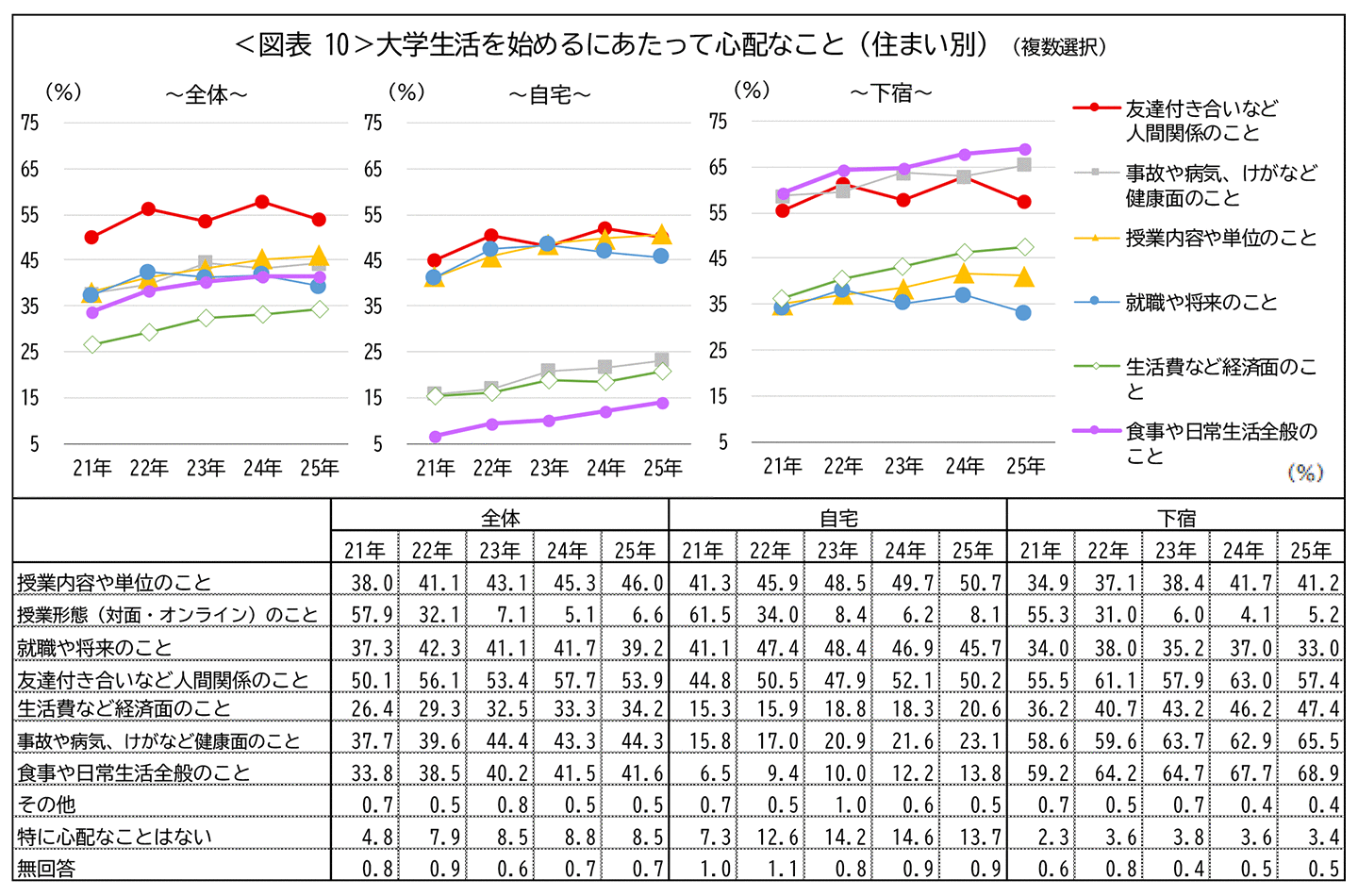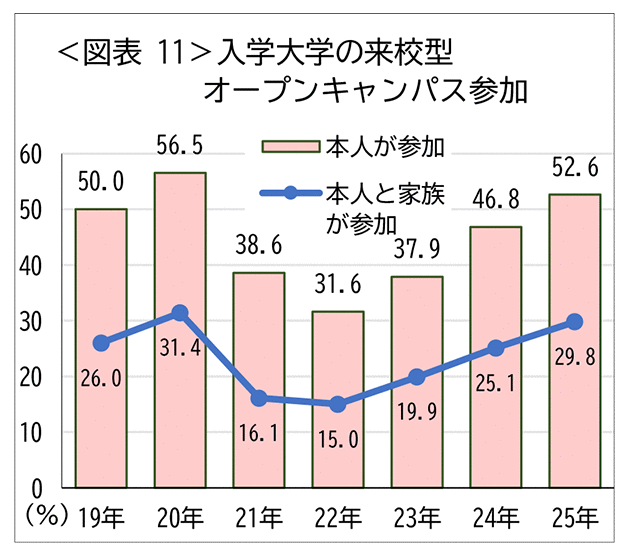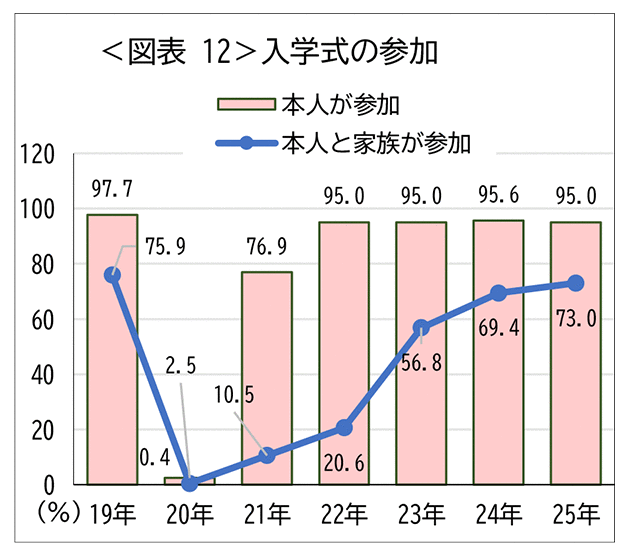- HOME
- 学生・大学院生・保護者調査の報告
- 2025年度保護者に聞く新入生調査概要報告
新入生の保護者29,473名から回答
「2025年度保護者に聞く新入生調査」概要報告
※データの無断転載はお断りいたします。
2025年8月1日
全国大学生活協同組合連合会(以下 全国大学生協連)では、2007年から毎年4月~5月に新入生の保護者を対象とした「保護者に聞く新入生調査」を実施しており、2025年は156大学生協の29,473名の方から回答をいただきました。
「保護者に聞く新入生調査」では、受験から入学までにかかった費用と保護者の意識(受験から入学までに困ったことやお子様が大学生活を送る上での不安等)を調査しています。あわせて大学生協の事業に対する評価を伺っています。
<2025年度の特徴>
- 入学までにかかった費用は「入学大学納付金」が最も多いが、それを除くと「未入学大学納付金」「入居・引越費用」「教科書・教材・パソコン費用」の順となっている。<費用明細を一部変更したため、前年数値は参考値>
- 受験から入学までの費用面で予定と違って困ったことは、「教科書や教材、パソコンの費用が高かった」、「家賃や新生活用品の費用が高かった」、次いで「入学しない大学に入学金や授業料を支払った」となっている。
- 受験から入学までに困ったことや悩んだことは、「子供の体調や精神面のこと」が一番多く、続いて「受験大学(学部・学科)の選び方」、「受験・入学手続きのスケジュール管理」となっている。
- 大学生活を始めるにあたって一番心配なことは、「友達付き合いなど人間関係のこと」、続いて「授業内容や単位のこと」、「事故や病気、けがなど健康面のこと」となっている。
<調査の概要>
| 【調査の目的】 | 大学受験までにかかる費用、下宿生のお部屋探しなどにかかる費用ほか、入学準備について調査し、大学生協の取り組みやサービス改善に活用する。 |
|---|---|
| 【調査対象】 | 2025年4月に入学した新入生(学部生)の保護者 |
| 【調査期間】 | 2025年4月~5月 |
| 【調査方法】 | インターネット調査(各大学生協の名簿からランダムサンプリングして郵送やメールで依頼、Web画面から回答) |
| 【回収数】 | 29,473(回収率 31.1%) 161大学(国立64・公立35・私立62) |
サンプル特性
▲ クリックで拡大 ▲
<平均額について>
- 「各費目」および「合計」の平均額は、それぞれ「0」と無回答を除いた「有額平均」で表示しています。
- 費目に「0」が含まれていても「合計」の平均額に反映されるため、「各費目の平均額合計」と「合計」は一致しない場合があります。
<各費目の内容>
| 出願費用 | 受験料/願書を取り寄せた費用 |
|---|---|
| 受験交通・宿泊費等 | 入学した大学の受験時交通費/宿泊費/滞在費(同伴者にかかった費用を含む) |
| 入学大学納付金 | 入学した大学への入学金・授業料・施設拡充費・その他/寄付金・学校債 |
| 未入学大学納付金 | 入学しなかった大学への入学金・授業料・施設拡充費/寄付金・学校債・その他(総額のみ、後日返金分を除く) |
| 入学式交通・宿泊費等 | 交通費/宿泊費/滞在費(同伴者にかかった費用を含む) |
| 教科書・教材・パソコン費用 | パソコン/教科書/教材 ※24年までは電子辞書やその他講座費用など含んでいた |
| 部屋探し等交通・宿泊費 | お部屋探し・説明会などのために入学前に大学キャンパスに訪れた時の、交通費/宿泊費/滞在費(同伴者にかかった費用を含む)※25年から新設した項目 |
| 入居・引越費用 | 礼金・入館金・敷金・前家賃・斡旋手数料・仲介手数料など/引越費用(自家用車やレンタカーを利用した場合は、同伴者の費用やレンタカー代やガソリン代なども含む)※24年まではお部屋探し交通費等を含み、引越費用は含まなかった |
| 生活用品購入費用 | 寝具・家具・家電・自炊用品・インターネット契約・配線工事・電話機・携帯電話・日用雑貨・自転車・バイク・入学式衣類や身のまわりの小物・防災用品 |
| その他 | 4月分の生活費/予備の貯金/大学生協への支払い・生協出資金・共済・生協のミールシステムなど ※24年までは引越費用、お礼その他を含んでいた |
1.受験から入学までにかかった費用(図表1~7)
(1)受験から入学までにかかった費用
国公立・自宅・文科系1,250,100円から私立・下宿・医歯薬系2,597,900円まで
-
自宅生の受験から入学までにかかった費用
○国公立1,294,200円
受験料など出願にかかった費用が約13万円、教科書・教材・パソコン費用が約23万円、入学しなかった大学への納付金が約26万円
・国公立文科系1,250,100円・国公立理工系1,338,300円・国公立医歯薬系1,298,300円○私立1,611,000円
受験料など出願にかかった費用が約16万円、教科書・教材・パソコン費用が約19万円、入学しなかった大学への納付金が約27万円
・私立文科系1,455,800円・私立理工系1,828,500円・私立医歯薬系2,170,000円 -
下宿生の受験から入学までにかかった費用
○国公立1,927,400円
受験料など出願にかかった費用が約12万円、教科書・教材・パソコン費用が約25万円、入学しなかった大学への納付金が約27万円
・国公立文科系1,865,400円・国公立理工系1,943,700円・国公立医歯薬系2,063,100円○私立2,226,100円
受験料など出願にかかった費用が約14万円、教科書・教材・パソコン費用が約21万円、入学しなかった大学への納付金が約27万円
・私立文科系2,104,100円・私立理工系2,423,900円・私立医歯薬系2,597,900円
▲ クリックで拡大 ▲
(2)受験から入学までにかかった費用の特徴
①受験から入学までの費用は入学大学の設置者、専攻、自宅か下宿かにより大きく違い、国公立・自宅・文科系が1,250,100円と最も低く、私立・下宿・医歯薬系の2,597,900円が最も高い。
②支出金額がもっとも大きい項目は「入学した大学への納付金」で700,400円。次に「入学しなかった大学への納付金」で265,500円、「入居・引越費用」227,500円、「教科書・教材・パソコン費用」225,200円が続いている。なお、今回、費用明細を一部変更したため、前年数値は参考値としている。
③「出願にかかった費用」の多くを占める「受験料」は、昨年から増加して127,300円となった。私立の受験料は国公立よりも27,400円高い。
④受験から入学までの費用面で予定と違って困ったことは、「教科書や教材、パソコンの費用が高かった」46.3%、「家賃や新生活用品の費用が高かった」23.8%、続いて「入学しない大学に入学金や授業料を支払った」22.1%となっている。なお、入学しなかった大学への納付金は国公立文科系で245,100円、同理工系で262,300円、同医歯薬系で380,700円、私立文科系で246,700円、同理工系で283,400円、同医歯薬系で375,200円だった。
⑤受験から入学までの費用面で準備・工夫したことは「学資保険に入っていた・進学用の貯金をしていた」54.4%と半数以上が長期間にわたる準備をしている。続いて「奨学金を申請した(する)」34.8%、「貯蓄を切り崩した」31.2%となっている。なお、「奨学金を申請した(する)」34.8%は対前年2.7ポイント増加しており、「授業料の減免を申請した」11.0%は対前年4.5ポイント増加している。
⑥下宿生の「お部屋探し等交通・宿泊費」は44,300円、「入居費用」は195,200円、「引越費用」39,500円だった。「生活用品購入費用」319,000円は前年より増加、過去10年間では2016年に次いで2番目に高額となっている。
⑦地域別にみると、東京・埼玉・千葉・神奈川の入居費用が268,600円、1ヶ月家賃平均が69,900円となっており、他地域より顕著に高い。
▲ クリックで拡大 ▲
2.保護者の意識
(1)受験から入学までの保護者の意識(図表8~10)
①「大学に進学させた理由」を聞いたところ、1位「本人の希望が強かったから」88.8%、2位「色々な経験をさせたいから」58.3%、「就職や資格取得のために大学卒の学歴が必要だから」43.4%だった。
この上位3つの理由の順位は、2015年から変動していない。
②受験から入学までに困ったことや悩んだことは、「子供の体調や精神面のこと」が54.3%、と一番多く、続いて「受験大学(学部・学科)の選び方」44.8%、「受験・入学手続きのスケジュール管理」39.7%となっている。特に「受験・入学手続きのスケジュール管理」は21年から継続的に増加しており、自由記述の内容からも入試方法が複雑化、多様化していることや、合格決定時期の遅れの影響が伺える。
③大学生活を始めるにあたって心配なことは、「友達付き合いなど人間関係のこと」53.9%、「授業内容や単位のこと」46.0%、「事故や病気、けがなど健康面のこと」44.3%となっている。なお、自宅生では「授業内容や単位のこと」「就職や将来のこと」が上位なのに対して、下宿生では「食事や日常生活全般のこと」「事故や病気・けがなど健康面のこと」を心配している。
▲ クリックで拡大 ▲
(2)入学までの行動(図表 11~12)
①来校型オープンキャンパスの「本人の参加」は52.6%で前年より5.8ポイント増加した。 また「本人と家族が参加」は全体の29.8%でコロナ禍前の水準に戻った。自由記述欄からは、受験生本人のモチベーションアップや、入学前と入学後のギャップを埋めるためにオープンキャンパスに複数参加することの意義が語られている。また、参加した新入生を100としたときの同行率は56.7%(前年+3.1ポイント)であり、19年の同行率52.0%、20年の同行率55.6%と比べても大きな違いはない。
②入学式の本人参加は95.0%、本人と家族の同行は全体の73.0%となり、コロナ禍前と同水準になった。参加した新入生のおよそ8割は家族と参加している(参加した新入生を100とした同行率76.8%・前年72.6%・19年77.7%)。
▲ クリックで拡大 ▲
これから受験されるご家庭へのアドバイス
~保護者の工夫・経験からのアドバイス自由記入欄より~
<費用について>
- 学費は準備していましたが、一人暮らしのための準備は想定以上にお金が必要でした。
また、共通テスト後に志望大学を変更して遠方の大学を選んだので、受験のための交通費・宿泊費用も想定以上でした。準備はされているかと思いますが、それ以上に余裕をもって資金を準備しておくことをお勧めします。インターネットで見ていた情報ではとても足りない、と思いました。(国立・医歯薬系・女子・自宅外・一般選抜) - 学資保険はかけていて良かった。奨学金について、給付型などもう少ししっかり調べていた方が良かったなと思う。遠方の受験であれば合格までにも交通費やその他もろもろお金がかかるのは、意外と算段に加えてないのでそのあたりも考えていた方がいい。
本人の頑張りや、合格してほしい…という気持ちの方が勝って、どのくらいお金を使ったか麻痺しがちなのできちんと記録しておくといい。(国立・理工系・女子・自宅外・推薦等) - 思った以上に細々とかかりますが、我が家は多子世帯で今年度から無償化の対象となったため入学金と授業料がかからないのが助かりました。しかし、入学金は無償化とはいえ、一度納入しなければいけないので資金準備は早めに調べておくのが大事だと思いました。(公立・文科系・女子・自宅・推薦等)
- 学費と仕送りを中心に考え、学資保険でかなりまかなえると思っていましたが、パソコン関連とひとり暮らしの準備に思ったよりお金がかかり、受験〜入学までに仕送り以外のお金に280万程かかりました(私立は共テ利用で交通・宿泊費がかからなかったにもかかわらず)。これから自動車学校や後期のお金もかかります。正直、無償化の恩恵を受けられないけれど裕福でもない我が家には、自分の老後の資金もないのに出すのが大変な金額でした。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
- 大学進学にかかる費用について、想定以上の金額がかかり驚いている。充分に情報を収集し、もう少し早めに準備を開始していれば良かったと感じている。在籍している大学の入学金や授業料は準備していたものの、入学式で着用するスーツ等一式や、大学で使用するパソコンの購入代、今後の留学費用などの大きな出費は想定外であった。また、複数の大学の受験料、入学しなかった大学への入学金、学習塾代などがかなりの負担となっており、我が家は自宅生だが、想定費用プラス300万円は必要だったと考えている。(私立・文科系・女子・自宅・一般選抜)
- 多子世帯対象の国の補助金の申し込みがわかりにくかったです。高校在学中に、補助金申し込みに必要になる書類等(成績証明書)がわかれば、申請しておけたのに、引っ越し後、入学後にわかったので、郵送で申請しなければならず、とても面倒な手順になりました。
また、高校在学中に申請しておいた「予約採用」も多子世帯補助金対象者には必要なかったので、それもあらかじめわかるようなシステムにしてもらいたいと思いました。(私立・文科系・男子・自宅外・一般選抜) - 地方からの首都圏への進学は本当に予想以上にお金がかかったというのが実感です。準備していた以上に出費があり急遽奨学金の申請も行いました。奨学金の申請も本人だけでは難しい部分も多いので高校在学中の申請など、親と一緒にいる間にできたほうがいいなと思いました。実際、進学後も洋服代や新しいかばんを準備するなど細かくお金がかかりました。(私立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
- 大学受験は高校受験・中学受験と比べて、比べものにならない程お金がかかる。塾代だけでも中古の自動車が数台買える程かかるのに加え、共テ利用を含む併願校の受験料、交通費など多額の出費が一度にやって来た後、更に滑り止め私立の入学金、授業料を直ぐに納め、国立の授業料の支払い、それが済めば入学後に使うものの準備、と経済的にも精神的にも追い詰められる。
支払いのスケジュールがタイトなので、ただ漠然とお金が必要と考えていると、手遅れになる。スケジュール管理は試験日だけでなく支払日と金額もあわせて行った方が良い。(国立・文科系・女子・自宅・一般選抜) - 予想以上に出費が増えますので、予備の資金の準備が必要だと思います。
あと、奨学金や補助金など、政府は個人にお知らせしてくれません。自分でリサーチして、アクセスし、申請しないといけないので、抜けのないようにお気をつけください。(国立・文科系・女子・自宅・一般選抜) - 学資保険を積み立ててきたが高3の秋までに満期を迎えるものと卒業までに満期を迎えるものとに分散させて積み立てていたのが結果的によかったと感じた。
一般入試だけでなく選抜型入試など入試方法の幅が拡がっている昨今では、大学資金は高3の秋までに目処をつけるべきだと、声を大にして言いたい、と感じた。(私立・文科系・男子・自宅・推薦等) - 奨学金は高校の時に予約しておいた方がいいです。結構早い時期に審査申込みがあるので、ゆっくりできます。というのも、子供が借りる時には18歳で成人のため、本人からの申請。そしてネットから。やり方の冊子はあるけれどかなりややこしいので、ゆとりある時にして良かったと思いました。(公立・文科系・男子・自宅・推薦等)
- 多子世帯に該当したので、入学金や授業料の支払いをしていません。大学の費用は多額になりますが、授業料免除の制度などは条件があえば利用できるので、制度を把握しておくのは大事だと思います。(国立・医歯薬系・男子・自宅・一般選抜)
<大学選びや情報収集について>
- 基本、子供に任せるコトが肝要だと思います。高等教育機関は「行かされる」のではなく、親に学費を用立ててもらい「行く」場所ですから、「大学選び、健康管理、ひとり暮らし準備」などは自らの責任において成した方が、受験勉強と並行しての作業は大変ですが、結果としては入学後の生活にも自覚が芽生えると思います。(国立・理工系・性別回答無・自宅外・一般選抜)
- 高校1年の時から来校型オープンキャンパスに参加したことで本人のモチベーションと行きたい気持ちを固めることができました。「入学してみたけどこんなはずではなかった」というズレを少しでも減らしておくことで、休学や退学のリスクを減らすことができます。旅費は多くかかりましたが何度も参加してよかったです。入学後は初めての一人暮らしと慣れない大学授業体制で不安なことも多くあります。身近に気軽に相談できるメンター制度があればいいなと思いました。(国立・理工系・女子・自宅外・一般選抜)
- 資料請求やオープンキャンパス、オンライン見学など、志望校が決まってなくても、たくさん参加するなかで決まることがあると思います。また、受験までの準備、入学準備は、子どもが主体となる良い機会です。
親が管理しすぎないようにすると良いと思います。(私立・文科系・女子・自宅・推薦等) - これだけ受験方法や日程などが複雑になると親の関与は不可欠だと思う。教育方針もあるだろうが個人的にはしっかり親も関わって受験戦略を立てて情報を共有しつつ進めることがよいと思う。またどんなパターンになっても慌てないようにあらかじめ想定し対応を決めておくことも重要。子供が安心して受験勉強に集中できるようにすることが大切だと思う。(国立・文科系・男子・自宅・一般選抜)
- 受験は予定通りに進むとは限らないので、さまざまなパターンを考慮しておくべきで、滑り止めで念のための受験だとしても、そこに通う可能性もあるので、通学可能なのか含めて慎重に受験校選びをしたほうが良いです。学部によってキャンパスが異なることが多いので、具体的に通うキャンパスまで調べる必要があります。受験校、学部は基本的に子どもに任せましたが、受験スケジュールや手続き、支払期日のスケジュールについては子どもの管理に任せるだけでは不安なので親も関わりました。(私立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
- オープンキャンパスはできればいろんな大学に出向いた方がいいです。学部情報はもちろん、在学生のリアルの声を聞けるところも参考になります。また、毎日のことなので、通学時間や交通事情なども重要です。
今は、親子で行くのも当たり前のようで、学費以外のお金事情も聞けたりして保護者にも役立つ情報を得ることができました。(私立・理工系・男子・自宅・推薦等) - 今はいろいろな形の受験方法があるので、早めに大学選びをすることでその大学を受験する方法の選択肢がぐっと増えます。希望大学の総合型選抜を受けてもし結果がダメであっても、日程的に大丈夫ならまた同じ大学の公募推薦を受けることもできます。推薦入試の対策をしながら一般受験の勉強もしなければならないので、夏休みあたりは本当に大変だと思いますが、推薦で決まれば12月ごろには終わるのでがんばってください。(私立・理工系・女子・自宅・推薦等)
- 大学選びから始まり、住む場所、乗る電車に至るまで、どんな些細な事においても『本人の意思』であることが一番大事だと感じます。自分で決めたことには責任が伴うからです。高校生までの『子育て』の感覚を一区切りして、大学生はいよいよ就職前の独り立ちの準備期間ととらえて、各種手続き・調査・決定まで、本人主体で行動するよう、親は手を引く意識が必要なのかなと感じます。とはいえまだまだ成長過程なので見守り、必要な時はそっと助言できるようにしていたいです。(国立・文科系・女子・自宅・一般選抜)
- 今は、ボタンひとつで受験申込ができる時代です。ネットでの買い物に慣れている私たちにとって、「リコメンド」の様に次々表示される受験方法、申込前に何度も届くリマインドに揺らいでいると、受験費用だけで、大幅な予算オーバーになります。不安を解消してあげたくもなり、ここでケチるのはどうだろうと思いもしますが、本命はどこなのか、合格した場合、本当に通う意思があるのか、親子で地に足を付けて話し合っておく必要があるなと思います。(公立・理工系・女子・自宅・一般選抜)
- 受験から入学までの費用は予想以上に必要です。自宅通学なのか、一人暮らしなのか。国立の場合、私立の場合、またいくつ受験するのか等々によってかなり変わってきます。受験生本人とよく家庭の事情含めてしっかり話すことも重要ですが、本人には勉強に集中させてあげたいもの。ある程度決まったら親は少しでも早く情報を集めてだいたいどれくらいの時期にどれくらい必要か計算をして、準備を始めたほうが良いです。また書類や入金の締め切り等も大学によって違います。本人が把握しているとは思いますが、親の方でも受験スケジュール用のカレンダーや資料用ファイルを用意して不備がないようにしました。受験する大学のホームページも頻繁にチェックするようにしていました。(国立・文科系・女子・自宅・推薦等)
<受験から入学まで>
- 受験当日、試験時間の繰り下げによって、予定していた飛行機に間に合わず、急遽延泊することになり、思わぬ出費がかかりました。はじめから余裕をもったスケジュールにしておけば安いプラン、飛行機をとれたのになと後悔しました。受験前後は余裕をもったスケジュールをオススメします。(国立・理工系・女子・自宅外・一般選抜)
- 国公立大は合格から入学までの期間が短いので、受験前から合格後に必要な事や物のシミュレーションをしておくと安心。今回は寮を希望だったが入れずバタバタとしてしまったので、一人暮らしの準備ももっと考えておけば良かった…と言うのが反省点。バタバタでも何とかなりましたが、大変でした。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
- やはり、子供が通う大学なので子供本人が「ここに行きたい。」と頑張るなら、親は見守るしか無いですよね。しかし、何でも子供任せにしてしまうと提出する物、期限、振込みなどを忘れていたりするので、大学の候補が絞れて来たら親もキチンと調べて申込み、振込、提出をチェックしましょう。でも、親が率先して手続きしてしまうと今後大学の手続きなども子供が親に頼ってしまうので極力子供に任せて、親はサポートするだけで。自立の第一歩ですね。(国立・理工系・女子・自宅外・一般選抜)
- 当たり前のこと(十分な睡眠時間の確保・栄養管理)しかしませんでしたが、これらが一番大切だったと感じます。願書取り寄せと提出、受験料支払い、入寮申請などは、期限が決まっているため、複数の大学を受験する場合は、スケジュール管理が結構大変です。本人と保護者がしっかり管理したほうがよいと思います。入学する大学が決まってから、大学のオリエンテーションが始まるまで12日程度しかありませんでした。
その間に、卒業旅行、大学入学準備、一人暮らしの生活環境整備などをしました。大学入学準備では、大学のシステムに入るための設定や研修受講など、思いのほか時間がかかりました。入学前のシミュレーションとスケジュール管理が大切です。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜) - 大学学部選び・受験から入学時までは子供まかせにして正解でした。自分がしたいことをするためには、勉強以外の様々な細かい作業、たとえば細かいことですが書留郵送方法や窓口での振込もしたことがなかったため、オンラインで済ませられないこともあるということも学べたと思います。親は、「何かもれがあったら困るから情報共有はしっかりしてもらう」というスタイルを徹底し、子供主体で行動させました。学費は親が準備しましたが、入学金や授業料の振込は子供にもダブルチェックをさせて、これだけの費用がかかるということも理解してもらいました。「こんなにかかるのか・・・」と子供がもらしていたため、大学生活を無駄にダラダラ過ごさない気持ちにはなったかなと期待しています。ちなみに子供は推薦合格だったため、もし一般受験だったら何校も受験日との兼ね合いもあるため、すべてを子供任せにすることはしなかったとは思います。食事と健康管理だけは心配ないように親主体でした。(私立・文科系・女子・自宅・推薦等)
- 受験料、入学金、授業料以外にもPCに私服や何かと次々に、国公立自宅通学でもお金が出ていきました…。とにかく親も大変ですが、資料請求や併願先などの情報集収集、出願事務手続、宿泊手配、下宿探し…手伝う中、ポツリポツリ出てくる子の気持ちをふんふんと聞きながらご飯作って、祈って、一緒に頑張ってください!!(公立・医歯薬系・男子・自宅・推薦等)
- 受験から入学に至るまで、手続きはほぼインターネットなので、本人だけでなく保護者もある程度の知識が必要だと思いました。説明を読んだだけでは分からない事も出て来るので、問い合わせしたり、いろいろなところで情報を自ら集める事が大事かなと思います。
また、学費だけでなくパソコンや教材費、寄付金など、思わぬところでお金がかかるので、費用面では余裕を持った準備が必要です。(国立・理工系・男子・自宅・推薦等) - 年明け〜入学前になり、期限付きのスケジュール管理、出費、交通予約等々、急に慌ただしくなりました。
その上、18歳から成人扱いとなったことで、親の代理手続きにも委任状が必要だったり、本人限定郵便物の受取等、不便もあり、期日よりも少し早めの手続きを心がけることをお勧めします。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
<一人暮らしの準備やお部屋探し>
- 受験日に合わせてマンションを決めるため現地に同行しましたが、相談しながら住まい探しは出来なかったので秋から事前にエントリーしておけばよかったと思いました。
ひとり暮らし準備は、土地勘がなかったり車がなかったことでホームセンターなどへ出かけたり、大きな荷物を運べなかったり苦労がありました。ある程度は地元で購入して送ったり、通販を利用する方が時間の短縮になるかもしれません。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜) - 地方の大学で一人暮らしをする場合、ゆうちょ銀行の口座はあらかじめ開いておいたほうがいい。公共料金の支払いは地元の銀行かゆうちょ銀行の口座振替しか選べなかったので、新生活準備をしながら、平日しかできない口座開設をするのは大変だった。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
- 引越しは入学式の半月前にしました。初めは1週間前位が良いと思っていたのですが、早めに行っておいて正解でした。アパートでの一人暮らしだったので、引越し荷解き、生活用品の購入、転入手続き、定期購入、PC等の受取・セットアップ、オリエンテーションなど意外とやる事満載で、1週間前だったらバタバタだったと思います。早めに行ったことで、買い物場所や飲食店などいろいろ探索できたのも良かったようです。(公立・理工系・女子・自宅外・推薦等)
- 一人暮らしの家具や家電は、地元で注文して現地に配達してもらいましたが、これも早めに依頼しないと枠がいっぱいで希望日に配達してもらえないことがあるので注意が必要です。
大きな買い物が続くと、金銭感覚が麻痺してあまり必要でないものまで念の為…と買ってしまったりしますが、後からでも買えるので必要最低限で大丈夫だと思います!(自分への反省です・笑)(公立・理工系・男子・自宅外・推薦等) - 遠くに離れて行く子供の事はとても心配で、寂しくもあります。我が家の場合は、本人の強い希望がありましたので、私たちも応援することに決めました。
家を決めるためと、引越しとで2回移動しましたので飛行機など、やはり交通費がかかりました。少しずつ大学貯金はしておいたほうが良いかと思います。物件はやはり実際見て決めたほうが、周りの環境などもわかるのでよかったと思います。(公立・理工系・男子・自宅外・一般選抜) - 新居は学生会館だったので、家具家電など一通り揃っており、引っ越しは殆どお金をかけませんでした。
ネット通販で購入したものをそのまま新居へ送るので、基本的に送料0円でした。または、店舗受取可能なお店で購入し、新居近くの店舗で受け取りにして送料をかけませんでした。そのため、実際の引っ越しにかかった費用は家から送った衣類や日用品のみで、ダンボール二箱分の送料6,000円くらいでした。
現地での引っ越しも、市内にある安いレンタカーを早めに予約していたので、レンタカー代も抑えることが出来ました。学生会館は朝夕食事付で、大学に行っている日は学食でご飯が食べられるので、安心しています。何年そこに住むかはわかりませんが、学生会館だと同じ会館の友達もすぐにできていたようなので、大学生活のスタート時には安心かなと思いました。(公立・理工系・男子・自宅外・一般選抜) - 合格後について、自宅通学か自宅外通学で違うが、①入学手続き書類の記載・確認、②子供の住むところの決定・入居手続き(電気・ガス・水道含む)および住居近くの病院確認、③子供名義の口座開設、④生活圏内のハザードマップの入手、などについてはできるだけ早く対応し、余裕をもった準備が必要に思いました。4月の入学式前後は、子供は引っ越しやガイダンス・履修申込・授業開始、保護者は自分自身の仕事も年度末・当初の多忙な時期と重なってしまい心身ともに余裕がなくなるからです。(国立・理工系・男子・自宅外・推薦等)
- 3年前に兄弟が独り暮らしを始める際にかかった費用と比べて、1.5倍から2倍近い費用を要しました。
物価の高騰を実感させられました。置いておける場所があるのであれば、早めに購入してしまうことをお勧めします。(私立・理工系・女子・自宅外・推薦等) - アパート探し一人暮らしが前提のお話ですが、ほぼ受験予定の大学が決まり、お子様が受験勉強の追い込みをしている時、親御さんは、お子様の新生活の準備の為の準備を始めて良いと思います。この大学の場合、住むところはこのあたりを探そう、こっちの大学ならこのあたりなど。
特に、一人暮らしをされる場合、一般入試では、合格が決まってからは、かなり忙しくなります。住むところを1から探すのと、ある程度候補があるのでは、かなり負担が変わってくると思います。
願書を出すところが決まってくる時期では、更に具体的に、候補のエリア内で物件の間取りや広さ、駅からの距離、それに対しての家賃を色々と探し始めると相場感がなんとなく掴めると思います。その位まで進めておいても無駄にはならないはず。このくらいのスピード感で、保護者の方はスタートを切っておいたほうがいいと思います。(国立・文科系・女子・自宅外・一般選抜) - 地元から遠方の大学に進学する場合、気軽に現地まで足を運ぶことが出来ないので、オープンキャンパス等で大学に行く機会があれば、大学周辺にも足を運んで住む場所の見当をつけておくと、部屋を探す段階になって慌てる必要がないかと思います。もちろん、申込や手続き自体はwebでできますし、部屋探しのフェア等に参加しての合格前予約もできますが、そもそも土地勘がないままに部屋探しをするのが、骨が折れます。
また、国公立大学に進学する場合、合格発表が3月ですから、入学ガイダンスやオリエンテーションが始まる3月末までに引っ越しを終えてしまうことを考えると、住居手続きから引っ越しまで、思いのほか時間の余裕がありません。住むところさえあれば、その他はあとから何とかなります。(国立・文科系・男子・自宅外・一般選抜) - 引っ越しは業者を使わずに(そもそも空いてない)、宅配便や配送を同じ日にまとめることで極力費用を抑えるように対応しました。引っ越し日近辺に転居先の大学周辺の量販店で買い物をして細々したものを揃えようと考えていました。洗濯用品、収納用品はおろかティッシュペーパーまでも品切れで、親子連れで大盛況でした。みな同じことを考えているのだな、自分の必要なものは皆も必要なのだと痛感しました。
アレルギー、花粉症があるので3月中にかかりつけ医に多めにお薬をもらっておきました。(国立・理工系・男子・自宅外・一般選抜)
<大学入学後の生活>
- 学費そのものよりも出願料、入学金、スーツ、定期・交通費、教習所、パソコン、私服、ミールクーポンなど、それ以外のところで予想以上に費用がかかる(どこまで出すかだけれど)。
授業が思ったより詰まっていて、クラブやサークルにも参加していると、さらに教習所やバイトというのはなかなか難しい(特に慣れるまで)。(私立・理工系・男子・自宅・推薦等) - 履修登録終了まで見守る必要のある子がいると思います。大学合格で安心して、急にお子さんの手を離してしまわれるケースがあると思いますが、合格後に大学から大量に送られてきた書類への対峙の仕方をみて、"これは…"と感じたら、親も一緒に履修登録関係の書類に目を通したり、アクセシビリティ推進室の説明会に親だけでも出ておくなど、トラブル予防のための情報収集をしておくのがおすすめです。(国立・文科系・性別回答無・自宅・一般選抜)
- 食事付きの寮にして、良かったです。娘は初めての1人暮らしで、初めは思うようにいかないこともあったりで、軽いホームシックになっていましたが、そんな、精神的に病んでいても、栄養の考えられている食事が、出てくるので、とても安心です。(国立・理工系・女子・自宅外・一般選抜)
- 自宅から2時間弱で通学できる為、当初は頑張って自宅から通ってもらうつもりでしたが、勉強だけではなく部活やアルバイトなど大学生の時でしか出来ないことも思う存分やってほしいと思ったのと、本人の希望もあり、急遽一人暮らしをすることにしました。結果、させて良かったと思います。
自宅通学であれば入れなかったであろう部活に入り、今まで全くしてこなかった家事をやり、大変な思いもしながら充実した日々を送っているようです。ホームシックにもなりましたが、講義や部活で大学に行く時間が長くなるうちに、友達も増えたせいか落ち着いたように思います。(私立・文科系・男子・自宅外・一般選抜) - 親は前倒して学費の準備はもちろんですが、住まい探し、家電、家具の購入に伴う納期の調整等を行い備えました。早めに生活が整っていると、近隣の把握、自炊等の生活が実際の授業が始まる頃には慣れていて良かったと思います。生活で「できる」が増えて行くと自信に繋がっていると思います。その結果、バイトも早くから始められたように思います。(私立・文科系・女子・自宅外・推薦等)
- 入学後、友だちや部活の先輩とご飯を食べに行くことが多く、思いの外、それらの費用がかかることがわかりました。本人は、大学に入ったらバイトする予定でしたが、前期は毎日1限から4限まで授業があり、部活にも入ったので、バイトする時間がなく、しばらくは親がお小遣いを渡す必要が出てきました。
授業だけでなく、交友関係も大切にしてほしいので、必要な出費だとは考えています。(国立・理工系・男子・自宅・一般選抜) - 入学直後はさまざまなお金がかかります。とくに部活動やサークルに関しては親が無制限に子どもの希望通りに払うものでもないと思います。ですが、まだ、履修登録や部活サークルのスケジュールが固まらない段階でアルバイトをハードに始めるのも難しいです。我が家は、生まれてからこれまでいただいたお祝いやお年玉の残りをためた口座の貯金を入学を機に渡しました。それでアルバイトを始めるまでの間は乗り切れると思います。ご参考になれば幸いです。 (国立・理工系・男子・自宅・一般選抜)
- 入学後しばらくは新しい環境になれるまで大変だと思います。
親からの過干渉は嫌かもしれませんが、子供の体調や精神面は付かず離れずの距離で寄り添ってケアしてあげるのが良いと思います。(国立・医歯薬系・女子・自宅・推薦等) - 今までお風呂やトイレ、キッチンなどの掃除をさせてこなかったので、やり方をLINEで聞いてくることがあります。家を出る前にひと通りやらせてみればよかったなぁと思いました。(私立・文科系・男子・自宅外・一般選抜)
- 自宅通学でもひとり暮らしを始める親子にとっても新生活は本当に大変だと思います。新生活や大学生活への期待や楽しみと共に乗り越えなければいけない現実的な問題も多々あると思います。
ですが大学進学への強い気持ちがあれば、経済的な問題を相談したり、いろんな制度を利用しながら必ず夢を実現できます。お子さんの体調面で気になることも、大学の保健相談室や対策支援室がありますので、悩みを抱えたままにせず大学側に相談して大学生活を楽しいものにしていけると思います。ひとつひとつ不安は払拭できます。自分の大学生活をイメージして前向きに楽しい日々を送っていきましょう。(国立・文科系・男子・自宅・一般選抜)