コンビニの24時間営業って?
全国大学生協連院生委員会 2024.12.04 Vol.68
24時間営業は本当に必要なのか?
みなさん、こんにちは。院生委員の石田です。今日はコンビニの24時間営業について考えていきたいと思います。
食品から日用品まで幅広く品揃えされているコンビニエンスストア。いまや24時間営業なのは皆さんにとって当たり前なのかもしれません。しかしながら、コンビニの24時間営業問題は、現代社会における重要なテーマの一つとなってきています。24時間営業は消費者にとって大きな利便性を提供していますが、従業員や経営側にとっては多くの課題を抱える問題でもあります。
消費者にとっての利点として考えるものは、仕事帰りや急な必要品の購入時など、24時間営業のコンビニは生活を便利にしており、特に夜間や早朝に外出する人々にとっては不可欠な存在となっていることです。また、公共料金の支払いや宅配便の発送・受け取りなど、多岐にわたるサービスを提供しており、社会的なインフラとしての役割も果たしています。しかし、従業員の過重労働や経営側の負担が問題として浮上している現状もあります。24時間営業を維持するためには、夜間の時間帯を含めた勤務が必要となり、特に夜勤を担当する従業員にはやらなければいけない業務の過多により、心身への負担や健康問題を引き起こすことも少なくありません。また、経営側にとっても、24時間営業を維持するための人件費や設備投資が膨大であり、店としての利益が減少しているケースも少なくありません。これが一因となり、経営が厳しくなり、閉店に追い込まれる店舗も増えています。さらに、地域社会の視点から見ると、24時間営業が引き起こす騒音問題や治安の悪化も懸念されています。夜間の営業により、深夜帯に店舗周辺での騒音や酔っ払った人々の集まりが問題視されることがあります。このような問題を解決するためには、地域との協力が欠かせません。この問題の解決策として、より効率的な運営やスタッフの労働環境改善が挙げられます。例えば、会計などでの自動化技術の導入や、シフトの見直し、AIなどの人工知能を活用した人員配置の最適化などが挙げられます。また、コンビニ業界全体での取り組みとして、24時間営業の見直しや営業時間を縮小することを選択する店舗が増えることも、一つの方向性かもしれません。
結果として、消費者・企業・従業員の三者が共存することができる関係性を見つけていくことが重要です。社会全体がより持続可能な形で発展していくためには、深夜営業のあり方を再考し、労働環境や経営面での改革を進める必要があると言えるのではないでしょうか?
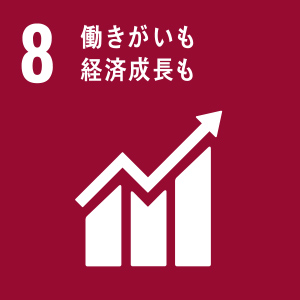

大学生協は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています
発行元
全国大学生協連合会 全国院生委員会