大学院進学の価値を考える
全国大学生協連院生委員会 2025.01.08 Vol.72
大学院進学は必ずしも人生を豊かにしない
みなさんは、「大学院」と聞いて何をイメージするでしょうか?研究や学問が好きな人が行くところ?それとも、学生を続けたいだけの人が進学するところ?私の体感は、前者:後者=2:1くらいです。
研究に興味がなくとも、就職のために高学歴を目指すという方もいるでしょう。実際、ストレートで進学する年齢の22歳人口(約120万人)に対し、入学時点で大学院修士課程は7%(7.5万人)の高学歴ということになり、初任給で差をつけている企業も多くあります。また、大学と違い、どの大学でも入試の競争率が低く、容易に進学できます。
全体で見れば7%の稀少な大学院生ですが、私の所属していた北大理学部では、毎年9割以上の学生が大学院に進学します。そのため、学部時点で就活の情報はほとんど入ってきません。さらに、研究室に配属されるのは4年次からとなるため、研究が向いていないことに気付いても、その頃にはほとんど採用が終わっています。結果として、就職しそびれてしまった学生は、惰性で大学院に進学することになるのです。しかも、修士卒での就職を目指すと、入学早々に企業のインターンシップの選考が始まり、修了のために授業の履修も必要となるため、研究に十分な時間を割きづらくなります。研究するために進学したはずが、忙しくしているうちに修士論文を書く時期になっていた、なんてこともあるかもしれません。
私は、すべての大学生が、人生設計について考える時間を持ってほしいと思っています。大学院進学が当たり前の環境にいる学生も、将来何がしたいのか、そのために大学院に進学する必要があるのか、研究をし続ける覚悟はあるのか、冷静に考えてください。惰性で進学した私の周りの学生は、いつも辛そうにしています。また、既に進学した大学院生は、国で7%の高度な人材だという自覚をもって生きてほしいと思います。
【参考文献】
1)文部科学省「令和5年度学校基本調査」
2)文部科学省「2040年を見据えた大学院教育のあるべき姿」

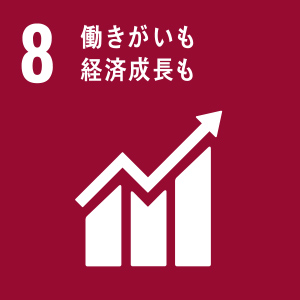
大学生協は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています
発行元
全国大学生協連合会 全国院生委員会