日本私学小学校中学校高等学校保護者連合会 役員インタビュー
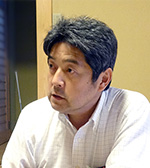
会長 門傳 英慈
昭和37年9月25日生まれ。
宮城県築館高等学校卒業後、岩手大学人文社会科学部へ入学。
同大学卒業後は、家業である有限会社川口納豆へ入社。
| 平成12年 | 宮城県納豆事業協同組合 専務理事 |
|---|---|
| 平成14年 | 全国農協青年組織協議会 会長 株式会社日本農業新聞 取締役 |
| 平成20年 | 古川学園高等学校父母教師会 会長 |
| 平成30年 | 日本私学小学校中学校高等学校保護者連合会 会長就任 |


全国大学生協連 専務理事
毎田 伸一
日本私学保連に関わるようになったきっかけ
毎田専務理事(以下毎田):自己紹介をお願いします。中村相談役(以下中村):私、日本私立小学校中学高等学校保護者連合会の相談役の中村良彦と申します。歳は62歳です。よろしくお願い致します。
門傅会長(以下門傅):同じく、会長の門傅英慈です。年齢は55歳です。
毎田:お二方とも、保護者の代表ということでこの会のお仕事をされていると伺っているのですが。
中村:私は4人子供がいまして、2人が男の子、2人が女の子なのですが、25年前に長女が文京区にあります村田女子高等学校に入学した時に、校長先生から役員をやってくれないかということで役員をやりました。
それで2年間後援会の会長をやったわけですね。そのあとに次女が同じ学校に入学しまして、その時も役員をやって後援会の会長を2年やったわけですが、その時に東京都私立中学高等学校父母の会中央連合会というのがございまして、東京の会で、その中から副会長をやってくれないかということで副会長に入りました。
それから5年後に今度は東京の会長をやりまして、東京の会長をやれば今度必然的に全国の副会長になるわけです。全国の副会長をやりまして4年前に全国の会長をやりました。ですから、どっちかというと学校流れの流れで会に入っていったと。半ば強制的というかある意味蟻地獄というか。(笑)

毎田:役員を引き受ける最初のきっかけはそのようなかんじで始める方も多いかと思いますが、蟻地獄とは言ってもそれだけ魅力があったからなのではないでしょうか。どのあたりに魅力をお感じになられたのでしょうか。
中村:やはり、人との出会い触れ合いがあるからではないですかね。僕らは当然ボランティアですし無償だし、その中でやっぱり一生懸命やることが楽しいことだと思います。門傅副会長もご存知のとおり、2人でよく食事を行っていますからそういう出会い触れ合いがとても良いのではないかなと思います。
毎田:お母さん方がわりと多いのでしょうか。
中村:うちの全国の場合は今、顧問入れて17名いますが女性は1人だけです。
毎田:お父さん同士で繋がりが出来て、楽しそうですね。
中村:どっちかと言うと、みなさんお酒が好きだから飲みニケーションというやつですね。
毎田:そうは言っても教育の話題で盛り上がることができる飲み友達なのですね。
中村:そうですね。ですから、そういう話もしますし、また別の話もしますし、当然いろいろな県から来ますから、県の話をしたりします。
毎田:門傅副会長の場合はどうでしょう

門傅:私も子供が3人いてですね、宮城県なのですが長男は最初公立に行くのかと思ったのですが私立に行くと。今は古川学園という名前で、入った当時は古川商業という高校でそこに子供が行ったのがきっかけですね。
そうしたらたまたまいろいろ知っている方と、PTAの役員をやっていて、おまえやらないかという話で、いつの間にか学校の会長になって県の会長になって、東北ブロックの副会長になってというかんじでした。
3人とも全員同じ古川学園にみんなお世話になってそれぞれ大学に行ってそれぞれ生協さんにもお世話になったというわけです。
毎田:一番上のお子さんから3人ともとなると長い期間役員をやられたのでしょうか。
門傅:上と下で5歳しか差がなかったので、かぶるときは…。2人かぶっていることは何年かありましたが、会長は多分3年ぐらいだと思います。
毎田:実際にはそれぞれの学校での会長さん、役員の間ではどういうことが一番テーマになっていったのでしょうか。
中村:当然、公立の小学校と違ってそんなに役員会というのはないので、年に1学期に1回とか2回くらいですが、大体話題になるのが、体育祭の手伝いだとか、音楽のそういう手伝いとかが話題になりますね。
毎田:門傅会長のところもそうでしょうか?
門傅:そうですね。各委員会みたいなものがあって、例えば新聞を発行するところがあるなど、あとはいろいろな大会の応援ですよね。学校行事の手伝いが多いです。あとは、保護者会で講演会を企画したりしていましたね。
毎田:そういうことをやっている間にお父さん同士横で繋がったり、飲み友達が出来たり。
中村:私の場合は、高校の場合はほとんどが女性だったのでそういう飲み会はなかったですね。ですから食事会は行くのですが、そういう飲みみたいなものはなかったですね、お母さん達が多かった。女子校というのもありますからなかなかそれでまた違うのだなと思います。
一番大きい仕事や魅力的な点、また現在のお立場について
毎田:高校単位の保護者会の、楽しみ、醍醐味と申しますか、引きつけられたことを教えてください。
中村:引きつけられたこと、非常に難しい質問だな。
ただですね。先ほども言いましたが一つの大学があるわけではないですか。例えばどこか旅行に行こうというのもあったわけで、そういうのでも楽しかったしまた一方で例えば部活動で全国大会、みなさんで応援に行くわけではないですか。そういうところでみんな一緒になっていくというのがすごく魅力的に楽しかったと思いますね。
門傅:私立学校だったので、当然民間ですから公立だったらどうか分からないですが、私の場合は進学を頑張るクラス、部活動と勉強を頑張るクラス、勉強はちょっと苦手だけどもやりたい、というそういう3つのコースがあったので、やっぱりそれぞれのコースの子供達は将来目的目標がありますので。それに当然、私立高校の先生は基本的には転勤はありませんので、転職しちゃえば別ですけども、ですから必死ですよね。言葉が悪いですが、預ける親とか子供というのは経営から見るとお客さん的立場になっちゃうわけですね。
だから、迎合するわけではないのですが、いろいろな意見を直接学校の先生や、理事とか評議員とか、役員になると接する機会が多かったのでそういうのを聞こうという姿勢もありました。良い意味で繁栄して良い学校にして更に生徒が集まるようにという思いは一緒でしたので、そこはもしかすると公立とは違うとこかもしれないですね。
良い学校を作って、お世話になった子供達がいるので更にいろいろな意味で恩返しをしたいというのは非常に一番強いところですね。
毎田:たいへん密接というか、近いと申しますか、そのような雰囲気があるのですね。
高校単位での活動から、中村さんの場合は次は東京都といった枠での活動に移られたわけですが、そうなると、活動の内容が少しずつ変わっていくのでしょうか。
中村:基本的には私たちは西学と呼んでいますけれども、大きな行事と言えば総会ですよね7月、それから12月の47都道府県、2200名ぐらい集まってくるのですけども。それと先ほども話してありますが、研修会が大きな行事なので、それに合わせてみなさん会議するわけですよ。その中で会議の中でどうやっていこうとか、そういう話をしてみんなで盛り上がって、その後にじゃあみんなでお疲れさま会をしようというのが、そこにやっぱり人との出会いがあるのだなあと僕は思いますけどね。
毎田:門傅会長の場合も、同じく東北という枠組みでの活動なった時にはいかがでしたでしょうか。

門傅:最初、宮城県の会長だったのですが宮城県の総会とか宮城県の私学振興大会と学校の先生がたと一緒にやるのがメインであとは研修会も総会の時にするなどがメインです。
東北地区とすると、総会ぐらいしか活動がなかった。予算も小さかったので、新年度からは更に研修会等々もやって、いろいろな私学を巡る情勢を勉強しながらもお互い意思疎通を図る。我々はいろいろ情報交換をしました。
県によっては、1年間で会長が変り、名前も顔も覚えないうちに変るみたいなことがあったので、最近は役職を退いてもまたいろいろ繋がりを持ってとかそういう形にも少しずつ東北地区は変ってきました。
大学に求める事などについて
毎田:今度はだんだんと大学の話になっていくのですが、今大学の進学率は大体54、55%ぐらいで、高校生の約半分が大学に行く状況です。中村:親は子供の社会人に向けての教育的のロマンの中で社会性だとか、道徳性、人間性を、しっかり貯金をして社会人として幸せになってほしいなという気持ちが親はあると思います。当然大学に求めることということだと思うのですが、それぞれの家庭によっても違うし、またお父さんお母さんの考えも微妙に違うと思うのです。大学生活を通じて社会経験として大変貴重なことだと思います。各部の専門的知識を高めて大学を卒業することが、社会人になるための教育の先行投資ではないかなと思います。
また一方で、引き出しの多い教育、教養をつける教育、そして将来の進路やライフスタイルを考えた資格の取得を出来るそういう大学になってほしいなと思っているし、また一方で大学も、専門学校もそうですけども入学したメリットを親と子に説明できるようにしないとだめだろうなと思いますね。
毎田:門傅会長はいかがでしょうか。

門傅:大学も我々の時は、いわゆる共通一次世代でしたがいろいろな意味では多様化していると思います。大学の数も増え、学部もいろいろ、入試の形態も大分変って何がどうなのだか分からなくなっているという、選択が増えたのはいいのですが、もちろん学費等々の時代の流れである程度高くならざるを得ないのは分かります。ただ、学生が多分非常によく勉強をしているところもあれば、そうでないところもあるでしょう。いろいろな意味で幅も広くなり、大学はまさに生き残りをかけてやっていていろいろ工夫されているので、求める学生が大学で言えば研究と教育の両輪というのは当然あるわけです。大学の先生もこれは大変だろうなというのが正直あるわけですよ。まさに昔、大学は出たけれどではないのだけども。
当然、大学からすれば高校に対してきちんと高校で勉強させて下さいよというのと、逆に会社からすると、ちゃんと大学で一定程度の資質は備えてくださいよというそれぞれの段階がみんなあるではないですか。かといってそのライセンスでやるわけにはいかないが、ただいろいろな個性がいっぱいあるので一律的に切るわけにはいかないのですが、そこの緊張感をそれぞれお互い持ってやらないと、これは永遠の課題だと思います。どの時代でも小学校からすれば、幼稚園でちゃんとしつけしてくれよみたいな、それは各段階で全部あるのでいずれ高大接続だって同じ話ですよね。仕組みは変っても競争は免れないわけでその中で磨かれていくのはいつの世も同じですから。 ただ正解はないわけですよね。
まさに18歳から受験、飛び級までは分からないですが。逆に、もし我々でも大学に入ろうと思ったら、大学院は高卒でも大学院に入れるではないですか。色々な18歳、19歳だけじゃなくていろいろな経験を持った方々がいろいろな方法で、大学大学院に行ける事、これは大変いいことだと思っています。そういう意味での大学としても非常に社会への開かれている面はどんどん進んでいると思います。

毎田:我々は大学社会の中で仕事をしているのですが、かなり以前から「2018年問題」という言葉がよく使われてきました。要は18歳人口がさらに減り始める年が今年2018年から、という意味です。このことはもともと人口構成上分かっていたことでもあるので、大学自身はおっしゃる通り生き残りをかけて、ウチの大学の特色はこれです、という取り組みをされています。そうはいっても実際、私学では4割ぐらいが定員割れを起こしていてます。 今の話をうかがっていると、大学側の努力が高校生の親御さんにちゃんと届いているのかどうかが、大学の悩みになっているのかなと思いました。
門傅:でもオープンキャンパスって昔はなかったですよね。今受験生だけではなくて親も行く時代でしょ。だからいろいろな意味では良いではないですか。入ってからあれって思うことが減ってくるのではないかと。我々のときには大学に入っても全然大学に来ない人とかいつの間にか退学した人とか普通にいましたからね。今そういったメンタル含めて、かなりフォローアップするようになっているとは聞いていますが。
毎田:大学によりますが、退学者をどれだけ出さないようにするか、も努力する一つのポイントになっていますね。
中村:男子は様々な進路を模索しながら、大学だけではなく専門学校等の選択も増えてきていますね。すると女子を狙うということで、今東京の私立の学校もいわゆる大学がこれから経営するためには共学をして男子校に今後入れようというそういう経営の的でやっている大学がけっこう多いです。ですからここ10年間で、共学になったというのが60校ぐらいあるわけですよ。それも男子系大学がみんな付属高校でそうやって大学の中に入れようという意識の中でやっているのですよね。大学も大変だなと思います本当に。
高大接続や大学入試についてのご意見
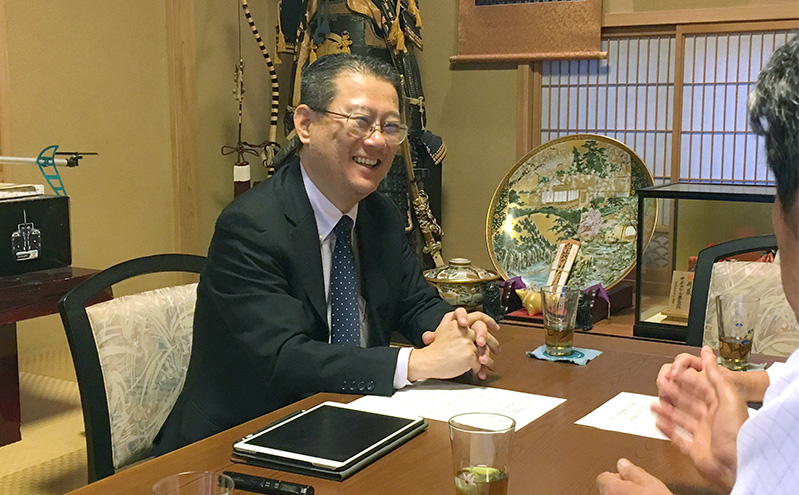
毎田:高大接続という言葉が出はじめた頃、すごく変わっていくなと私たちも思いました。これから入試制度も変っていくことも決まっているのですが、この点について高校の先生方や保護者の方の受け止めはいかがでしょうか。
中村:今、中央教育審議会の中で高校から大学の継続が課題になっていますよね。当然子供達は未来に向けて大きな「ロマン」を持っていると思い当然親も期待しているというわけです。その中で高校と大学が連携の中で親と子が熱い思いを教育のドラマの中で考えて教育のステージを組み立てていくということが、僕は必要なことだと思っております。
また2019年からセンター試験中心になりますよね。2020年から共通テストということで、文科省でいろいろ考えているのだなと思いますが一つ共通テストのいいところは、記述式になるじゃないですか。人間味のある試験で良いのではないかと思っています。高校大学一貫教育、これも非常にいいことだと思います。ただやっぱり高校と大学の調整をしていくということでスリムな教育をしようということだと思いますが、今のところ大学と付属の高校、私立しかやっていないわけですよね。公立をこれからどうやっていくのというのが課題だと僕は思っていますね。その中で、今度共通テストになった時にでは、高校推薦とOA推薦はどう変化していくのかと。これもやっぱり考えなくてはいけないのかなと思っています。
門傅:中村会長が今言ったとおりなのですが、現場の先生は大変だろうなと思いますよね。
中村:本当にそうだと思う。

門傅:実はうちの古川学園の進学コースというのはちょっと変っていて、推薦は一切受け付けない。全部通常の入試だけでやらせる。良い悪いは別ですね。学校の方針として進学コースは、推薦は受け付けないとしている。どんな大学から推薦依頼が来ても。センター試験を受けて、2月の私立大学の(一般)入試を受ける、ただ親のニーズからすると「なんで推薦を使っちゃだめなの?」という話も出ています。
あくまで学校の方針だと言ってどこまでそれが守れるかどうかは分かりません。どっちがいいか悪いかは分かりません。高校の実績から言えば推薦であっても一般入試であっても○○大学に何人入りましたと一つ売りになるではないですか。良くも悪くも。そこをどう考えるかは分からないですが。
新しい記述はいいけども、現場の人は大変ですね。いずれ情報公開で、自分の点数がなんでこれが何点だとなるでしょう、採点ミスという形で出て来るではないですか、何十万人と受けるわけではないですか。Aiが採点するか人間がやるかは分からないですが。
中村:いずれにしても各大学でやはり個々でうちの価値観はこういうところがあるよ、と親と子に強くアピールしないと僕はだめだと思います。
毎田:先ほどオープンキャンパスの話でも出ましたが、大学自身も保護者の方に理解をしてもらうということにすごく力を注ぐようになりましたよね。入学してからも、親元に成績表が送られてくるようになっています。昔は自分の大学の成績なんて親になんか見せなくてもよかったと思うのですが、今は成績表が親元に直接送ってきます。
中村:お父さん、お母さんのニーズが高いですからね。いろいろありますからね。
毎田:大学も保護者の方の目線を大切にしています。以前は入学式に親が来るという話をすると「えー」という反応でしたが、今はもう当たり前、しかも是非来てくださいと言っています。入学式が終わると子供は子供でオリエンテーションなどを受けますが、それと並行して保護者向けのオリエンテーションを行う大学も増えているように感じます。
門傅:うちの子供の時はなかったな…あったかな。
毎田:いらしているのであれば親御さんを集めて、うちの大学はこういうことをやっていますという説明をされています。大学によっては、例えば5月とか6月に保護者の方を招いてキャンパスツアーを行っています。そのくらい、今、大学の保護者の方に対する情報公開とか情報提供を行うようになってきています。
中村:いろいろな考え方がありますから。
門傅:説明責任の一つなのかも分からないですがね。
毎田:大学生協で行う説明会では、例えばアパート紹介や下宿用品をご案内するときに、食生活や授業のこと教科書のことなどを先輩学生が話をしていますが、この5〜6年くらいでしょうか、保護者の方も是非来てくださいと言うようになってきました。新入生本人だけじゃなくて保護者の方にもお伝えすると、今の大学はこうなっているのか、昔の自分たちの大学生の時とはずい分変っているな、という受けとめをされています。
中村:びっくりするのは親が子供の入試に一緒に東京に行くとか信じられないですけどね。
毎田:今はめずらしくありませんね。
中村:親が息子、娘のアパートの部屋の掃除に行くとか、ぶったまげます。
とてもではない。そのような暇があったら、自分の仕事をしています。
毎田:本当にめずらしくありませんよ。
中村:携帯で間違いなく行くでしょう。そこに。
毎田:そうかもしれませんが...
実際は、親子で東京にやってきて、子供は入試に行く、その間に時間を持て余すので生協では保護者向けの説明会をこのタイミングで開催しているところもあります。すると大変感謝もされるのですが、それ以上に、いやいや今説明を受けるだけではなく今直ぐ下宿先アパートの下見に行きたいのだが行けるか、といったことも言われます。
中村:え!入試の時に?
門傅:子離れしないですね。
毎田:合格発表前のアパート予約については、不合格だったら当然キャンセルは無料ですとしています。

中村:東京の場合は電車網が沢山あるじゃないですか。地方の高校に行くと、今は自分の子供達を車で送り迎えですよね、あれにはたまげちゃいます。校門の前が渋滞するのですから。
だからやっぱり、子供がかわいくて仕方がないのは分かるけど、どこまでやっていいのかなというのもありますよね。
毎田:そこは、私たちもやりすぎかどうか、悩みながら行っているのですが。その他にも、ミールカードや学食パスという食堂で利用できるICカードシステムを開発して使っていただいています。いわゆる「定期券型」だと、ICカードに例えば年間20万円で1日1000円上限でいくらでも使えます、というしくみです。カフェテリア食堂で精算するときにピッとかざすのですが、そのとき購入したものの履歴が自分のマイページで見ることが出来ます。
当然メニューごとの栄養価がシステムに登録されているので、例えば、野菜が足りないぞといったことがわかります。自分で食べるものは、ちゃんと自分で管理しましょうということです。
ただ、それに加えて、実はそのマイページは親が見ることが出来る。もちろん設定次第なのですが、これがけっこう親御さんに好評です。
中村:何食べているかが…。
毎田:学校には必ず行っていると、引きこもっていないかなど。
中村:かわいそうだな。好きにやらしてあげればいいのに。
毎田:でもそれで、ちゃんと学校に行っているのだなと。焼き肉ばっかり食べているのではないかとか、カレーばっかり食べているのではないかとかいうことをとか。
中村:焼き肉行く前にちゃんとそういうのを教育しなさいと思います。家庭でしょ、食育は。
毎田:それが親御さんからすると一つの安心材料になっています。子供も自分が食べているものが親に筒抜けになるのはいやだなと思うのですが、少なくとも食べることに困らないということは確かなので、子供も半分しぶしぶ半分喜んでこのシステムを使っているようです。
門傅:世の中が変ったと言えば、それまでだけど。自分でちゃんと飯を食えるのか。と思いますがね。
大学生協で高校訪問の事や、高等学校や各県単位の私学保連へのアプローチについて
毎田:大学生協では、いくつかの地域では高校訪問を行っています。その高校の卒業生が自分の母校に行き、例えば入学準備説明会を行っているので来て下さい、とか、学食はこんな感じです、授業はこのような雰囲気です、といった説明をしています。主に生活面について、高校生から大学生にスムーズに馴染んでいただきたいという思いからです。例えば仙台ではけっこう重点的に廻っています。東北学院大生協、東北大生協、宮城大生協などのメンバーで、だいたい130校ぐらい廻っていると思います。中村:今、大学生協のアプローチの仕方だということだと思いますが、これはやっぱり、人の繋がりでアプローチしていったのがよろしいかなと思います。僕は今後援会の顧問をやっていますが、学校側に聞いてどうでしょうかと、学校がうんと言えば大勢の前でお話が出来るということだと思いますし、また全国も一方で、例えば門傅会長是非大学生協で力貸してよと言えば、それなりに力は貸してくれると思います。そういう人の繋がりの中でアプローチしていくのが一番にベストなのかなと僕は思います。
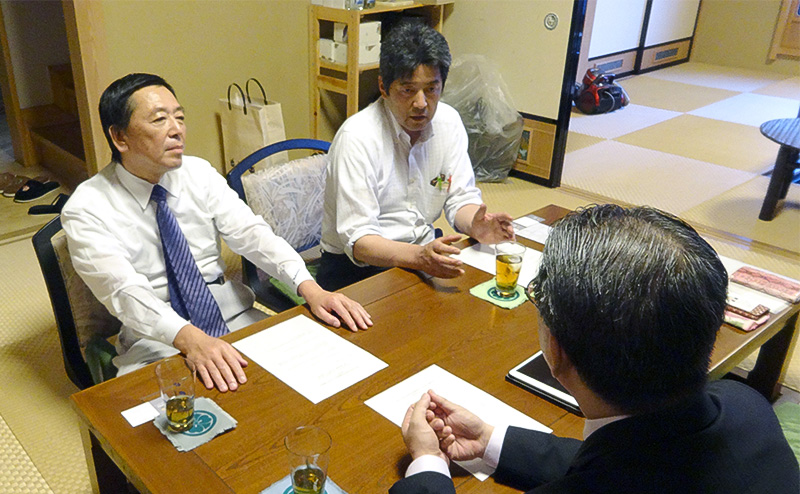
門傅:これは現役の大学生が自分の出身高校に行って、いろいろその大学生活の中で、その中で、生協の話も言ったり喋ったりとか…。
毎田:はい。そういった例もあります。「実は京大に行った子が大学生協の活動をやってくれていて、それでポスターを貼っていくんだよ。毎年張り替えてくれるんだ。」という話も聞いたことがあります。
中村:なるほどね。
今東京で高校427校ありますけども、行きあたりばったり行っても多分だめでしょうね。PTAの繋がりの中から行ってもらうというのが一番にベストだと思いますがね。
毎田:今回、大会にお邪魔をして資料をお配りさせていただきますが、これなどをご覧になられて、なるほどこのようなことを卒業生が来て話してくれるのはいいな、と先生方や保護者のみなさんが思っていただくことで、少しずつ各地の大学生協と繋がりが出来ればいいなと思いますね。
門傅:今全国の4年生の大学って何校あるのですか?
毎田:700校ぐらいあります。
門傅:そのうち生協がある大学は?
毎田:200校ぐらいですね。
門傅:もっとあるかと思ったらそのぐらいなんだね。
毎田:学生数だと、大体大学生の半分くらいになります。
門傅:なるほどね。大学の規模もいろいろあるからね。
毎田:私たちは今後も、高校生や保護者の方との繋がりを作っていきたいと思っております。その中でご協力頂ける部分があればご協力いただきたいと思いますし、逆に何かこちらからご提供できるものがあれば喜んで、とも思っています。
中村:私も門傅副会長も、そういう意味では頼まれればお力になりますよという気持ちでいることは間違いないですね。
毎田、中村、門傅:今後ともよろしくお願い致します。
