- HOME
- 全国大学生協連のご紹介
- Campus Life WEBインタビュー 〜大学生協理事長へ伺いました〜
- 福山市立大学生協 渡邉 一成 理事長
Campus Life WEBインタビュー
〜大学生協理事長へ伺いました〜
福山市立大学生協
渡邉 一成 理事長
みんなで生協を愛して、支えていく
「FOREST」という名称と共につなぐ、学生主導で創立した想い
学生有志による生協設立準備委員会の立ち上げから2年の時を経て、2017年12月に福山市立大学生協は創立されました。
生協設立に向けた学生たちの努力と熱意を、当時から支え見守り続けてくださった渡邉一成理事長にお話を伺いました。
【参加者】
- 福山市立大学生協 理事長 渡邉 一成 先生
- 福山市立大学生協(広島大学生協兼務)専務理事 塩崎 昌哉
【聞き手】
- 全国大学生協連 広報調査部

【参加者】
- 福山市立大学生協 理事長 渡邉 一成 先生
- 福山市立大学生協(広島大学生協兼務)専務理事 塩崎 昌哉
【聞き手】
- 全国大学生協連 広報調査部
CONTENTS
(以下、敬称を省略させていただきます)
生協設立の経緯
聞き手:生協設立に関しては、学生主体の動きがきっかけだったとお聞きしています。その経緯を先生はどのように捉えておられますか。
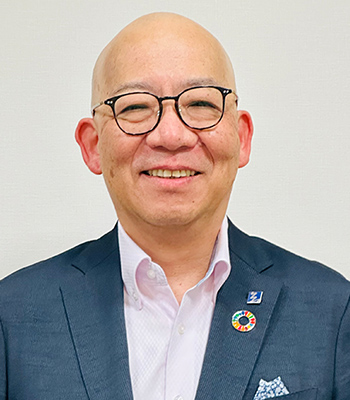
福山市立大学生協 理事長
渡邉 一成 先生
福山市立大学生協 渡邉 一成(以下 渡邉):生協が出来る前は民間の事業所が食堂やショップの経営をされていましたが、1000人規模の小さな大学ですので、やはり利益追求型の民間事業者では経営が厳しく、厳しくなるとサービスの質が落ちていき、品数は減り価格は上がるということで、学生の利用も離れていく状況でした。私は2014年に着任しましたが、最初は弁当を持ってきていました。ですので、学生も近隣のコンビニなどを利用しており、こんな食生活でいいのだろうかと危惧していました。
民間の事業者も経営が成り立たないので、撤退しては入ってという繰り返しで、この状況はよくないと学生の方から声があがり、自主的にいろいろと調べてくれて生協にたどり着き「生協設立準備委員会 FOREST」として”私たちの大学生協”を作るという運動を学生がスタートさせたという経緯になります。
そこから最初は苦難の連続で、当時は大学が市役所の一組織だったので、大学生協の設立は市役所の許可が必要であり、学内も生協設立に消極的な風潮がありました。でも学生はめげずにアンケートを取ったり、学生たちの想いを整理したりし、その熱意を受けて事務局の方も市役所と交渉してくださった結果、生協が立ち上がることになりました。
これにおそらく2年ぐらいかかりましたので、生協が必要だといって頑張ってくれた当時の学生たちは、生協の設立を見る前に卒業してしまい、卒業後にたまに遊びに来てくれた時に設立に尽力してくれた生協を見てもらっています。やはり生協ができて、大学が間違いなく明るくなりました。学生もそうですし、学内の雰囲気も断然変わったと思っています。
聞き手:生協ができることで学生さんが元気になったり、さまざまな学び合いがあったりというのは素晴らしいですよね。先生方や職員の方々の受けとめはどのような感じですか。
渡邉:教職員も生協設立によって食堂や購買が利用でき、いろいろなサービスを受けられることで、環境が整ったと思ってくれているはずです。
学生を中心として声が上がり、次は事務局を巻き込んだ流れとなり、教員は少し取り残された形になりましたが、学生や職員の方から促されて我々も教授会等でしっかりと議論をし、委員会を立ち上げて参画していった経緯があります。私たち教員は学生主導であることを尊重しつつ、アンケートの取り方や集計の方法などにアドバイスをしたり、大学事務局との向き合い方や計画の立て方を伝えたり、一生懸命に支援しました。
聞き手:先生ご自身の大学生活での生協の思い出はございますか。
渡邉:東京都立大学在学中は生協を利用していましたし、いま家庭でも生協に加入していろいろと購入しているので、比較的生協は身近な存在です。学生時代は確かカレーライスが格安の150円だったと思いますが、みんなで「金無いす(カネナイス)」って言いながらありがたく食べていた覚えがありますね。
設立後の学内における変化
聞き手:生協設立(※1)から約8年経過しましたが、設立当初から理事である先生からご覧になって、学内に変化はございますか。

(※1)福山市立大学生協食堂と店舗のオープニングの様子
福山市立大学 新しい店舗と食堂2018
渡邉:雰囲気は変わっていないですが、少し危惧しているのが、生協は生活インフラですので、あって当たり前のところがあるので、そのあって当たり前感がすごく出てきているのかなと思いますね。もう少しみんなで生協愛を高めていきたいと思っているところですけども。もちろん一人ひとりはお昼が食べられていいとか、本が買えていいとか、サービスを受けていることにすごく満足はしてくれているとは思いますが、私からすると今一つ愛が足らないな、みたいな。設立当初の愛から比べると、もうちょっとみんなで生協を愛していこうよとはすごく感じますね。
聞き手:今日は学生委員会のメンバーが階下でつかみ取りをする企画をされていますよね。自分たちがやりたいことを頑張って実現しようという感じが見えました。
渡邉:ソフトクリーム企画は学生の発案ですね。うちのゼミ生にも好評で、みんな楽しみにしてくれていますよ。あれは我々の発想では出てこないからすごいなと思って見ています。
企画の実行にはかなり手間をかけていると思いますが、歴代の店長さんもすごく知恵を出して頑張ってくださって本当に助かっています。
聞き手:実際の店舗や食堂で何か意見が上がってきていることなどはございますか。

福山市立大学生協(広島大学生協兼務)
専務理事 塩崎 昌哉
福山市立大学生協 専務理事 塩崎 昌哉(以下 塩崎):現在は食堂の混雑がすごくて、そこは大学の方も気にされているところで、昨日も理事会でその話がありました。席に座れないのでトレーを持って別の場所で食べている利用者がいる状況なので、利用してくれていることは本当にありがたいのですが、そこは改善していかないといけないと思っています。
聞き手:11時のオープン前にお邪魔したのですが、電気がつかない中で学生の皆さんが勉強をされていましたよね。結構な人数がいて、一言カードを拝見したら「もう少し早くから電気をつけてほしい」という意見もありました。
渡邉:それは生協の問題というよりは、大学の問題ですね。そういう意味では、食事をする場所とともに、集う場所としてみんなから愛されている空間なのではないかと思っています。
食堂の混雑に関しては、トレーチェック(※2)を昨年の11月に導入しましたので、少しは緩和されたのではないでしょうか。
(※2)トレーチェック:中国・四国地方の大学生協で行われている、ミールプラン利用者限定のセルフ清算システム。アプリをダウンロードし、専用のテーブルで画像を撮影することで会計が終了するため、レジに並ぶ必要がない仕組み。
塩崎:レジを待つ時間は緩和されたと思います。トレーチェックの利用自体は、現在中四国事業連合内でも一、二を争う利用率になっています。
現在の課題とその解決に向けた対応

聞き手:いま福山市立大学生協の中で抱えている課題はございますか。またその課題について、どのように解決しようとお考えでしょうか。
渡邉:おそらく一番の課題は、お昼時間の混雑緩和だと私は考えています。ただそれはみんなで知恵を出し、工夫してやっていく必要があるでしょうし、実は2年後に新しい学部の新設予定があり、学生が一学年あたり50人増える予定ですので、そうすると今よりもっと混雑することが予想されます。ですから食堂をもう少し広げてもらうとか、場合によっては時間差で学生が昼食を取れるように工夫するとか、これは大学の教務とも関係しますが、いずれにしても何らかの混雑対策を取らなければならないと思っています。
塩崎:これまでは設立時から関わってくださっていた先生方に頼っていたところも大きかったのですが、先生方も変わられていく中で、先々のところで理事になっていただける教職員の方と想いをつなげていくサイクルを続けていきたいと考えています。

渡邉:理事の皆さんには、生協は学生にとっては不可欠なインフラだと理解してもらい、もう少し熱意を持って取り組んでもらえるように、機会あるごとに強く伝えていきたいですね。
やはり学生生活で大事なことの一つはお昼だろうし、それから授業で使う教科書だとか、そういったところをしっかりと支えてくれている、だからこそみんなで支える必要があるということを共有していきたいですね。
うちの大学は若い先生が比較的多いので、その先生方にしっかりと引きついでいけるのではないかと思っています。先日、若手の先生と話した時に「生協の食堂がすごく混んでいるので、自分が利用すると席が一つ少なくなると思うと、なかなか行けない」と言われたので「時間をずらして行けばいいじゃないですか」と提案しました。生協の利用を促進するために、そういう話も積極的にしていきたいと思っています。
聞き手:先生方の中には、学生時代に大学生協を利用された方もいらっしゃると思いますので、ご自身の学生時代の思い出と生協の利便性を一致していただけると、より深くご理解いただけるのではないでしょうか。
渡邉:みんなそれぞれ大学で生協にお世話になって暮らしてきているはずなので、そういう意味では理解してもらえると思いますし、大学生協がない大学出身の先生にはうちの大学生協が立ち上がった経緯を伝えていくことで、理解を深めてもらいたいと思っています。

塩崎:私自身の問題で大変恐縮なのですが、兼務をしている広島大学生協と距離が離れていることもあり、こちらに来ることができる頻度が少なく、教職員の方々と関りを持つ機会がなかなか取れないというのが、自分自身の中で少しストレスを感じるところです。
広島大学生協と福山市立大学生協とでは全くカラーが違っていて、福山市立大学生協は本当に学生と先生、職員さんとの距離が近く、生協の事業はもちろんですが活動もできている印象があります。店舗で行う企画などを目の当たりにできる距離感というのはここならではで、本当にこの大学の中に我々生協がいて、そこで活動できているというのは素晴らしいことだと思っています。
渡邉:うちは本当にみんな顔見知りの規模ですので、そんなフレンドリーな中で上手く動かしていければいいのではないかと思っています。決して経営的には潤沢ではないからこそ、みんなで支えないとダメだよねというところをやはり認識してほしいですし、そのためには何が必要なのか考えるとやはり「愛」ですよ。本当にみんなで生協を愛して、支えて、回していかないと絶対にダメだということです。
塩崎:そうですね。本当にそこは生協の原点であり、やはりみんなで利用してもらわないと成り立たないんですよ、ここ福山市立大学生協は。そういうところをしっかり皆さんで考えてもらえるようにしていけたらいいかなと思っています。
渡邉:うちの大学では2024年度の入学生から「Bring Your Own Device」を実施しており、学生は基本的に自身が所有するパソコンを持参して学ぶようになっています。生協で購入するとアフターサービスも優れていますし、売り上げ的にも大きな商品なので、新入生は生協でパソコンを買うということが浸透してほしいですし、そのためには大学の広報とも上手く連携しながら、早い段階でアプローチできるように進めていきたいと考えています。
「FOREST」の由来とひきつがれる設立の想い

聞き手:近年は比較的大学主導の生協設立が多く、学生が主体になり先生方も含めてそれをバックアップする形で大学全体の動きになっていったというのは、あまり聞かない話でした。生協設立の熱気のようなものを、どう次の世代に引き継いでいくのかというのが、おそらく今の一番のテーマになっているのではないかと思います。先生ご自身が日常的に行っていることはございますか。
渡邉:一生懸命みんなで議論をして作り上げたという過程があるので、そういう意味でもその想いというのは、学生委員会である「FOREST」に受け継がれていて、その「FOREST」という名前も、設立に向けて最初に頑張ってくれた教育学部の女子学生の名前が「森さん」で、彼女の名前に因んで「FOREST」になり、今もその名称は受け継がれています。私も先日の総代会での冒頭の挨拶でこの話にふれましたが、現在活動している学生たちにもその経緯と想いを共有してもらい、生みの苦しみの中でできた生協であるということを折にふれて話をしていこうと思っています。
ですので、私自身というよりも、学生たちが「FOREST」という名前を大事にして、その想いをしっかりと日々の活動に展開してくれていることが素晴らしいと思いますし、いろいろな大学との交流や連携にも関わってくれている。そういう意味では、まさしくうちの大学の生協の立ち上がりが、そのまま今でも活動としてつながってきていると私は認識しています。毎年10名ほどですが、後輩たちが生協の活動に加わってくれて、派手なことはできないですけど、しっかりと着実に自分たちの想いを活動として展開してくれていることは、我々教職員も見習わなければいけないところだとつくづく感じています。
聞き手:「FOREST」が、その設立時の想いというものをずっと体現してつないでくれているということですね。学生は入れ替わっていくので、なかなか難しいですよね。
渡邉:そこはうまく引き継いでくれているとは思っていますし、何よりも「なぜFORESTなの?」と多分みんな最初に引っかかるはずなので、自然と設立の経緯や名前の由来に話が及びますし、学生委員会の名前は未来永劫「FOREST」であり続けて、その想いを紡いでいってほしいと思いますね。その中で時代時代の具体的な活動は積極的に展開してもらえばいいし、学生たちの頑張りを見守っていきたいですね。
塩崎:直接OBやOGの皆さんと関わりがあるわけではないのですが、機会があるごとに設立の経緯は話してきているのと、先日の総代会での冒頭の先生のご挨拶は非常に私自身感動して、私も最初から関わっているわけではないので、やはり実際に関わられた先生の言葉はグッと響きました。
ちょうど5周年を迎えた時に、設立時のいろいろなものを引っ張り出してきて、5周年記念企画を開催した時に、森さんとリモートでお話しさせてもらう機会もありましたので、より想いを強くしましたね。
渡邉:実は生協の設立趣意書は、私が作ったんです。設立趣意書はずっと残るものなので、残したい想いを絶対に書いておきたいという思い入れがありました。全体的な構成は他の生協さんのものを参考にしましたが、趣意書の中にうちの大学生協ができた経緯を入れました。それでみんなに手入れしてもらい、今この趣意書があるんですけども、そういった意味では、やはりうちの大学生協は学生が主体となって作り上げてくれたものなので、その歴史というか経緯は忘れないでほしいし、多分それはもうしっかりと「FOREST」の中では引き継がれているのではないかと思っています。
あとはそれをどのようにしっかりと繋げていけるのかということですよね。どうしても規模が小さいので、本当に最低限でも学生の福利厚生をしっかりと支えられる、そういった生協であり続けたいと思うので、そこで何ができるのか、何をしていけるのか常に考えていきたいと思ってはいます。


今後の生協運営の展望
聞き手:大学生協関係者に向けて、今後の生協運営の展望についてのメッセージをいただけますでしょうか。
渡邉:生協というのは「みんなで創って、みんなで運営する」そのことが原点だと思っていますので、うちのような中小規模の生協としての強みは引き続き持ち続けつつも、そこの原点はやはり外さないでやる必要があると思っています。本当にそこが生命線であり、立ち上げのところでの学生たちの想いでもあるので、それをしっかりと受け継いでいきたいと思っていますね。それはぜひとも全国の大学生協の組合員の方々にも忘れないでいただきたいなと思うところです。
塩崎:福山市立大学生協は、規模としても事業としても手広くやっているわけではないのですが、やはりその設立された理由というのが今やっていることに集約されていると思うので、そこは崩さずに今後もやっていきたいですし、設立時の想いを薄めないようにしていきたいと思っています。
渡邉:塩崎専務は、大規模な広島大学生協と小規模な福山市立大学生協の両方を見ておられるので、そういう意味では小規模の良さを大規模に伝えていたただき、大規模の良さを我々にご伝授いただけると、いろいろと良い影響があるのではないかと思います。実際にパソコンの一括購入なども我々のような小規模生協でもそれなりの価格で取り扱いができるというのは非常にありがたいことですし、まさしく連合体としての取り組みの中で我々は生かされていますので、小さいながらも頑張っているところを示していきたいと思っています。
2025年7月18日 福山市立大学にて
福山市立大学生協 理事長 渡邉 一成
福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科,大学院 都市経営学研究科 教授 工学博士
- 1982年
- 東京都立大学工学部工業化学科 卒業
- 1984年
- 筑波大学大学院環境科学研究科 環境科学専攻 修了
- 1992年
- 東京大学 博士(工学)
- 1984年
- 株式会社芙蓉情報センター
- 1987年
- 筑波大学社会工学系技官
- 1991年
- 一般財団法人計量計画研究所
- 2014年
- 福山市立大学 都市経営学部 教授
- 2015年
- 福山市立大学 大学院都市経営学研究科 教授
- 2021年
- 福山市立大学 大学院都市経営学研究科長 兼 都市経営学部長
(現在に至る)
