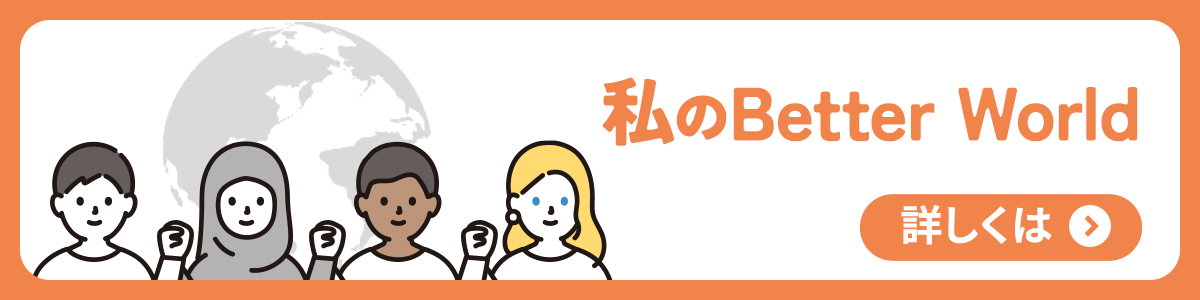2025国際協同組合年
国際協同組合年とは
国連は毎年、世界的に重要なテーマに対して国際年を定めていますが、2025年は「国際協同組合年」として協同組合の活動を推進する年となります。これは、2012年以来2回目で、協同組合の役割を評価し、SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けて協同組合が果たす役割に注目しています。日本の協同組合もこれを機に、認知度の向上や活動の拡大を目指して、政府や関係者と協力する方針です。
協同組合の理解を深め、学び、実践し、発信することが重要です。具体的には、協同組合や国際協同組合年について学び、協同組合の本質を再確認し、実践を通じてつながりを広げることが目指されます。そして、これらを発信することで地域社会にも協同組合の意義を伝え、共感を広げていくことが期待されています。
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- 世界の協同組合
- 世界には農協や生協などと同じ協同組合が広がっています。国際協同組合同盟(ICA)には百か国から10億人以上の組合員が加盟しています。協同組合は19世紀ヨーロッパで産業革命による経済格差への対抗手段として生まれ、現在も世界中で生活の向上や持続可能な社会実現に取り組んでいます。
各国での協同組合の役割も多様です。スイスでは生協が食品小売の70%以上を担い、ニュージーランドの酪農協同組合は同国の輸出の25%を占めています。スペインのバスク地方では労働者協同組合が地域経済を支え、ドイツでは住民が電力協同組合を立ち上げて自然エネルギー利用を進めています。2025年の国際協同組合年に向けて、日本も世界の協同組合と連携し、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
--------アコーディオンパーツを削除する際は、この一行上の空白行から[アコーディオン終了]まで全てを選択し削除してください--------
- 日本の協同組合
- 協同組合は、人々がたすけ合いながら、より良い生活や社会の実現を目指す自主・自立の経済組織です。江戸時代には、二宮尊徳や大原幽学によって協同的な経済システムが生まれ、大正期には賀川豊彦が貧困層支援や社会改革を進め、神戸購買組合(コープこうべの源流の一つ)を設立しました。協同組合は1900年の産業組合法を機に全国へ広がり、現在も発展を続けています。
日本では、協同組合が個別の法律に基づいて活動し、約1億820万人が組合員として加入しています。日本における協同組合による付加価値総額は約4兆9千億円に上り、国民の加入率は個人ベースで46.5%とされています。2025年には協同組合同士の連携を深め、さらなる社会課題の解決が期待されています。
--------[アコーディオン終了※このテキストエリアを編集しないでください。パーツ等の追加は必ずこの枠の下に追加をしてください。]--------
2025国際協同組合年(IYC2025)への
国連事務総長メッセージ
両事務局長から8/29開催の『全国学生委員長セミナー2024』に
ゲスト出演され全国の学生委員長にメッセージをいただきました。