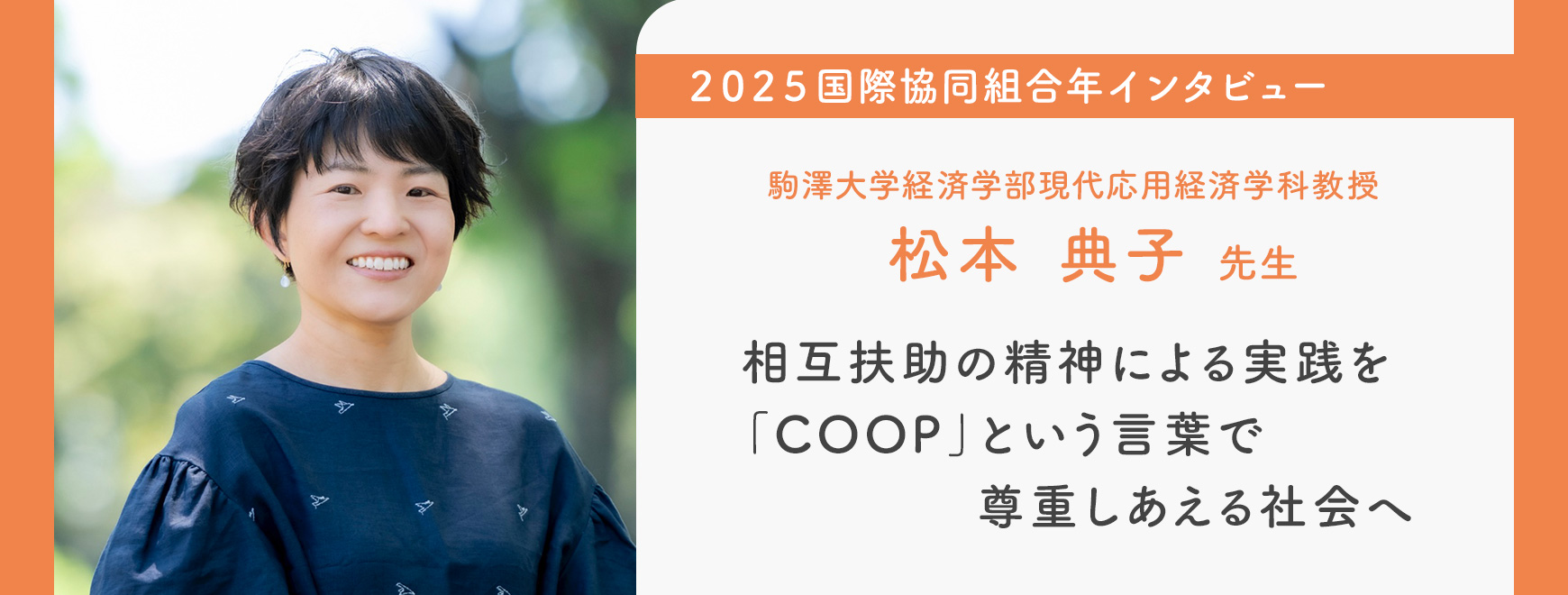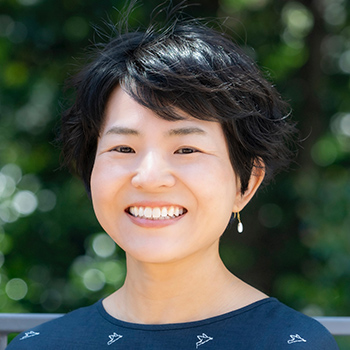2025国際協同組合年インタビュー
駒澤大学経済学部現代応用経済学科 教授 松本典子 先生
2025年は国連が定めた国際協同組合年になります。
記念すべき年を迎えるにあたり、駒澤大学教授の松本先生に、さまざまな協同組合の取り組み、また協同組合が目指す社会の在り方などについてのお話を伺いました。
聞き手

全国大学生協連
全国学生委員会
委員長 加藤 有希
(司会/進行)

全国大学生協連
全国学生委員会
高須 啓太

全国大学生協連
広報調査部 部長
大築 匡
CONTENTS
はじめに
労働者協同組合について
協同組合が目指すBetter World
(以下、敬称を省略させていただきます)
はじめに
自己紹介とこのインタビューの趣旨
本日はインタビューを受けていただき、ありがとうございます。
全国大学生活協同組合連合会で学生委員長を務めております、加藤有希と申します。
同じく全国学生委員会の髙須啓太と申します。
2025年は、国連が定めた国際協同組合年になります。私たち大学生活協同組合の組合員である学生は、学内で大学生協にふれる機会はあっても、他の協同組合に目を向ける機会は少ないと、学生委員である自分自身も感じています。
そこで、労働者協同組合に関しての研究をなさっている松本先生と、各地の協同組合の取り組み、また協同組合が目指す社会の在り方などを、対話させていただく中で読者に伝えることができたらと思っています。本日はよろしくお願いします。
静岡県磐田市で子育てをしつつ、駒澤大学に勤務し、二拠点で活動をしています。
大学のゼミは、世田谷区の用賀商店街振興組合というところで、まちづくり活動の一環としてYouTube上での放送局づくりのお手伝いをしています。商店街も振興組合という形の協同組合の一つと捉え、地域の中で主体的に何かをやってみたい人たちをまちづくりにどう巻き込んでいくかという課題に対して、学生と一緒に地域の人たちに関わりながら活動しています。
磐田の方では『いわたツナガル居場所ネットワーク』という労働者協同組合を2023年の11月に立ち上げて、私も組合員の一人として活動しています。不登校親子の居場所づくりをしているのですが、労働者協同組合の設立や運営を通じて、さまざまな方とのつながりが広がっている感じです。
もとはNPOの研究をしていたのですが、協同組合に可能性を感じて、労働者協同組合の組織論を研究しようと思い、生活クラブ運動が母体となったワーカーズ・コレクティブで大学院の時に3年ぐらいインターンをしながらアクションリサーチのような形で学んで博士論文を執筆し、2007年にそのまま母校の駒澤大学に着任しました。
『いわたツナガル居場所ネットワーク』が日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会の準会員になったので、そういう意味ではアクションリサーチみたいなことを今も続けていることになり、かれこれ20年ぐらい労働者協同組合について研究しています。現在は協同組合学会とNPO学会の役員もやっているので、両者の架け橋になるようなことを行っていくというのがテーマになっています。
研究内容とゼミでの取り組み
松本先生ご自身の研究内容とゼミでの研究内容とでは、かなり差があるように感じました。それぞれの内容について少しお話いただけますか。
『労働者協同組合とは何か』という本を2025年の2月に出版する予定で、市民活動や協同組合を担う人たちが、主体性を持って地域課題を解決するところにテーマがあります。
ゼミでは、東京の地域課題である希薄な人間関係をどうつなげていくのかということをテーマに、特に用賀商店街の商店主さんたちの中でやる気がある人たちを学生だったら上手くつなげられることもあるのではないかと思い、十数年前から、用賀の商店マップを作ったり、商店主さんにインタビューをして地域の人たちにアピールしていくために『YOGAzine』という冊子を作成しました。あとは用賀だけでなく『せたがや図鑑』という形で、せたがやの人に焦点を当てたnote(SNS)の作成をして、その活動を紹介しています。
基本的には何かやりたいけどなかなかできない人たちが、組織や人とどのようにつながっていくのかに興味があって、ずっと研究してきたように思います。市民や労働者を主体とする社会運動がいま広がってきていて、コロナ禍明けから特に、働くことだけでなく地域の中で生活・暮らしと仕事をどう両立させていくのか、あとは副業的なものとして、地域の中で土日を活用してつながりを作っていくと仕事につながったとか、そういった形で主体性を持って行動することが広がってきた中で、ちょうど労働者協同組合を設立したので、著書ではそれについてまとめて、労働者協同組合の歴史や役割や法律などとあわせて取り上げています。
労働者協同組合だけでなく、協同組合全体に言えることですが、運動性が強いのと同時に閉鎖性も強いと思っています。もともとの協同組合の成り立ち自体が、みんなで地域を変えていこう、社会を変えて変革していこうみたいな方向性にあって、経済的に弱い立場に置かれている人たちを相互扶助で発展させていくことに運動性を持つことから考えると、協同組合を知らない人は入りづらいため、さまざまな主体に開かれた組織を作っていかないと組合員が増えていかないことが、協同組合の大きな課題になっていると思います。
私自身、学生からはNPOやソーシャルビジネスについてやっている人とか、まちづくりをやっている人と思われているのですが、その時点ですごく難しいなと思っています。直接的に協同組合というと、学生もゼミに入りにくかったりすると思うので、いろいろな言葉や人との接点の中で、協同組合を伝えていくという感じですね。
協同組合の活動は、信念を持って活動するという意味では、宗教的なパワーに近いかもしれませんが、逆に言うと協同組合には信念があるので、宗教的な要素が入ってこないことはすごいと思います。ただ、その強みの分、閉鎖的になりやすいので、そこを少し広げるための接点を自分の中でなんとなく無意識に考えていて、ゼミ生とまちづくりの活動をしていたことが、最近気づきました。
確かに学生委員会の中でも「組合員の良い生活のためにやっている」みたいなことを言うと「宗教っぽいよね」って言われたりします。自分たちは別にそういうことでもないと思っていましたが、やっぱり客観的に見てもそうなんですね。
そういう感じに見られてしまいがちですかね。
でもその中で、誰かが何かをやりたいと思っていることから、人と人とのつながりを広げていくというようなところは、やっぱりすごく素敵だなと思います。
労働者協同組合について
生活協同組合との違い
自分を含めて、大学生協で活動していると労働者協同組合についてふれる機会が意外と少なく、労働者協同組合とはどういったものなのか、生協との違いなどお話いただきたいと思います。
労働者協同組合は、労働者が所有も管理もする協同組合です。他の協同組合とは誰が主体になっているかが大きく違います。なので、経営することも少し違いがあり、積極的かつ主体的に全組合員が発言をし、意思決定をしていくことになります。2020年12月に成立した労働者協同組合法に興味を持つ方もいて、農業関係者の中でも労働者協同組合の立ち上げを検討するケースが出てきていて、どの協同組合にも労働者協同組合は作れると思っています。
日本は農協と生協がかなり大きいので、協同組合というとそのイメージが強いと思いますが、諸外国はそうではなく、労働者協同組合がスーパーを経営して、オーガニックなものを作って売るところまで担うなど、みんなが経営に関わるケースも多いです。本当は分けきれないものですが、日本では労働者協同組合、農協、生協と分けられてしまいます。
労働者協同組合は労働組合と間違えられることがあるので、最近は、働く人たちは「労働者であり経営者です」という言い方をしています。一番わかりやすいのは働く人全員が共同経営者であり労働者であるという言い方や、経営者がみんなと共に働く組織という言い方です。
雇用される労働、雇用されない労働
労働者協同組合という組織を、労働者である経営者と理解するのを難しく感じていて、大学でまちづくりや居場所づくりなどの勉強をしていたのですが、ゼミの中で会社を労働者協同組合に変えたところ従業員の理解がなかなか得られなかったという話を扱った記憶があります。今までは従業員として働いていたのに、なぜ急に働くためのお金を払わなければならないのか、経営者になってどう変わるのかがなかなか理解されなくて難しかったというのを思い出しました。
やはり一番大きいのは、現在の労働において賃労働が当たり前だということが浸透しすぎて、本当の労働とは何だろうと考えることが日本には不足していることです。企業や誰かに雇用されて働く労働と、雇用されない労働というのは、形が大きく違うことを日本社会ではまだ理解されていないと思っています。
大学生協は規模が大小あるので、ある会員生協では専務で役員でも別の会員生協では従業員になるなど、役員と従業員を行き来する場合があります。労働保険などは基本的に賃労働で働いている人を前提に守っているもので、原則的には役員になった途端に外れますよね。労働者協同組合では雇用保険や労災保険などはどうなるのでしょうか。
労働者協同組合法では、労働者協同組合の労働者は労働契約をしなければならないことになっているので、代表は雇用する側になり雇用保険などが適用されません。自分で加入する必要があります。日本の労働者性の捉え方が、雇用される労働者が前提になってることにも課題があります。
諸外国などでは、一人一人に保険がかかる個人ベースの例もあります。働き方が変わってきているいま、日本でも労働者性の捉え直しと労働法との関係性を考えなければならない中で、労働法をどう変えるのかという研究報告もされていて、大変興味を持っています。
理論的にはわかっても結構難しいのが、役職に就く人を管理する側だと思ってしまう人がいることです。実はそれは機能的な部分であって本質はそうではありません。労働者協同組合の管理は、誰かを従属させようとする管理ではないということです。労働者を、管理労働者と現場労働者に分けるとしたら、現場労働者たちが、いつ管理労働者になってもいいという準備体制が必要ですが、それが案外ありません。一度管理する側になると理解できるけど、そうじゃないと分からない問題もあります。大きな労働者協同組合などでは誰が管理労働をするのかという問題が発生しています。責任が重くなるからやりたくないという人が増えると、管理労働に一度就いた人が現場労働に戻れないという問題も発生しています。
構想と実行の分離
大学生協では、自分たちの少し上の世代まで学生専務が存在していて、学生自身が自分たちで仕事を回していくという考え方でした。徐々にいろいろな形で分業して、基本は雇われている人たちで生協の仕事をするようになりましたが、そうすると学生が出資はしているけど単なる消費者のような感じになってしまっているのではないか。協同組合は運動性が強い団体ではあるものの、一方で事業も行うので必ず機能分化していき、それが単なる機能分化ではなく、魂を失うような感覚にならないのかと感じていました。
やはりみんなで参加することが、労働者協同組合の理想的な姿だと思うので、まさにその通りだと思います。資本主義企業の特徴は賃労働です。分業の結果の賃労働によって、構想と実行が分離されていきます。大学生協でも本来は出資をしてその運営に関わるべき学生が主体的でなくなっていくというのは、協同組合の本来の役割を考えると、やる意味があるかという大義の問題になります。だから、その組織が必要なのかということから、常に考えなければいけないと思います。
労働者協同組合も同じで、法律ができて、それに従って組織を作って運営し、意見反映をしているからそれでいいわけではないのです。共同経営者が自分たちも働く形をつくろうとした時、一番やりやすいのは一般社団法人だと思います。非営利型一般社団法人にすれば、出資はできないというデメリットはありますが、基金を作ることができるので、基金をみんなで共同所有する形にして労働者協同組合を作ることは可能だと思います。その方が案外考えながら運営することができるかもしれません。考えることを止めてしまったら、それは協同組合ではなくなってしまうんでしょうね、きっと。
自分でもこの一年間労働者協同組合に関わってみてかんじたことがいくつかあります。もともと磐田で不登校児の居場所を作っていた2人が、労働者協同組合にも興味があるということをききまして、その立ち上げには3人以上の発起人が必要だったので私が3人目として加わることになりました。大学教員をやりながらなので、その2人が頑張っているのをサポートする方向になっていたのですが、先日の理事会でやはり自分も意見を言って関わっていかなければならないと改めて感じたところです。このような気づきは、組織の内部にいると気づきにくく、外からきっかけを作ってもらう必要があります。たとえば、ファシリテーションを導入することは大事だと思います。やはり日本人は自分の意見を言うことが苦手だと思うので、自分の意見を安心して言える場づくり、対話の方法も大事ですがその場をどう作っていくのかについて、かなり工夫しないといけないと感じています。
NPOとの違い
NPO法人と労働者協同組合は似ている部分もありつつ、NPOは代表のリーダーシップで突き進んでいくイメージがあって、労働者協同組合は法律で賃金関係や意思決定の資格などのルールがしっかり決まっているイメージがあるのですが、分かりやすい違いについて教えていただけますか。
法律的には一人一票であったり、非営利目的であったり、NPOも労働者協同組合も基本的に同じでして、大きな違いは出資ができるかできないかということだけだと思います。
もともと地域の中で住民自治や地域自治をしていた人たちが求めてきた特定非営利活動促進法(NPO法)が1998年に施行されたところまではよかったのですが、2000年の介護保険法と2003年の指定管理者制度の影響がやはり大きくて、それによって一部のNPOは地域のために非営利の事業をする組織でありながら、行政からの下請け的な存在に、この20年ぐらいで位置づけられてしまった感じもします。NPO も当初は、自治の精神を持った人たちがきちんとアドボカシー(政策提言)していくことが重視されていたのですが、一部のNPOではそこが実践として抜け落ちてしまったということが、大きな違いになっていると思っています。
ただ、これは労働者協同組合にも起こりうることです。自治の精神をもちアドボカシーをしていくことをやめてしまったら、下請け的なNPOとほぼイコールになってしまいます。
設立の目的や動向
NPOも含めて、違う協同組合同士で、自分たちの協同組合が何者なのかを考えていくことは、よりコミュニティやつながりを作りやすいのかなと、お聞きしながら思いました。
もう一つお聞きしたいのは、労働者協同組合がどのように起こるのかにすごく関心があるのですが、社会的課題の解決に貢献したい人が集まって労働者協同組合ができるのか、もしくは失業や就職困難などで仕事がなく、協同でお金を出し合い仕事を作って、その事業内容が社会的な課題を解決するものに方向が向いていたのか。手段としての協同労働なのか、人手のための協同労働なのか、どちらの場合が多いのでしょうか。
今までの例でいくと、ワーカーズコープは失業者の労働運動から成り立っています。例えば、生活困窮者や障害者などの社会的に弱い立場に置かれた人たちを守りながら、仕事を作っていくことが重視されています。一方ワーカーズ・コレクティブは、今でも生活クラブ運動の一環として、生協とワーカーズ・コレクティブ運動と代理人運動の三本柱でやっていまして、資本主義経済ではない、オルタナティブ経済を作るという発想の下で、障害者や女性でも働きやすいものを作ることを目的に活動しています。
しかし近年、新しい労働者協同組合ができることによって分かり始めたことは、これまでにはないさまざまな類型がつくられているということです。厚生労働省が紹介する労働者協同組合の好事例として、いくつかの新しい事例がYouTubeで配信されていますが、地域課題の解決から成り立っている事例に「労働者協同組合うんなん(島根県雲南市)」があります。地域が小規模多機能自治を推進する中で、地域課題を解決することを上手く組織化し、地域の自治組織から労協法人に移行する形で、自治体の仕事を引き受けている団体です。
一方、「労働者協同組合こども編集部(兵庫県神戸市)」は、カメラマンやライターやイラストレーターなどの本職を持つ人が、子どもたちに自分たちの仕事を体験してもらうなど、課題解決という目的だけではなく活動していたり、「労働者協同組合アソビバ(兵庫県豊岡市)」という団体は「遊ぶように働く!」と掲げて、地域おこし協力隊の人がきっかけになって、自分たちにとって楽しいことをしようと始まったものであったり、仲間同士の居場所を作っていくようなことも、実はできるようになったのではないかと思っています。
なので、今までの「就労機会創出型」やイデオロギー重視の「オルタナティブ型」のように課題解決を第一義的目的にしているところとは別に、「参加重視型」というのが出てきていて、仲間同士で楽しいことをしよう、地域を盛り上げていこう、みたいな感じの団体が結構あります。目的も動向もさまざまな労働者協同組合がつくられはじめているということになります。
それともう一つ、ゼミでも少し関わりがあるのですが、尾山台の「おやまちプロジェクト」などは、社会課題を解決しようと思って組織を立ち上げたわけではないという、そういうNPO的なところも増えてきています。代表の想いが名言ですけど「つながりが先/やることは後」「課題からはじめない/私たちからはじめる」「まちを自分事にする」とか。「異質な人とのつながりが大事」という考えは、つながる機会を作って、気の合った人同士で事業を立ち上げていく可能性があります。労働者協同組合法人も今その一つの選択肢になっているのかなと思います。
自分が思っていた以上に、労働者協同組合はいろいろな形と目的があることを知りました。
そうですね、非常に面白いと思っています。それも法律ができたことで、出資や経営に加えて意見反映が強制的なのは意外と重要だと思います。意見反映って、誰かが意見を聞いて、それを経営に反映させていきましょうという一方通行な感じもありますが、それでも大きな組織で主体的に関われていなかった人たちからすると、法律ができたことによって、自分たちの意見も反映されるとか、もっと意見を出さないといけないとか、個々に考えるようになるという意味で、法も意外と重要な側面を持つと思っています。
他の協同組合に目を向ける機会がなかなかないと思うのですが、「協同組合」という言葉でつながるじゃないですか。日本は他国と違って、法人格にこだわる傾向にあります。もっとその枠を取り払う意味でも、ちょうど国際協同組合年でアイデンティティの話が出ていましたけど、やはり協同組合基本法を作る必要性を感じますね。協同組合基本法があって、その中で好きな法人格を選ぶにしても、みんな基本は一緒だということにならないと、可能性はすごくあるのにもったいないと思っています。
今後の社会への広がり
大学生協も主体となる大学生が求めたからであり、労働者協同組合も多分そうだと思うのですが、2022年に法が制定されたということは、やはり社会全体が求めたことだと思っているので、その労働者協同組合そのものが、この後社会のどのような層に広がっていくのかに興味があります。例えば、今は学生が起業もできてしまう時代なので、大学生自身が労働者協同組合を設立することもできるかと思いますが、どのような層にどのような形で広がっていくのか、どのようなお考えをお持ちですか?
学生もこれからNPO 法人や一般社団法人などの立ち上げや、企業に勤めながらも地域のことに取り組む可能性が高い中で、労働者協同組合の立ち上げも一つの居場所づくりのような形でうまく取り組める可能性があると思うので、柔軟な発想でいかに作れるか、いろいろ試しにやってみるのもいいと思います。自分や相手を知るとか、意見反映はどうすればよいのかとか、共同経営するとは何かを知ることができるという意味では、すごく面白いし可能性がありますね。
今度駒大で講演してもらう予定なのですが、アーバンズ合同会社代表社員の田井さんは、若い時からいろいろと事業を起こし、現在は8人の社員と、労働者協同組合法にとらわれない労働者協同組合的な運営をすることで、働く仲間との対話を重ねて、民主的な運営と平等化のプロセスを実践しています。「崇高な理念を掲げ、単に法人格を取得しただけでは上手くいかない」と論文に書かれています。「コシャリ」というエジプト料理や水たばこ、IT関係など、労働者それぞれが事業を持っていますが、最近だとIT関係は事業高が高いのに対して飲食業は低いという特徴があります。この現状について、事業高の高いIT関係の事業をやっている人からみんなで助け合うことが必要だからという意見がでてきて、全ての社員で利益を等分に分けるようになったそうです。このようなことを学ぶことは働くとは何かを考えるきっかけになるのではないかと思います。私も労働者協同組合に関わって、生きる世界が全く異なる人たちが出会って融合して何かを生み出すことはすごく面白いと実感しているので、ぜひ大学生のみなさんにも体感してほしいと思います。
協同組合が目指すBetter World
「COOP」でつながる世界
IYC2025のテーマが「Cooperatives Build a Better World」であり、全国大学生協連としては、全国の組合員と一緒に「Better World」を考えてみようという企画をいま考えているところです。大学生協は組合員に対しての内向きの組織のように見えて、実は外向きの力があるということを、今日のお話の中でも実感したところです。松本先生が考える「Better World」をぜひ教えていただきたいです。
2014年に1年間イギリスで労働者協同組合の研究をして、アメリカで2018、19年に1週間ずつ調査に行った時に思ったのは、NPOを表現する場合、nonprofitとか、third sectorとか、国によっていろいろな呼び方がありますが、協同組合の場合は「COOP」という言葉で全世界がつながっていて、しかも「協同組合の7原則を知っているよね」という感じで話が通じるんですよね。今まで豊富な活動や共通の用語を協同組合が生み出してきたという意味でも、世界がつながるきっかけを協同組合が作っていけるし、実際に作っていると思います。いまやさまざまなツールの発展で言語を越えることはできるようになりましたが、思想や文化や人種を越えることはまだまだ難しいことだと感じます。その中で「COOP」という言葉があれば、越えられるものがすごくたくさんあることを10年前から感じています。協同組合の可能性について、日本人はあまり意識してない人が多いので、そこに可能性を見出しつつ、自分たちのことを自分事として考えたり、相手を尊重しながら発言したり、そういう自分たちで頑張ってる実践みたいなものを「COOP」という言葉で尊重し合いながら多様な人とつながることができればいいですね。
協同組合の研究を始めて強く感じることは、相互扶助の精神があるからなのか、国内外問わず、協同組合の人たちは懐が深くて、自然と助けてくれる人が多いことです。それは協同組合の実践の中で培われているのではないでしょうか。ソーシャル・ビジネス的な話では社会をよりよく変革すると言いますが、その社会というのは、人によっては良くも悪くもあります。人を尊重すること、人権的な話、教育や平和につながることを、相互扶助的なところから学んでいるというか、鍛えられているのだと感じます。
社会に出る前の学生たちが協同組合で培った、その協同を社会に広げていこうという大学生協の想いが、日本の社会、ひいては世界に与える影響でもあるのかなと、僕自身も考えました。本日はありがとうございました。
2024年11月19日リモートインタビュー
プロフィール
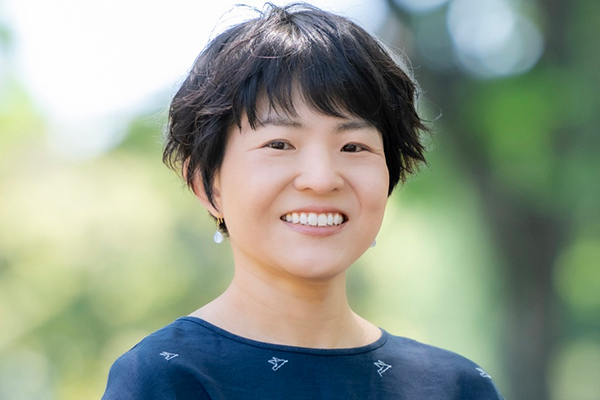
駒澤大学経済学部現代応用経済学科 教授
松本典子 先生
研究テーマは非営利組織や協同組合の経営学。
1980年東京都生まれ。
駒澤大学大学院商学研究科にて、博士(商学)を取得。
2007年に駒澤大学経済学部現代応用経済学科に着任。
日本協同組合学会常任理事、日本NPO学会副会長、日本地域経済学会理事。
一般社団法人協同総合研究所常任理事、駒澤大学経済学部現代応用経済学科ラボラトリ所長、労働者協同組合いわたツナガル居場所ネットワーク理事。
▼researchmap
松本 典子(MATSUMOTO NORIKO)- マイポータル - researchmap