特集記事
「4・14 ~ 4・16 熊本地震(2016)」
~あれから9年、自身の記憶を再認識させるために~
スペシャルメッセージ
あの時のことを振り返って思うことは
熊本大学大学院 教育学研究科 准教授
黒山 竜太 先生

熊本大学大学院
教育学研究科 准教授
黒山 竜太 先生
熊本地震から9年が経とうとしています。私は当時、とある大学に学生相談カウンセラーとして勤めていました。山の中にある不便なところでしたが、その不便さを補って余りある雄大な自然と、人情味にあふれた人たちで構成されたコミュニティを擁した、とても働き甲斐のある素敵な場所でした。
あの時被災し、生き残ることができた学生たちは、今はもう大人になって、それぞれの人生を生きていると想像します。今でも時々、みんなどうしているだろうと振り返ることがあります。そして、災害が起こるたびに、やはり当時のこと、関わった人たちのことを思い出します。それだけ私の人生に、特に大きな影響を与えた出来事であったことは、間違いないと言えます。
人が過去のことを記憶し記録するのは、未来に生かすためです。しかし、記録に残した人の思い(記憶)は極めて主観的なものであり、またすべてを表現しきれないものです。そしてその記憶は日々更新され、本人ですら絶対的かつ同義の価値を持ち続けるわけではありません。さらには、過去の記憶の評価には、「今」の自分自身をどう受け止めているかが、大きく影響します。つまり、過去の記憶とともに、「今」をしっかりと生きていくことが大切なんだろうと思います。
今の学生へ向けたメッセージということでしたが、なかなか難しいですね…何かを感じ取ってもらえたら幸いです。
(2025.02.15)
熊本地震から学ぶジブンゴト
仲間 英(宮崎大/既卒/25年度全国学生委員会/激甚災害支援・防災分野リーダー)

仲間 英
(宮崎大/既卒/
25年度全国学生委員会/
激甚災害支援・防災分野リーダー)
9年前、当時13歳の時私は沖縄に住んでいました。何気なく1日を過ごしていて、テレビをつけたその瞬間、そんな何気ない日常とはかけ離れた映像が映し出されていました。その時の衝撃は今でも忘れません。2011年の東日本大震災の騒動から徐々に落ち着いてきたそんなある日に衝撃的な映像が流れていて目を疑いました。しかしそんな当時の私はジブンゴトとしてその災害を受け入れられませんでした。
しかしその2年後、修学旅行で熊本を訪れた際に、熊本城の石垣が崩壊しているのを見て改めて熊本地震の被害の甚大さ、そして何より実感、ジブンゴトへとつながりました。
このように実際に見ることで私はジブンゴトにつなげることができました。でもそれは少し遅すぎたような気もしています。私たちが住むこの日本は災害大国と呼ばれています。いつどこで災害が起きるかはわかりません。なので、常に災害をジブンゴトとしてとらえておく必要があります。他地域の災害に目を向け、明日は我が身で災害をジブンゴトとして常に考える必要があります。
しかし、先ほど私も経験したように他地域の災害をジブンゴトとしてとらえるのは難しいことだと思います。その中でしっかり目を向け、学び、時には支援しながらジブンゴトしてとらえ、災害に備えましょう。
忘れず、心の内に
浦田 行紘(奈良教育大/既卒/25年度全国学生委員会)
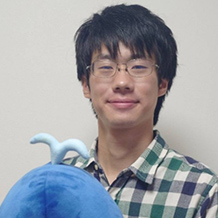
浦田 行紘
(奈良教育大/既卒/25年度全国学生委員会)
本震が自宅を襲った夜、必死に私を叩き起こしてくれた母の姿が、今も脳裏に焼き付いています。自分が「地震」を舐めていたのだと、本気で気づかされました。前震の約8秒、本震の約20秒が、多くの人々の人生を壊したという事実。生活が一瞬で崩れたのだと、避難所の中で夜な夜な考えたものでした。ただ、それゆえに全国各地からの温かい言葉や支援物資の存在に涙が溢れそうになったことも記憶しています。熊本城は天守閣にも入れるようになりましたが、あの時覚えた心からの感謝の想いを私は決して忘れたくありません。いつまでも大切にしたい宝物です。
13歳の僕が出会った“備える心”
髙田 優希(熊本大学/4年/熊本大学生協組織部)

髙田 優希
(熊本大学/4年/熊本大学生協組織部)
被災した当時は中学1年生ですが、今でも地震の揺れには敏感です。発生時は偶然家族全員が自宅にいたため助け合えましたが、誰かが外出中だった場合を想像すると、連絡手段の重要性を痛感します。安否確認の手段を事前に決めておくことが大切だと感じました。また、約3週間にわたる断水を経験し、飲み水だけでなく、歯磨きやトイレなど衛生面でも水が欠かせないことを実感しました。現在では、水や食料を1週間分備蓄し、災害時に家族が別々の場所にいても自分の身を自分で守ることを前提に行動するという意識を、家族で共有しています。