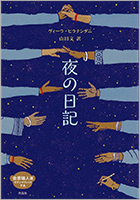あの頃の本たち
「弱さを生きる」山田 文
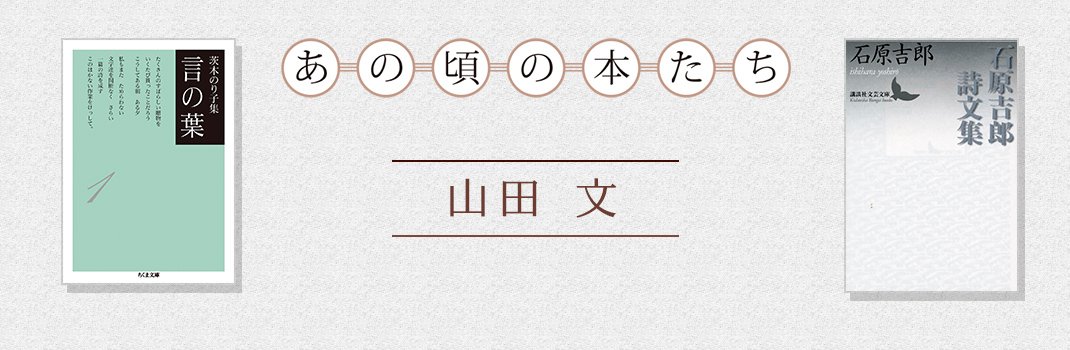
弱さを生きる
山田 文 Profile 関西の郊外にある大型書店でアルバイトをしていたとき、店長のNさんとふたりでレジに入ることがたまにありました。開店直後は人もまばらで、自然と雑談がはじまります。「あのな、あたらしく入ったAくんっておるやんか」Nさんは丸い顔に微笑を浮かべ、いつも恥ずかしそうにぼそぼそと小声で話します。「あの子めっちゃおもろいねん。履歴書の短所の欄にな、“間食が多いこと”って書いてんねん。おもろいやろ? こりゃ採用せなあかんなと思って」
その書店はどこか風通しがよく、社会にうまくなじめない二十代のわたしにも居心地のいい場所でした。
*
書店員時代に同僚との会話をきっかけに読みはじめ、いまも折に触れて読み返す詩人がふたりいます。茨木のり子(1926-2006)と石原吉郎(1915-77)です。なかでも茨木の詩「汲む―― Y・Yに―― 」と石原の随筆「ペシミストの勇気について」は、幾度となくくり返し読んできました。「大人になるというのは/すれっからしになることだと/思い込んでいた少女の頃/立居振舞の美しい/発音の正確な/素敵な女のひとと会いました」―― 「汲む」はそうはじまります。その女の人はいいます。「初々しさが大切なの/人に対しても世の中に対しても/人を人とも思わなくなったとき/堕落が始るのね」。それを聞いた少女の「私」は「どきんとし/そして深く悟りました」。大人になっても振る舞いがぎこちなくたってかまわないのだ。なめらかに話せなかったり、顔が赤くなったりしてもかまわないし、傷つきやすい感受性をそのまま保っていたって問題ない。むしろそのほうがむずかしいのだ。「すべてのいい仕事の核には/震える弱いアンテナが隠されている きっと……」(『茨木のり子集言の葉1』ちくま文庫、pp.136-8)
もちろん、生きのびるために「すれっからし」にならざるをえない人もいるでしょう。図太くたくましく生きたいと願い、そのように生きられる人もいるにちがいありません。けれども、そのような図太さを持ちたくても持てない人や、そもそも持ちたいと望まない人も―― とりわけこれを読んでいる人のなかには―― 多いのではないでしょうか。わたしもそうですし、おそらくNさんやAさんもそうでした。
「ペシミストの勇気について」はシベリアの強制収容所について書かれたエッセイです。収容所という極限の環境のもとでは、人間は均され、「生きのびる」ことだけをもっぱら志向する動物に還元されます。だれかが死に近づけば、ほかのだれかの生きるチャンスが増える。食うか食われるか。死にたくないのなら加害者になるしかない。そんな環境のなかにあって、自分の意思で絶食し、撃たれるリスクの高い列の外側にいつも並んで、最も過酷な労働現場をみずから選ぶ鹿野武一という人がいました。彼のことを書いたのがこの文章です。
「鹿野をもっとも苦しめたのは〔中略〕加害と被害の同在という現実であったと私は考える」。「一人の加害者が、加害者の立場から進んで脱落する。そのとき、加害者と被害者という非人間的な対峙のなかから、はじめて一人の人間が生まれる〔中略〕私が無限に関心をもつのは、加害と被害の流動のなかで、確固たる加害者を自己に発見して衝撃を受け、ただ一人集団を立去って行くその〈うしろ姿〉である」(『石原吉郎詩文集』講談社文芸文庫、pp.98-117)
わたしたちは強制収容所で生活しているわけではありません。いや、ほんとうにそういいきれるでしょうか。もちろん大多数の人は死と隣りあわせの極限状態を強いられてはいませんし、だれかの死がすなわちみずからの生であるような環境に置かれてもいないでしょう。けれども、わたしたちもまた文化や経済や社会や政治のさまざまな規範や圧力によって競争と対立の世界に追いこまれ、加害と被害の流動のなかに投げこまれているのではないでしょうか。加害者になりたくない、あるいはなれないにもかかわらず、絶えず加害者になり被害者になって傷つきながら生きることを強いられてはいないでしょうか。
*
Nさんが店長を務める書店は、どこかそうした競争と対立の論理から外れた場のように感じられました。震える弱いアンテナを持ち、加害者になることをひどく恐れる人たちが、かろうじて居場所を見いだせる場所でした。本の世界には、そうした人たちがよく生きていける余地がすこし残っているのかもしれません―― やさしく、生きづらそうで、いい仕事をする人たちに触れるたびに、いまもそう思います。そして、そういった場がなくなってほしくはないなと心から思うのです。P r o f i l e
略歴(やまだ・ふみ)翻訳者。訳書にヴィーラ・ヒラナンダニ『夜の日記』(作品社)、ミシェル・オバマ『心に、光を。―― 不確実な時代を生き抜く』(KADOKAWA)、アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』(勁草書房)、キエセ・レイモン『ヘヴィ―― あるアメリカ人の回想録』(里山社)などがある。
山田文 訳書