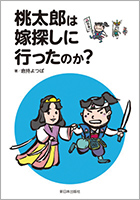いずみ委員の読書日記 181号
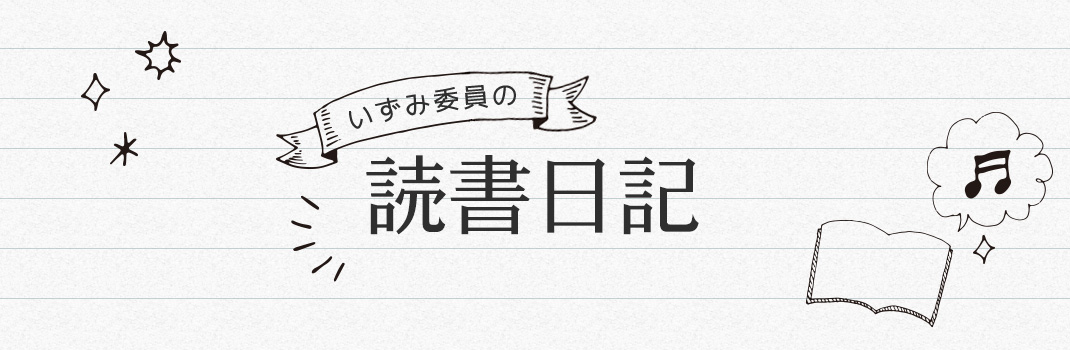
レギュラー企画『読書のいずみ』委員の読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
早稲田大学4年生 力武麗子
九月初旬
 中学生のころから支えられている米津玄師さんの新アルバムに、『わたしを離さないで』(カズオ・イシグロ〈土屋政雄=訳〉/ハヤカワepi文庫)から着想を得た曲が収録されているとインタビューで知った。その曲はちょうどアルバムを手に入れてから毎日寝る前に子守歌のように聴いていた曲だったので、日々をともにする曲をもっと知りたいという思いで文庫を購入。海外文学はあまりなじみがないけれど折り返したばかりの夏休みにはぴったりだ。『わたしを離さないで』購入はこちら >
中学生のころから支えられている米津玄師さんの新アルバムに、『わたしを離さないで』(カズオ・イシグロ〈土屋政雄=訳〉/ハヤカワepi文庫)から着想を得た曲が収録されているとインタビューで知った。その曲はちょうどアルバムを手に入れてから毎日寝る前に子守歌のように聴いていた曲だったので、日々をともにする曲をもっと知りたいという思いで文庫を購入。海外文学はあまりなじみがないけれど折り返したばかりの夏休みにはぴったりだ。『わたしを離さないで』購入はこちら >
九月下旬
 他の本をつまみ食いしながらほぼひと月かけて『わたしを離さないで』を読了した。主人公キャシーが終始読者に過去を回想して語り聞かせる、というスタイルに戸惑いなかなか読み進まない時期もありつつ、じわじわと明かされるキャシーの人生に惹きつけられて読み切ることができた。キャシーの境遇は一見現実離れして見えたけれど、周囲との関係性や葛藤に心のどこかが共鳴したように感じた。ふだんと違う読み味や満足感に圧倒され、もっと海外文学やカズオ・イシグロ氏の本を読んでみたいと思うようになった。
他の本をつまみ食いしながらほぼひと月かけて『わたしを離さないで』を読了した。主人公キャシーが終始読者に過去を回想して語り聞かせる、というスタイルに戸惑いなかなか読み進まない時期もありつつ、じわじわと明かされるキャシーの人生に惹きつけられて読み切ることができた。キャシーの境遇は一見現実離れして見えたけれど、周囲との関係性や葛藤に心のどこかが共鳴したように感じた。ふだんと違う読み味や満足感に圧倒され、もっと海外文学やカズオ・イシグロ氏の本を読んでみたいと思うようになった。ちなみにつまみ食いしていた本の一つは『えーえんとくちから』という笹井宏之さんのベスト短歌集(ちくま文庫)。表題作の朗読をテレビで見てこの本を手に取った。自分の想像の半歩外のような作品が並んでいて、新たな世界の手触りを教えてくれるような一冊だと思った。自分の感じたことをぎゅっと凝縮させてとっておくことができる短歌がやっぱり好きだなぁと思う。『えーえんとくちから』購入はこちら >
十月初旬
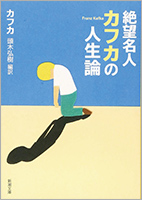 少しだけ秋を感じた晴れの日、友人がおしえてくれたルイーズ・ブルジョワ展に行ってきた。「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」という副題にしびれたことが訪れた理由の一つだ。作品の展示と一緒にルイーズ・ブルジョワの当時の状況や考え、言葉が通常の展示より詳細に記されており、アーティストの考えがふんだんに伝わってくる展示だと思った。深く思索に沈み思いつめていた様子を追っていくうちになんだか既視感を覚えた。なんだろうと記憶を探ったところ、最近読み終えた『絶望名人カフカの人生論』が思い当たった。落ち込みのプロであるカフカの日記や文章を読んでいると、自分のネガティブなんてまだまだひよっこ!と思えてかえって気持ちが浮上したが、そのときと同じような感覚があったのだ。勝手に脳裏で二人を出会わせてひとり納得した。自分の頭の中だけでばたばたしないで一息つける、読書も美術館巡りも自分には欠かせないひとときだなとにんまりした一日だった。『絶望名人カフカの人生論』購入はこちら >
少しだけ秋を感じた晴れの日、友人がおしえてくれたルイーズ・ブルジョワ展に行ってきた。「地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴らしかったわ」という副題にしびれたことが訪れた理由の一つだ。作品の展示と一緒にルイーズ・ブルジョワの当時の状況や考え、言葉が通常の展示より詳細に記されており、アーティストの考えがふんだんに伝わってくる展示だと思った。深く思索に沈み思いつめていた様子を追っていくうちになんだか既視感を覚えた。なんだろうと記憶を探ったところ、最近読み終えた『絶望名人カフカの人生論』が思い当たった。落ち込みのプロであるカフカの日記や文章を読んでいると、自分のネガティブなんてまだまだひよっこ!と思えてかえって気持ちが浮上したが、そのときと同じような感覚があったのだ。勝手に脳裏で二人を出会わせてひとり納得した。自分の頭の中だけでばたばたしないで一息つける、読書も美術館巡りも自分には欠かせないひとときだなとにんまりした一日だった。『絶望名人カフカの人生論』購入はこちら >
千葉大学4年生 高津咲希
10月上旬
 『音とことばのふしぎな世界 メイド声から英語の達人まで』(川原繁人/岩波科学ライブラリー)を読んだ。「ゴジラ」の濁点を取って「コシラ」にすると、何だか弱々しく感じるのはなぜなのか、どうして外国語の発音を習得することは難しいのか……? 音や言葉に関する素朴な疑問に迫る「音声学」の入門書。今まで何となく抱いていた「言葉の音」に対するイメージには、こんな理由があったんだ!と、目から鱗が落ちるとはまさにこのこと!?『音とことばのふしぎな世界 メイド声から英語の達人まで』購入はこちら >
『音とことばのふしぎな世界 メイド声から英語の達人まで』(川原繁人/岩波科学ライブラリー)を読んだ。「ゴジラ」の濁点を取って「コシラ」にすると、何だか弱々しく感じるのはなぜなのか、どうして外国語の発音を習得することは難しいのか……? 音や言葉に関する素朴な疑問に迫る「音声学」の入門書。今まで何となく抱いていた「言葉の音」に対するイメージには、こんな理由があったんだ!と、目から鱗が落ちるとはまさにこのこと!?『音とことばのふしぎな世界 メイド声から英語の達人まで』購入はこちら >
10月中旬
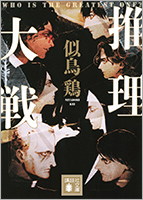 無性にミステリー小説を読みたくなり、以前から気になっていた『推理大戦』(似鳥鶏/講談社文庫)を手に取った。タイトルから、「さあ推理が始まるぞ、正々堂々と真っ向勝負だ!」という勢いが伝わり、ワクワクする。あらすじを読むと、なるほど……とある貴重なお宝を手に入れるため、世界中から超人的な能力を持つ最強名探偵が集結し、推理力を競うようだ。
無性にミステリー小説を読みたくなり、以前から気になっていた『推理大戦』(似鳥鶏/講談社文庫)を手に取った。タイトルから、「さあ推理が始まるぞ、正々堂々と真っ向勝負だ!」という勢いが伝わり、ワクワクする。あらすじを読むと、なるほど……とある貴重なお宝を手に入れるため、世界中から超人的な能力を持つ最強名探偵が集結し、推理力を競うようだ。やはり名探偵たちがあざやかに謎を解決していく姿は読んでいてスカッとする。何より各国の名探偵それぞれがとてもチャーミング。それでいて人間離れした能力を持ち合わせているというギャップもたまらない! 一気に読み進め、物語の結末は…⁉『推理大戦』購入はこちら >
10月下旬
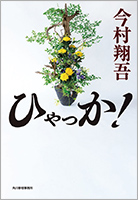 いけばなの展覧会を初めて観に行った。花器に生けたものから、空間いっぱいに広がる大作まで、個性豊かな様々な作品が並んでいる。秋を感じる真っ赤なタカノツメやキツネのような可愛らしい実をつけるフォックスフェイスなど、色鮮やかな植物たちがひときわ目を惹く。初めて名前を知る植物もたくさんあった。
いけばなの展覧会を初めて観に行った。花器に生けたものから、空間いっぱいに広がる大作まで、個性豊かな様々な作品が並んでいる。秋を感じる真っ赤なタカノツメやキツネのような可愛らしい実をつけるフォックスフェイスなど、色鮮やかな植物たちがひときわ目を惹く。初めて名前を知る植物もたくさんあった。率直な感想は「思っていた以上に自由!」だ。葉や茎を籠のように編み込んだり、あえて枯らした向日葵の花を使ったり……驚くのはまだ早い。葉に和紙を貼り付けたり、木の枝や花びらに色を塗ったり、枝にカラフルな結束バンドを結び付けたり……。さらには靴やCD、ペットボトルに卵の殻など、意外なアイテムが次々登場。「それもアリなんだ!」、「その発想はなかった!」と思わされる作品ばかりでとても興味深い。何から着想を得て、何をイメージしているのだろうか……とても気になる。
帰宅後、いけばなをテーマにした小説を探してみた。高校生のいけばな大会を舞台にした『ひゃっか!』(今村翔吾/ハルキ文庫)を早速、読みたい本リストに追加した。『ひゃっか!』購入はこちら >
名古屋大学6年生 後藤万由子
9月某日
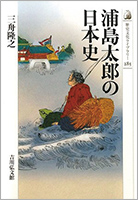 昨日の夜、母とウォーキング中、私が小さい頃に読んでいた昔話の話題になった。
昨日の夜、母とウォーキング中、私が小さい頃に読んでいた昔話の話題になった。「スーパーのレジ横の絵本、嬉しそうに『買って欲しい』ってねだってたわ」
「そういやそうやったな」
笑いながら、「桃太郎」のきび団子って美味しいのかな、だとか、「一寸法師」って最後どうだったっけ、だとか、ずっと喋っていた。
今朝、前に気になってネット書店で注文した『浦島太郎の日本史』(三舟隆之/吉川弘文館)を少し開いてみた。へー、桃太郎と一緒で浦島太郎って全国に伝説あるんだ。海沿いにあるのはわかるけど、まさか木曽の方にもあるとは。中国の思想が丹後(京都)に伝わって、それがいろいろな地域に広まって変化していくところ、梶原先生(『izumi』175号でインタビューした考古学の教授)の考古学の授業を思い出した。
試験勉強があるから休憩を少しだけにしようと思っていたら、30分もたっていた。『浦島太郎の日本史』購入はこちら >
10月某日
そういえば「桃太郎」の話も全国にあるんだよな。古事記の桃の話を思い出して気になったこともあり、これまた前に注文した『桃太郎は嫁探しに行ったのか?』(倉持よつば/新日本出版社)を開いた。えっ桃太郎ってこんなに色んなところにいたの!?︎ 犬山は知っていたけど……。しかも、地域によって主人公の性格はかなり違うし、岡山の吉備津彦の伝説は桃太郎話と全く違うものだったなんて。東北は力持ちだったり中国地方は怠け者だったり。色んな地域の話がまじりあって物語が変化していき、とても奥が深い。何より倉持さんのリサーチ力に驚いた。全国の図書館に問い合わせたり、自ら伝説地の博物館に赴いたり、すごい行動力だ。この本の前のシリーズ『桃太郎は盗人なのか?』(倉持よつば/新日本出版社)を読むのを楽しみに勉強頑張ろう。そうこうするうちに11時になった。そろそろお腹が空いてきた。今日のお昼ごはんは、「桃太郎」(三重県北部にあるおにぎり屋チェーン)のおにぎりと唐揚げにしてもらおうかな。
10月某日
最近S先生(文学部、日本語学の先生)の講義を聴きにいけなくて寂しい。最後に授業を聴いたのは去年だっただろうか。「竹取物語」の授業は面白かったな。もともと興味はあったけど、「かぐや姫」といい日本昔話って勉強してみるとかなり楽しいのかも。夏休みの自由研究、小学校のときは一番嫌いだったけど今なら楽しくできただろうな。来年春から自由研究、やってみよう。

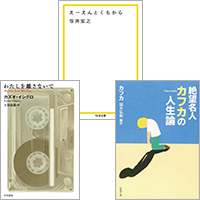 早稲田大学4年生
早稲田大学4年生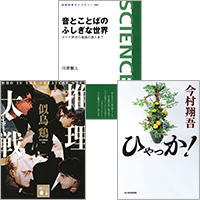 千葉大学4年生
千葉大学4年生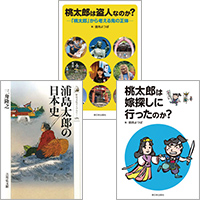 名古屋大学6年生
名古屋大学6年生