読書マラソン二十選!183号
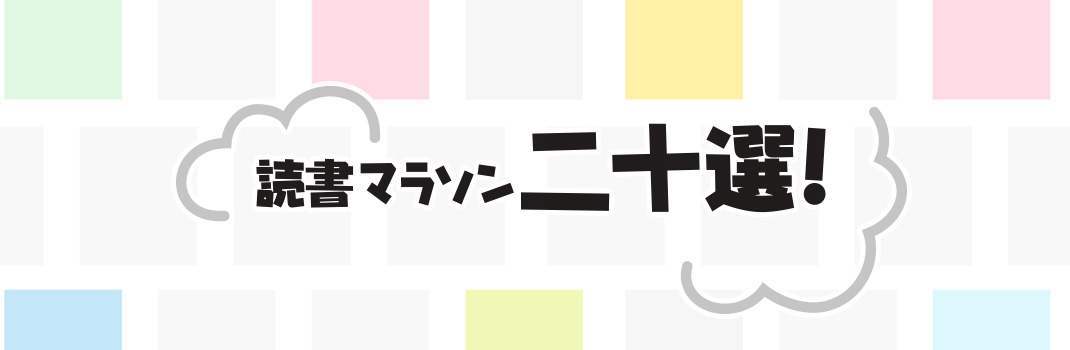
2024年度WEB読書マラソンに投稿が多かった作品
WEB読書マラソンが本格始動して2年目。運用ルールの見直しを経ながらも、日々たくさんの投稿コメントが寄せられ、ますます盛り上がりを見せています。「みんなはどんな本を読んでいるの?」「どんな感想が寄せられているの?」―― そんな声にお応えして、今回は2024年度WEB読書マラソンに投稿された全コメント(約6000件)の中から、投稿数の多かった上位20作品をピックアップ。編集部が選んだ注目コメントとともにご紹介します!-
1位
 『コンビニ人間』
『コンビニ人間』
村田沙耶香/文春文庫購入はこちら > 日常生活でみんなと同じ、集団に馴染めない少し自分は変わり者だけど周りにそれを伝えることもできない、という人に読んでほしい一冊。
主人公は、周りとの違いを感じつつも、ある種の擬態をしながらコンビニで18年間働く女性。白羽という男と同居することをきっかけに彼女の周囲が変わり始め、その過程で真の自分を発見していく。主人公同様に、社会の同調圧力や「正しさ」に押しつぶされず、自分の天命だと思えるほど好きなものにのめりこんでみたい。(九州大学/チャーリーブラウン)
-
2位
 『正欲』
『正欲』
朝井リョウ/新潮文庫 購入はこちら > 「多様性」がおめでたい言葉になっていることに私はイラついていた。同時に、誰も傷つけたくないと思う自分を罪深く感じていた。だって、薄っぺらな多様性を叫ぶ世の中と同じように、私もいつか理解不能な誰かを拒むかもしれないからだ。p.439から読む手が止まった。八重子と大也の摩擦は私の中にあったから。2人の対話が始まりそうな予感にうっすら希望を感じた。誰だって抑圧する側とされる側を行き来している。「あってはならない感情なんてこの世にない。」そう言える強さが欲しい。(西南学院大学/Uka)
-
3位
 『アルジャーノンに花束を〔新版〕』
『アルジャーノンに花束を〔新版〕』
ダニエル・キイス<小尾芙佐=訳>/ハヤカワ文庫 購入はこちら > 物語の道筋は、ほぼすべて作中で示唆されている。そういう意味で、意外な結末が待っているわけではない。しかし、この本が突出して面白いこともまた、疑いようがない。本書はチャーリイの人生そのものの追体験であり、誰もがチャーリイの中に自分を見ることになる。確かに序盤はひどく読みにくいけれど、これはこれでなければいけないのだ。我々が本文に感じる感情は、そのままチャーリイに対する他者の視線の投影である。チャーリイが置かれている状況を想像し、そのことが私とチャーリイを更に重ねるのだ。紛れもない良書である。(東北大学/鷽秋かおす)
-
4位
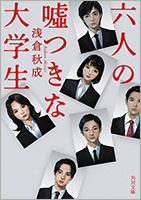 『六人の噓つきな大学生』
『六人の噓つきな大学生』
浅倉秋成/角川文庫購入はこちら > 人は嘘をつく生き物である。その人とどれだけ親しいと思ってもその人の本当の顔は誰にもわからない。六人が塗り重ねた嘘が一つ一つ剥がされ、また一つ一つ嘘が積み重ねられていく。終盤の伏線回収は鮮やかで心惹かれる展開だった。まるで自分もその場にいるのではないかという手に汗握る展開、人間の先入観をうまく利用する伏線、就活の疑問や人間の醜い部分を曝け出すようなストーリー。すべてが六人の大学生たちを輝かせていた。(愛知教育大学/Mal)
-
5位
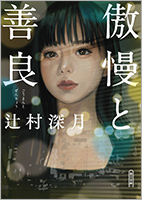 『傲慢と善良』
『傲慢と善良』
辻村深月/朝日文庫購入はこちら > 小さな世界ではある点と点がすべてだと思い、たとえ歪だとしても無理やり線で結んで辻褄を合わせようとしてしまう。一見浅い知識ゆえの仕方ない行動に思えるが、もっと周りを知ろうとしていないのであればそれは傲慢だ。スマホやゲームなどの娯楽の発展で恋愛にのめり込む現代人は少ないが、いつかはそれなりに恋をしてビビッとくるいい人と結婚して子供を産みたいと高望みしている。自分という形に完璧に合わせてくれる人は絶対にいないのに。寄り添うだとか支え合うだとか妥協でものを言う資格は自分にあるのか。その答えを教えてくれる。(名古屋大学/アサ)
-
6位
 『博士の愛した数式』
『博士の愛した数式』
小川洋子/新潮文庫購入はこちら > 数学と記憶障害と阪神タイガース。この結びつけようにも結びつかないようなキーワードが、家政婦の「私」と「私」の息子のるーとと記憶が80分しかもたない博士によって美しく織り成されます。優しい人々による優しい物語です。3つのキーワードのうちどれか1つでも興味がある人にはぜひ読んでいただきたいハートフルな内容です。(愛知教育大学/にょーん)
-
7位
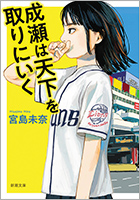 『成瀬は天下を取りにいく』
『成瀬は天下を取りにいく』
宮島未奈/新潮文庫購入はこちら > 自分に正直でまっすぐかつ才色兼備で成績優秀、そして周りの目を気にしない。自分らしさをこんなにも表向きにしている姿に眩しさを覚える。行動力が頭一つ抜けている成瀬だが、その行動のほとんどは誰にでも始められることであり、やってみることの大切さがわかる。好奇心赴くままにたくさんの種をまいて1つでも咲く花があれば良い。失敗してもそれは肥やしになる。こう考える人がありふれた毎日を変える一歩を押してくれる人なのであろう。かっこよさに惹かれた、といった安直な理由でも始めることは本当にかっこいいのだ。(名古屋大学/アサ)
-
8位
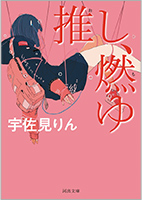 『推し、燃ゆ』
『推し、燃ゆ』
宇佐見りん/河出文庫購入はこちら > 推しは偉大だ。私にも推しがいる。主人公ほどの熱意を持っているとは言えないが少なからず生きる一つの目的になっていることは事実であり、そのような推しを「背骨」と表現したこの物語を忘れることはないだろう。背骨という表現はとてもしっくりくる。誰しも日常を送るためには背骨が必要であり、これが推しの人もいれば仕事の人もいるだろう。背骨を大切に生きていこう。(滋賀大学/ぽてじゃが)
-
9位
 『方舟』
『方舟』
夕木春央/講談社文庫購入はこちら > ある地下施設に閉じ込められた。一人犠牲にすればその人以外は全員助かる。犠牲にするのは殺人犯だ。良心は痛まない。たとえその犠牲となる人が、過去に愛した人であっても。
選択を迫られたときに、その人と共に残る、その人の代わりに犠牲になるという決断ができる人はある意味で狂っていると思う。
わたしはこの『方舟』の中で死んだ。(東京大学/ゆき)
-
10位
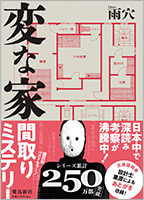 『変な家』
『変な家』
雨穴/飛鳥新社(文庫版)購入はこちら > 「ネット上で話題」では収まりきらない名作ミステリ。
著者・雨穴のもとに届く、どこかが変な間取り図を中心として話題が転換していく。魅力的な助っ人も加わり、いくつかの間取りを見ていくうちに、バラバラであるはずのそれらの家に、不気味な共通点があることに気がついてしまう。その共通点が指し示すものは何か、何のためにその家は「変な家」になってしまったのか、それらを解き明かしたときに、人間の闇に突き当たってしまう。誰を責めることも出来ない感情に苛まれたい人におすすめ。(新潟大学/本を読む看護学生)
-
11位
 『世界でいちばん透きとおった物語』
『世界でいちばん透きとおった物語』
杉井光/新潮文庫nex購入はこちら > 結末に近づくにつれて、「これも伏線!? こっちも!?」と驚くことばかりの物語。この小説を完成させたこと自体天才だと思う。藤崎翔の『逆転美人』と同じように、絶対に電子書籍化はできない小説。紙の本でないとこの小説の感動や衝撃を味わうことはできない。とりあえず読んでみてほしい。今までにない本の美しさを感じることができ、この小説以外に「世界でいちばん透きとおった物語」というタイトルをつけることができないと感じられる。(弘前大学/りゅ)
-
12位
 『告白』
『告白』
湊かなえ/双葉文庫購入はこちら > 章を追うごとに登場人物の人間像が変わっていき、人間の口から出る言葉には事実以外にも自分の都合や保身が混ぜられていることがあるという考えればわかるがふとした時に忘れてしまうような感覚をつかれた気がした。僕自身、本音のような感じを出しながら自分の考えを自分がよく見えるように脚色してしまっているなと感じることがある。告白というのはその人のすべてをさらけ出すのではなく、その人の譲歩できる限りを出しているに過ぎないのだなと思った。(岩手大学/かわなぎ)
-
13位
 『新装版 殺戮にいたる病』
『新装版 殺戮にいたる病』
我孫子武丸/講談社文庫購入はこちら > 2度読み不可避、最終段落までのすべての章が伏線であり、どんでん返しにすべてをかけたエンタメ性が高い作品だった。であると同時に、母性への執着や、人間が本質的に本能的に抱く死への関心を、殺人という刺激的な方法で鮮やかに描かれている点は、芸術的だなと感じた。
違和感をおぼえる一方で、それを見逃してしまったことに悔しさも感じる作品だった。(お茶の水女子大学/バースデーケーキ)
-
14位
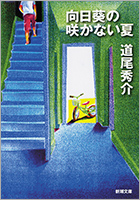 『向日葵の咲かない夏』
『向日葵の咲かない夏』
道尾秀介/新潮文庫購入はこちら > 読み終わってまず、ゾッとした。そして再読後にまた、ゾッとした。「誰だって、自分の物語の中にいるじゃないか。自分だけの物語の中に。その物語はいつだって、何かを隠そうとしてるし、何かを忘れようとしてるじゃないか。」複雑に絡み合ってしまった事件の背景には、登場人物たちの苦しみがあるのではないかと思った。すべてが一気には明らかとなるラスト目が離せず、読む手が止まらなかった。そして、一つの“物語”に終止符を打った主人公の今後の“物語”がとても気になった。(宇都宮大学/げっこー)
-
15位
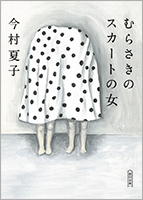 『むらさきのスカートの女』
『むらさきのスカートの女』
今村夏子/朝日文庫購入はこちら > なんなんだろう、この薄気味悪さクセになる。
「わたし」の近所に住む「むらさきのスカートの女」が「わたし」と同じように気になって仕方がなかった。「むらさきのスカートの女」が気になって仕方がなかったはずなのに、いつの間にか「わたし」が気になって仕方がなくなっていた。
なんだろう、この何とも言えない奇妙な感じは……妙に頭に残って、不思議な読書体験になった。(東京農業大学/ふぁくせ)
-
16位
 『ハンチバック』
『ハンチバック』
市川沙央/文藝春秋購入はこちら > 93ページという短めの物語だが、とても長く感じられた。淡々としながら貫禄のある文体で障碍者の性と生を描く。文章を目で追っていくとき、絶えず作者からの冷ややかな視線を感じた。「本当の息苦しさも知らない癖に」というのは作中からの引用だが、自分の特権性を暴かれる読書体験だった。また、「読書」というのは特権性に満ちた行為であると突き付けられ、衝撃を受けた。本を持つこと、ページをめくることが難しい人々がいる。市川沙央に健常者の世界を軽やかに淡々と痛烈に批判され、もっとこの人の物語を読みたいと思った。(お茶の水女子大学/M)
-
17位
 『カラフル』
『カラフル』
森絵都/文春文庫購入はこちら > 自分が見ている世界、感じている世界は一面的で、実はとてもカラフルなもの。頭では分かっていても、日々の積み重ねや感情の流れの中では、黒は黒かグレーにしか見えないと思ってしまう。人生は身体を借りたホームステイと捉えて、多面的に考えられたら、もっと生きやすい世の中になるんだろう。 でも、主人公のように一度死ななきゃ、やっぱり気がつけないのかなとも思った。(龍谷大学/本好き)
-
18位
 『かがみの孤城』
『かがみの孤城』
辻村深月/ポプラ社購入はこちら > 読むのは二度目。確認したら最初に読んだのは高校に入学する年の四月二日。夢いっぱいの高校生活が始まるほんの数日前であった。中学校までの私は友達がたくさんいた。しかし、高校ではあんまりできなかった。高校時代、休み時間は教室の隅で本を読んで過ごした。だからだろう。以前読んだときよりも、この本に書かれていることにより共感できた。思い返せば、結局、高校を一日も休まずに卒業できたのはこの本を読んでいたからな気がする。思わぬところで人生に役立つ。それが小説だなと思った。(同志社大学/おかず)
-
19位
 『流浪の月』
『流浪の月』
凪良ゆう/創元文芸文庫購入はこちら > 二人の居場所は普通からのシェルターであった。優しさが人を傷つけることはよくあるテーマだが、普通が加害者であるとしたら私たちは自分自身の普通の定義を疑うことになるだろう。著者は、二人の関係が世間から見れば不安定で居場所が無いから流浪と名付けた。私はこの流浪に普通の投げつけあいを感じた。更紗は世間の普通により苦しんできた側ではあるが、更紗自身も無意識に自分の普通を他者に押しつけていたのである。『傲慢と善良』と話題は被るが、結局人には普通を原点とした傲慢さと善良さがありそれは対人により決まるのだ。(名古屋大学/DB好き)
-
20位
 『氷菓』
『氷菓』
米澤穂信/角川文庫購入はこちら > そう分厚くないミステリ小説の中で展開される、学校を舞台にした幾つかの謎解きと一つの古典部にまつわる過去。目の前にあるヒントをさらっと駆使して淡々と解決する“省エネ”主人公・奉太郎の謎解きショーは、スパッと読めるのに満足感があり、ミステリ初心者にも忙しい誰かにも、おすすめするのにうってつけの一冊です。(東京都立大学/san)



