読書マラソン二十選! 173号
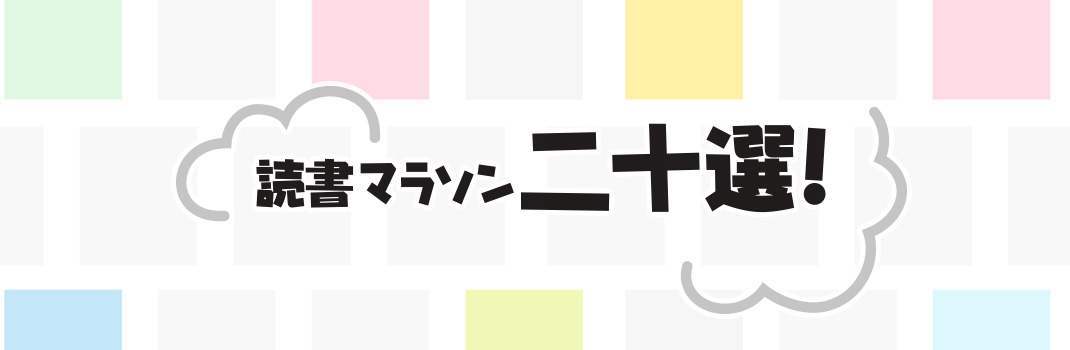
新学期号からご紹介してきた第17回全国読書マラソン・コメント大賞、ナイスランナー賞授賞作品のコメント紹介は今回が最後です。小説、評論から専門書まで、まだまだあるたくさんの素敵な作品とコメントの中から、選りすぐりの20点をピックアップしました。
※次号(2023年新学期号)からは、第18回全国読書マラソン・コメント大賞の授賞作品をご紹介する予定です。どうぞお楽しみに!
-
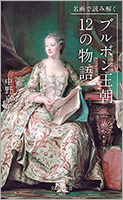 『名画で読み解く
『名画で読み解く
ブルボン王朝12の物語』
中野京子/光文社新書 「ブルボン朝」という王朝は、一般にどれだけ知られている言葉なのか。「ルイ13世とか14世とかがいた王朝だよ」と言うとようやく「ああ何か聞いたことある、ベルサイユ宮殿とか?」と。まあ、そんな感じ。
ブルボン朝は、250年間王朝として存在した、ヨーロッパ名門中の名門。みんなが知っているフランス革命以前も以後も様々な人物が活躍し、歴史に影響を与え続けている。他国は二の次。ただフランスにのみ注目して、この王朝を見てみよう。世界史を知らない人にはその入り口に。学んだ人は、さらに深く学ぶきっかけになると思う。(九州大学/きむ)
-
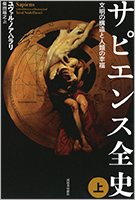 『サピエンス全史 上・下』
『サピエンス全史 上・下』
ユヴァル・ノア・ハラリ〈柴田裕之=訳〉/
河出書房新社 ヒトは未来を思い描くことができる。ヒトは神を信じることができる。しかし、ヒトは地球を幸せにすることができない……。
誕生から様々な革命を経た人類が今、直面するのは核戦争、地球温暖化、パンデミック。「幸福」のために何をすべきなのか、誰も知らないのではないかと感じていた。そんな時、この本の著者・ハラリの言葉が胸に刺さった。「『私たちは何になりたいのか』ではなく『私たちは何を望みたいのか』」
地球の「幸福」を望むこと、それが我々人類にできる最上の幸福への第一歩であることをこの本は教えてくれたのだ。(同志社女子大学/西村寧々)
-
 『ロビンソン・クルーソー』
『ロビンソン・クルーソー』
デフォー〈唐戸信嘉=訳〉/光文社古典新訳文庫 独りで暮らしたい。複雑な人間関係や形式的な平等主義に嫌気が差し、このような思いを抱いた経験は誰にでもあるだろう。その意味で、難破の末に漂着した無人島でのロビンソンの生活は憧憬の的かもしれない。住居の確保や家畜の飼育などを通じて、ロビンソンは孤島での安定した生活を実現できたからだ。しかし、家畜の合理的な飼育や生活品の分散保管などは、プランテーション経営で得た経験に依るところが大きいと思う。こう考えると、独りで暮らすことは不可能だということになる。殊更、他者との学びは重要な役割を果たすと言えよう。(慶應義塾大学/大天丼返し)
-
 『黄泥街』
『黄泥街』
残雪〈近藤直子=訳〉/白水Uブックス いったい何を読まされているのだろう、という混乱にはじまる。
機械工場と共にある、薄汚れた幻のような街。その街の物語が語られ、どこへともなく消えていく。街には糞尿の汚泥。悪臭。跳梁する鼠やゴキブリ。人も動物もモノも全てが膿みくずれ蛆が湧いていく。溶け出すのは肉ばかりではない、ありとあらゆる境界だ。個人の境界、時間の境界。果ては生と死さえも同化し、区別は意味をなさなくなる。
混沌を煮詰めた滅びの物語なのに、不思議と後味は爽やかだった。
いったい何を読まされていたのか。わからないまま一冊分の爪痕が残される。(金沢大学/深緋)
-
 『先生はえらい』
『先生はえらい』
内田樹/ちくまプリマー新書 これまでに出会った先生たちが私に教えてくれたと思っている事柄のほとんどは私の内面での解釈にすぎず、それらは彼らが本当に言いたかったことではないかもしれないが、児童生徒が先生の主張を様々に解釈できる余地があることで、多様な価値観が生まれるのだと思った。先生から学ぶことは科目の知識が多いと思っていたが、先生という存在自体からも学べることはたくさんあり、良い先生や偉い先生だったかどうかは、その先生の下を離れた後で回顧的にわかることなのかもしれないと感じた。(法政大学/クルリ)
-
 『愛するということ』
『愛するということ』
エーリッヒ・フロム〈鈴木晶=訳〉/紀伊國屋書店 「愛する」ということが一体何を意味するのか、なんて今まで考えたこともなかった。しかもそれが訓練して身につけなければいけない能力だったとは……。「大学を卒業して職業に就いたら、いずれは家庭を築きたい」なんて安易に考えていたが、実際に家庭を築く前にこの本に出会えて良かったと思う。数年後、ある程度人生経験を積んだら、またこの本を読み返して、自分を、家族を、友人を、他人を、愛することができているのか、問い質してみたい。(名古屋大学/佃煮)
-
 『図面でひもとく名建築』
『図面でひもとく名建築』
五十嵐太郎、菊地尊也、東北大学/丸善出版 私は建築学生ではないが、建物を眺めるのは好きだ。お金のない大学生にとって、散歩するというのはもっとも安上がりで刺激的な趣味だと思う。
この本には有名どころの建築が載っている。詳しい人なら知っているものが多いだろう。だがこの本は、まだ知らない人こそ楽しめる。右のページには建築の図面が、そして問いが載っている。この建築がどうすごいのか、ヒントを元に考えてみよう、というわけだ。
ページをめくると、どこの建築だったかの答え合わせと、どんな意図があるかの解説がある。解説を読むと尚更、この目で見てみたくなる。(京都大学/夕凪)
-
 『東洋天文学史』
『東洋天文学史』
中村士/丸善出版 サイエンス・パレット 古代の文明発祥から現在に至るまで、人々は星空を見上げてきた。そして、星を航海の道標や暦の作成や占いに用いた。昔の人々にとって、星は興味の対象だけでなく、生活に密に関わるものだったに違いない。
星を見るとき、多くの人は綺麗だと思うに留まるだろう。しかし、この本を読んでから星空を見上げれば、きっと、自分たちと同じように星を見上げる昔の人々の姿が思い浮かび、彼らと繋がれたように感じるだろう。
本からも星からも時の流れを感じるという滅多にない体験をした。(広島大学/桜橘)
-
 『カラフル』
『カラフル』
森絵都/文春文庫 「カラフル」という題名は自分の色、世界の色を自分で決めつけなくていい、自分が思った色と違ってもいいんだ、というメッセージに聞こえた。主人公が生き方を変えていったように、誰にでも人生の転機は訪れる。自分で思い込んでいた色とは違う色になっていくことだってある。周りの色も自分の色もどんどん、どんどん変わっていく。一番悲しいことは、世界をその色だと疑わないことなのかもしれない。このお話を読んで、もっともっと人生をカラフルにできるとわかった。そして変えられるのは自分だけであることも。(愛知教育大学/アップルパイ)
-
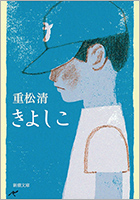 『きよしこ』
『きよしこ』
重松清/新潮文庫 小さいころ、本を読むときに読み間違いはしませんでしたか。
クリスマスソングでよく流れる「きよしこの夜」を「きよしこ、の夜」と勘違いが物語の始まり。きよしこは我が家にやってくる―― 。そんな名前のやついるわけない。主人公のきよしは吃音で思ったことをうまく伝えられない。イブの夜にくる「きよしこ」には自分の気持ちを打ち明けられた。だれかに何かを伝えたいとき、抱きついたり、手をつなげば伝わる。君は独りぼっちじゃない。言いたくても言えないとき、言葉以外でも何かは伝わると思うようになりました。(新潟大学/ふ)
-
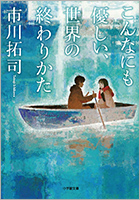 『こんなにも優しい、世界の終わりかた』
『こんなにも優しい、世界の終わりかた』
市川拓司/小学館文庫 世界の終わりという様々な劇的な発想をしやすい設定の中でここまで心躍ることなく落ち着いて読み進めることができるのは、ストーリーの静けさのみならず、それを伝える言葉の取捨選択が的確であったが故だと考えた。フィクションであると分かっていながらも、登場人物があたかも生きているような言葉の使い方や言い回しで独自性を放っているからこそ、いい意味で世界の終わりにそぐわないストーリーの世界観がノンフィクションの香りを醸し出すのではないかと考え、この作品においてはどの一要素が欠落してもいけないものであると感じた。(日本福祉大学/珊瑚樹茄子)
-
 『キリン』
『キリン』
山田悠介/角川文庫 「女性は“母親”になると、自分の仕事ではなく、自分の子どもで評価されるようになる」小説を読んで、教授がジェンダーの授業で語った言葉を思い出した。
物語の中で、女性たちは理想の子どもを産み育てて「成功者」となるため、容姿端麗・高学歴・高収入の男性の精子を落札し、酷烈な子育てを強行する。「誰の子どもを産みたいか」ではなく、「どれくらい完成度の高い子どもを産むか」に女性たちが夢中になる。約10年前に出版された本だが、女性の人生・子育てに対するプレッシャーと医療技術が高まる今、物語のリアリティに震撼する。(立命館大学/涼)
-
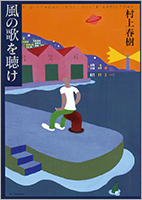 『風の歌を聴け』
『風の歌を聴け』
村上春樹/講談社文庫 私の純文学の始まりは村上春樹であった。
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」この書き出しに心を奪われてから三年、気付いたら〈僕〉と同じ大学生になっていた。鈍く輝く、気だるく寂しい大学生の青春をこれ程爽やかに描ききった小説には未だ出会えていない。
文面の多くを占める登場人物たちの会話には「空白」が隠されている。読者はその空白を思い思いに埋める。思いやり、冗談、皮肉、そして悲しみ……。
情報の氾濫した現代社会、解釈の自由と喜びを味わうバカンスのような読書体験を是非。(東京工業大学/エフ)
-
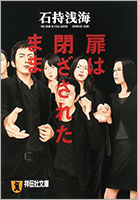 『扉は閉ざされたまま』
『扉は閉ざされたまま』
石持浅海/祥伝社文庫 「解かれてはいけない」最後の最後まで私は犯人の気分だった。倒叙ミステリーと呼ばれるこの小説は、冒頭から犯人がわかった状態で物語が進んでいく。トリックも全てわかることで、つまらないと感じる人もいるかもしれないがむしろその逆で、気づけば犯人の気分だ。ページをめくる度にトリックが暴かれるのではないかというドキドキと、探偵によって華麗に推理が進められるとつい探偵が憎くなる。犯人がわからない状態で探偵となり、トリックを暴いていくのも良いが、たまには犯人の気分になってみるのも悪くないのかもしれない。(法政大学/h)
-
 『蜜蜂と遠雷 上・下』
『蜜蜂と遠雷 上・下』
恩田陸/幻冬舎文庫 文字から物語を辿ると同時に、載っている曲を実際耳で聴くことにより、立体的に物語を想像することができた。それぞれの登場人物(演奏者)が性格や特徴に合わせた曲を弾いており、一人ひとりが独立して異彩を放っていると感じた。
風間塵の衝撃的な演奏、トラックの上でピアノを奏でる心地良さ、天才肌だと実感させられる絶大なる集中力には、私も呼吸が浅くなるほど興奮した。また、栄伝亜夜においては自身の課題に対する張り詰めた緊張感や独特なマイペースさに感情が振り回されつつ、成長していく姿に心動かされた。(横浜市立大学/ののせ)
-
 『シンプルに生きる』
『シンプルに生きる』
ドミニック・ローホー〈原秋子=訳〉/
講談社+α文庫 私の悪い癖とは「ハマりやすく、すぐに貢ぎ、飽きてしまう」ことである。具体例としてはアイドルにハマり、写真などを買いまくり、別の推しを見つけ飽きたことが複数回ある。一人暮らしを始めその癖に拍車がかかり、気づけば部屋は物だらけで嫌な気持ち(※貢いでいる瞬間はとびきり楽しい)。軸決めてしっかりせんかい! ということで本屋に行き出会ったベストセラー。一読し、私はこの本に忠実に生きることに決めた。悪癖に対しては「大好きなものだけをとっておくと心に決める」というお言葉を頂戴し、現在進行中である。目指せシンプル。(法政大学/コミタン)
-
 『幸せについて』
『幸せについて』
谷川俊太郎/ナナロク社 谷川氏が生み出した言葉の数々は、余計なものをまとわない人間のありのままの瞬間が切り取られたようです。「幸せ」という人間にとって大きなテーマを四方八方から感じられる本でした。私は、他の動物が子孫を残すために命を使うのに対し、人間だけが思考し幸せを追い求めるために命を使うことに疑問を持っていました。本の中にある様々な詩を通して、「幸せ」という考え方自体が人間の生んだ身勝手なのかもしれないと感じました。大学生という自分自身や人生に向き合う時期にこの本に出逢えて良かったです。(広島大学/しろろ)
-
 『暇と退屈の倫理学』
『暇と退屈の倫理学』
國分功一郎/新潮文庫 昨年から続くコロナ禍の影響で、今年も暇な時間が多かった。緊急事態宣言が発令し、オンライン授業も続いた。私は家に閉じこもって惰眠を貪った。非常に退屈だった。ふと、なぜ私は退屈しているのか、なぜ人は退屈するのか、そんなことが気になった。睡眠はばっちりで、食事にも満足している。動物としては、健康で、食べるものが十分にあれば幸福であるはずなのに、なぜか退屈だと感じる。そんな時に母から「暇なら勉強なり読書なりしろ」と言われた。正論である。そのとおりだ。故にこの本を手にとった。良い退屈のお供になった。(立命館大学/じろ)
-
 『ぼくはイエローでホワイトで、
『ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー 2』
ブレイディみかこ/新潮社 社会を信じることは、「あるコミュニティの中で共に生活している人々の集団」を信じることである。
これは、この作品を読んで一番印象に残っている内容だ。社会に対する信頼度が低いと、人やものを排除してしまうことがある。社会を信じるために必要なことは何だろうと考えさせられた。またこの作品を通して、多くの社会問題の存在に気付かされてきた。“ぼく”が親離れしていくように、私も作品から学ぶ受け身の姿勢ではなく、作品から離れて自分なりに社会問題について考え続けていきたいと感じた。(東京学芸大学/蜜柑)
-
 『絶叫委員会』
『絶叫委員会』
穂村 弘/ちくま文庫 著者の短歌を読もうと思ったのに、ついついはまってしまいました。エッセイなのかと思えば、創作としか思えない浮ついたエピソードが出て、やっぱり創作かと思って読み続けると、選者として出会った短歌や実在する本からの引用が出てきて、本当なのかもしれないなとずいぶん惑わされました。現実との距離感がとても心地よいです。独特のセンスについついにやけてしまうので、人の多いところで読むことはお勧めできません。(東京工業大学/有閑マダム)




