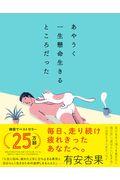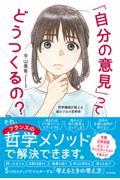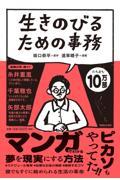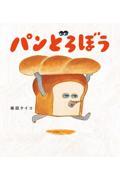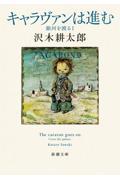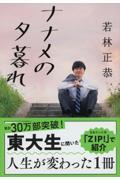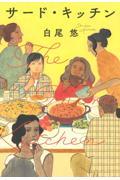今月のナイスコメント(2025年2月)速報
2025年4月7日現在
【ナイスコメント:6件】図書カード1000円プレゼント!
書名クリックで、情報・オンライン注文へ
- コメント:
- インターンや企業説明会で必ず設けられる質問の時間。もし積極的に手を挙げる学生がいたら、他の人はその学生に対してどう感じるだろう。「うわ、意識高い」と思う人が多いかもしれないが、もちろんそれは純粋な褒め言葉ではない。
出る杭は打たれる。それが現代の若者の暗黙のルールであり、私もそれに従うように生きてきた。しかしこの本を読んで、そんなルールこそが個人の能力の発揮を阻んでいることに気づいた。ESを書くときも、答えはネットの中じゃなく「私らしさ」の中にある。他人と違うことを恐れないための勇気をもらえた。
- ペンネーム:
- 詩暢
- 大学・学年:
- 京都大学 1年
- 書名:
- 死刑について
- 著者:
- 平野啓一郎
- 出版社:
- 岩波書店
- コメント:
- 犯人を一生ゆるさないことと、死刑を求めないこと。これらが両立可能だとする一文にはっとする。死刑制度への賛否と、被害者のゆるしを結びつけ、画一的な被害者像を形成していた自分に気づかされた。被害者への視点が日本では弱い、という指摘が鋭く刺さる。
憎しみの連帯ではなく、優しさをもった社会を、という主張には共感できた。だが抽象度が高くなることで何か見落としているのでは、と少しモヤモヤもした。被害者の感情と、国家の制度との間にあるべき「何が正義か」という問いに、自分なりの答えを見出すための鍵がある気がする。
- ペンネーム:
- あげぱん
- 大学・学年:
- 名古屋大学 4年
- 書名:
- 政治的に無価値なキミたちへ
- 著者:
- 大田比路
- 出版社:
- イースト・プレス
- コメント:
- 大学の学費から法を守り、働く理由まで、実感だけが詰まったパンドラの箱。著者の政治的立ち位置と諸外国の状況という前提を共有してから話が始まるので、インターネットで「日本おしまい」みたいな議論を見ているだけでは分からない、不自由さと不平等のリアルがあります。最終章には希望があるので元気なときに一気読み推奨。
- ペンネーム:
- くりごはん
- 大学・学年:
- 北海道大学 2年
- 書名:
- あやうく一生懸命生きるところだった
- 著者:
- ハ・ワン 岡崎暢子
- 出版社:
- ダイヤモンド社
- コメント:
- 社会によって作り出された、こうあるべきという型に、無理矢理自分を押し込んでいる人は多いのではないだろうか。○○さえすれば幸せになれる。他人との比較で成り立つこの幸福幻想には果てがない。そんな中で著者は語る。生き方に同じものはなく、すべてユニークなのだと。遅れても、理想と違っても、失敗ではない。立ち止まってみることを提案してくれる。全体的に緩く脱力した雰囲気のあるこの本には、私たちが掬い取れていない大切な見方がたくさん散りばめられている。読むと肩の力が抜け、自然と笑顔になれる。
- ペンネーム:
- さつまいも
- 大学・学年:
- 大手前大学 1年
- 書名:
- ここで唐揚げ弁当を食べないでください
- 著者:
- 小原晩
- 出版社:
- 実業之日本社
- コメント:
- この本をひとことで表すと「ありのまま」がぴったりだと思う。自分の拙さ、愚かさなど、大抵の人があまりさらけ出したくないと思っているであろう部分が、飾ることなく書かれているエッセイである。文章を書くとなると、よく見せたいという心理が無意識に働いてしまい、きれいごとばかりが書かれたものになってしまいがちである。しかし、この本はそうではない。良い意味で肩の力が抜けているので、気楽に読むことができるのだ。自分の失敗も許せるような気になれる。日々の生活のそばにずっと置いておきたい本である。
- ペンネーム:
- ねいろ
- 大学・学年:
- 愛知教育大学 3年
- 書名:
- 「自分の意見」ってどうつくるの?
- 著者:
- 平山美希
- 出版社:
- WAVE出版
- コメント:
- ちょうど卒論の内容に悩んでいたときに出会った。この本では著者がフランスの哲学的思考を実体験を中心に分析し、自分の意見を作る方法を5つのステップに分けて分かりやすく説明している。特に問いの立て方については、「なぜ必要なのか?」「どんな状態?」のようにどういった部分に焦点を当て思考を組み立てればよいのかが例示とともに説明されていた。試しに卒論のテーマでやってみたところ、びっくりするくらい案が出てきた。卒論のテーマ決めに困っている人や授業のディスカッションが苦手な人にもぜひ読んでほしい。
【次点:11件】
書名クリックで、情報・オンライン注文へ
- コメント:
- 「6つの短編を好きな順で読んで良い」という試みが何より面白い。その紹介に惹かれて買ったのだが、期待を超える面白さだった。6つの短編はひとつひとつがただ面白いだけではなく、繋がっている。順番が指定されていないのに、どこから読んでも繋がりがある。よくこんなものを考えたなと素直に感嘆した。特に物語の舞台が1つではなく2つあり、それらが対称的になっているのは秀悦である。私は前から1つ目を最初に読んだ後、6つ目を次に読んだのだが、舞台は異なるのに不思議な親和性を感じ、その美しさに感動した。良かった。
- コメント:
- 将来の夢のモヤモヤが一気に解消され、進むべき道がスッキリすることができた本。
夢はあるけど、頭の中でモヤモヤしていて実現できそうにない。そんな不安を抱えながらこれまで生きてきた。その霧をハッキリ見える方法がこの本には書いてある。読み終えたあと、早速その方法をやってみると、本のように夢に対する迷いが消えた感じがしたのだ。「こんな考え方があったのか…」と、自分に衝撃が走った感覚を得ることができた。この本に登場するジムが「否定すべきは《己》ではなく、己が選んだ《方法》のみである」は胸にぐさりと刺さった。
- コメント:
- とにかくパンの匂いがする!何故だかわからないけれど、読んでいるとどこからともなくパンの焼けた香ばしいかおりが漂ってくる。よく考えると絵本を読むのは小学生以来かもしれないが、絵本って、何歳になっても読んでいいんだなぁと気付かされた。小さい頃にはきっとなかった観点でも、物語を楽しめるのが嬉しい。温かなタッチの美味しそうなパン達と、軽快でクスリと笑える文章に大人でもこころくすぐられるに違いない。忙しい日常を気づけば忘れ、登場キャラに何だかぽかぽかと癒されながら、私もすぐさまパン屋に駆け込みたくなった。
- コメント:
- 耳馴染みや漂う雰囲気、浮かぶ情景など色々な観点で好きな言葉がありますが、時期によってその“感度”に波があります。“キャラヴァン”は好きな言葉の一つですが、ここまで意識に達したのは初めてです。恐らく初めての出国を控えているからだと思います。辞書的意味には旅をさせておくとして、私にとってのキャラヴァンは“何にも属していない・保護されない、ある種の宙ぶらりん状態”を連想させるものです。私はある意味それを求めていたように思うのですが、思ったよりタフなことであるみたいです。この本を携えて出国するでしょう。
- コメント:
- これは、私だ。本を読んで初めてこんな気持ちになった。
どうして思い切って言いたいことが言えないんだろう、どうして思い切って楽しむことができないんだろう。他人の目が気になるから??
『他人の目を気にする人は、“おとなしくて奥手な人”などでは絶対にない。』
考えすぎてしまう、という若林さんの言葉が、みんなみたいになれなくて自分は惨めで可哀想なんだ。と自己防衛した心に、ガツンと衝撃を与えた。
- コメント:
- 私は大学生から一人暮らしを始めて、親からの仕送りと自身のアルバイトの収入で生活を送っている。クレジットカードを作るとき、親から「リボ払いだけはしないように。」と言われた。
この本は、お金にまつわる悩みを抱えた人々が交差する小説で、リボ払いに関する話は第一話に書かれている。他にも、投資の失敗や奨学金の返済など、自身にも関わりうるお金のエピソードがあった。色々なお金の使い方、増やし方があることを知ったが、お金に関するうまい話なんてなくて、地道に働いてコツコツ貯金するのが私には向いていると感じた。
- コメント:
- 脳科学の視点で笑いを探る試みは、まるで人間情動の秘密の扉をこじ開けるかのようだ。大阪と東京の笑いは、単なる地域差に留まらず、各々の文化と神経回路が奏でる独自のリズムを感じさせる。さらに、fMRIの厳格な制約下では、笑いは絶対に封じ込めねばならない。大きく開かれる口や横隔膜の躍動という自然の暴動が、精密な装置内で抑制される――それは、笑いという普遍現象の奥底に潜む探求心と、技術的挑戦への真摯な問いかけを象徴しているようだ。
- コメント:
- 「困った。全然不幸ではないのだ。」
どういうことだ。不幸ではないことに不満を抱くなんて。冒頭のこの文に惹かれて、私はこの小説にのめり込んでいった。
優子というバトンを懸命に繋げていった人たちの愛情が、彼女を思いやりあふれる人にしたのだと思う。多感な時期の家族の変化を、すぐに受け止めることはきっと難しい。それでも彼女はもらった愛情を決して忘れない。
読みながら、自分の周囲の人のことを考えてみた。私も様々な形で、たくさんの人にリレーされてきたのだ。折に触れて、この本と、人とのつながりを思い出していきたい。
- コメント:
- 個人を構成する要素の一つとして、言語も含まれると思う。話す言語が変われば、声のトーンだけでなく性格まで少し変化するような人もいる。
この小説では、故郷の国を失った女性・Hirukoが、同じ母語を話す人を求めて旅に出る。これは、かつて母語に結びついていた感情や、忘れてしまった自分自身を探す旅でもあると感じた。留学に行き、日本語を話す時間が減った経験のある人なら共感できる一冊ではないか。
旅の途中で続々と増えていく仲間も個性が豊かで、わくわくする。夢中になって読んだ。3部作ということなので、続きも要チェック。
- コメント:
- 「俺のようになるな」
テストで悪い点をとってきた息子に対して、ちゃんと勉強しないと俺のような賃金の低い仕事しかつけないぞ、という意味で言われたセリフだ。
私はこのセリフを言葉の通り受け取り、自分を反面教師にしてお前は立派な大人になれよ、という意味で深く考えず捉えた。しかし、中学生の息子は「このシチュエーションが悲しい」と涙する。テストの点が悪かったとか、父親に怒られるとか、そんなことよりもっと広い視点で物事を捉えられていて、私は自分が恥ずかしくなった。
- コメント:
- 1998年のアメリカに正規性として留学した一人の日本人大学生の話。大学生活を送る中で、主人公は「サード・キッチン」というマイノリティにとってのセーフスペースで日常の差別や歴史問題に向き合い、ひいては自分自身を発見していく。主人公のように海外の大学で留学したことはないが、私も自身の大学寮で留学生とよく交流しているため、身につまされた。特に、自分自身が主人公と同じように日本の戦争や歴史、つまり加害者としての側面を軽視してないかという部分は重く心にのしかかった。これから留学する/した人に読んでほしい作品。