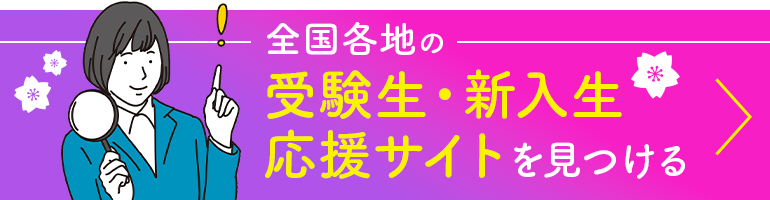受験生(高校生)保護者座談会@東洋大学(2024年開催)
多様化する入試方式を活用することでチャンスを掴む
近年、大学の入試方式が多様化しています。一般入試や推薦に加え、AO入試や共通テスト利用入試、学校推薦に学力試験が組み合わされた入試など。大学によっても異なり、初めは困惑するかもしれませんが、うまく活用できると志望大学の合格の可能性が高まります。今回は、受験生の保護者と現役大学生にお集まりいただき、大学・学部選びや受験勉強、入試方式に関するお悩みや実情を伺いました。

〈参加者〉
- 大澤 智子さん
(東京都立高等学校 保護者) - 山形 則子さん
(東京都立高等学校 保護者)
- 岡 早紀子さん
(東京都立高等学校 保護者)
〈学生〉
- 細川
知幹 さん
(東洋大学 生命科学部 生命科学科3年生) - 三宅 千枝里さん
(東洋大学 文学部 国際文化コミュニケーション学科3年生) - 清水
遥日 さん
(東洋大学 経済学部 総合政策学科2年生)
〈講演者〉
- 東洋大学生協 理事長
鈴木 道也さん
Contents
質問会
受験生の保護者座談会
現役学生からのメッセージ
東洋大学の特徴と入試方式
- 東洋大学の特徴
-
- 130年以上の歴史がある総合大学。
- 4キャンパス(白山、赤羽台、川越、朝霞)、14学部、49学科・専攻を有する。学生数は3万人以上。
- 2017年に開設した「情報連携学部」では、最先端のコンピュータ・サイエンスを基盤としながら、文・芸・理で連携し、組織や社会を変革できる人材育成を行なっている。
- 駅伝をはじめスポーツに力を入れている東洋大学では、2023年に「健康スポーツ科学科」を開設。学問として健康・スポーツを学び、アスリートの養成なども行っている。
- 東洋大学の入試の特徴
-
大きく分けると「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」がある。
一般選抜
- 一般選抜には「一般入試」と「大学入学共通テスト利用入試」がある。
- 「一般入試」は大学独自の学力試験(マークシート方式)を行い、その成績で合否判定を行う。試験日は複数あり、試験日が異なる入試を併願でき、大学入学共通テスト利用入試との併願も可能。前期は2月、後期は3月に実施。
- 「大学入学共通テスト利用入試」は個別学力試験を行わず、大学入学共通テストの成績のみで合否判定を行う。前期は1月、後期は2月以降に行う。
学校推薦型選抜
- 学校推薦型選抜(公募制)には「総合評価型」や「基礎学力テスト型」などがあり、公募制以外では「指定校推薦」などもある。
- 「総合評価型」(専願)は学校長の推薦を受けて受験する推薦入試。出願には全体の学習成績の状況などの条件があり、小論文や面接などの総合評価により合否判定を行う。試験日は11月~12月。
- 「基礎学力テスト型」(併願可能)を2025年度入試から実施。学校長からの推薦に加え、2教科2科目(英語と国語、もしくは英語と数学)のマークシート方式の試験を行う。英語は英検やGTECなどの外部試験のスコアの利用が可能。試験日は12月1日で、12月10日に結果発表。
総合型選抜
- 総合型選抜(公募制)には「AO型推薦入試」と「自己推薦入試」がある。
- 「AO型推薦入試」(専願)は勉学に対して明確な目的意識があり、各学部・学科が求める人材像(アドミッション・ポリシー)に合致している学生を募集する入試。小論文やプレゼンテーション、面接などを実施。試験日は10月~12月。
- 「自己推薦入試」(専願)は学校長からの推薦がなくても自分の意思で受験できる。書類選考や小論文、面接などを実施。試験日は10月~12月。
質問会
都市部の大学と地方の大学の違い
岡早紀子さん(以下、岡さん):
うちの子は地方の大学に興味を持っているのですが、私は住んでいる東京の大学に通うのも良いのではと考えています。東京の大学は地方の大学と比べてどんな違いやメリットがあるのでしょうか。
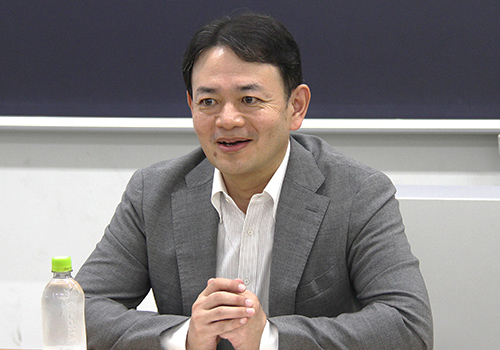
鈴木道也さん(以下、鈴木さん):
東京の大学は数が多く、情報がたくさんあります。また、東京に本社機能を持つ会社が多いため、就職活動の点で有利だと考えられます。
もちろん地方の大学の良さもあります。私は地方大学出身ですが、地元とのつながりができますし、魅力的な研究を行っている大学が多数あります。

受験生の保護者座談会

部活と勉強の両立

大澤智子さん(以下、大澤さん):
高校1年生の娘はガーデニング部に所属しています。親としては、もう少し体力が付くようなスポーツ系の部活に入ってほしかったのが正直な気持ちです。部活は週1日程度で「勉強を頑張る」と言っているので、信じて見守りたいと思っています。

岡さん:
高校2年生の息子はサッカー部に所属しています。小学校から続けている自分の得意なことを追求していること、団体競技で仲間との信頼関係を築いていること、嬉しい思いや悔しい思いを経験できていること、そして部活動をサポートしてくれる方々との交流があること。これらは本人にとって非常に良いことだと思っています。ただ、理数系の学部を目指す中で勉強が大変になり、部活とのバランスが少し崩れているようです。様子を見ながら、本人のやりたいことをサポートしていきたいと考えています。

山形則子さん(以下、山形さん):
高校2年生の娘は吹奏楽部に所属し、週5~6日の活動で日々頑張っています。部活を終えて帰宅が19時を過ぎる日などは、勉強している姿を見たことがありません。ただ、テスト1週間前になると部活も休みになり、スイッチが入って塾や図書館で勉強しています。
大学進学に関する不安と期待
大澤さん:
受験勉強を1年生から始めて長続きするのか心配です。スポーツ系の部活をしている人は「引退してから勉強に集中する」という話を聞くのですが、体力がなく、寝てしまう娘を見ていると、「飽きてしまわないか」「疲れて嫌になってしまわないか」と不安になります。
岡さん:
大学や学部の選択肢が非常に多く、どうやって子どもが選択していくのかが不安です。
山形さん:
高校受験の際、娘も私たち家族もナーバスになってしまった経験があります。大学受験は高校受験より期間が長く、文化祭が終わったらすぐに受験に向けて動き出すのかと思うと不安でいっぱいです。

大澤さん:
人間性が広がるような大学に行ってほしいです。幅広い知識や教養に加え、たくさんのことを経験して、自分の進みたい方向をしっかり見つけてもらうことを期待しています。
岡さん:
私自身、大学時代が一番楽しかったので、子どもにもそうあってほしいと思っています。そして、将来の仕事につながるような専門知識を、楽しく、幅広く、深く学んでほしいです。
山形さん:
高校までとは違い、大学は「自分で決めていくこと」が多く、自分の考えや意見を出す必要が出てきます。うちの娘はそういったことが苦手なので、克服してもらえたらと考えています。社会人になる前に、良いことも悪いことも失敗も含めて経験して、成長してほしいと思います。そして、「本当にやりたいこと」を見つけ、将来につなげてほしいと願っています。
オープンキャンパスの重要性
大澤さん:
娘が夏休みに海外留学をしていた関係で、オープンキャンパスには行けていません。親だけで行くケースもあるとのことなので、来年は積極的に足を運んでみたいと思います。
岡さん:
九州の大学に夫とオープンキャンパスに行きました。
山形さん:
専門学校のオープンキャンパスには子どもだけで行き、大学と短大のオープンキャンパスには私も一緒に行きました。

三宅さん:
私は行って良かったと思っています。ちょうどコロナ禍でオープンキャンパスをやっている大学が少なかったのですが、予約制で開催された大学に行ってみました。すると、そこは何階もある校舎なのにエレベーターが1個しかなかったんです。「毎日、階段で上るんだ」と思ってしまったのですが、オープンキャンパスに行くことで「自分が大学生になったらどういう生活をするのか」がイメージできます。
細川さん:
大学合格前に「自分がどういうところに通うか」は見ておいたほうがいいと思います。コロナ禍で東洋大学のオープンキャンパスには行けず、初めて行ったのは入学手続きのときでした。(現在は閉鎖されている)板倉キャンパスへは最寄り駅から徒歩で約15分かかり、周りにお店などもないことがそのとき分かりました。
清水さん:
僕も重要だと思います。「自分が行きたい大学がどういうところか」を知っておくことはもちろん、「通いやすさ」や「大学の周りにどういうお店があるか」なども大事です。大学の近くに行くだけでも分かることはたくさんあります。
一人暮らしで心配なこと
大澤さん:
娘は高校1年生なのでまだイメージはできていませんが、治安の良し悪しや犯罪に巻き込まれないかという不安はあります。
山形さん:
生活面はそこまで心配していませんが、犯罪に巻き込まれないかが一番心配です。

岡さん:
食事が心配です。料理の経験をさせておいたほうが良いと思い、「朝ご飯作ってくれない?」と少しずつお願いしています。
高校生のデジタル端末の使用状況
大澤さん:
東京都からの補助があり、タブレットを購入しました。使いこなせているかは分かりませんが、塾のオンライン講座を受講したり、毎日のように使っています。
岡さん:
家での使用頻度は高くないと思います。ベッドの上でタブレットを触っていると思ったら、英語の勉強をしていることはたまにあります。

山形さん:
家ではテスト前に使っているのを少し見る程度です。学校ではおそらく毎日使っていると思います。
保険の加入状況
大澤さん:
他人に損害を加えてしまった場合に保障が出るタイプに加入しています。けがについては家族保障として生まれたときから入っている保険があります。
岡さん:
学資保険に加えて、けが・病気・入院を保障する保険に加入しています。
山形さん:
赤ちゃんのときから生命保険に入っています。
現役学生からのメッセージ

三宅 千枝里さん(東洋大学 文学部 国際文化コミュニケーション学科3年生)
細川
清水
現役学生からのメッセージ①
東洋大学 生命科学部 生命科学科3年生 細川知幹さん
生命科学部 生命科学科3回生の細川知幹です。僕は指定校推薦で入学しました。
志望大学・学部の決め手

大学入試を意識したのは中学校3年生の頃です。小さい頃から生きものが好きで水族館に何度も行き、魚の研究をしたいとずっと思っていました。調べる中で東海大学の海洋学部を知り、そこを目指して指定校推薦が出ているという高校に進学しました。ですが、いざ高校に入学してみると東海大学の指定校推薦枠がなかったんです。「そのために来たのに…」とがっかりしました。でも、生きものが好きなのは変わらないので、今度は「生物学」を勉強できる大学がないかを探したときに、東洋大学の生命科学部を見つけたんです。
受験対策の仕方
もともと「指定校推薦で行こう」と決めていました。ただ、東洋大学の指定校推薦は1枠しかなく、同じ大学を目指す人が複数いると校内での競い合いとなるため、高校1~3年生の間で高い評定平均を維持することに注力しました。自習はなるべくしたくないので、いかに授業時間中に頭に詰め込めるかに専念。成績上位となり、指定校推薦枠を取ることができました。指定校推薦は12月頃に願書と自己推薦文、課題を提出します。自分のときはコロナ禍で面接がなくなり、書類のみで合否が決まるのですが、無事合格することができました。
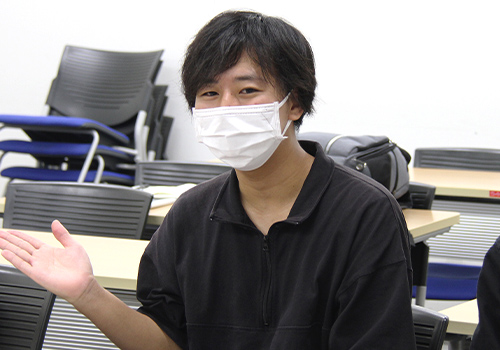
東洋大学 文学部 国際文化コミュニケーション学科3年生 三宅千枝里さん
文学部 国際文化コミュニケーション学科3年生の三宅千枝里です。私は総合型選抜のAO型推薦入試で入学しました。
志望大学・学部の決め手

両親ともに東洋大学の卒業生だったことが大きな要因です。私が生まれたときから同窓会を年に数回開いていて、子ども同士も今でも仲良くしています。「こんなに長く交友関係が続く大学はすごい!」「こういう友達を作りたい!」と思い、私の志望は東洋大学で決まっていました。学部・学科は好きな「英語」「話すこと」を重視して探しました。東洋大学には留学生比率が約20%の「国際文化コミュニケーション学科」があり、国際的な知識を養えるのと同時にスピーキング・プレゼンテーションなどでさまざまな国の人が交流できます。ここを選んで大成功だったと思っています。
受験で大変だったこと
AO型推薦入試で受験しましたが、実はその前に指定校推薦も申し込んでいます。ですが、校内で複数志望者がいて私は候補から落ちてしまいました。9月11日に指定校推薦に落ちたことが分かり、AO型推薦に切り替えたのですが、一次試験の締め切りが9月17日だったんです。約1週間、いかに質の良い小論文に仕上げるかが大変でした。出題されたのが「宇宙人が来たとして、地球上の文化文明をあなたならどのように説明しますか?」というユニークな質問。いろんな人に「こういう問題があって、あなただったらどうする?」とヒアリングして回り、参考にしながら自分の考えを小論文にまとめました。そのあとはひたすら、高校の先生と二次試験のプレゼンの練習です。終盤には学生や友達などをギャラリーとして呼び、その人たちの前でプレゼンの練習をしました。二次試験からさらに半月、11月1日に無事合格が決まりました。この1カ月半はすごくナーバスで、家族の中でも大変でしたが、一番濃厚な時期だったと思います。

東洋大学 経済学部 総合政策学科2年生 清水遥日さん
経済学部 総合政策学科2年生の清水遥日です。僕は一般入試で入学しました。
志望大学・学部の決め手

もともと国公立大学に興味があったのですが、大きな転機は高校1年生のときのコロナ禍です。外出自粛となり、家で街作りのゲームをしていたのですが、そこから「街作り」に興味を持ち、公立大学の都市環境学部を志望するようになりました。ですが、コロナ禍で授業がなくなり、勉強をする習慣が付かないまま高校2年生に。このままではまずいと、英語だけですが高校から近い予備校に通い始めました。国公立大学は何校も併願できないので、私立大学も視野に入れるようになり、親の出身校である東洋大学を併願校として考えるようになりました。
受験で大変だったこと
コロナ禍で部活も制限される中、ネックになったのが体力です。高校2年生の後半から本格的に勉強を始めましたが、体力が持たなくてすぐに眠くなってしまうこともしばしば。気合いで何とかやっていましたが、どうしても集中力が切れてしまっていました。加えて、高校3年生の夏休みに百日咳にかかってしまい1カ月半は丸々勉強ができず、得意だった英語以外がぼろぼろに。国公立大学は諦め、私立大学だけに絞りました。そこからはスマホを封印し、終電の時間まで予備校にずっとこもって勉強をする日々。2月の一般入試では、相変わらず英語以外は苦戦しましたが、何とか東洋大学に受かることができました。

受験期の親との関係
うちの両親は生活面でサポートをしてくれました。受験勉強中に軽食を置いてもらえたときなどは嬉しかったです。
保護者の方からの質問
岡さん:
清水さんは英語のために予備校に通っていたということですが、高校では得られないような情報を予備校で得られることはあるのでしょうか。
清水さん:
高校にもよると思います。予備校に匹敵するぐらいの情報量を高校の先生が持っている場合もありますが、僕が通っていた高校はそうではありませんでした。それに一般入試は大学ごとに特色があり、高校の授業だけでは対策に限界があるので、苦手科目だけでも予備校を利用するのは一つの手です。予備校によっては受付に質問担当の人がいて、質疑応答だけなら授業を取らなくてもできる場合があります。
山形さん:
うちの娘は高校2年生ですが、「入試のことを誰に聞いていいのか分からない」といまだに言っています。皆さんはどのように情報収集をしていましたか。
清水さん:
情報収集は予備校がメインです。加えて、高校2年生のときの担任が進路指導部長だったこともあり、セカンドオピニオンのような感覚で相談をしていました。高校の進路指導室には大学に関する資料がたくさん置いてあったので、それらも参考にしていました。

三宅さん:
高校1年生の頃から各大学のホームページを見て情報収集をしていました。進みたい方向性は決まっていたのですが何から手を付けていいか分からず、早慶上理・GMARCH・日東駒専など聞いたことのある大学や近所の大学の学部・学科を片っ端から書き出していました。そうすることで、何をしている大学かが見えてきたんです。
細川さん:
自分の通っていた高校は進学する人の8~9割が指定校推薦です。どの大学へ指定校推薦で行けるかがまとめられた冊子があり、それを見て自分の興味がある大学に資料請求をしていました。パンフレットを見ると、どういう大学なのかが分かります。また、高校の担任の先生に「こういう大学に進みたい」「自分は何をすればいいのか?」と相談すると、親身にアドバイスしてくれました。
ご参加いただきましてありがとうございました。
2024年10月11日 東洋大学白山キャンパスにて
Contents
質問会
受験生の保護者座談会
現役学生からのメッセージ