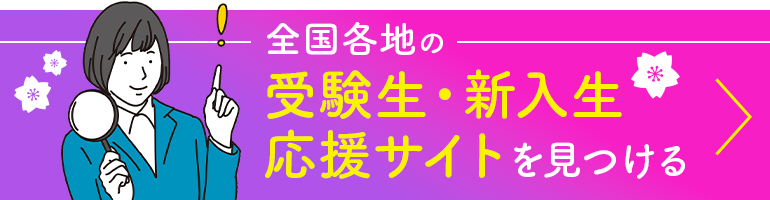受験生(高校生)保護者座談会@同志社大学(2024年開催)
大学受験には様々な方法があり、可能性がある
大学入試の変化とともに、年々早期対策の重要性が高まっています。その中で、高校生本人はもちろん、親はどのような心構えが必要なのでしょうか。今回は、高校生のお子さまがいらっしゃる保護者の方、そして現役大学生にお集まりいただきました。情報収集や志望大学・学部の選択、受験や入学後の生活について、親・学生・大学の三つの立場からお話ししていただきました。

〈参加者〉
- 片山 政利さん(大阪府立高等学校PTA会長)
- 岡﨑 美紀さん(大阪府立高等学校PTA副会長)
- 赤井 礼子さん(大阪府立高等学校前PTA会長)
〈学生〉
- 大橋 楓子さん
(同志社大学政策学部1年生) - 南 日菜乃さん
(同志社大学商学部1年生)
〈講演者〉
- 同志社大学 入学センター入学課 入学広報係
宝田 将志さん
Contents
質問会
同志社大学の特徴と入試方式
- 同志社大学の特徴
-
- 2025年で創立150周年の歴史ある大学。
- キリスト教主義教育が徳育の基本。知識・技術だけでなく、人格形成を含め、総合的に学生を育てていく方針。
- 14の学部からなる総合大学。
- 文理融合型の学部がある。文化情報学部、スポーツ健康科学部、心理学部などでは文系的な教育に加え、データ分析なども行う。
- 高校では情報が必修科目だが、同志社大学の各学部は情報が必修ではない。
大学案内で情報を詳細に公開
- 4年間でかかる学費、入学金、学会費、父母会費、教育充実費、研究費や、奨学金制度などを掲載。
- 学部ごとの特色や取れる資格を掲載。
- 留学制度として正規プログラム一覧を掲載。4年間で卒業できるようにプログラムが組まれ、1年間留学しても卒業が1年延びることはない。
- 就職先を学部別に掲載し、学部卒と大学院卒の特徴も紹介。近年は理系であればメーカーが多い。大学案内に載っているような企業が、学内で就職説明会を開くなど、大学全体として就職をサポートしている。
- 各学部の専任教員一覧と専門分野を掲載。高校に比べて大学は専門性が高くなり、各教員の専門分野を軸に深く教えるのが特徴。教員やその専門分野が何かを知ることは大学・学部選びにおいて大切。
- 同志社大学の入試の特徴
-
- 同志社大学の入試は、AO入試などを含む推薦入試と、一般入試を含む学力入試。
- 推薦入試は、学校長の推薦書が不要な「総合型選抜」と学校長の推薦書が必要な「学校推薦型選抜」の主に2種類で、他には「指定校推薦入試」がある。
- 学力入試は「一般入試」と「大学入学共通テストを利用する入学試験」の2種類ある。
推薦「総合型選抜」
- 総合型選抜には「AO入試」と「自己推薦入学試験」がある。他大学ではAO入試と自己推薦は同じ扱いのところもあるが、同志社大学では明確に分けている。
- 「AO入試」は、「何にどのように取り組んできたか」「その過程を通してどのような学びがあったか」「将来どのようなことをやりたくて同志社大学のこの学部を選んだのか」などを自己アピールする試験で、面接時間が長いのが特徴。出願書類も特徴的で、2000字のエッセーがあり、「自分はこういう物事の捉え方をする」「こういうところに興味がある」など課題活動の戦績など数字で測れない部分も見ようとしている。
- AO入試は4学部で募集しており、各学部で募集人数や出願資格が異なる。
- 「自己推薦入試」は一芸一能入試に近く、例えば「野球で甲子園に出場」などの実績、語学力であれば「英検何級」などの実績をアピールできる試験。
推薦「学校推薦型選抜」
- 学校推薦型選抜の「推薦選抜入学試験」は、学校長の推薦書が必要なこと以外は「自己推薦入学試験」と同様の考え方。
学力「一般入試」
- 試験は2月4日~2月10日の1週間のみ。
- 試験日1日に対して1学部・学科しかエントリーできない。ただし、試験日が違えばすべて併願できる。日を変えて同じ学部をエントリーしたり、理系から文系に変えて受けることもでき、最大7回併願可能。
- 問題の違いは、学部ごとではなく試験日ごとで、例えば2月4日はどの学部を受けても全員同じ問題を解く。科目ごとの出題委員会が1週間分の問題を一気に作るため、学部ごとの対策が不要となるため、「何学部を受けるからこの勉強をしないといけない」ということはなく、どの学部でも応用が利くため併願がしやすい。
- 基礎を重視した問題を作成するという出題方針がある。「高校での着実な学習努力が報われるように難問や奇問を避ける」「マークシート方式でなくて記述式に」という方針が決まっている。そのため、平均点が高め。同程度の私立大学で6~7割が平均点とすると、同志社大学では7~8割近くが平均点となる。過去問題等で問題のレベル・傾向を確認しつつ基礎を固め、本番ではケアレスミスをしないよう、着実に点数を取っていくのが同志社大学の一般入試を受ける際に大事なこと。
学力「大学入学共通テストを利用する入学試験」
- 国公立大学の受験生が必ず受ける「大学入学共通テスト」の点数を使い、私立の同志社大学に行けるという試験。
- ほとんどの学部は、大学入学共通テストの点数のみで合格判定が出る。ただし、いくつかの学部や受け方によっては個別学力試験を実施し、大学入学共通テストの点数プラス個別の学力試験の点数の合算で合否判定を行うケースがある。その場合、同志社大学独自の勉強を行い、同志社大学で受験をする必要がある。これは大学入学共通テストで思うように点数が取れなかった場合に個別学力試験で挽回できる仕組みでもある。大学入学共通テストのあとに出願締め切りの学部もあるため、大学入学共通テストの自己採点を見てから「国立だけで考えていたけど、私立も受けておかないと」となったときにも受けられる試験がいくつかある。
同志社大学からメッセージ

宝田将志さん(以下、宝田さん):
「入試=勉強をして学力を上げること」が前提でありながらも、受け方や科目、出願日程を考えて組み合わせていくと、いろいろなところにチャンスが転がっています。ただ、大学ごとに様々な入試制度があり、それを理解して活用するのは本当に難しいと思います。受験生はそこまで考える余裕がないと思いますので、保護者の皆さまにも制度を知っていただき、「意外とこういうのを受けられるんじゃない」という助言やバックアップをしていただくと受験生の負担が減り、家族全体で入試を乗り越えていけると考えています。
受験業界として年内入試・推薦入試がトレンドです。そのためには早くに大学選びを行い、受験に備える必要があります。高校1~2年生のうちに大学案内やオープンキャンパス、全国で行われる大学の入試説明会などの機会に足を運び、見比べていただくと、それぞれの大学の特徴が見えてくると思います。
質問会
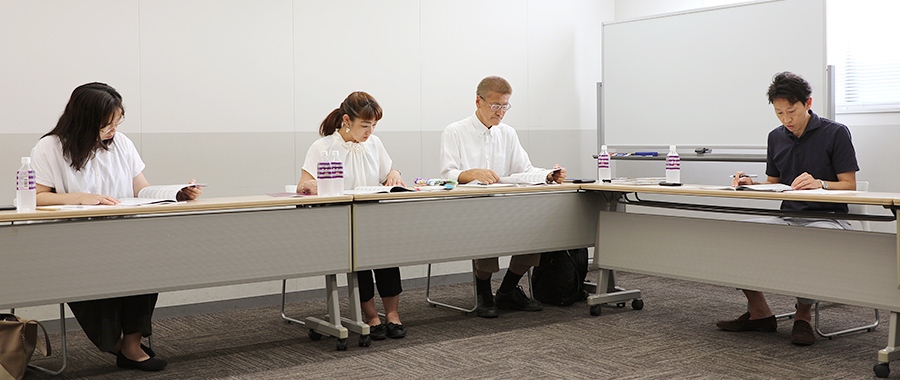

片山政利さん(以下、片山さん):
入試についてお聞きします。うちの子は理系の学部に進むと思うのですが、理系の英語の試験方針などがあればお伺いしたいです。

宝田さん:
同志社大学の入試は、英語で受験学部に関連する専門性を測るものではありません。理系学部の試験で文系の題材を出すことがありますし、その逆もあります。文理関係なく英語は大事だと考え、様々なテーマが出題されます。
同志社大学の英語は、「長文問題が長くて読むのに時間がかかる」とよく言われます。理由は英語の基礎力を重視し、単語力があるか、精読ができるか等を見るためです。一つひとつ丁寧に読み解いていこうとすると時間が足りません。単語帳に載っている一つ目の意味だけでは読み解けない問題もあり、分からない単語があったらひとまず読み飛ばし、前後の文脈から言葉を類推して読み解いていく力も必要です。
厳しく聞こえるかもしれませんが、単語力や熟語、構文などの基礎固めをきちんと行うなど努力すれば点数に反映されるように作問しています。受験生からすると大変ですが、それをクリアしてきた学生の皆さんは、ベースとなる学力を生かしながら、学部の学びの中でも応用していけたり、入学してから困らないように様々な学びができるように考えています。

岡﨑美紀さん(以下、岡﨑さん):
推薦では英検などを持っていたほうがいいのでしょうか。英検以外にも何かあれば教えていただきたいです。
宝田さん:
受験では英検やTOEICなどがよく使われます。ただ、同志社大学の一般入試では検定試験結果による加点はありません。他大学であれば、英検等で何点を持っていたら加点やみなし点となるケースもあります。語学に自信がある方、英語の検定試験の結果をうまく活用したい方は、英検やTOEIC等を受けて点数を持っていると様々なところで応用が利く可能性があります。あとは、ベネッセが行っている中高生向けの英語検定「GTEC」を入試で使える大学もあります。
英検やTOEICは外部試験なので、そのための勉強や費用の負担が必要になります。高校生の方は大変だと思うので、1~2年生のうちは高校内で受験可能なGTECで学習し、受験期になり志望大学がGTECを使えるのであればそのまま継続。GTECが使えない大学であれば、英検・TOEIC等の指定された外部試験を2年生の終わりか3年生の春先に受けるという考え方もあります。外部試験の受験時期が遅いと、結果が出るのが入試に間に合わなくなる可能性があるので注意してください。
片山さん:
今日は今出川校地に来ていますが、理系は京田辺校地にあるとのことで、交流などはあるのでしょうか。
宝田さん:
交流として代表的なのはサークルや部活動です。サークルや部活動は、文理関係なく行われています。サークルのボックス棟と言われる部室の集合施設が今出川校地と京田辺校地の両方にあり、曜日で練習する校地を変えたり、共通で活動したりしています。2校地間を走る無料シャトルバスや電車も多く、それらを利用して、京田辺校地で勉強してサークルのために今出川校地に来るという学生もいます。私は大学で野球をやっていたのですが、専用グラウンドが京田辺校地にあるので、今出川校地で勉強したあとに京田辺校地に行っていました。
あと、同志社大学では学園祭が年2回開催されます。今出川は「EVE」、京田辺は「クローバー祭」と言い、校地の枠を超えて様々な学部やサークルが模擬点等を出店しています。
授業では全学共通教養教育科目があり、その科目を取るために今出川校地に理系学生、京田辺校地に文系学生が行くこともあります。距離は離れていますが、交流する機会は多いです。
片山さん:
無料シャトルバスは片道どれぐらい時間がかかるのですか。
宝田さん:
道路の混み具合にもよりますが50~60分程です。その時間で仮眠したり、勉強したり、学生は自由に使っています。

受験生の保護者座談会

勉強と部活の両立
片山さん:
うちは部活で野球をずっとやっています。土日を含めてほとんど毎日練習で、週1回休みがあるかぐらいです。部活に集中して勉強は全然していなかったので、これから「さあ大変」という状況になっています。うちの子は両立が難しかったと思っていますが、同じ野球部でもきちんと両立している方もいるので、「部活をやっているから勉強との両立ができない」というわけでもないと考えています。今まで部活で発揮していた集中力を、引退後に勉強で発揮して受験に臨む方もいると聞きました。うちの子もそうなってくれたらいいなと期待しています。
岡﨑さん:
うちは2年生ですが、塾はまだ行かず、部活と家での自主勉強だけです。夏は学校の補講に参加したり、担任の先生が独自に「オンラインでこういう勉強をするといいよ」と教えてくれているようなので、活用して家でやってくれていると信じています。

大学の情報収集と進学に期待すること
片山さん:
大学によって入試のシステムが複雑になってきていて、言い換えると大学によって個性・特色が出ているとも思っています。最終的に決めるのはあくまで本人ですが、親も含めて「子どもにどのシステムが合っているのか」「どの大学に行きたいのか」「何をやりたいのか」という選択肢を提示してあげることが大事だと思っています。情報を集めてきて選択肢を示してあげたいのですが、選択肢を見つけるための情報の入手の仕方が今のやり方でいいのか、網羅できているのかが不安ではあります。
片山さん:
私はインターネットがメインで、集めた情報をExcelで一覧表にまとめています。一番信頼性が高いと思っているのが大学の公式ホームページで、そこからの情報だけを書くようにしています。いろんな方がブログで出している情報もありますが、あくまで参考情報として捉えるようにしています。
岡﨑さん:
私は資料を集めたり、インターネットを見たりです。また、大学受験のお話を聞きたくてPTAに入り、保護者の方々から情報を集めています。あとは先生ですね。
片山さん:
私は行ったことがないです。ただ、PTAの活動として保護者の大学見学会を毎年企画していて、そちらには参加しています。昨年、今年ともに、それぞれ私立一校、国公立一校に行きました。
岡﨑さん:
私は上の子の受験のときに、子どもと二人で何校かオープンキャンパスに行きました。

片山さん:
最終的に選ぶのは本人ですので、それを尊重したいと思っています。期待することは二つあります。一つは、専門性をしっかり身に付けてほしいのが大前提です。もう一つは、自立してほしい、成長してほしいという思いがあります。
大学に入ったら一人暮らしをしたいと本人は言っています。私も大学のときに一人暮らしをして、親のありがたみがわかったり、自分ですべてやらないといけないという経験がすごく良かったと実感しました。今後、息子が一人暮らしをするかどうかは分からないですが、大学に入って自立や社会人になるための第一歩を学んでほしいと思っています。
岡﨑さん:
入学してからは、勉強や資格はもちろんですが、社会に出てから大学で学んだことをどう生かせるかですね。将来を見据えてやってもらいたいです。
一人暮らしに対する親の心配と実情
片山さん:
心配なのは食事です。今は親が食事を作って本人は食べるだけですが、大学に入って一人暮らしになると誰も作ってくれないので食事をどうしていくのかですね。朝昼夜と大学生協で食べるのか、自炊をするのか、外食をするのか、栄養の偏りがないかという心配があります。

岡﨑さん:
一人暮らしは考えていませんが、もしするとなったら事故や事件が心配です。

赤井礼子さん(以下、赤井さん):
食事を作れるかや、家賃をどうするかが心配です。同じ学年で他県に行った方は「家賃相場が分からずに急に行って部屋を決めてこないといけないから、この金額で決めて良かったのかすごく不安だった」と話していました。
片山さん:
一人暮らしについて学生の二人にお聞きしたいのですが、大学への通学時間や家賃、仕送りがどれぐらいかなど、可能な範囲で教えていただけますか。

大橋楓子さん(以下、大橋さん):
私は新町キャンパスまで自転車で約10分です。10月に引っ越すのですが、歩いて5分と近くなります。家賃は、今住んでいるところが65,000円程度で、引っ越すところは75,000円程度です。光熱費、水道代、家に関する費用はすべて実家の親が支払ってくれています。他の生活費は奨学金から払っています。高校3年生になったタイミングで私の学校は一斉に案内が配られて、みんなが申し込む奨学金がありました。月6万円程度の奨学金が自分の口座に入るので生活費に充て、実際に使うのは4万円程度です。

南日菜乃(以下、南さん):
私は西陣のほうに住んでいて、大学まで自転車で10分程度です。同志社大学の女性専用の場所で、家賃は6万円前後です。
片山さん:
食事は、どうされていますか。
大橋さん:
私は自炊が多いです。1回に何品も作れないので、だんだん体重が落ちていってしまい、親に怒られました。「近くにおいしい惣菜店があるなら、そこを利用して」とよく言われます。
南さん:
私は自炊が週1~2回ぐらいです。
片山さん:
大学生協の食堂は利用していますか。
南さん:
みんな使っています。
大橋さん:
それがないとやっていけないので、ありがたいです。
高校生のパソコンの使用状況

片山さん:
デジタル端末が一人1台貸与されています。
片山さん:
使えると思いますが、あまり使っているところを見たことがありません。
赤井さん:
学校でもあまり使っていないようです。「探究」という授業で、自分たちでいろいろ調べて発表するというのを3年間かけてやるのですが、みんなで共有したり、スライドを作るときに使っていました。ただ、それ以外はほぼ家に置きっぱなしです。あまり使わないのは、インターネット制限などがかかっているのも理由かもしれません。

現役大学生からのメッセージ

大橋 楓子さん(同志社大学政策学部1年生)
南 日菜乃さん(同志社大学商学部1年生)
現役大学生からのメッセージ①
政策学部 1年生 大橋楓子さん
同志社大学 政策学部政策学科1年生の大橋楓子です。高校ではずっと野球部で、全然勉強をしたくないし、大学は関東や大阪、神戸あたりに行くのかなとざっくり思っていました。
高校での勉強状況

私はずっと文系です。高校のときは「探究科学科」という文系と理数科が一緒になったコースにいて研究などをしていました。高校は早い段階で古文単語や英単語をやり始め、片道30分の通学で朝は必ず単語を読むのが習慣に。でも、定期テストも勉強しないし、引退しても勉強をしていなかったです。受験科目は国語と英語と文系数学で受けました。英語が得意科目なので得点源なのですが、友達から「同志社大学の数学は難しい」と聞いていた通り数学は壊滅的でした。
志望大学の決め手
大学入学共通テストまではずっと国立に行きたかったのですが、テストに失敗して私立を探した中で同志社大学に切り替えました。夏に別の大学のオープンキャンパスに行ったときに同志社大学を目にしてすごくきれいで、駅から近くて場所も良くて、一目ぼれというか「ここに行きたい」という思いが芽生えました。私は将来働きたい業界や会社が明確にあって、同志社大学からその業界へ毎年一定数進んでいるのを知ったのが大きな理由です。留学先の選択肢も多く、学習環境がすごく整っていることもポイントでした。その中で、一番の決め手は地方受験ができたことです。地元が富山なのですが、近場で受けることができました。
学部は政策学部です。大学でやりたいことが決まっていなかったのですが、「楽しそうだな」「ここならやっていけるかな」と思って選びました。
部活引退後の受験モード
私が所属していたのは、選手7人・マネージャー2人の少ない部活でした。引退後にすごい勢いで勉強し始めて、大阪大学や慶応大学に受かった人もいます。個人的な意見ですが、部活で頑張ってきた人は、スイッチを入れたらすごい勢いで勉強するイメージがあり、吸収も早いと思います。
あとは受験期にうちの親は何も口出しをしてこなくて、伸び伸びとできました。その間、親は大学のことをかなり調べてくれて、大学ごとの配点の違いや受け方などのアドバイスをしてくれました。大学入学共通テストが悪くて焦っていたとき、大学や配点の話をいっぱいしてくれたので安心して受けられましたし、ありがたかったです。

保護者の方からの質問
片山さん:
親から毎日わあわあ言われると、辟易してしまいますよね。
岡﨑さん:
入学してから、何人ぐらいで授業を受けているんですか。
大橋さん:
政策学部の必修科目では300人ぐらいで、大きな部屋に全員入って受けています。英語など20人程度の授業もあって、そちらで友達ができたりします。英語はクラス分けがあり、上のほうに行くと課題が楽だったり、外国人の先生で英語をたくさん使ってくれるのですごく楽しいです。部活は、いろんな学部から集まり40人程度です。
赤井さん:
今は何が一番楽しいですか。入る前に思っていたことと違うところなどもお聞きしたいです。
大橋さん:
この大学に入ってまず人の多さに困惑しました。国公立の大学は定員が数十人程度で、他の大学に行った人はもう友達ができたのに私はできなくて、つらい時期もありました。今は英語の授業で友達ができましたし、実は友達が近くに住んでいたり、部活をしたり、話せる相手がいるので楽しいです。
商学部 1年生 南日菜乃さん
同志社大学 商学部商学科のフレックス複合コースに所属しています南日菜乃です。
私が受けたのはAO入試です。AO入試は自分のやりたいことなどを大学にアピールする形式で、誰でも挑戦できる入試だと思っています。私は本当は一般入試が本命で、AO入試はチャンスを増やすためのものでした。
志望大学の決め手

同志社大学を選んだポイントは二つあります。一つ目が、私は公認会計士を目指しているのですが、そのために学習できる環境とカリキュラムがあることです。二つ目が、京都に住むことに小さい頃から憧れていて、大学生活は京都で過ごしたいという気持ちが強かったからです。
志望大学を決めたのは高校2年生の秋頃で、地元・広島で開催された同志社大学の説明会に参加しました。そのときまでは会計士を目指すなら経済学部かなと思っていたのですが、「公認会計士を目指すには、どの学部が適していますか?」と質問したときに「商学部がいいですよ」と教えてもらい、そこで第一志望として決めました。ただ、その時点ではAO入試を受けるつもりはありませんでした。その後、高校2年生の春休みに同志社大学の今出川キャンパスを見に家族で行き、その日の夜に入試について調べる中でAO入試を受けることを決意しました。
AO入試を受けた理由
AO入試は少し特殊ですが、受験しようと思った理由は二つあります。一つ目は、大学受験を早く終わらせて、簿記や会計の勉強や英語など自分のやりたいことに時間を使いたかったからです。二つ目は、AO入試の目的に魅力を感じたからです。自分のやりたいことをアピールする試験で、私は会計士というやりたいことが明確にあるので、それで合格できたらいいなと思いました。
9月にはAO入試の出願で、6月に部活を引退し、夏休みをまるまる使って志望理由書や自己紹介書、エッセー、調査書、評価書、英語の自己PR動画を用意しました。一般入試も受ける予定だったので、9月は過去問を解く、一般入試の勉強。AO入試のほうは一次審査の通知が来て、10月に二次審査があるので、その直前は面接や英語のプレゼンなどの対策です。11月に合格通知が来て、それ以降は自分のやりたい簿記などの勉強をすることができました。
入試の苦労
商学部のAO入試は、出願資格のうち英語では[TOEIC、TOEFL、TEAP]などで何点以上という規定があります。その出願資格を取るのにかなり苦労しました。高校3年生の5月に初めてTOEICを受けたのですが、結果は550点程度。出願資格として650点以上が必要で、このままでは受験できない状態でした。出願まで期間が短くてTOEICを受けられるのもあと1回しかチャンスがなく、周りの先生にも「諦めたら?」と言われていました。母親からも「あと1回で100点以上上げるのは厳しいんじゃない?」と言われたのですが、父親は「もう1回だけ頑張ってみたら?」と言ってくれて。一生懸命勉強して7月にもう一度受けて、出願前のぎりぎりに結果が分かったのですが、695点まで上げることができました。
もう一つ苦労したことは、AO入試対策と一般入試対策の両立です。夏休みは一般入試の勉強の山場だと思うのですが、AO入試は出願書類がたくさんあり、夏休みはほぼそちらに時間をかけていました。
受験を振り返って
おそらく親は、私の受けるAO入試についてよく分かっていなかったと思います。一般入試が本命でAO入試はチャンスを増やすため、運が良ければ受かるくらいとずっと伝えていたので、親はAO入試にそれほど期待していなかったと思いますが、私は内心「AO入試で決めてやる!」という気持ちがありました。
AO入試に限らず、推薦入試や一般入試にも関係すると思うのですが、「自分は何をやりたいのか」と自分に向き合って、強みや弱みを分析することが重要だと感じました。学校の先生や親など大人にいっぱい頼って、アドバイスをもらってくるのも大切です。AO入試に関して親はあまり干渉してくることはありませんでしたが、私から「こんな感じで志望理由書を書いたんだけど見てほしい」とアドバイスをもらったり、面接の練習などで助けてもらっていました。あとはやはり自分に自信を持って、「自分以外、誰が受かるんだ!」という精神で挑むことが大事だと思います。

保護者の方からの質問
片山さん:
AO入試にチャレンジするという、すごい意志を感じました。一般入試との両立が難しかったということで、AO入試対策との配分はどのようにしていましたか。
南さん:
期間で区切っていました。出願前の8月いっぱいはAO入試に振り切って、出願後の9月いっぱいは一般入試の勉強を、10月はまたAO入試の二次試験の英語のプレゼン対策をするという感じで、それぞれ集中して頑張っていました。
片山さん:
二次試験は、面接官の前でプレゼンするのですか。
南さん:
そうです。課題は決まっていて、面接の冒頭に5分間ほど英語でプレゼンします。
片山さん:
どんな課題で、どんなことを話したのですか。
南さん:
「ChatGPT」に関する日本語で書かれた文章を英語でプレゼンする課題で、一次審査の合格通知と一緒に送られてきました。英語の原稿を作成して、覚えて、プレゼンする練習を10月に行っていました。
片山さん:
プレゼンでは、英語の発音よりもプレゼンテーション能力を評価するのでしょうか。
青木理事長:
きちんと論理が通っているか、丁寧にちゃんと単語が言えているかなども見られます。
岡﨑さん:
商学部の人数や授業の人数などを教えていただけますか。
南さん:
商学部自体は900人ほどいます。授業によりますが、少ないものだと40人ほど、多いものだと300人で一緒に受ける授業があります。
片山さん:
300人も受ける授業では、出席はどのように取っているのですか。
南さん:
今受けている300人の授業では出席を取っていません。授業後のレポート提出で確認しているようです。
ご参加いただきましてありがとうございました。
2024年8月8日同志社大学今出川キャンパスにて
Contents
質問会