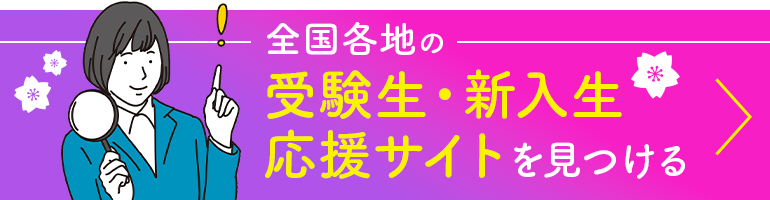受験生(高校生)保護者座談会@埼玉大学(2023年開催)
学びたいことを学べる環境なら、人間的に大きく成長できる
埼玉大学では、地元で役に立ちたいと願う人材を多く輩出しています。また、すべての学部が同じキャンパスに集まっており、進学後に進路を選択しやすいのも大きな特徴です。今回は、受験生の保護者様と現役の埼玉大生にお集まりいただき、埼玉大学の入試や受験対策について、また部活と勉強の両立についてなどをお話していただきました。
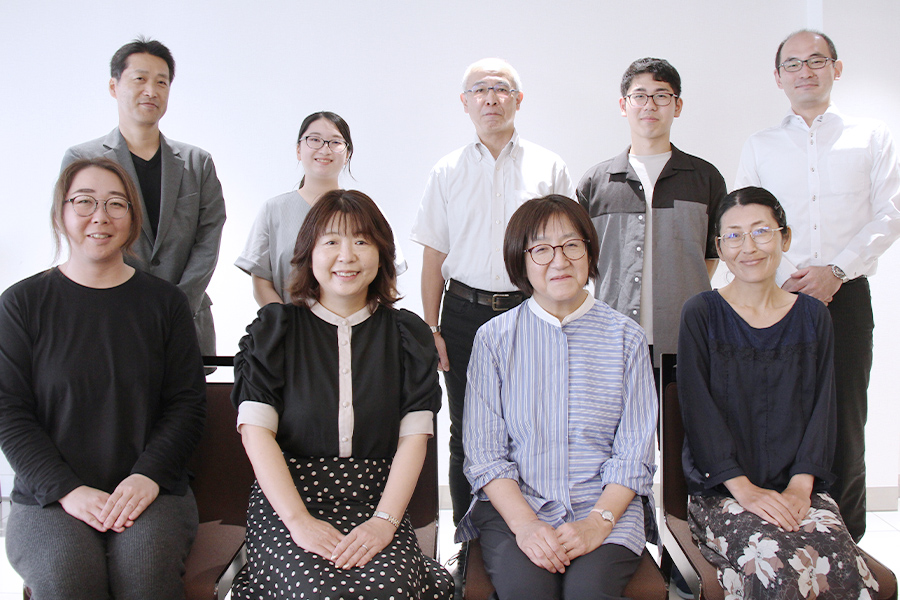
〈参加者〉
- 木田 陽子さん(長男が埼玉県立高等学校)
- 川下 弘子さん(長男が埼玉県立高等学校)
- 荒井 雅子さん(次男が埼玉県立高等学校)
- 中島 恵さん(長男が埼玉県立高等学校)
- 曲渕 修さん(次男が埼玉県立高等学校)
〈学生〉
- 藤木 一聡さん
(埼玉大学理学部1年) - 長尾 みずきさん
(埼玉大学教育学部1年)
〈講演者〉
- 埼玉大学生協 理事長
藤原 隆司先生
Contents
質問会
埼玉大学の入試方法
- 埼玉大学の特徴
-
- 埼玉大学にはいろいろな学部があるが、一つのキャンパスに全学部が集まっている。
- 学生は全体の6割くらいは関東の方です。そのうち、埼玉県は3割ぐらい。
- 下宿するよりも安いため、栃木県の宇都宮からなど、関東圏からだと家から通う学生も多い。
- 入試について
-
- 国立大学なので、入試の方式は私学のようなバリエーションはない。
- 理学部の基礎化学科では、前期試験は共通テストの成績だけで判定される。
- 共通テストは年によって大きく内容が変わるので、埼玉大学を志望する方は、受験システムをきちんと調べていただくと良い。
- 受験のシステムは複雑なので、できる限り調べることをすすめる。
- 埼玉大学からの選択肢
-
- 4年生まで埼玉大学に通い、他の大学院に行くこともできる。
- 例えば、東京工業大学や東京大学の大学院に進学する学生もいる。反対に、地方の国立大学を出てから埼玉大学に来るというパターンもある。
- 大学4年間で進路を決めなければならないわけではないので、大学院に行きたかったら3、4年生で頑張って、上の大学院を目指すのも一つの考え方。
- 在学中に短期留学して、面白いからと海外へ進学する学生もいる。
質問会


藤原 隆司先生(以下、藤原先生):
それではここからは、皆さんのご質問にお答えしたいと思います。
まず初めに、保護者の方から、自己紹介をお願いできますでしょうか。

木田 陽子さん(以下、木田さん):
木田陽子と申します。長男が高校1年生です。ついこの間まで受験生だったので、また受験かという感じですが、早い方がいいのかなと思いましてお話を聞きにきました。どうぞよろしくお願いします。

川下 弘子さん(以下、川下さん):
川下弘子と申します。長男が高校2年です。私は長男を埼玉大学に入れたいと思っております。先日、本人がオープンキャンパスに行きまして、いろいろ考えたことがあるようです。よろしくお願いいたします。

荒井 雅子さん(以下、荒井さん):
荒井雅子です。次男が高校1年生です。2学年上の女の子もおりまして、ちょうど今年受験です。ちなみに、長男はこの間大学を卒業して就職しました。ですので、長男の時に受験は経験しているのですけれども、6年も空いてしまうとだいぶ受験の事情が変わってしまうこともあるかと思いまして、今回参加しました。よろしくお願いします。
中島 恵さん(以下、中島さん):
中島恵です。長男が今年高校に入学したばかりです。部活動と勉強の両立を皆さんがどのようにされているのか伺いたいです。子どもは部活に重きを置いているようで、進学には今のところあまり興味がなさそうなので、ちょっと不安です。よろしくお願いします。

曲渕 修さん(以下、曲渕さん):
曲渕修と申します。次男が高校1年生です。理系・文系、どちらを選ぶか悩んでいた中、一応、理系を選択しましたが、親のかじ取りでそちらに行ってしまったような気がしています。できれば、自分の進路については自分で選択してほしいと思っていますが、ついつい口を出してしまう日々です。
藤原先生:
ありがとうございます。では、質問をお願いします。
木田さん:
やはり理系は、大学院へ行くのが当たり前と考えるものなのでしょうか。
藤原先生:
埼玉大学の理学部は大学院への進学が比較的多いです。ただ、修士課程に2年行って、その後、博士課程に3年行くと、年齢的には27、28歳になってしまいますので、そこから就職するのはなかなか大変です。本人は研究所や大学の先生になりたいという気持ちが強くても、なかなか門が狭くなっていきますので、その辺りは親御さんも覚悟して送り出してあげないといけないと私は思います。
博士課程を出てすぐは大学に就職できないので、いったん海外で2、3年修行して戻ってくるなど、そういうことをしないと難しい状況というのが正直なところですね。埼玉大学では50人の定員で、30人ぐらいが修士課程に進学しています。
一方で、工学部はそうでもありません。工学部はどちらかというと実学なので、すぐに役立ちます。電気回路系や機械系などは密接に産業界とリンクしているので、働くイメージが湧きやすいのかもしれません。その点、理学部の6割ぐらいは修士に進学する傾向にあります。
木田さん:
埼玉大学の理系学部は、理学部と工学部とがありますよね。まだ理学部にするか工学部にするかわからないという段階では、理工学部のように一つになった大学を考えた方がいいのか、それとも各学部の研究内容を見たうえで、理学部か、工学部かを決めた方がいいのか、アドバイスをいただけますか。
藤原先生:
研究内容から判断するのは、高校生にはなかなか難しいですよね。また、理学部の先生でも工学部出身であったり、工学部の先生でも理学部出身であったり、ということもあります。
木田さん:
1、2年生の間は基本的に両方とも学ぶのですか。

藤原先生:
学部では基礎的なこともやりますが、やっぱり工学部だったら工学部の勉強を中心に学びますね。
ただ、大学によっては理工学部のようなところもあるので、そのような大学は学科が細かく分かれていて、理学部っぽい学科と、工学部っぽい学科があるようです。でも、学部としては混ざっているから、理学部の先生と工学部の先生がいます。
木田さん:
高校1年生の時に理系と文系の選択をしますが、息子はそこでもやっぱりなかなか決めかねているので、大学に入る前に学部まで決めてしまうのは不安ではないかと思います。
藤原先生:
学生の中には進学してから、転部する学生もいます。理学部に入ったけれど、やっぱり文系に行きたいと埼玉大学教養学部に転部するような形です。私が思うに、それはもしかしたら受験の時の指導で、先生に言われてしまって決めてしまったのかもしれないかもと感じています。でもやっぱり転学したいと思う学生も一定数いるようです。理学部から工学部へ転部する子はあまりいないような気がしますけれども、文系に行く学生が時たまいますね。文系から理系はちょっと大変ですが、理系の教科を受けていたら、文系の学科は何とかなります。例えば経済学部では数学をやりますから。 最近は、文部科学省で学部や学科を再編しているので、かなり分離の境目が曖昧になっている気がします。理学部でも、コンピューターでシミュレーションするような研究をテーマにする先生もいて、そこの研究生はいわゆるIT系のところに就職したりもします。ですから、インターネットなどで学部の情報を見てピンと来るところを選ぶといいと思います。例えば、生物で何か研究がやりたいなと思っていたら、そういう研究室があるような大学を探されて行くと良いと思います。ただ、インターネットで調べて面白そうだなと来てみたら、先生が定年で辞めてしまったりする場合もあるので、そこは注意をされてください。
曲渕さん:
令和7年度から、埼玉県内の教員志望人数が少ないので、地元で教員になることを想定した地域枠を設定すると聞きました。教育学部ではどのぐらいの地域枠を設ける予定でいるのでしょうか。
藤原先生:
学科によって違いがあるかもしれませんね。教育学部1年生の長尾さん、いかがですか。
長尾 みずきさん(以下、長尾さん):
教育学部は、小学校コース、中学校コース、それから、乳幼児教育、特別支援教育と、あと養護教員というのに分かれていて、小学校・中学校コースはさらに教科ごとに専修が分かれています。その専修によっても、全体の募集人数や推薦と一般を合わせた人数も結構違っています。例えば、私が今、所属している中学校コースの社会専修は、定員が一般の先生を合わせて10人で、推薦が2人、残りの8人が一般です。
藤原先生:ありがとうございました。
現役大学生からのメッセージ

藤木 一聡さん(埼玉大学 理学部1年)
長尾 みずきさん(埼玉大学 教育学部1年)
現役大学生からのメッセージ①
理学部 1年 藤木 一聡さん
興味を持てば、勉強も苦でない

改めまして、理学部基礎化学科の藤木一聡です。理学部に決めたきっかけは、かっこいいからですね。理学をやっている人は、難しい専門用語を普通に操っている。それから、突き詰めていくということ。例えば私たちは、普通に生活していたら、空気は物質だなと思わない。正直、元素が何でできているのか知らなくたって、生きようと思えば生きられますよね。そんなことを突き詰めていく人たちはかっこいいし、面白いなと思ったので、理学部にしました。
受験勉強を始めた時期は、学部選びとも密接に関わるかと思います。私の場合はスタートが遅くて、高校1、2年生は他に打ち込むことがあったので、勉強はすごくおろそかにしていました。高3の春に受けた共通テストの模試が380点という、もうどこも受けない方がいいのではないかという点数でした。そこからようやく火が付いて、とりあえず学校の近くの塾に入りました。始めてみると勉強って面白いもので、自分は世界史がすごく得意だったので、高2の終わり頃には全部勉強を終わっていたんです。理学の中では化学が特に楽しくて、夏ぐらいまでには全部終わらせました。
高校のカリキュラムは大学でやる内容をちょっとずつ網羅しているので、ちょっとでも興味があるとか、何でこんなことができるのか不思議だとか、自分もロケットを飛ばしたいとか、そういうのがいろいろ出てくると思います。
私自身も大学のホームページやパンフレットは全然見ていなくて、勉強していたら好きなことが見えてきましたね。
今は一人暮らしをしていますが、親がいないのは寂しいもので、毎日電話をかけています。いつもありがとうねみたいな話をして、今日こんなことがあったとか、家で飼っている犬の話をしたりなど、1時間ぐらい話しています。
卒業後の進路については、順調に進んでも4年間あるので、まだあまり決めていません。ただ、そのまま研究者として進むのか、それとも何かやりたいことを見つけるのか、早いうちから決められる方もいらっしゃいます。
自分の高校の理数科は、ほとんど全員が医学部に行くクラスでした。だから、クラスの8割、9割ぐらいは入学時点で医者になるとか、薬剤師になるとか、獣医師になるとか決めていました。私は卒業してもう9カ月になりますけど、何をするかと聞かれたら、まだわかりません。その時にしたいことをすればいいかなと思っています。好奇心で生きているような人間なので、好奇心の赴くままにとりあえずやってみています。
保護者の方からの質問
曲渕さん:
先ほど高3の春から本格的に火が付いて、勉強をする過程の中で「面白い」という表現をしてくれていましたが、どの部分で受験勉強が面白いという感覚になったんですか。
藤木さん:
私の場合は集中力がなくて、みんなみたいに400問出題されるようなワークを解けないんです。それよりも1問を突き詰める方が楽しい。教科書って、一応網羅はしているんですけれども、表面しか出てこない。表面の知識を知ったところで全然わからないけれど、何か興味ありそうなところにストローを突き刺して底の味を覚えると、面白い、面白い、面白いってなります。面白いのは教科書以外のことですね。
曲渕さん:
深掘りしていくということですか。
藤木さん:
そうですね。教科書を読んだり、先生の話を聞くというのは、もちろん大事なことなのですが、小学校6年間、中学校3年間、高校2年間、その大事なことをそんなにしていなかった。それよりも、じっくり教科書を読むと、「よく考えたら、原理の説明をちゃんとしていないな」と引っかかるところがあるんです。そういうところを掘り下げる。例えば、炎色反応を覚えていらっしゃいますか。金属に火を付けたら色が出るというあれです。ナトリウムは黄色というような。何か頑張って色を覚えたけれども、その理由は習っていない。教科書は、「え、なんで?」という突っ込みポイントがたくさんあるんです。そういうものを深掘りする過程が楽しいんです。
自分でやることなので、モチベーションが下がらないんですよ。だから、1日の勉強時間は受験期でも1時間もやっていないくらいでした。ですが、普段の教科書の読み方が変わったので、共通テストの模試では380点だったのが、本番は705点取れましたし、浪人もしませんでした。
あと、そういう掘り下げは大学に入ってからも役立ちます。普段からそういう読み方をしていると、常に疑問を持っているから、教科書を読んだ時にどこがわかっていないのかもすぐわかるし、自分なりのテーマが見つかります。大学の授業は、いろいろな専門分野で深い話を聞くので、テーマがなかったら全部ばらばらな学びになってしまいますが、テーマがあれば、自分はこういうことをベースに学ぼうとか、どこかの分野から似たところを見つけて学ぼうといったことができるので、そこが楽しいです。
木田さん:
親御さんはどういう風に見守っていらっしゃったのかなというのが気になります。一人暮らしをしていても毎日1時間もお話ができる関係性で、私もそのようになりたいなと思います。親御さんはどういう風にバックアップされていたんですか。
藤木さん:
うちの親は結構、自由放任でした。ただすごく恵まれたなと思っています。勉強の本だったら買ってくれるんですよ。こういう動機があって、こういうことを学びたいんだよねという話をしたら、それに対して惜しみなく投資をしてくれるんです。
ゲームや漫画は絶対に買ってもらえないし、そういうのはお小遣いでやってと言われるんですけれど。
私は大学に入ったらいろんな言語をしゃべれるようになりたいなと前々から思っていて、ラテン語とアラビア語を中心に勉強しているんですけれども、その話を電話でしたら、1週間後にラテン語の教本が4、5冊届きました。
木田さん:
親御さんがピックアップして勝手に送ってくれるんですか。

藤木さん:
はい。中古だけどねって言って、辞典と練習用のノートみたいなものを送ってくれました。口に出さないけれども、応援しているよというのがよくわかります。何か期待されている感があって、こっちもその期待に応えようと思います。
木田さん:
高3の春まではどんな感じだったんですか。
藤木さん:
本当に自由放任なので、宿題をやれと言われたこともあまりないですし、テストの点が低くても怒られなかったです。ただ、しつこく何回も言われたのは、「あなたの責任だからね」って。どうなっても私は責任は取らないからねって。あなたのやった行動で全部決まっているのだから、サポートはするけれども、与えられた機会で勉強をしなかった。例えば、大学に全部落ちて、あまり行きたくないところに就職することになったとしても知らないからね、と言われました。でも、やりたいということに対しては、頑張ってねと応援してくれる親でした。
川下さん:
掘り下げて勉強するようになったと言っていたのは、塾でそういう時間を持てたということですか。
藤木さん:
いえ、中学校ぐらいから、それはしていました。ただ、掘り下げる内容が5教科じゃなかったので、成績がとことん落ちていました。中学校の時は仏教や歴史をやっていたので。
川下さん:
でも、スイッチが入ってから点数が伸びたわけですよね。
藤木さん:
そうです。開いていなかった教科書を開くようになったら、意外と気になる点が多かったので。あと、あんなに成績が低かったのにも関わらず受験は応援してくれて、塾にまで入れてもらったらやるしかないと思っていました。
塾もアウトプットするとものすごく定着が早いんです。例えば教科書の内容をまとめ直すとか。先生の板書を取るのも、書いてあることをわかりやすく整理するだけだったら簡単なんですけれども、追加で疑問点を書き加えたりとか、その疑問点を調べて解決してみたりとか、自分用の教科書をつくるとすごく納得がいくんですよ。
そうして学んだことを他人に話すとどこで話が止まったかわかります。塾に行ったら、少なくとも勉強する気のある人が学校よりは多いので、「勉強を教えます」というのはしやすかったです。
木田さん:
予備校にそういう時間があったんですか。
藤木さん:
いや休憩時間中に、その時に周りにいた人を捕まえて教えたりしていました。
教育学部 1年 長尾 みずきさん
自分の譲れないことから受験校を吟味

私は、大学を選んだ理由と、部活と勉強の両立についてお話しさせていただこうかなと思います。私は埼玉大学を受験すると最終的に決めたのは、共通テストが終わってからでした。もともと候補として考えてはいたんですけれども、一段上のところを目指していて、共通テストはそこまで数字が取れなかったので、埼玉大学に決めました。
高校に入った頃から教員になりたいと思っていて、それなら普通の教育学部や教育学科よりも、教員養成の課程を学びたいなと思いました。教員養成の授業が受けられるところを調べていくと、国公立が多かったのです。私は文系科目も理系科目も満遍なくできるタイプだったので、それも生かせる国公立がいいかなというところで調べていきました。最終的には、埼玉大学と、あともう1校を候補に選びました。私自身は埼玉の出身で、将来は埼玉で教員になりたいと思っているので、地元で教員を目指すためにはいいのかなと思っています。
受験校を絞る上で大切にしていたのが、自分のやりたいことや、自分の中で絶対に譲れない条件ときちんと合っているか、吟味することでした。私は高校に入学してすぐの頃から教員になりたかったので、教員養成の課程があることと、教員になる上で幅広くいろいろ学べるところ、というのが譲れない条件としてありました。
私立で教員養成の課程がある大学はかなり狭まってしまって、関東だと3、4校ぐらいしかありませんでした。私の場合は歴史がやりたかったので、歴史学科をいろいろ調べました。その中でも、入学する段階で東洋史、西洋史、日本史というふうに専攻が分かれてしまうところと、入学してから2年、または3年生で専攻が分かれるところ、あとは4年間分かれないところもあります。初めから偏ってしまうのは嫌だったので、少なくとも1年生のうちは、東洋史とか西洋史とか関係なく、幅広く学べるところを探しました。
部活を続けるからこそ、短い時間を有効活用

次は、部活と勉強について話をしたいと思います。私は、高校時代は3年間陸上部でマネージャーをやっていました。平日と土日に1日ずつ休みがある程度で、部活がある日は、授業が終わった後にだいたい16時〜19時ぐらいまで3時間みっちり。休日は午前中に練習をしっかりやるという感じでした。なので、確かに部活をやっていたころは勉強と両立するのが大変でしたが、私は部活をやめて勉強に集中しようと思ったことは一度もなかったです。というのは、ちょうど高校1年生の冬休みから3学期にかけてコロナ禍で、埼玉県から部活動は原則禁止という要請が出たのです。それで、冬休みの始まりから3月の初めぐらいまで、まったく部活ができなかった。その時にきちっと勉強を頑張れればよかったんですけれども、自由に使える時間が増えたことで、なんとなくだれてしまって。部活をやめたところで勉強をしないのであれば、あまりにも厳しいなと思ったんです。なので、部活は続けてきました。
部活がある間は本当に部活中心で、あとは帰ってから1時間ぐらい勉強するか、電車に乗っている時間に英単語帳を見る程度でしたね。そういう隙間時間の勉強と、家庭で最低限のことをやる。次の日の授業に支障が出ないように、自習程度にとどめていました。その代わり、テスト1週間前からは部活が休みになったので、その間は勉強にしっかり集中していました。部活が休みになったら、仲の良い友達と学校に残って、みんなでわいわい勉強して過ごしていました。
私は部活と勉強のメリハリをしっかりとつけてやることを大切にしていましたが、周りには、勉強に集中するために途中で部活を辞める人もいましたし、実際にそれで東大に行った人もいます。集中力があるのであれば、部活をやめるという選択肢も決してなくはないのかなと思っています。
受験生の保護者座談会

部活も進学先も子の思いを尊重したい
木田さん:
とてもタイムリーな話で、昨日の夕方、息子が急に部活をやめていいかと言ってきました。今は陸上部に入っています。高校の部活の中では、陸上部はだいぶ緩い方だと思います。土日もどちらか休みですし、平日もお休みがあります。通常の場合だと、中島さんがお話されていたように、部活をやりたくて勉強がおろそかになっていくことが多いと思うのですが、うちの息子は勉強を頑張りたいようです。テストや英検の日に部活を休みますと言うのが嫌みたいです。私自身は両立してほしいと考えているので、もう一回考えてみてと話して保留にしています。部活動はやはり、最後の力を振り絞れるところが良さではないかなと思っています。
息子の学年は、高校1年生の時にコロナ禍になってしまい、学校に行けない期間が約6カ月、部活動がまったくできない期間が約1年ありました。ですから、学年全体の平均的な体力も低いと思います。高校の3年間、部活としっかり両立してほしいなと私は思っています。
川下さん:
うちの子は今、卓球部に所属しています。高校は文武両道の伝統的な男子校です。ラグビー部や野球部、サッカー部は土日も休みがなくて、先生がものすごく厳しいです。
卓球部には顧問の先生が4人いて、先生たちはローテーションで休んでいますが、子どもたちに休みはない。休むということを言えないんですね。息子は海外に留学したいので英語の塾にも行っていますし、予備校にも行っているのですが、部活が終わってからだと間に合わない。でも部活は早退できないんです。
本当に大変だと思いますけれども、先ほど木田さんがおっしゃっていたように、先生たちは「最後まで部活をやり抜いた子は体力も集中力もある」という考えが基本にあるようです。今回県大会に行ったら、先生方の目の色が変わったので、学生を評価する対象にもなっているかなと思います。
高校は男子校なので、生徒同士はすごく仲がいいんですね。うちの子は、この子たちと一緒に卒業アルバムに載りたいという一心で部活を頑張っているようです。

荒井さん:
高校1年生の次男は、軽音学愛好会というサークルにおります。活動日も週に1回。それでも彼は勉強をしないから、両立以前の問題だと思います。ただ、高校3年の姉は、3年間部活をやってよかったと言っています。大学を卒業した長男も3年間サッカー部に所属していて、それこそ土日は休みがありませんでした。それで成績が急降下してしまい、1年間浪人したんですけれど、それでも達成感は半端なかったと言っていました。しんどそうでしたけれども、後悔しなくてよかったなと思っています。
ですから、上下関係が度を越えて厳しい部活でなければ続けるのがいいのかなと、3人を見ていた経験から思いました。
中島さん:
息子も部活動をやりたくて今の高校を選びましたが、うちの子は野球部なので、土日の練習がかなりハードです。私としては、部活動をやりたいという気持ちはやはり尊重してあげたいです。今の時代に部活動を一生懸命できる場はそんなにないと思うので、長い人生を考えたら、高校でやりたいことをしっかりやっていくのはいいことだなと。社会に出てからもきっとどこかで役立つかなとは思っています。部活から帰ってくると疲れて寝てしまうことの方が多いので、親としては不安が強いんですけれども。引退してからでも巻き返しはできるので、今は見守ろうかなと思っています。
曲渕さん:
私の息子は中学までソフトテニスをやっていまして、当然高校にもソフトテニス部はあるのですが、関東大会に出場するくらいの強さでレベルが高い。それで、今はダンス愛好会にいます。愛好会なので、先生主導ということもなく、生徒一人一人が考えて活動しています。自分の子どもが自分なりに考えて、精いっぱいできることをやっているところを見ていると、やっていて損はないのかなと思います。一生ものの友ができると、よく高校でも言っています。友情を築ける場でもあるので、入っていた方がいいのではないかなと思います。
木田さん:
この間、高校受験が終わったばかりなので、まだそこまでは考えていません。ただ大学へ進学するにあたって、できれば学校主導で、大きな世界があるんだよということを教えてほしいなと思います。私が知っている世界より、子どもが考えている世界はまだ小さいし、私も今の時代をわかっていないので。昔と違って、いい大学を出ればいい就職先があるという時代ではないということを、もっと子どもにはわかってほしいです。先ほど留学というお話もありましたけれど、高校、大学からグローバルなものを伝えていただけたらいいなと思っております。
川下さん:
うちの子どもが心配しているのは、2025年から大学入試が変わって、出題科目が多くなるということですね。親としてもそこを一番心配しています。下の代の子たちは人数が多く、すごく優秀なんですね。長男が受験した6年前は違って、公立などは1浪ありきだったのですが、うちの子は浪人という選択肢は絶対ないようです。
コロナで部活がお休みになって、勉強する時間を持てたようで、みんな現役で大学に行っています。ですが、また部活が始まってしまったのでこの子たちの代から大変。浪人もできないのでとても心配しています。合格するにはどのくらい努力が必要なのかということを、今日は聞きたいなと思っていました。
荒井さん:
心配なことは学力です。勉強量が足りているかなと。確かに現役で入れるのが理想ではありますけれども、それで自分を追い込み過ぎておかしくなってしまったらかわいそうなので、そこは気にしていません。
大学は椅子取りゲームのように決めてはいけないと思うから、学力だけで決めてほしくないという面もあります。でも、高校生の時点で、自分が大学で本当に勉強したいこと、将来に向けて学びたいことをつかんでいる子の方が少ないと思います。その辺の兼ね合いが難しいですね。
中島さん:
先ほどお伝えしたとおり、今は部活に専念しているので、学習の面がやはり心配です。中学では進学塾に通わせていてそこが頼りだったのですが、今は予備校にも行っていないので。ただ、自分が学びたいという気持ちがないと、やたら塾に通わせても意味がない。大学ではより専門的なものを学ぶわけですから、自分で楽しいというものを見出して、それに専念してほしいです。今は模索中ですが、応援しています。
曲渕さん:
冒頭で話したとおりなのですが、息子はまだ高校で理系と文系のどちらにしようかなと迷っているぐらいの初歩的なところなんですね。親としては、長男の大学受験の経験があるので、どのぐらいからスタートしなければいけないのかはなんとなくはわかっています。でも、例えば将来どのような仕事に就きたいとか、どういったことを学びたいということさえ、わからない状態なんです。おぼろげながらも「こういう方向に行きたい」とか「こういう大学のこういう学部に行きたい」といったところが明確にできれば、道筋も見えてきますし、勉強をやり出すきっかけにもなると思うんです。
親の希望を押し付けると、限界を決めてしまう可能性もあると思うので、限界を取っ払って、自ら希望を見出してほしいなという気持ちがあります。見守りつつ、なんとか仕向けていきたいです。
自分の進む道を見つけることに期待
木田さん:
私はもっぱらインターネットです。情報誌なども特に取り寄せていません。先日、冊子のようなものを購入してくださいと高校から300円ぐらいの請求が来ました。それはいろいろな大学の情報が載った冊子だったようです。
川下さん:
私もインターネットで調べることが多いですけれども、今2年生で、志望校を検討する時期なので、毎日のように大学案内の冊子が届きます。どこの大学も大手の塾と提携していて、10校選ぶと図書券をいただけるというキャンペーンがあって。地方の大学からも案内が来ていますね。
荒井さん:
私もまずはインターネットで集めます。でも、インターネットは結局良いことしか書いていないので、行ける範囲で足を運んで、実際に大学を見るようにしています。
中島さん:
私はたまにインターネットを見るぐらいです。本人が何をやりたいか明確には決まっていないので。親ではなく子どもが自分でどんどん情報を収集してくれるようになるのがベストだと思うので、それを横で一緒にサポートできるような状態になるのを、今は待っているところです。

曲渕さん:
先ほど、パンフレットをまとめて取り寄せできるという話がありましたが、うちも無料のものを取り寄せた程度です。
川下さん:
GMARCH以上、早稲田・慶応は有料です。1冊500円〜600円程度なので、送料だけだと思いますが、人気が高いところは全員に無料で送っていたら大変な経費がかかるのだと思います。
オープンキャンパスについてお伺いしたいと思います。オンラインも含み、オープンキャンパスには行きましたか。
木田さん:
1年生で一番きらきらしたところを見たほうがいいだろうと思ったので、東京大学か明治大学に行こうということで、友達と話し合って明治に行ってきました。オンラインは東京工業大学に申し込みました。
川下さん:
オンラインは、キャンパスまでちょっと距離がある筑波大学だけ。実際に足を運んだのは、去年は埼玉大学、今年は明治大学です。
荒井さん:
オンラインは参加したことがありません。1年生は、夏休みの宿題でオープンキャンパスに行かなければならなかったので、本人に探させて、甲府の山梨大学に父親と2人で行ってきました。
中島さん:
うちも宿題で出ていたようなんですけれど、本人に聞いたところ、お友達も行かずに書くということだったので、そんなレベルです。
曲渕さん:
うちもオンラインは見ていないです。オンラインだとその大学の肌感が分からない、雰囲気が分からないと思うので。
木田さん:
やはり大学に期待するのは、もっとできることはたくさんあるんだと、世界を見させてほしいということです。
曲渕さんからもお話があったと思いますが、まだ職業を選べるような年齢ではないのかなと。去年、高校を選ぶにあたっても、どのように選んだらいいかもわからないという状況でしたから。大学を選ぶ時も、たぶん職業まではイメージが掴めないと思います。うちの息子はIT系に行きたいそうなのですが、カタカナばかりで、私自身も一体どのような職業なのかすらわからない。新しい職業がどんどん出てきますから、この時代に、私たち親世代が「この職業がいいんじゃないの」なんてアドバイスするのもおこがましいような気がします。手堅い職業もたくさんありますけれど、親が知っている職業から選ぶのではなくて、このような分野で活躍できるのではないかというものを、大学で見つけてほしいです。君にはこういうものが合っているのではないかと、身近な大人以外からも教えてもらう年齢だと思うので。息子は片田舎の小さな中学校から都内や海外に出ていくことになるので、そういう知らない世界を教えていただきたいなと思います。

川下さん:
うちの子が選ぶ大学であれば、保護者としては全力で応援するしかないんですけれども、私個人の意見としては埼玉大学が一番で、埼玉県のために役に立つ人材になってほしいと思っています。それは常日頃から、息子にもそれとなく話しています。生まれも育ちも埼玉なのだから、埼玉の企業でもいいですし、何か埼玉県の役に立てるような人間になってほしいと。
荒井さん:
私は勉強を好きになってもらいたいです。何かを一つ深く学ぶでもよし、広く学ぶでもよし。それで学ぶことが好きになってもらいたいです。
中島さん:
大学に行くのはやはり学ぶ目的があるわけであって、みんなが行っているとか、名前が知れているとか、そういったことではなくて、本当にやりたいものを探しに行ってほしい。やりたいことを存分に学べる環境が、一番期待することです。
せっかく行ったのに、やっぱりちょっと違ったなとかいうのがあっては困るので。自分が楽しいと思えることを学べるのが一番いいのかなと思います。将来に渡って学び続けられること、自分に役立つことを見つける場として、大学に通ってほしいというのが希望です。
曲渕さん:
皆さんと同じです。基本的に大学は専門性を養う場ですよね。私も今の年齢になって、また学び直したいなと思うことがあります。大学は教授との距離が近いので、コミュニケーションを取って、自分の力になってもらう本当にいいチャンスだと思います。そういった巡り合いを期待しています。
放っておくと食べない?食事面には不安
木田さん:
本当にできた息子で、決まった時間に決まったことをやるタイプなので、生活面に関しては心配していません。ただ、誰かに誘ってもらわないと家から出ないと思うので、その辺りですかね。人との交流より、自分で全部考えてやっていくことを優先するタイプなので、友達付き合いがちょっと心配です。

木田さん:
そうですね、結構自分で食べたいものを作っています。逆にコミュニケーションはちょっと心配なので、家から通えないところだったら、寮に入れようと思っています。コミュニケーションが取りづらい年代なのかなと思っていて、いやが応でも人が来るような寮がいいかと思っています。
荒井さん:
うちは、一にも二にも食事です。今の若い子は、放っておいたら何も食べない子が多いですよね。長男も一人暮らしをしていましたけれど、見ていると、朝は食べない、昼は食べない、夜はお腹が空いたら食べるといった感じです。お金がもったいないのではなくて、お腹が空かないからどうのこうの、現代の人間は1日1食でいいんだとか屁理屈をこねてみたりするので、親としては心配でした。
若い人が食べないのは、日本だけではないらしいです。ある外国のバレエ団を受け入れる仕事をしたことがあるんですけども、そこの団長さんは、とにかく夕食はみんなで一緒に食べることが条件だと言うのです。普通、芸術団が日本で公演する時は夕食を付けないのですけれども、そのバレエ団は付けてくれと。受け入れ側としては困ったことなんですけど、団長さんが若い子にとにかく食べさせたいという気持ちは痛いほどわかりました。
曲渕さん:
私は、学生時代に一人暮らしができなかったので、それを子どもにはさせてあげたいなと思っています。確かに食事が心配な面ではあるのですが、長男も今、一人暮らしをしていて、親のありがたみがわかってきたようです。たまに帰ってくると、何かにつけて親に対してありがとうと言います。一人暮らしも有意義というか、必要な部分なのかなと思いますね。
木田さん:
埼玉県の県民共済に入っています。けがを補てんするものと、何か壊してしまった時の物損関係の保険に入っています。
川下さん:
うちも同じです。
荒井さん:
うちは、特に入っていないです。家族保険に一緒に入っている感じです。
中島さん:
生命保険はやはり同じで、県民共済に入っています。あとは学資に入っていますね。
曲渕さん:
私もそうですね。学資保険と、埼玉県の県民共済。長男は一人暮らしなので、生協さんの一人暮らし用の保険に入っています。個人賠償責任は一家で入れる保険でカバーしています。
本日はありがとうございました。
2023年9月24日(日)埼玉大学にて
Contents
質問会