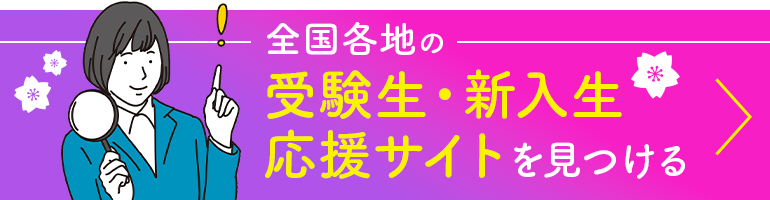近畿地区組合員保護者座談会(2024年開催)
子どもの意思を尊重しながら進める、受験と大学生活
時代とともに、大学入試、生活スタイル、デジタル活用、国際性・多様性など、学生を取り巻く状況は変わってきています。
今回は、近畿地方の大学に進学された学生の皆さまとその保護者さまにお集まりいただき、受験期や新生活準備の苦労、実際に大学に入ってからの生活についてお話を伺いました。

黒字:保護者様 青字:お子様
写真後列左より(保護者)
- 増田 一実さん(長女が立命館大学2年)
- 稲嶺 正一さん(長男が同志社大学3年)
- 南部 美穂さん(長男が京都大学1年)
写真前列左より(お子様)
- 増田 実玖さん
立命館大学産業社会学部2年 - 稲嶺 一廉さん
同志社大学経済学部3年 - 南部 悠樹さん
京都大学総合人間学部1年
Contents
受験期の学習状況と、親の不安
増田一実さん:
うちは自分の部屋があって、机もちゃんとあるのですが、リビングでやることが多かったです。
増田実玖さん:
自分の部屋は静かで集中はしやすいのですが、試験本番は大勢いる中でやるので。臨場感を味わったほうがいいと思って、常に何か音がする状況でも集中して取り組めるようにリビングでやっていました。
稲嶺正一さん:
うちの場合、上の娘のときはリビングでやっていたのですが、息子は自分の部屋です。あとは学校で少し残って勉強をすることもありました。
南部美穂さん:
私が知る限り、家ではやっていませんでした。学校の図書館や予備校の自習室でやって、家はもう休む場所と捉えていたと思います。私たちが寝静まった後は分からないですが、彼が家で勉強している姿を見たことはありません。
増田一実さん:
急に立命館大学を受けると言われたことです。
増田実玖さん:
高校3年生の7月初め頃です。保護者と受験生向けの大学説明会に父と行ったのですが、AO入試や総合選抜でも受けられて将来の幅が広がりそうだなと感じ、立命館大学を受けてみようかなと思いました。

増田一実さん:
10月には試験を受けて、その間に書類など一式を学校に揃えていただいて。私の気持ちが追い付かないまま決まってしまいました。不安なのは、私が一番何も分かっていなかったということです。
稲嶺正一さん:
受験期間中では、ちょうど新型コロナなどもあり、特に妻が体調管理の部分を気にしていたと思います。もともとイベントのタイミングに体調を崩すことが多かったので、そういうことがないよう、できるだけ気を使わない環境をつくっていました。
南部美穂さん:
うちは京都大学を受けようと決めたのが昨年8月頃だったので、志望校が決まるまでに時間がかかりました。家から通える大学を狙うか、一人暮らしになる京都大学にするかで、ずっと迷っていて。サポートの仕方がまったく変わるので、どうなるか心配でした。
あとは入試のためのホテル予約です。9月頃に入試のためのホテルを予約しようと、京都大学生協のホームページを見ました。会場までの送迎バス付きプランがあったのですが、その時点で全部埋まっていました。
大学選びにおける親としてのアドバイス
増田一実さん:
アドバイスは、たぶんしていないです。

増田実玖さん:
いえ、してくれました(笑)。今所属している「産業社会学部がいいんじゃない」というのを、両親が提案してくれたんです。産業社会学部は、多角的に社会学について学ぶことができ、[現代社会専攻・メディア社会専攻・スポーツ社会専攻・子ども社会専攻・人間福祉専攻]に分かれています。決めきれないながら私は、「メディア社会専攻」がいいと思っていました。カメラや映像も好きなので「メディア社会専攻に行きたい」と言っていたら、「それだと志望理由として少し甘いんじゃない?」と言ってくれたんです。私は「ただやりたいことをやるため」に大学に行く感じだったのですが、「将来にどうつなげるかを考えたほうがいいよ」と、母が気付かせてくれました。子どものことが好きということもあり「子ども社会専攻」にしたのですが、すごく入って良かったと思います。
増田一実さん:
自覚はあまりないのですが、それがアドバイスになっていたんですね。東京の大学にもそういう勉強ができるところがあって、立命館大学を推していたわけではないのですが、夫と娘でどんどん話が進んでいきました。
稲嶺正一さん:
私も「こうして」とアドバイスした覚えがあまりなくて。ただ、「行けるところよりは、行きたいところを自分で意識しながら選んだら?」と言っていたと思います。
南部美穂さん:
うちは、志望校選択は完全に彼の意思決定によるところで、アドバイスは一切していません。
増田一実さん:
すべて子どもに任せました。

稲嶺正一さん:
うちは中高一貫校だったので、学校説明会があったり、受験の具体的な情報を比較的早いうちに聞けていました。あとは予備校です。偏差値などを比べながら、息子も行きたい大学を重ね合わせながら、情報を見ていたと思います。
南部美穂さん:
参考にしていたのは、予備校の保護者会などで提供される情報です。また、「テレメール」という大学からパンフレットなどを送ってもらえるサービスを利用して、受験の可能性がある大学から資料を取り寄せていました。このサービスに登録すると、その大学からいつも情報がアップデートされるので、必要なものを息子に伝えていました。
増田実玖さん:
私は東京の学校に通っていて、実は立命館大学のオープンキャンパスには行っていません。立命館大学に決めたのが高校3年生の7月頃で、AO入試までの期間がものすごく短く、その期間に小論文の対策と面接対策をしなければいけなかったので。「オープンキャンパスに行かなくていいの?」と母から言われましたが、行っている余裕がありませんでした。
稲嶺一廉さん:
自分は高校2年生のときにコロナ禍に入ってしまって、最後に見たのが高校1年生のときの学校の課題としていきました。そのときはまだ志望校も全然決まっていない中、友達と淡路島を出て京都大学のオープンキャンパスへ父親に連れていってもらいました。それ以降はコロナ禍で行けなくなりました。
南部悠樹さん:
自分はオープンキャンパスには行っていません。志望校を決めたのが7月終わりから8月初めぐらいと遅いこともありまして。それに、オープンキャンパスに行って受かるならいいのですが、「意味があるのかな?」という思いも少しあり、行きませんでした。友達や母親から大事な情報は教えてもらっていたので、十分かなと考えていました。
学生が受験期で一番悩んだこと
増田実玖さん:
私が通っていた学校には付属大学があり、高校3年生の7月より前の時点では、そこへ行こうと考えていました。併設校受験は評定で決まるので、必死にしがみついていました。それから、立命館大学をAO入試で受けることになり、一般入試との時期の違いなどで、友達関係で少しギスギスしてしまったことがあったんです。私が小論文などをやっているときに、横で「あそこに遊びに行こう」「最後の夏休みだからここに行こう」という話をされたり、逆に私の受験が終わってからは一般入試を受ける人が忙しくなり「いいよね、気楽で」と言われたこともありました。やっぱり受験期はメンタルが弱くなってしまうので…。でも、今の自分からそのときの自分にアドバイスするとしたら、「自分の信念さえ持っていたら、そんなの全然気にしなくていい」と言ってあげます。

稲嶺一廉さん:
自分は、受験期に成績の波があって、ずっと安定しなかったことが悩みでした。高校3年生のときは模試を受ける回数が多くなりますが、良かったり悪かったりの波が激しくて。いつまでたっても不安で、悩んでいました。もう一つは志望校です。大まかに経済学部を受けようという気持ちはあったのですが、どの大学を受けるのか、どの日程で何回受けるのか、私立も何回受けたら安心なのかと、決めるのが難しかったです。
南部悠樹さん:
受験期は自分のペースを保つのに苦労しました。友達からは「1日何時間、勉強しているよ」「模試で何判定だよ」「今、何の参考書やっているよ」という話が出たり、インターネットでは「京都大学に受かるなら、高3のこの時期なら、これぐらいの偏差値は取りたいよね」のような本当かも分からない情報が手に入りすぎる中で、「自分はこれで間に合うのか」「もっと睡眠時間を削ってやったほうがいいのかな?」という迷いが生じて、気持ちを保つのが大変でした。
合格決定後の入学準備の実情
増田一実さん:
うちは夫の転勤が決まり、家族全員で京都に行くことになりました。子どもを一人で送り出す心配はなくなったのですが、引っ越しを私自身がしたことが一度もなかったのでそちらの心配のほうが大きかったです。
稲嶺正一さん:
うちの場合、上の娘が先に大学に入っていたので、入学のためにすべきことはある程度分かっていました。今、息子と住んでいる部屋は、以前は娘と住んでいたところです。

南部美穂さん:
不安はやはり住まい探しです。3月10日が合格発表で、決まったらすぐに探しに行かなきゃと。受かるかどうか分からない中で内見もできないので、そこから決まるのかは本当に不安でした。
合格発表の前に息子から、「何となく受かるんじゃないか」という言質を取りまして。2月中ぐらいに、もし残念だったら「ひそかに取り消しておけばいいね」という考えで、息子には知らせずに親だけで不動産屋に予約を入れました。うちは引っ越しの経験が多いので、一人分の引っ越しくらいはもう何でもないと思っていました。
増田一実さん:
合格後に送付されてきた資料の中に案内が入っていました。何も分からないので、とにかく資料やホームページがあるものは全部見ていこうと、娘と一緒に見ました。実際に出向かなくても情報を得られるのでありがたいです。
稲嶺正一さん:
妻は見ていたかもしれませんが、私は存じ上げていなかったです。中心にしていたのは「テレメール」で、入学準備に関する様々な情報を見ました。その中の情報にZoom説明会があり、妻と息子が見たということを聞いています。
増田一実さん:
うちは幸いなことに合格決定が早く、大学生協主催のZoom説明会を一通り受けられました。とても手厚く、分かりやすいと感じながら、余裕を持って手続きができました。
稲嶺正一さん:
手続きはまだやり方が古いというか…。専用の振込用紙が送られてきて、平日の昼間に銀行窓口まで行って振り込む必要があり、ネット振込などは使えませんでした。それは、立命館に通う上の娘のときも同じでした。
南部美穂さん:
うちの場合、3月10日に合格発表があり、14日までに手続きを完了させる必要がありました。振込用紙は、2次試験の最終日に各受験生に配られていました。合格発表の10日は日曜日だったので振り込めず、翌日本人と夫が京都に向かう中、私は銀行へ。振込用紙と共通テストの受験票を大学へ「14日必着」で送るという過酷なタスクで。家探しと入学手続きを同時にするのは、本当に大変でした。
増田実玖さん:
私は立命館大学のオープンキャンパスに行っていなかったので、どういう学部があるのか、自分の通う学部・専攻の授業はどういうものがあるのかなど、大学の詳しいことを知っておきたいと思いました。高校から「自分が行く学部・専攻でどういうことを学んでいきたいか?」という入学前の課題があったので、大学の授業を調べ、「この授業だったら自分の知りたいことを学べそうだな」といろいろ考えていました。
また、衣笠キャンパスでは「プレ・エントランスデー」という合格者を対象にしたイベントがあります。12月末に行き、どういうことをしていくかという説明を受けたり、キャンパスツアーに参加しました。
稲嶺一廉さん:
大学に合格した直後は、入学式までに何をすべきかの情報を集めるために、インターネットで調べていました。届いた書類にも案内があり、入学までにすべきことや実際にどういうルートで通うのかなどをチェックしていました。

南部悠樹さん:
受験期は、受かるかどうかしか頭になく、受かった後のことはまったく考えていませんでした。いざ受かってからは、親に言われるがままに京都大学に一緒に付いていって、大学から届く資料に書いてあることにとりあえず従って、気付いたらもう入学式という感じでした。
南部悠樹さん:
親に頼ってばかりでした。
南部美穂さん:
試験が終わってから合格発表までは時間があったので、その間に大学生協のホームページや不動産屋のホームページを見て、どのくらい値頃感のアパートを斡旋しているのかや間取りなどをある程度研究して、合格後にそれを持って不動産屋に行きました。ただ、土地勘がまったくなく。夫が一緒に行ったのですが、動けるのは1日だけしかなく、内見も1つだけでその場ですぐに決めました。
南部悠樹さん:
部屋は「住めればいいかな」くらいに考えていたので、ぱっと決めました。生活用品は、知識も特にないまま母に付いてきてもらって、「これが必要」と言われるがままにです。
南部悠樹さん:
料理は結構好きで、自炊するつもりでした。でも、最初はやっていたのですが、授業が始まってくると、いろいろ面倒くさくなってしまって、5月以降はやめてしまいました。ただ、生活をするのに便利なように家を決めたので、大学まで歩いて通える距離ですし、スーパーが近くにあり、飲食店もあるので、頼りながら何とか暮らしている感じです。そこは運が良かったと思っています。 あとは実際に1~2カ月住んでみて、初めての一人暮らしで見えてくるものがあり、自分で考えていろいろ買い足したり、東京から送ってもらったりしながら、「とりあえず暮らせればいいかな」という気持ちでやっていました。
大学生活には保障も大事

大学生になり、いろんなことが変わっていく中で、どのような備えをされているのかお聞きしたいです。
増田一実さん:
学生総合共済に加入しています。合格後に送られてきた書類の中に案内が入っていて、内容を見て入っておいたほうがいいと思い、早々に加入しました。
稲嶺正一さん:
うちは、私が勤めている会社の組合でファミリーを対象にした共済に加入しています。保障内容を比較した上で、病気・ケガ・自転車の事故など賠償責任もカバーできていて十分だと感じました。
南部美穂さん:
大学生協ではなく、宅配のほうの生協でコープ共済のたすけあいジュニアコースにすでに加入していて、子どもが小さいときから入れています。保障内容も問題なく、大学入学の際に見直して手続きをしました。
学生総合共済に関しては、大学生協が主催する説明会の中で紹介していますが、お聞きになったことはありますか。

増田一実さん:
立命館大学では「プレ・エントランスデー」というイベントがあり、子どもと保護者と別々の会場での説明のときに聞いたと思います。
稲嶺正一さん:
2年半ほど前の話ですが、Zoom説明会の中で説明されていたと思います。
南部美穂さん:
息子が学生を対象とした大学生協のZoom説明会を受けるということで、リビングで視聴している際に耳にしました。
CO・OP学生総合共済とは?
授業のデジタル活用状況とパソコンの購入の仕方
増田実玖さん:
私は先輩とのつながりがあったので、大学に行ったらパソコンを使ったり、iPadでメモを取ったりするという認識はありました。高校ではiPadが生徒一人ひとりに支給されていたので、それを使って勉強するんじゃないかなと思っていました。
稲嶺一廉さん:
メモや資料作成もすべてパソコンで終わらせてしまうのが、大学の授業の受け方なのかなとイメージしていました。
南部悠樹さん:
うちは3歳上の姉がいて、大学でiPadを使ってノートを取ったり、レポートの作成もiPadを使用していると聞いていました。自分も高校のときからiPadに触れる機会が多く、パソコンはあまり得意ではないので、大学に入ってもiPadを有効活用していくのかなと思っていました。
増田実玖さん:
高校の情報の授業では、Word・Excel・PowerPointを事細かくやっていました。ルーラーの出し方やExcelの関数の使い方、PowerPointのアニメーションや図形、オブジェクト作成など、手厚い授業です。全員ではないですが、早期合格者の人がPowerPointで「これから大学に入るにあたって、どういう学びをしていくか」をまとめてオンライン発表という機会もありました。 大学に進学してから「パソコンスキル講座」があったのですが、「高校で習った範囲だな」と思うぐらい、大学で使える知識を教えてもらいました。
稲嶺一廉さん:
うちの高校の情報の授業は、半分が座学で半分が実習でした。座学は、「ギガバイト、テラバイトとは?」や情報リテラシーなど、教科書の導入的な内容です。実習はPowerPointだけですが、基本操作を教わり実際にスライドを作って発表も行いました。
南部悠樹さん:
高校2年生のときに、情報の授業が週に1~2時間程度ありました。ただ、パソコンを与えられた男子高校生がゲームをやっているだけの時間という感じで…。授業で得られたものはあまりありません。
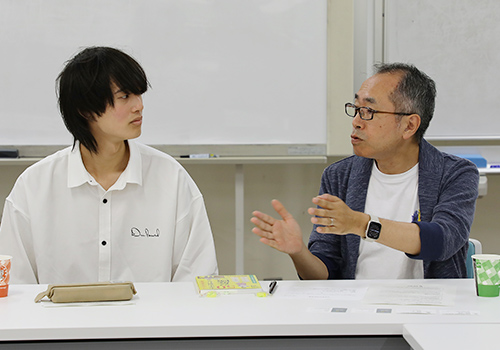
稲嶺一廉さん:
同志社大学では、1年生後期にMOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)でやるような内容の授業があり、そこでやっとスキルが身に付きました。その授業を受けていない1回生前期では、Word・Excel・PowerPointの使い方を知らない状態だったので、レポートや資料作成は苦労しました。
南部悠樹さん:
入学したばかりなので、一つひとつ調べながら何とかやっている状況です。もう少し高校のときにやっておけば良かったなと思っています。
南部悠樹さん:
パソコンとiPadの両方を使っています。自分はiPadのほうが慣れていて、だいたいのことはiPadでやり、課題や文章をたくさん書くようなときはパソコンを使っています。周りも8割方はiPadとパソコンのどちらも使っている印象で、ノートを取るのはiPad、課題はパソコンが多いですね。授業中に資料を見ながら何か書きたいときは、パソコンで資料を見てiPadで書く、という使い方もしています。
増田実玖さん:
私が所属している立命館大学 産業社会学部では、1年生の春だけ必修で「情報リテラシー」という授業がありました。パソコンルームで一人1台パソコンを使い、課題は家で自分のパソコンを使って行います。
それ以降で情報リテラシーやWord・Excelなどについて学びたい人は、「情報リテラシーⅡ」を選択することになります。
稲嶺一廉さん:
自分は同志社大学 経済学部なのですが、商学部と一緒にパソコンの使い方、特にWord・Excel・PowerPointを中心に教わる授業が1年生の秋か2年生の春に取れるようになっていました。あくまでも選択で必修ではなかったです。
南部悠樹さん:
京都大学 総合人間学部では必修の情報の科目はなく、選択で「情報基礎」がありました。私は選択していないのですが、Word・Excel・プログラミングなどについて扱っているようです。
増田実玖さん:
私の学年では、高校1年生のときから一人1台iPadが支給されました。私が中学3年生だったとき、中学1年生は入学と同時にiPadが支給され、学年によってiPadを渡されるタイミングが違いました。
増田一実さん:
タイミングの違いは、おそらくコロナ禍で学校に行けなくなったのが理由だと思います。本来は高校生からの支給のところ、中高一貫校ということで全員に支給して自宅で授業が受けられるように、という学校側の配慮だったと思います。
増田実玖さん:
はい。「Google Classroom」や「Classi」という2つのアプリで、国語や数学など授業単位の連絡はGoogle Classroomから、学校全体の学年便りや生徒会便りはClassiから来ていました。iPadが導入されてから、紙媒体の配布物は圧倒的に少なくなったと思います。
増田実玖さん:
担当の先生によります。紙での提出の先生もいれば、iPadを使いこなしている先生は「Google Classroomにファイル添付して提出してね」という提出の仕方でした。
稲嶺一廉さん:
自分の学校では端末の提供はなく、ずっと紙媒体で連絡は行われていました。
南部悠樹さん:
自分の学校では、情報の授業の間だけ一人1台パソコンが貸し出されていました。iPadは高校3年生のときに一つ下の学年から貸し出されることになり、自分は学校から貸し出されたことはありません。
中学3年生の1学期にコロナ禍で休校になっていたのですが、そのときは授業や課題提出がGoogle Classroomで行われていました。そのときも「各自用意してください」と言われ、学校から貸し出されることはなかったです。
増田一実さん:
家電量販店で購入しました。大学生協のサポートは手厚くすごく迷いましたが、家族全員で引っ越すので「困ったことがあっても家電量販店に行けばいいよね」ということで。子どもだけでなら大学内で完結したほうがいいのですが、うちは特殊なケースだと思います。
稲嶺正一さん:
ネット通販で購入しました。私自身パソコンが好きで、海外メーカーのスペックや、いただいたパンフレットに記載のパソコンのスペック、学部指定のスペックを見ながら、通販で選びました。大学生協は故障時の保障が特徴的で、パソコン選びに慣れていない場合はそちらで購入したかもしれません。
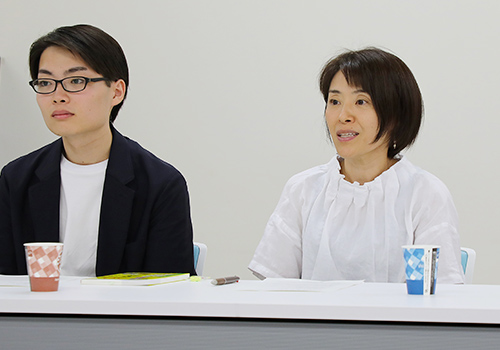
南部美穂さん:
うちは、もともと持っていたパソコンを大学に入ってからも使っていたのですが、どうにも使いにくく、本人から「購入したい」と言われ大学生協で購入しました。大学で使うものは大学仕様になっていたほうがいいですし、パソコントラブルは私では対応できないので、それも含めて任せられる大学生協を選びました。
南部悠樹さん:
大学が始まる前はパソコンをどれぐらい使うかも分からないので、入学のときに買うか少し迷っていました。実際に入ってみて、学校以外でもパソコンを使うことがあったり、バイトでもパソコンを使うこともあったので。パソコンは得意ではなかったので、大学生協で買ったほうが安心かなと思い購入しました。
外国語学習の近況と学習ツール

増田実玖さん:
私はAO入試でしたが、「英語の習熟度分けのテストがある」という話を先輩から聞いていたので、そのために少しずつ英語を勉強していました。大学に実際に入ってみると本当に習熟度分けで、産業社会学部は5段階で分けられ、個々のレベルに合った学習が行われています。私の聞いた限りの話では、一番上のクラスは英語でディスカッションをしたり、ディベート大会などをしているようで、下のほうのクラスでは基礎的な英語の文法などをやっているようです。
私のクラスは、先生によって授業のやり方が違うのですが、週2日あるうちの一人の先生は「Wordを使って英語で文章を書く」という授業で、レポート作成がメインでした。もう一人の先生は「英語のCMを作ってみよう」と動画編集ソフトなどを使い制作して、こだわったところを発表するという授業でした。高校の授業に比べてすごく楽しかったです。
稲嶺一廉さん:
同志社大学は、単位数は一緒ですがレベルで4段階に分かれます。一番上はかなり難しいと聞くのですが、自分は上から二番目で、受験の英語と比べてそこまで差異がない内容です。授業は2種類に分かれていて、週1回ずつあります。一つは筆記で教科書を中心に、高校でやってきたような授業です。もう一つは英会話を中心にしたリスニング・スピーキングで、先生にもよりますが高校でやってきた授業とあまり変わらない授業も多いです。
南部悠樹さん:
京都大学は、リーディングの授業が週に1コマ、ライティング・リスニングの授業が週に1コマあります。リーディングは日本人の先生が選んだ英語のテキストをみんなで読む形式で、いわゆる受験英語の知識で十分かなという印象です。ライティング・リスニングは、リーディングが40人のクラスなのに対して20人のクラスで、ネイティブの先生が担当をしています。リスニングは授業外での課題になっていて、自分で学習していきます。リスニングも受験の知識で何とかなるレベルで、ライティングに関しても英作文を受験で十分にやったので、今のところ困っていません。
1回生前期の時点では、学力によるクラス分けはなくて、さらに英語を学びたい人は「E2」という授業を選択します。すべて英語で行われる授業で、TOEFLの点数によって1回生の後期から履修資格が取れ、2回生の後期からは誰でも履修できる授業もあります。

増田実玖さん:
私の学部では、英語の授業は1回生だけでした。そのときは、高校のときに配られた『Vintage』という英語の参考書と、スマホアプリ「Duolingo」という英語に限らず外国語を学べるアプリを使って勉強していました。
増田実玖さん:
分からない単語を調べるときに、大学ではスマホで検索をするようになりました。ただ、いろんな英語の翻訳サイトを見ていると少しずつ意味が違っていて、結局どれが正解なのか分からないことがあり、電子辞書を使って意味を調べるほうが良かったのかなと思います。実際、大学に入ってからも電子辞書を使っている友達は「すごく便利だ」と言っていました。
稲嶺一廉さん:
授業の課題として学内サイトから出るものや、外部アプリを使う指定があったため、パソコンやスマホでそのアプリを使って復習することが一番多かったです。アプリも特に問題なく、苦労はあまりありませんでした。
南部悠樹さん:
リーディングに関しては受験期からずっと紙と電子辞書で、紙に書き込みながら読んでいくのに慣れています。iPadでやろうとも考えましたが、慣れたものでやるのがいいと思い、紙と高校で購入した電子辞書を継続しています。電子辞書は、余計な機能がないのがいいところです。スマホでは別のものを見てしまうこともあり、勉強する点においては電子辞書のほうがいいと思い使っています。
リスニングは、京都大学に「GORILLA」というサイトがあり、そこで出された課題を最低限こなす程度です。ライティングは、受験期から英作文の添削にAIを使っていて、「おかしなところを直してください」と指示を出せばすぐに直してくれます。そういう面ではAIやスマホを有効活用していました。
増田実玖さん:
立命館大学はどの学部も共通で第二外国語は6単位分取得する必要があり、学部・学域にもより選べる範囲が違います。産業社会学部は[朝鮮語、中国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語]から選べ、私は朝鮮語を選択しました。
学習する上で、朝鮮語の紙の辞書を買ったり、電子辞書で調べたりはしていません。学校で配布された教科書に掲載された二次元コードから、学校が用意したサイトにログインして、そこで検索していました。
稲嶺一廉さん:
私は中国語を選択しました。同志社大学 経済学部は、基本的に8単位で、2年生の後期までに取る必要があります。学部によっては4単位を1年生までに取り終えるところもあるようです。初めて見るような単語は、教科書の巻末に書いてあったり、教科書内で完結していることが多かったです。それでも分からない部分は、インターネットで検索していました。
南部悠樹さん:
私は中国語を選択しています。他の学部は分かりませんが、京都大学 総合人間学部は英語が必修ではなく、入学時点で[英語、中国語、ロシア語、アラビア語…]と7言語ほどから2~3言語を選びます。ほとんどの人は英語を第一外国語にしていますが、英語を取らず「ロシア語とアラビア語を取る」という人もいました。中国語は、基本的に教科書で完結しています。どうしても分からないときは、図書館に行って辞書を使ったり、スマホで調べたりもするのですが、今のところはそれで困ったことはありません。
大学生活、就活など悩みは尽きない
増田一実さん:
すごく困ったのは入学初日です。入学式で初めて登校する日の朝に、いきなり娘から電話がかかってきて「バスに乗れない!」と言うんです。すぐ車でバス停まで行き、そこから私が送りました。京都は観光客が多くて長蛇の列だったそうで、「これが毎日続くのかな」と不安になりました。今は一つ手前のバス停にずらしたり、図太くなりコツを覚えて問題なく行っています。

稲嶺正一さん:
私が覚えているのは二つです。
一つは通学です。淡路島は電車が走っていないので、息子は電車通学をしたことがありませんでした。事前に下見で電車に乗りましたが、やはり実際の通学時間とは違いがありました。幸い、同志社大学は地下鉄の駅と直結しているのですが、阪急京都線は混むこともあります。
もう一つは授業です。新型コロナの関係もあり、リモートとリアルの授業が交互にありました。大学でリモートの授業となったときに学内のWi-Fi環境が悪く「つながらなくて授業を受けられない」となり、慌ててモバイル回線でつないで授業を受けることもあったようです。最初の1~2カ月ぐらいは、授業を受けるのに少し支障が出ることもありました。
南部美穂さん:
うちは一人暮らしを始めてから、学校が始まるまでに時間がなさすぎて。日々こなすことで精いっぱいで、余裕がありませんでした。
増田一実さん:
心配はいろいろありますが、大学から保護者に向けて就職の説明会や、保護者としてどういうふうに見ていてあげたらいいかという講座がありまして、夫と行ってきました。
「今の就職事情は、本当に大変だな」と思っていた矢先に受けた講座でしたが、それでも「親は口出しをせずに見守ってあげてください」という内容で、その通りにしようと考えています。もちろん相談があれば乗りますが、大学受験と同様、本人に任せてみようと思います。
稲嶺正一さん:
うちは3年生になるので、もう就活の時期です。大学進学のときもそうですが、口を出さずに、本人に「やりたいことは何?」と聞いています。公務員試験を受けるということなので、大学生協の学内講習などを利用しています。やはり受験に不安はありますが、見守るしかないと思っています。
南部美穂さん:
うちは1年生で受験が終わったばかりなので、まだ考えられないですね。
増田実玖さん:
来年の3年生の春からはインターンが始まるんだろうなと頭にあるのですが、今までは小学校の教員免許を取っていたこともあり、「自分が今、何に力を入れたいのか」を考える夏休みにしようと思っています。教職以外に幅広く教育関係について見ていくのか、大学生協の学生委員会でやっている広報に力を入れていくのか、悩んでいます。今年の夏休みでそこをしっかり見極めて、3回生から就活に力を入れていこうと考えています。
稲嶺一廉さん:
自分は、市役所職員の行政職として働ければと考えています。街のプロジェクトや問題解決ができるような職員になりたいと思っています。
南部悠樹さん:
自分は、「何か興味を持ってやれることを見つけたい」という思いもあって総合人間学部を選んだので、決めつけずにいろんなものに触れてみて、一つでも何か面白いと思えることが見つかればいいと考えています。
何かあったときに頼れる「大学生協」の安心感
増田一実さん:
娘と一緒に住んでいるので、そこまで求めることはないのですが、もし下宿だったらと考えると、寄り添ってもらえる本当にありがたい機関なんだなと感じました。
稲嶺正一さん:
もう30年も前のことですが、私が大学生だった頃に比べ、大学生協の役割も時代に応じて少しずつ変わってきていると思います。その中でも、やはり「安心感」というのでしょうか。インターネットなどを使って自分たちで選べるようになる一方で、「詐欺じゃないのか?」「ちゃんとしたものが提供されるのか?」という不安がある部分を、「大学生協を通じてだったら安心して提供していただける」という安心感があります。パソコンや、公務員試験の学内講習、自動車教習所の斡旋など、安心感をベースにしっかり寄り添っていただけるのは、期待しているところであり、実現していただいているところだと思っています。
南部美穂さん:
私が通っていた大学の生協に比べると、守備範囲がだいぶ広くなったなと感じます。私の頃は、教科書の割引や資格試験の学校の割引、免許の斡旋程度でした。今回、息子が一人暮らしをする上で、インターネットではあまりにも情報が多すぎて、何を信じて何をしたらいいのかわからないところ、「これさえやっておけば」「こっちに行けばいいんだ」という道しるべとなる情報を提供してくださって本当に助かりました。
期待したいのは受験時の宿です。息子の受験のときは満室で泊まれず、ホテル選びには本当に困りました。ホテルから受験に向かう人は多かったので、事前にどういうところに泊まればという情報をもう少し充実していただけると、皆さん嬉しいと思います。
増田実玖さん:
組合員の一人として、共済にせよ、パソコンや保障にせよ、手厚い活動をしている大学生協が自分の通う大学にあることが本当にありがたいと日々、実感しています。食堂でおいしいご飯を食べられるのも、栄養を摂れるのも、パソコンが壊れてもすぐにメンテナンスに出せるのも大学生協があるからで。ケガや病気など、もしもの時に共済金を受け取ることができる保障制度がある大学生協は、本当にありがたいと思います。
大学生協の学生委員会として思うのは、ありがたい制度があるのに、あまり知られていないということです。自分の大学でも、「そんなのあるんだ」と言われることが結構あります。この間、委員会の中で共済の給付事例の報告書に目を通したとき、「『指を切った』でも通院すれば保障される事例があるんだ」ということを知り、まだまだ知らないことがたくさんあります。今回、皆さんから大学生協に対する思いや期待の声を聞き、私たち自身の手で反映していけたらなと思いました。
稲嶺一廉さん:
自分も普段から食堂やコンビニ、学内講座など大学生協の様々なサービスを利用していて、すごくありがたいと思っています。その反面、知らない人もまだまだいると思うので、より多くの人が利用するようになったら嬉しいなと、学生委員会の視点からもすごく感じました。食堂で「人が混雑しすぎて使えない」という声も聞いたりするので、より使いやすくなるといいなと思っています。

南部悠樹さん:
自分は18年間、東京に住んでいたのが、大学進学をきっかけにいきなり京都で一人暮らしでした。右も左も分からない中、大学生協という「何かあったときに頼れる存在」があるのは心の余裕にもなりますし、何かがあったときに頼れればと思っています。食堂やショップはあまり利用しないのですが、京都大学生協の本の品揃えは充実していると思います。授業で先生が言っていた本で、一般的な書店には置いていなくても、大学生協に置いてあることがありました。そこはいつもお世話になっています。
ご参加いただきましてありがとうございました。
2024年8月4日大学生協大阪会館にて開催
Contents