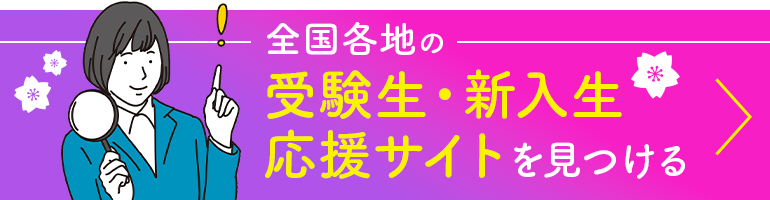「高校生×大学生座談会」(2024年開催)
自分に合った勉強の仕方と今しかない高校生活

これから大学受験を迎える高校生たち。「大学や学部をどう選ぶ?」「勉強は何から手を付ければいい?」「部活との両立はどうする?」「受験期はどのくらい勉強すればいい?」など、受験が近づくにつれ不安は大きくなります。そこで今回は4名の高校生と5名の大学生による座談会を開催。難関大学に合格した先輩たちが、高校生たちの疑問や悩みに答えてくれました。
〈高校生〉
- 野口 健さん(埼玉県立高等学校2年)
- 小林 佑輝さん(埼玉県立高等学校2年)
- 加藤 真弥さん(埼玉県立高等学校2年)
- 原口 大広さん(埼玉県立高等学校2年)
〈大学生〉
- 司会:太田あかりさん(早稲田大学人間科学部3年生)
- 石田 廉さん(東京大学 理科一類2年生)
- 佐藤 祐太郎さん(東京大学 文科三類1年生)
- 吉澤 慶彦さん(早稲田大学 政治経済学部 政治学科1年生)
- 橋本 実和さん(慶應義塾大学 文学部2年生)
Contents
今の大学・学部を決めた理由
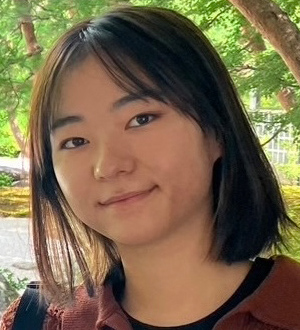
早稲田大学 人間科学部3年生
(司会)太田あかりさん(以下、太田さん):
早速、自己紹介から始めたいと思います。大学生の皆さんは、大学や学部を決めた理由の紹介もお願いします。
私は早稲田大学人間科学部人間情報科学科3年生の太田あかりと申します。この学部に決めた理由の一つは文系と理系の両方を勉強したかったからで、もう一つは情報系に興味があったからです。今はVRなどの研究をしたいと考えています。

東京大学 理科一類2年生
石田廉さん(以下、石田さん):
東京大学理科一類2年生の石田廉と申します。学部はまだ決まっていません。高校のときにやりたいことが決まっていない中で、できるだけ多く選択肢を残した状態で大学に進学して「やりたいことを見つけたい」と思ったので、進学振り分け制度がある東京大学を選びました。

東京大学 文科三類1年生
佐藤祐太郎さん(以下、佐藤さん):
東京大学文科三類1年生の佐藤祐太郎と申します。東京大学を選んだのは、言語学を学びたいと思っていたからです。学部から言語学を学べる大学が少ない中、文学部に言語学専修があるこの大学を選びました。
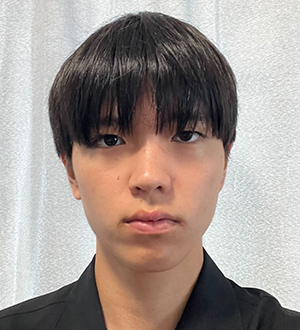
早稲田大学
政治経済学部 政治学科1年生
吉澤慶彦さん(以下、吉澤さん):
早稲田大学政治経済学部政治学科1年生の吉澤慶彦です。他大学と併願で、入試日程やレベルなどを見て決めました。もともと政治や経営、法律、経済の学部に興味があり、幅広く学べる政治経済学部政治学科を選びました。

慶應義塾大学 文学部2年生
橋本実和さん(以下、橋本さん):
慶應義塾大学文学部1年生の橋本実和と申します。
私は私立文系に絞っていて、早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・GMARCHを順に受けていき、早稲田大学と慶應義塾大学に合格しました。どちらも興味深くなかなか選べない中、社会人向けに就職のアドバイスをしている人に「どこの学部がいいですか?」と相談したところ「合格した中では慶應義塾大学文学部が一番就職に強い」とアドバイスをいただき、それが決め手になりました。
続いては高校生の皆さん、自己紹介をお願いします。所属している部活や志望先なども教えていただきたいです。
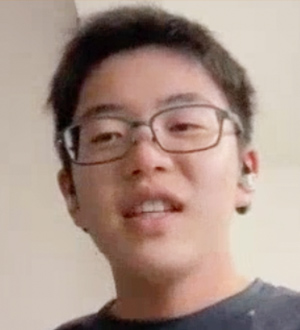
埼玉県立高等学校2年
野口健さん(以下、野口さん):
2年の野口健です。部活は科学部に入っています。志望は文系で、法学部に行きたいと考えています。

埼玉県立高等学校2年
小林佑輝さん(以下、小林さん):
2年の小林佑輝です。部活は弓道部に所属しています。進路は理系で、都市計画などをやりたいと思っています。

埼玉県立高等学校2年
加藤真弥さん(以下、加藤さん):
2年の加藤真弥と申します。部活は地学部に入っています。

埼玉県立高等学校2年
原口丈広さん(以下、原口さん):
2年の原口丈広です。吹奏楽部に所属しています。東京大学を志望しています。
部活に所属中の勉強状況
大学生の皆さんに、高校では何の部活をやっていたのか、その間はどのように勉強をしていたかを教えていただきたいです。
私自身はテニス部に所属し、週5~6日は部活動をしていました。週末は練習試合などで忙しく、部活メインの高校生活を送っていました。高校2年のときは、部活の休み期間はテスト直前の1週間しかなく、詰め込んで定期テストを乗り越えるという状態でした。塾には通っていません。基本的に学校の授業や宿題、自分で買った参考書で勉強していました。
石田さん:
中学から続けている柔道部に、高校1年~2年の12月まで所属していました。週3~4日の部活の日は勉強できないこともありましたが、土日はなるべく勉強していました。僕も塾には通っていません。定期テストを中心に学校の勉強をして、定期テスト期間以外は自分でやりたい勉強を進めていました。
佐藤さん:
部活には所属せず、代わりに友達と放課後にいろんな活動をしていました。時間はかなりあったので、高校1年から徐々に勉強量を増やしていきました。塾には通わず、参考書や学校の教材などを使っての勉強です。当時は歴史科目が苦手で、3年生の夏頃から論述のオンライン添削サービスを利用することもありました。
吉澤さん:
僕はサッカー部を高校3年の6月まで所属していて、週6日ぐらいの部活中心の生活でした。受験を意識したのは、2年の8月下旬に東進に通い始めてからです。そして、本格的に受験勉強を始めたのは、部活を引退した3年の6月からでした。
橋本さん:
私は弓道部と文芸部、そしてクイズ部に所属し、弓道部では副部長を務めていました。弓道部は週6日で、早めに終わった日にクイズ部と文芸部に参加していました。塾は高校2年の夏期講習から入りました。受験勉強を本格的に始めたのは、弓道部を引退した3年の7月からです。
受験期のタイムスケジュール
加藤さん:
高校3年の受験勉強中の休日のタイムスケジュールを教えていただきたいです。
私は朝型で、朝に勉強時間を寄せて、夕方からはのんびりしていました。5時頃に起きて、9時半に開く図書館に行く前に家で1時間半ぐらい勉強し、図書館では昼食を挟みながら16~17時には切り上げていました。1日の勉強時間は6~7時間、多い日で8時間ぐらいです。
吉澤さん:
平日は、朝に補習の日がありました。その日は7時頃に家を出て、学校で授業が始まる前に1時間ぐらい勉強し、授業が終わったら塾に行って17時~22時ぐらいまで勉強していました。
休日は、塾が開いている9時~22時頃まで勉強をしていました。その間、ご飯を食べに出たり、人と話している時間はあります。家ではだらだらして全然勉強ができなかったので、なるべく塾に行って勉強をするよう意識して、「家では勉強しない」と割り切っていました。
橋本さん:
休日は、塾が開いている10時~22時まで極力長くいて時間を確保するようにしていました。ただ、怠惰な受験生だったので、1ヵ月間ぐらいまったく勉強していない時期もありました。10時~22時までいることが大事ではなくて、自分が継続できる時間でしっかり勉強したほうがいいと思います。
石田さん:
僕は塾に通っていません。休日は市のコミュニティセンターに行き、部屋を9時~21時まで一人で借り、昼食や休憩の時間を抜くと1日10時間ぐらい勉強していました。家では疲れてすぐ寝てしまうことが多かったので、たっぷり時間がある日は集中できる家の外で勉強していました。
佐藤さん:
私も塾には通わず、公民館に行って勉強していました。朝が弱く、休日はリズムが乱れがちでしたが、朝8時までには起きるように頑張っていました。
橋本さん:
私は私立文系で、「Study plus」というアプリで記録していた受験期の総勉強時間を調べると1503時間でした。365日で割ると1日約4時間です。滑り止めにかけるのは1日4時間程度、高校2年の7月から1500時間勉強すれば大丈夫だと思います。
私も「Study plus」を使っていました。勉強時間を記録するのはおすすめです。
小林さん:
高校2年は平日忙しいと思いますが、どのようなスケジュールで勉強をしていましたか。
部活がしっかりあったときは、朝は6時半頃に学校に着き、誰もいない教室で1時間半ぐらい自習していました。夜は部活が19時頃に終わり、塾に通っていなかったので20時頃に家に着いていました。夜はほとんど勉強していなかったと思います。やるとしても、次の日の小テストの暗記物を30分頑張るくらいです。
吉澤さん:
僕は部活が終わるのが18時半頃で、19時半頃には塾に行き、3時間ぐらい勉強していました。朝は学校で1時間でも勉強できたらいいなと思ってはいましたが、なかなか起きられませんでした。
橋本さん:
弓道部は総体があるため引退は高校3年の7月で、それまで塾以外ではまったく勉強していなくて、すごく後悔しています。高校3年の5月頃に部活を引退した人との2ヵ月の差は大きく、あとから追い付けませんでした。
石田さん:
僕は柔道部で、高校2年の12月までやっていました。部活があった日は疲れてしまって勉強できないので、早ければ20時台には寝て、4~5時に起きられた場合は勉強をしていました。起きられなければ「仕方がない」と割り切り、もし溜まっていたら週末にまとめてやる、と部活がある時期はやっていました。
朝早く家を出るには家族の協力も必要です。簡単にできるわけではありませんが、できるなら疲れていない朝に勉強をできたらベストだと思います。ただ、疲れていて無理に勉強するよりは、早く寝て次の日の集中力を上げるのもいいのではないでしょうか。
通学時間の使い方
原口さん:
皆さんの通学時間の使い方をお聞きしたいです。
佐藤さん:
私は自転車通学で、本を読んだりはできません。ただ、学校で勉強した帰りには「この単語ってこういう意味だよな」「こういう流れだったよな」と思い出していて、定着に役立ちました。自転車通学の人は、安全に気を付けながらやってみてもいいかもしれません。
吉澤さん:
僕は45分ぐらいバスに乗って通学していたことがありました。その間に英単語や日本史・世界史の暗記などをやったり、スマホを見たり、眠ったりと気分次第でした。
石田さん:
僕は高校2年までは電車とバスで通っていました。その間に何をするかは特に決めず、眠っているか、小テストなどがある日は勉強をしていました。部活終わりで同じ方向の友達と帰るときは勉強していません。3年になってからは親に送ってもらっていて、睡眠時間に充てていました。
私は家から最寄り駅までは自転車で、学校までは20分電車に乗り通っていました。その20分で英単語や古文単語の小テストの勉強をしていました。運良く座れたら勉強しやすいですが、立っていてもできます。部活帰りは眠るときもありました。「友達と帰るときは勉強しない」というお話がありましたが、せっかく一緒に帰れる日は友達と話す時間にするのも大事だと思います。
受験期の息抜き方法
野口さん:
皆さんは、勉強の息抜きとしてどんなことをしていましたか。
橋本さん:
私は国語がすごく好きで、現代文や小論文、古典などすべてが息抜きになっていました。受験が近づいてきた頃はご飯の時間だけが息抜きに。ただ、その時間も英単語帳や歴史を赤シートで隠しながら見ているときもありました。
「息抜き科目」は私もありました。理系なのですが、数学に疲れたら地理を見ていました。それ以外の息抜きは、マンガや動画を見ることです。だらだらしないように、スクリーンタイムをかけたり、タイマーを設定して時間を切ってやっていました。
また、部活をやっていたときの息抜きは、机に突っ伏して15分間眠ることです。部活で疲れて、眠いままやっていると寝落ちしてしまうこともあります。それならと、タイマーをかけたスマホを膝の上に置いて15分間眠っていました。いい感じに眠気が取れておすすめです。スマホのアラームをバイブにすれば図書館でも使えます。
石田さん:
地理が息抜きになっていました。僕は理系で、東京大学の場合は共通テストがかなり圧縮されて、地理は数点分しかありません。その分、息抜きの時間になっていました。
勉強以外の息抜きは、楽器や運動です。すぐ近くに人が全然いない公園があり、「勉強が嫌だな」と思ったらすぐに行っていました。
吉澤さん:
僕は勉強が嫌で、人と話すのが息抜きでした。塾では疲れてきたときにチューターの人やスタッフの人と話したり、学校では休み時間に友達と話したり。受験が近づくほど、いい息抜きになっていました。
佐藤さん:
私は本を読むのが好きなのですが、『ビギナーズ・クラシックス』というシリーズがおすすめの息抜きです。『太平記』や『源氏物語』などの古典の現代語訳と原文と解説がコンパクトにまとまっていて、物語を楽しみながら自然と勉強になります。
暗記科目を始めるタイミング
原口さん:
理科基礎や世界史を取っているのですが、暗記科目は始めるのが早すぎると忘れてしまいそうで、遅すぎても間に合わなそうで不安です。皆さんはどうしていましたか。
佐藤さん:
理科基礎は焦る必要のない科目だと思います。3年から少しずつ覚え始め、共通テスト対策問題集をやり始めたのは共通テストの3ヵ月ぐらい前でした。ただ、地歴科目は二次試験でも使いますし、特に東京大学では論述の配点が重いので、2年の今頃から少しずつ教科書の内容を覚えていったほうが後々楽になると思います。私は「どうせ忘れてしまうし」と後回しにして3年で苦しんだタイプです。3年になってから始めても、最初のほうにやったことはどんどん忘れていくので、何度も覚えることを前提に地歴科目は早めに始めておくことをおすすめします。
吉澤さん:
僕は東京大学を受けて落ちてしまったのですが、落ちた身からアドバイスすると、東京大学は社会科目を二つやる必要があり大きな負担になります。僕は社会科目に手が回らず点を取れなかったので、早いうちから始めておくと後でだいぶ楽になると思います。社会科目の内容は絶対忘れるので、何度も繰り返すことが大事です。
理科基礎は学校の授業でやっていたぐらいで、本格的に自分で勉強し始めたのは共通テストの2~3ヵ月前でした。
数学の勉強の仕方

僕は数学がすごく苦手で、高校1年の基礎からやり直したいくらいです。教科書の問題集として『青チャート』など選択肢がいろいろあり、量も多すぎて何から手を付ければいいのか分かりません。どのように勉強をしていけばいいのか、教えていただきたいです。

僕も数学は苦手で、入試も数学が足を引っ張りました。その中で主に使っていたのは『フォーカスゴールド』です。『青チャート』と同様の網羅系の参考書で、まず解法を覚えようとしました。「こういう問題だったら、こういう解法」というパターンがあるので、問題を見て「自分だったらこう解く」という方針を頭の中で考えてから、解答を読み解法をひたすら覚える、というやり方です。それと並行して、学校で配られた参考書などで問題演習をしながら、ちゃんと身に付いているか試していました。
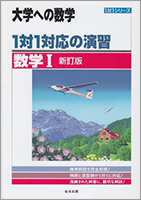
私が主に使っていたのは学校で配布された『フォーカスゴールド』です。基礎を固めるためなら、問題数が多い網羅系の参考書がおすすめです。特に『フォーカスゴールド』なら「ステップアップ」、『青チャート』なら「エクササイズ」という項目の終わりにあるまとめ部分の問題です。本編をやるより少ない問題数で、かつ大事なところが抜粋されています。他には『1対1対応の演習』という問題集を使っていました。これは量が少なくてやりやすいのですが、抜けが出やすいので注意が必要です。
学校では『青チャート』が配られました。私は理系でありながら数学は苦手で、長期休みなどにコンパス2~3の難易度が低めの問題を1周やっていました。もし基礎が分からない状態であれば、レベルの高いものは捨て、コンパス1~2だけに絞ってもいいと思います。基礎的なものだけを思い切って選んでやり遂げると、基礎固めになります。
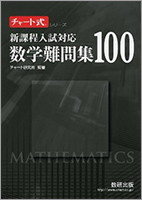
僕は数学が好きで『黒チャート』などをやっているのですが、皆さんの中で「やっていて楽しかった」と思えるような数学の参考書があれば教えていただきたいです。
石田さん:
僕は過去問演習が楽しかったです。『青チャート』や教科書傍用問題集などで基礎を固めたら、すぐに過去問に移っていました。自分が間違えた問題の解答を出している会社のものをすべて読み、良いところだけを集めてノートにまとめ、自分専用の参考書にしていました。そして入試前に間違えた問題の詳しい解説や自分が書いた解説を読んだりしていました。
佐藤さん:
私は、数学は早めに過去問演習に入っていました。他の教科は基礎を固めてから最後に過去問をやるのですが、数学の過去問はどの大学で出てもおかしくないので早めにやりました。特に数A分野が好きで、数A分野だけの参考書をやっていたときは楽しかったです。

『数学の真髄』
ぜひおすすめしたい参考書があります。それは青木純二先生の『数学の真髄』です。教科書には出てこないような数学の本質的な部分の「命題とは何か」「同値変形はそもそも何をしているのか」などが詳しく説明されていて、本質を理解していると記述問題を解くときなども表現に気を配るようになりました。「ここは同値変形でいいのか」などを考えるのは、数学が好きな人には面白いと思います。
原口さん:
皆さんは数学の教科書をどのように使っていたかもお聞きしたいです。
吉澤さん:
教科書はほとんど使っていません。授業で新しい単元を習うときに教科書を見ていたくらいで、一通り終わったあとは問題集を使っていました。復習をする際も、『フォーカスゴールド』の冒頭のまとめページを見ていました。
石田さん:
教科書は主に授業で使っていました。その授業は問題演習というより、問題を解く前の定理や公式の証明のために教科書が使われていました。演習は自分で買った参考書の問題をやっていました。
教科書は授業で使うだけでした。ただ、定理の導出などが最も丁寧に書かれているので、それが分からなくなったときは教科書を読んでいました。根本から原理をしっかり理解して基礎を固めたい場合は、教科書を読むのがいいと思います。
大学生がおすすめする参考書
せっかくですので、数学に限らず、おすすめの参考書を紹介していきましょう。
吉澤さん:
1冊目は『ヨコから見る世界史』で、時代ごとにまとまっています。多くの教科書や参考書は地域や時代がばらばらですが、この本は時代に基づいてまとまっています。「この時期に中国は何をやっていた」「ヨーロッパのほうでは何をやっていた」「アジアは何をやっていた」ということが同じ章に収録されています。同時代にどこで何があったのか、ヨーロッパと中国のつながりなどが書かれていて面白かったです。
2冊目も世界史で、『荒巻の新世界史の見取り図』は豆知識が盛りだくさんです。上中下3巻で内容が多く、理解の手助けになります。休憩気分で読める参考書なのでぜひ使ってみてほしいです。
3冊目は『日本史の論点』です。教科書では少ししか触れていない内容も詳しく説明されているので、日本史の理解が深まります。
ためになった参考書
世界史

『ヨコから見る世界史』
世界史

『荒巻の新世界史の見取り図』
日本史

『日本史の論点』
橋本さん:
1冊目は英文法の『全解説 頻出英文法・語法問題1000』です。この1冊をやっておけば、文法問題や単語問題の漏れがなくなると思います。入試は2~3点の差で合否が決まるので、漏れをなくすことは大事です。
2冊目は『漢文早覚え速答法』です。漢文をあまり勉強をしていなかったのですが、この参考書を1週間くらい勉強して共通テストに臨みました。正答率が高かったのでおすすめしたいです。
3冊目は『史料をよむ』です。私立文系では史料問題が出るようになってきています。『山川一問一答』などを仕上げていくと思いますが、長文の史料問題などが出たときに出題形式に慣れていない、もしくは単純に史料を知らない状態だと解きづらいので、『史料をよむ』で仕上げておくことをおすすめします。
ためになった参考書
英 語

『全解説 頻出英文法・語法問題1000』
漢 文
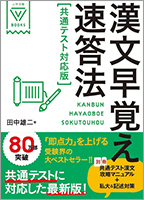
『漢文早覚え速答法』
日本史

『史料をよむ』
日本史

『山川一問一答』
佐藤さん:
1・2冊目は記述対策の問題集『得点奪取』シリーズの古文と漢文です。高校生3年生になるタイミングで、この問題集をやってから過去問演習に入りました。共通テストなどのマークシートと論述問題では解答のポイントが違うので、過去問演習に入る前におすすめです。
3冊目は私立向けですが、『スーパー講義 英文法・語法正誤問題』という正誤問題の問題集です。よく出る正誤問題がたくさん入っていて、解いていく中で「この文法事項あったな!」とインプットにもなります。後半には特殊な問題もあり、私立併願で受ける人におすすめです。
4・5冊目は過去問集で、『東大古典問題集』『東大数学問題集』です。特に東京大学志望の人におすすめです。解説が本当に詳しくて、理系志望でも古典はぜひやってみてもらいたいです。
ためになった参考書
古 文

『得点奪取』
漢 文
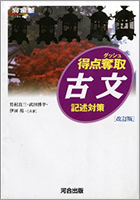
『得点奪取』
英 語

『スーパー講義
英文法・語法正誤問題』
古 典

『東大古典問題集』
数 学

『マドンナ古文単語230』
(学研プラス)
石田さん:
1冊目は『古文攻略マストアイテム76』です。古文単語をひと通り覚えたあとでも文章が読めず、つまずいたときに使いました。どういう世界だったかを中心に解説してくれるので、単語を学んだあとにやると文章が読みやすくなり、古典が親しみやすくなります。
2冊目は数学の『ランダム演習』で、高校2年の夏から冬にかけて使っていました。共通テスト対策になるのですが、50ページ程度で150問ぐらいと量が少なく、早めに1周終わらせることができます。『青チャート』でいう「N進法の問題」のような題名が付いていなくて、ランダムに問題が並んでいます。「この分野のこの題名だからこの解き方」で覚えていて、実はしっかり理解していないということを洗い出せます。付録には解法がすぐに浮かぶように、問題の指針が書かれています。問題を解いたあとに指針を確認するだけでも、共通テスト対策として仕上がると思います。
3冊目は英作文の参考書『英作文基本300選』で、英作文で頻出する大事な表現だけが300個収録され、1文1文が短くて覚えやすいです。この作者は「丸覚え厳禁主義」で、まず英語に訳しやすい日本語にしてからその日本語を英訳するという解き方で、英作文を鍛えたい人におすすめです。
最後は『基礎問題精講』シリーズの理科で、高校2年で使っていました。共通テストから国公立大学までをカバーできると思うので、共通テストを固めたい人におすすめです。
ためになった参考書
古 文
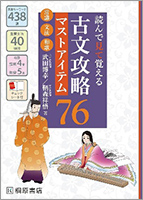
『古文攻略マストアイテム76』
数 学
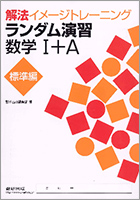
『ランダム演習』
英 語

『英作文基本300選』
理 科

『基礎問題精講』シリーズ
私が紹介したいのは、『出口式 現代文 新レベル別問題集』という現代文の問題集です。高校2年まで現代文をフィーリングで解いていて、得点が安定しませんでした。この本の「超基礎編」に現代文の解き方や掟が載っていて、忠実に従って解いていくと現代文が論理的な科目になり、根拠を持って答えられるようになりました。現代文が苦手な人、得点が安定しない人におすすめです。
ためになった参考書
現代文

『出口式 現代文 新レベル別問題集』
受験には英検何級が必要か
鎌田さん:
大学入試において、英検は何級まで取っておくといいでしょうか。
橋本さん:
準1級を高校3年の春に取り、早稲田大学と慶應義塾大学、上智大学の受験で使いました。また、明治大学の国際日本学部では、準1級保有で英語試験が免除になります。スコアによっては加点式のところもあるので、滑り止めを受けるときは調べてみてください。上智大学では、英語試験免除やスコア換算がされるので、英検で高いスコアを取るほど有利です。早稲田大学の商学部に関しては、私が通っていた塾の分析によると準1級を持っていると70点有利になるそうです。
石田さん:
僕は高校3年の6月に準1級を取りました。高校として全員が英検を受ける方針で、2年で2級、3年で準1級を受けました。
佐藤さん:
実力試しのために高校1年の冬に2級を取り、それ以降は受けていません。私は併願で早稲田大学の文化構想学部を受けたのですが、準1級でないと使えませんでした。
吉澤さん:
僕は高校2年の2月に準1級を取りました。周りが取り始めて焦っていたこともあり、具体的な目的はなく「取っておけば何かに使えるかな」という感覚です。
私は2級を取りましたが、受験では使っていません。力試しで英語の勉強をするなら2級でもいいとは思いますが、入試のためなら準1級がいいと思います。
大学選びで重要視したこと
小林さん:
大学選びのときに一番重要なことをお聞きしたいです。
石田さん:
僕はやりたいことが決まっていなかったのですが、大学選びでは可能性を最大限に残すことを重要視しました。その中で東京大学が、これから見つかるかもしれない「自分のやりたいこと」の実現可能性が一番あると感じ選びました。自分のやりたいことが最も実現しそうな大学を選んでほしいと思います。
佐藤さん:
私は言語学をやりたくて、学部からできそうな東京大学を選びました。やりたい学問が一つあることはモチベーションになるので、すごく大事だと考えています。例えば本を読んでいて、興味のある学問が一つでも見つかると、将来的にプラスに働くと思います。興味のある本を読んでも見つからない場合は、興味のない分野の本を読んでみることも一つの手です。現代文などで解いた問題を読んでみると、意外と「面白そう」というものが転がっていて、「こういう学問があるんだ」「こういう学部があって、こういう大学があるんだ」と道ができることもあります。入学後の4年間は結構長いので、学問への興味はモチベーションにつながります。
吉澤さん:
振り返ってみると、あまり良い大学の選び方ではなかったと思います。法学部や経済学部などに漠然として興味があり、その中で偏差値の高い大学を何となく選んで受けました。早稲田大学の政治経済学部と慶應義塾大学の経済学部ですごく迷いましたが、キャンパスや大学生活の雰囲気、就活の強さなどをいろいろと考え、最終的にはどちらが「自分に合っていそうか」「楽しそうかな」という観点で早稲田大学に決めました。
橋本さん:
大学生活は人生の中のたった4年、その先の就職のほうがずっと長いので、就職を軸に考えました。大学のホームページなどで就職実績を見て、「偏差値はここの大学のほうが高いけれど、就職実績はこちらのほうが高いな」というふうに調べていきました。ただ、数学がすごく苦手で、4年間耐えられるかを考えたときに「好きなことをやりたい」と思い、経済学部と商学部は受けませんでした。
私は「情報系を学びたい」という思いがあり、それができる学部や研究室がある大学を選びました。新しいことが好きで、情報系を学んでおけば、将来働くときも役立ちそうだなと思ったからです。その中で早稲田大学の他に慶應義塾大学や明治大学などと迷ったのですが、慶應義塾大学は入試の小論文が得意ではないと思ったので外しました。明治大学は合格したのですが、早稲田大学と比べたとき、私は周囲に引っ張られやすいので、周りのレベルが高い大学に行ったほうが自分のためになると思い早稲田大学を選びました。
先ほど「本を読んで興味がある分野を探す」というお話がありましたが、「行きたい分野が決まっていない」「迷っている」人は、大学のパンフレットで「どんな学部があるのか」を調べてみるのもいいと思います。私自身、興味のある分野が明確ではなかったのですが、パンフレットを見る中で、面白そうな研究をやっているところが多いと思ったのが早稲田大学の人間科学部でした。大学では研究をしたり、その分野で有名な先生の授業を受ける機会もあるので、先生や研究室を調べることも大事だと思います。
こちらから高校生の皆さんに質問です。
大学選びの一環として、高校生の皆さんはオープンキャンパスに行きましたか。
加藤さん:
行きました。自分の知りたい分野を中心に研究をしている学部があったので、行って良かったです。
野口さん:
僕は行きました。
小林さん:
すでに行った大学も、これから行く大学もあります。行った大学は「意外と駅から遠い」などの気付きもありました。
オープンキャンパスは行ってみて分かることがあります。私も実際に行ってみて、すごくきれいな建物でテンションが上がったり、体験授業などで「大学はこんな感じなのか」という気付きがありました。ぜひいろいろなものを吸収してほしいです。
ここで、一つ質問が届いています。「公募推薦を使ってみたいのですが、論文や面接対策にはどの程度時間がかかるのか、またその手段を教えていただきたいです」とのことです。高校の校長先生から推薦してもらうものだと思いますが、私の友達の話では時期が早く、経験のある先輩が少ないので、「学校の先生や校長先生と面接をする」と言っていました。学校の先生以外に頼れるところはなかったようです。まずは学校の先生に相談し、早めに動いておくに越したことはないと思います。
高校時代にやっておけば良かったこと
原口さん:
大学生の皆さんは、高校時代にやっておけば良かったことはありますか。
高校時代にやっておけば良かったのは数学です。数学はもともと好きな科目でしたが、先生との相性などもあり、高校2年の終わり頃から苦手になりました。長期休みや土日などに数学の問題を解く中でつまづいたとき、しっかり向き合って解決するところまでやっておけば良かったなと思っています。数学に限らず、とりあえず問題集を1周解こうとすると必ず簡単な問題が紛れていて、そこが解けて満足した気になってしまうことがありました。苦手になる前に、少しずつでも向き合って進んでいけると良かったです。
また、何をやればいいか、苦手な範囲が広すぎて迷ったときは、「この単元なら絶対に解ける」というものを一つでもつくっておけるといいと思います。テストは満遍なくいろんな単元から出てきますが、自分の得意な単元の問題で「これなら解けるはず」と思えると心が楽になります。私はそれができませんでした。
吉澤さん:
社会をもっと早くから勉強しておけば良かったと少し後悔しています。僕が本格的に勉強を始めたのは高校3年からです。それまでは学校の先生に「高校2年のうちは国数英を固めておこう」と言われていたのですが、受験を終えて振り返ると、社会を何か一つでも早めにやっておけばもう少し楽になっていたと思います。
私も「高校2年生のうちは、国数英をやっておく」と言われていましたが、理科や化学などの範囲が終わるのは高校3年の冬頃で大変だった記憶があります。国数英に限らずどの科目も早めにやっておけるといいですね。
石田さん:
僕は時間管理です。受験期は9時~21時まで「これとこれをやろう」とざっくりとしたスケジュールで勉強していましたが、分からない問題があったときに考え込んで何時間も使ってしまうことがありました。1時間や30分などで別の科目に切り替えたほうが、成績はもっと良くなっていたかもしれません。自分の得意・苦手を考慮して、科目ごとに時間を割り振ることも大事だったのではないかと思います。
私も考え込んでしまうことがありました。難しい問題を固執して考えすぎて、気が付くと2時間経っていることも。自分に合ったやり方があると思いますし、粘り強く考えるのも大切ですが、ある程度で割り切って答えを見て理解をし、改めてもう一度解き直したほうが効率良く勉強できることもあります。
橋本さん:
特に後悔はしていません。
唯一あるとすれば、高校3年の7月まで部活をやっていたのですが、早めに引退して受験勉強に切り替えておけば良かったなと思います。
佐藤さん:
大学生になった今、やっておけば良かったのは、英語のスピーキングとライティングです。入試ではスピーキングはほとんどなく、ライティングも英作文が少しある程度で、あまり力を入れてきませんでした。大学生になると、毎回のレポートや授業内のディスカッションなどで苦しむことがあります。入試だけではなく、その先もあることを考えながらやっておけば良かったなと感じています。
大学生から高校生へのメッセージ
高校生の皆さんには、部活や学校生活の行事などを目いっぱい楽しんでほしいです。大学生になると、クラスという概念がほぼなくなり、毎日同じメンバーと会って遊ぶことが少なくなってしまうので、高校の友達は大事にしてほしいと思います。
勉強に関しては、英単語や古文単語などは早めにやっておいたほうがいいです。理科や社会、世界史などは後になっても積み重ねができますし、高校3年で頑張れば何とかなります。でも単語は早くにやった者勝ちです。
石田さん:
僕は上京して一人で生活しています。高校生の頃は「自分のことは自分でできている」つもりでしたが、いろんな人にお世話になっていたのだと実感しました。受験は「つらいもの」というイメージがあると思いますが、その土俵に立てていることが幸せなことだと最近感じました。大学生からしたらうらやましくて、「受験をもう一回したいですか」と聞かれたら「絶対にしたい」と今なら答えると思います。貴重な機会なので頑張ってほしいです。応援しています。
佐藤さん:
高校の3年間はすごく大切です。大学に入った今でも高校の友達とよく遊ぶので、今の人間関係を大切にしてほしいと思います。それに、受験勉強に限らず高校時代にやってきた本を読むことや、趣味や部活などが生きる機会が多いです。日々の生活を大事にして、人間関係を大事にしながら受験に臨んでほしいです。
橋本さん:
受験は、分かりやすい偏差値で見てしまいがちです。周囲の人から「そんなところを受けるの?」「偏差値はいくつ?」などと言われる場面が増えてきますが、何が一番大事かを見失わないことが大切だと思います。 私は就職価値で大学を選びましたが、それが正解ではありません。同級生の中には、学びたいもので選ぶ人や偏差値で選ぶ人、家からの距離で選ぶ人もいて、何が正解かはその人次第です。自分の中で何が大事か、どうなりたいかを、周囲に惑わされずに目指せるのがいいと思います。自分を見失わないように頑張ってください。
吉澤さん:
高校時代に当たり前だった、毎日同じ友達との学校生活や部活、体育祭・文化祭、学校行事などは大学ではほとんどなくなります。高校生の今しか楽しめない学校生活や遊びを全力で楽しんでほしいと思います。
勉強に関しては、受験は本当に長くて途中でしんどくなるときもあります。もちろん合格が目標ではありますが。どんな結果かにかかわらず「やり切った」と思えるかどうかが大事だと思います。そう思えるような受験生活にしてもらいたいです。応援しています。
高校生の皆さん、たくさん質問をしていただいてありがとうございました。ぜひ今日の話を参考にして、高校生活を楽しみながら受験勉強も頑張ってください。
大学生の皆さんも、本当にありがとうございました。
2024年8月18日開催
Contents