安田大サーカス 団長安田 氏 インタビュー
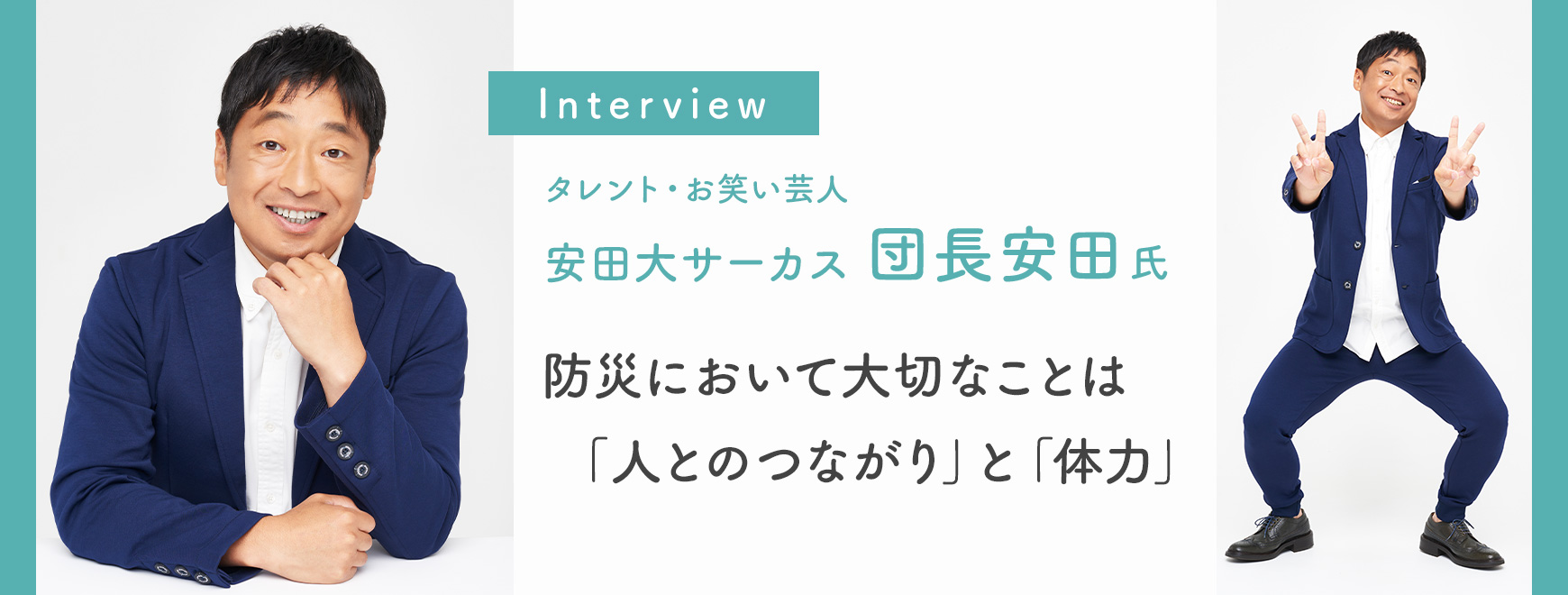
HIROとクロちゃんの二人に服を破らせる芸でお馴染みの、お笑いトリオ「安田大サーカス」の団長安田氏。多くの読者の皆さんと同年代の20歳の時に阪神・淡路大震災で被災されました。
お笑い芸人として経験を語ることをためらった時期、それでも語り始めたきっかけ、さまざまなことを乗り越えられて、経験者だからこそ語れる災害時の気持ちの持ち方など、従来の防災の知識や情報に加えてプラスαとなる、お話をお聞きすることができました。

全国大学生協連 全国学生委員会
委員長 加藤 有希(司会/進行)
インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会
久野 耕大
インタビュアー

全国大学生協連 全国学生委員会
伊藤 隼己
インタビュアー
はじめに
阪神・淡路大震災
経験を語るきっかけ
被災後に学んだこと
(以下、敬称を省略させていただきます)
はじめに
自己紹介とこのインタビューの趣旨

加藤- 本日はお忙しいところお時間をいただき、ありがとうございます。
全国大学生協連の学生委員会で委員長を務めております、加藤有希と申します。2023年の3月に広島県にある福山市立大学を卒業しました。本日はよろしくお願いします。

久野- 同じく全国学生委員会で学生常勤を務めております、久野耕大と申します。2022年の3月に埼玉大学を卒業しました。本日はよろしくお願いいたします。

伊藤- 同じく全国学生委員会の伊藤と申します。今年の春に東北大学を卒業して、現在はこちらで活動しております。よろしくお願いいたします。

加藤- 先ほど全国学生委員会と申し上げましたが、私たち学生委員は、大学内で購買や食堂を運営している大学生協という組織のなかで、大学生がより充実した学生生活を送れるように、友達作りの企画や自転車点検会、リサイクル容器を使ってお弁当を販売して容器を回収する取り組みなど、幅広く活動をしています。また、社会に目を向けた活動も行っていて、今回のインタビューの趣旨にも関わってきますが、防災や減災に対する取り組み、例えば大学入学時に一人暮らしの学生を対象として防災について考える「下宿生の集い」や、「令和6年能登半島地震」の支援として、学食で石川県の郷土料理である「めった汁」を販売し、出食数に対して一食あたり10円を寄付する取り組みなどを行っています。
全国学生委員会は学生委員会の上級生が集まって、各地の大学生協や学生委員会の活動の支援や、つながりを作るセミナーなどを行っています。

久野- 今回のインタビューの趣旨ですが、安田さんは20歳の時に阪神・淡路大震災を経験されて、大変辛い思いをされた中でその現実を受け止め、乗り越えて、災害支援活動への参加や、防災意識の向上に努められてきたと伺っています。今年も1月1日に能登半島で地震が発災したことから、より多くの大学生に激甚災害支援や防災について、意識を持って行動できるようになってもらいたいという想いがあり、アドバイスをいただきたいと思っています。
全国大学生協連に所属している大学生協は全212会員、その中で阪神・淡路大震災のあった関西地区は47大学、東日本大震災のあった東北地区は16大学あります。震災当時も大学生協内で協同してさまざまな支援を行ってきました。その教訓から、全国大学生協連のホームページに※1「防災の心得」というページを設けたり、※2学生自身が被災した経験を共有するSNSでの発信も行っております。
今回、お話を伺える機会をいただけて、少し緊張していますが、よろしくお願いします。

団長
安田- 安田大サーカスというお笑いトリオをやっています、団長です。
よろしくお願いします。
※1 全国大学生協連のホームページ「減災・防災の心得」HP https://www.univcoop.or.jp/society/society_1087.html
※2 活動を考える場 https://www.univcoop.or.jp/handbook/handbook_1649.html
阪神・淡路大震災
1995年(平成7年)1月17日

加藤- まず、阪神・淡路大震災当時はどのような生活をされていたのか、あとは実際に当時から防災の面で意識されていたことはありましたか。

団長
安田- 震災時は、成人式の2日後の朝5時で、僕は寝ていました。当時、関西は地震が全然ない地域で、備えというよりも地震なんて起きないと思っていたので、何も用意はしてなかったですね。揺れはじめると、ベッドの上でもトランポリンのように飛んでいる感じで身動きが取れず、お皿やガラスが割れる音がバリバリして、あとから見たら水槽が割れていて。でも眠たいし収まったから寝ていたら、部屋に来た母親が、寝ている自分を見てびっくりして「大丈夫か?」と。でも母親も動揺していたのか、固いスキーブーツが壁に刺さっていたのを見て「見てみ、スキーブーツあるで。あんたこれ、探していた奴やん」っていうのが第一声でした。
その後、父親の車で祖母の家を見に行くと、甲子園口の辺りから家が倒れていて進めず、逆に戻ろうとしても戻れずに揉めたり、あちこちで火事があったり、当時は信号も止まっていて混乱していました。なんとか祖母宅に行き、安否を確認してから帰宅したら、マンションの予備電池で一旦電気が普及したらしく、割れた熱帯魚の水槽の中のヒーターが漏電して火事になりそうになっていましたね。家電はまずコンセントを抜かないといけないと、それで火事になったお家もたくさんあったというのは後で聞きました。
当時は慌てて外に出て足の裏を怪我した人たちが何人かいたので、今はなるべく寝ている枕元にスリッパなどを置くようにしています。他のケガもそうですけど、足の裏の怪我は一度経験しましたが本当に辛いです。
当時の被災地の実情

団長
安田- もちろん水道も止まったので、洗いものができないから、お皿にサランラップ等の食品包装用フィルムを巻いて食事をしたり、人によっては寒い時期だったので体に巻いている人もいたような気がします。これが意外と役立つと覚えたのと、あとは給水が来ても水を入れるタンクがなくて、タンクを買いに行くと通常よりも高い金額を取られたりしました。
それこそ体育館の日当たりがいい・悪いでいがみ合うとか、給水が来ても手伝わないとか、カップラーメンを取りすぎだとか、もう小さなことでみんないろいろ揉めるのよ。そういうところはあまり表に出ないし、みんな一致団結して頑張っているみたいなことが報道されるけど、そんなのは本当に申し訳ないけど一部でしたね。
公園とかの和式トイレを排泄物が超えていたし、思い出すと未だに気持ち悪いよね。でも早めに自分たちの地域は食事も届いて、被災地にしては恵まれた環境ではありました。
問題はあるとこにはあって、ないとこにはないみたいなことが、当時はスマホもないので起きていることがもう口伝えや噂だけで、みんなの不満になっていたりしましたよ。そもそも目の前で起きていること、甲子園口の駅前のビルや阪神高速が倒れるなんて想像もつかなかったし、なぜ助けに来てくれないのかという感じでしょう。火の手はあがる、銀行のATMはブザーが鳴りっぱなし、自動車に電柱が倒れてクラクションも鳴り続けるとか。僕は車を盗まれましたし、近所の女の子は車の中に引きずり込まれそうになったと聞きました。治安も非常に悪くなっていたんじゃないかな。当然、電気も街灯もあまりついてないから暗くて、女の人は暗い中をあまり歩かないほうがいいと言っていましたね。
第一に自分のこと、余裕ができて人のこと

団長
安田- 被災した時は、マラソンと一緒でペースを保たないと無理なんですよ。マラソンはゴールがあるから頑張れる、だけど被災した時ってゴールがないでしょう。いつまで頑張れば自分の家に戻れるのかわからない。被災した友達を自宅に呼ぶと、仲が悪くなることもあります。家庭のルールってそれぞれ違うから、靴の揃え方、トイレの使い方ひとつとってもイライラするわけで、その小さいことがどんどん積み重なって仲が悪くなる。被災した時に、人のためにも自分のためにも頑張るというのは身が持ちません。それができる人はいいですけど、僕はできないと思うので、自分のことだけ考えるとまでは言わないけど「第一に自分のこと、余裕ができて人のこと」くらいにしないと、精神的に辛くなってくると思います。

加藤- 大学生協は協同組合では、その価値の一つに「自立」ということがあり、自分自身がある程度自立していないと誰かを助けることはできないというところで、今のお話に通じるものがあり、共感できました。
また、先ほど洗い物ができない時の食品包装用フィルムの活用法をお聞きしましたが、実は最初にお話した大学生協のリサイクル容器は、食べ終わった後にフィルムをめくって容器を回収するもので、それは阪神・淡路大震災当時の皆さんの経験から生まれた取り組みだと聞いているので、つながりを感じました。

団長
安田- 全く協力し合わなかったというわけではないけど、そういうリアルな一面を見てきた人は話すべきかと思っていて。ドラマチックにいいことや専門的なことは他の人にお任せして、リアルなことにちょっと笑いを入れて聞きやすくして話すことが僕の役目だろうと思っています。
今まで話すことをお断りしてきた時期もありましたが、スキーブーツの話みたいな、芸人のスタイルで話すようにしています。
経験を語るきっかけ
友人の死と掲載された写真

加藤- 話したくないと思っていた理由が、ご自身のなかにあったということですか。

団長
安田- お笑いって楽しいもので、悲しい話をするのは、自分にとってマイナスだと思っていたところがあります。だけど、きっかけはコロナ禍に僕も周りも仕事が減っている中で、阪神・淡路大震災から何年も経つのに取材が来たりしたことです。震災直後の読売新聞に写真が掲載されたことがあって、その写真の僕の目の前の倒壊したビルで「お笑い芸人をやれ」と言ってくれていた友達の恵介が亡くなりました。あの写真は不思議で、ビルに向かってずっと「恵介、恵介、頑張れ、頑張れ」って言っていたのに、たまたま写真は横を向いているので僕とわかります。すごいタイミングと奇跡だし、たくさんの写真の中から選ばれたということは何か意味がある、“まだまだお前、頑張れよ”っていうことだろうなと思って。
人の「死」って二つあると聞いたことがあって、一つは肉体が死ぬ時、もう一つは人の記憶からなくなった時。僕は恵介に二つ目の「死」を与えないために、語り部としてこの経験を話すようにしています。
被災後に学んだこと
人と人とのコミュニケーションの大切さ

加藤- 実際に被災した人は必要な情報を求めて、デマや噂に左右されることがあると思いますが、ご自身が情報源の選び方などで気を付けていたことはありますか。

団長
安田- 当時はスマホもなかったので、拡散される情報もなかったですし、デマに対する対策はなかったですね。そもそもどれがデマでどれが真実かは、今となってはもうわからない。被災地のどこで物が手に入るのか、給水はいつなのか、被災した時に役立つ知識などは、結局のところ「人」でした。人と人とのコミュニケーションが最終的には大事になるので、今思い返してみても、人から教えてもらう情報が正しいか正しくないかは人を信じるしかなったし、悪いことをしたのも、助けてくれたのも、教えてくれたのも人でした。だから常日頃から会うと会釈くらいはする間柄じゃないと、非常時に声をかけにくいと思うんです。
先日も、近所の高齢女性に連絡がつかないと近隣の人たちで声をかけあった時に、今まで話したことがない人と話す機会があって、やっぱりその時に普段会釈や挨拶だけでもしている人の方がコミュニケーションを取りやすかったですしね。やっぱり結局「人」なんですよね。
今からすぐにできることは、もう「にこっ」ですよ。ちょっと気持ち悪いと思われるのかもしれないけど、よく会う人に「にこっ」と会釈すること。結局、防災の原点の一つは「人」だと思います。
それぞれの「助け合い」のかたち

伊藤- 自分自身は東北出身で、東日本大震災を小学校3年生から4年生にかけての時期に経験しましたが、内陸の出身なのでひどい被災もなく、年齢的に情報もあまり入ってこなかったので、こうして著名な方が実際の経験をリアルに語ってくださることに感謝しています。
阪神淡路大震災を経験されて29年経ちますが、それ以降も東日本大震災や今年の能登半島地震など、さまざまな災害が起こっています。災害が起こった時にどう捉えられているのか、意識や災害支援の取り組みなどがあれば、教えてください。

団長
安田- 助け合いは人それぞれで違うと思っています。お金での支援は募金等できる範囲でやりますが、震災直後に行くことが正義みたいな感じもあれば、直後に行く人を攻撃する人もいて、何もしない人よりはした方がいいと思うくらいで、どちらが正解かは正直わからないです。ただ、売名行為のように見受けられる人もいるので、直後はとりあえず見守ろうと、ひとまず自分の現地の知り合いに連絡を取り、その人に何が足りないのか確認することに重きを置いてきました。
やはり個人で全員は守れないから、落ち着いてきたら観光に行くとか、友達が能登にいるので会いに行こうかなと思っています。落ち着いてからだと目立たずに行けると思うし、災害時にタレントとして注目されることは必要ないと思っています。なので、東北も落ち着いてから自転車を持っていって走ったり、仮設のお店で買い物したり、目立ったことはやってないですけど、それも一つの復興ではあると思うので。
お友達の自転車屋さんが能登にいますが、「もう今はいいから、大丈夫だから。落ち着いて自転車で走れるようになったら、その時に来てくれることが嬉しいから」と言われたので、そうしようと思っています。だんだんやっぱり薄れていくんですよ、みんな。時間が経てば経つほど。だから自分の武器としては、自転車でいくらでも走れるので、サイクリングを楽しみに行くというのは一つ、やろうと思っています。それが人助けになるかどうかはわからないですけど、そういうやり方もあるんじゃないかなと思っています。

伊藤- 今のお話で、二つ大事なポイントを感じました。一つは、被災した側からすると連絡をくれるのが知り合いだと安心するんですよね。もう一つは風化させないというか、現状を伝えていくことです。その地域の人たちの一年後、二年後がリアルに伝わるように、発信する側は行動していかないといけないと強く感じました。
経験で得た知識を伝えること

団長
安田- だから自分の身を削るだけが正義じゃないとは思うので。ちゃんとこっちも楽しんだ方が「やりに来ました」「やってあげますよ」みたいなことよりはいいし、だからそこに住んでいる知り合いに連絡することだけでもできると思います。
国の政策についてもいろいろニュースが出ますけど、復興が遅れているような報道を見て絶望的になる人もいるのではないかと心配になります。騒ぎすぎることは少し危険で、被災した人たちの不安を煽っているような気もするし、一方で声をあげてくれる人がいないと本当に支援が行き届いているか分からないところもあるし、難しいですね。
だから正しい知識が必要で、例えば家が「半壊」だと言われた後に、もう1度見てもらったら「全壊」になった人もいるし、納得がいかない場合は2回、3回と見てもらえることを知らない人も多いじゃないですか。みんな1回目の経験だと思うんです、多分1回しかないと思うんですよ、あんな経験は。

加藤- 先日、日本銀行のツアーで貨幣博物館に行った時に、震災で焦げたり焼けたりした原形を留めていないお札を持ち込むと、新しいお札に交換する取り組みがあることを知りました。そういう経験や知識を伝えていくことで、被災した人たちの生活がより良くなることはあると思います。
あとは、復興は長い目で見るというか、その場に日常を取り戻すまでがやはり復興なのだと改めて感じたので、支援はもちろんですが、自分たちの防災も改めて確認するべきだと思いました。
若い世代の皆さんへ

加藤- それでは最後に、読者の大多数は今の若者世代になるので、今までのお話を踏まえてメッセージをお願いします。

団長
安田- ピンチの状態になった時に頑張りすぎないということと、自分のできる範囲でやるということが大事なので、その範囲で頑張ってくれたら、頑張ってもらった側は本当にありがたいと思っていますので、皆さんのその勇気とか頑張りとか、いま大学生でできることをやってくれたら嬉しいなと思います。
僕も被災したのが20歳なので、無責任だったんですよね、正直。実家暮らしだったし。だから、今もしあの状況になったらプレッシャーはとんでもないですよ。お金の問題や、家族を守らないといけないとか。20歳って、そういう背負っているものは親世代ほどないと思うので、だから学生だからできることを自分で考えてやってくれたら嬉しいなと思います。でも無理はしないでほしいですね。
それと、一番鍛えておくといいのは体力です。自分の身を守るのも走れることが一番とよく言われますけど、体力はつけていた方がいいと思います。そういう意味で、一番の防災は「体力」と言えるかもしれません。

久野- 現在、全国学生委員会の中で、激甚災害支援防災の分野を推進していくリーダーを務めていますが、今まではいろいろな大学生協や学生たちが防災に前向きに取り組むことを推進していく立場として、実際に何か起きた時の行動につながるような情報を発信することが多かったのですが、お話をお聞きするなかで、防災において「人とのつながり」や「体力」も大切であるという、自分としても今まで考えられなかった新しい視点に気づかされましたし、勉強になりました。
これから大学生協連の学生委員会として、防災や激甚災害支援について推進していく上で、参考になる情報をたくさんいただけたと思うので、これからも学生が前向きに考えて行動していくことができるように、頑張っていきたいと思います。
2024年7月12日リモートインタビューにて
PROFILE
安田大サーカス 団長安田 氏

1974年 兵庫県西宮市出身。
HIRO、クロちゃんと共にお笑いトリオ「安田大サーカス」を結成。
リーダーでツッコミ担当、ニックネームは「団長」。
お笑い芸人にとどまらず、俳優、声優やナレーターとしても活躍。
スポーツ万能で自転車のロードレースを趣味とし、自らを「自転車芸人」と名乗り、著書も出版している。
(公式サイトより一部抜粋)
所属事務所HP 安田大サーカス |松竹芸能株式会社 (shochikugeino.co.jp)
Instagramhttps://www.instagram.com/dancyoyasuda/
X https://twitter.com/dancho_yasuda
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCl8AJj6Qxktq82x-PnOg40A


