ふくしま被災地スタディツアー2020 特別企画
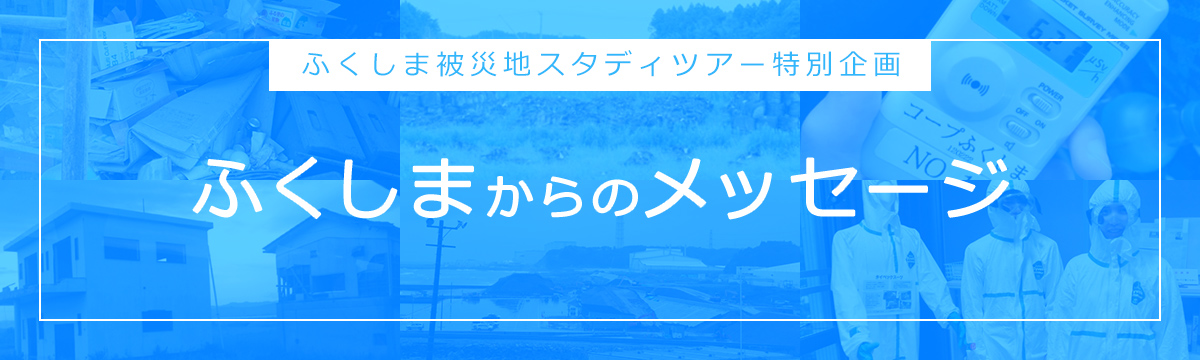
今年度は開催できなかったふくしま被災地スタディーツアーですが、例年携ってくれているふくしまの方々よりメッセージをいただきました。
元福島大学教授 清水 修二先生
福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター天野 和彦 先生
みやぎ生協コープふくしま 斉藤 恵理子 様
木戸川漁協 鈴木 謙太郎 様
――震災当時の様子

鈴木:仕事場でもある漁協は楢葉町にあるのですが、私の地元はいわき市なので毎日そこから通っていました。楢葉町にある漁協は津波の被害を受け、建物が流されるほどではなかったものの胸くらいまでは水に浸かってしまいました。漁協では鮭とアユの稚魚を飼育していたのですがそれらも津波や停電、そして何より原発事故の影響で全滅しました。放射線量の問題もあり避難することになり、そのまま立ち入りが制限されました。漁協にある大事な資料や機材の確認もしたかったこともあり役職員間で話し合って、事故から16日後にまだ原発の危険性もわからない中で1時間だけ滞在を決め見に行くことにしました。実際に行ってみると瓦礫が多く歩ける状況ではありませんでした。一度では貴重品を持ち出すことができず、数回に分け何度も漁協に戻って貴重品を運び出したんですが、その間ガラスを割られお金になるものは盗まれたりもしました。元通り仕事ができるようになるまでにはかなりの時間がかかる状況でしたが、組合員みんなで助け合って4月末くらいにいわき市に事務所を立てることができました。その事務所には商工会とかも一緒に入って運営していました。事務所を構えてからは組合員の安否確認などに奔走していると2011年は過ぎていきましたね。当時は福島県内の他の漁協も困ったと思うんですが、連合会がいろいろと手伝ってくれて再開への気持ちは途切れずに頑張り続けることができました。楢葉町に日中立ち入れるようになってからようやく仕事の本格的な再開の希望が見えてきました。2012年からは鮭や鮎に含まれている放射線量を図り始めました。楢葉町にとっては鮭は観光資源ということもあり町を盛り上げるためには大事だったので少しでも早く震災前の状況に戻りたかったと考えてたので、できるだけ早く稚魚を放流できるよう町の人とも話しながら復興交付金をいただいて立て直そうと進めていきました。その結果、再開できたのは2015年でしたね。2015年9月には楢葉町の避難指示が解除されたので9月には戻ってきてまだ小規模ですがふ化事業を再開することができました。
――今の生活
鈴木:短いようで長い10年だったと思います。例えば戻ってくる鮭の数で言ったら、震災前だと7万匹くらい毎年戻ってきていましたが、2015年では8000匹、去年なんかは300匹しか戻ってきませんでした。震災後は放流する数も年々減ってきていて、考えていたよりも厳しい状況です。加えて、去年は台風の被害もありましたし、全国的に鮭の不漁ということもあり、震災直後は再開できた2015年時点で10年かけて元に戻そうと考えていましたが、あと5年では以前の状況まで戻すことはできないですね。やるしかないとは思っているのですが…。個人的な生活の話だと、家の復旧は早かったですね。楢葉町での生活を考えてみると、震災後は子供たちの声が聞こえなくなったり、以前は川辺を歩く人たちを何人も見かけることがありましたがそれもなくなりました。ただ、最近は学校の機能が戻ったので子どもたちの声も聞こえるようになったし、以前よりも人の出入りは増えています。夏に川遊びをしている子供たちを見たり、幼稚園から大学生までの体験学習とかも3年前から再開したりしています。うちの漁協では地元楢葉南北小の4年生が第二孵化場として鮭の卵から飼育してみることも始めているので、それを3月の放流の時に子どもたちと一緒に稚魚を放流しようという計画もしています。今年はコロナがあったのでできなかったことも多いんですが、年々できることが増えてきていることも楢葉町の復興を感じる1つだと思います。それもあって仕事の方は頑張っていきたいと思っています。いつまで東電の賠償金が支払われるかもわからないので、早く自立できるようにしたいですね。とにかく今後のことは心配事が多いです。
――若者へ向けてメッセージ
鈴木:奇跡はなんどでも起きるのかなと思います。思わぬ形で良いことも悪いことも起こる。落ち込むときも多いけど、前を向いてコツコツやっていけば奇跡は起こるんじゃないかなとこの経験からお伝えできればと思います。みやぎ生協コープふくしま 宍戸 義広 様
――自己紹介をお願いします

宍戸:みやぎ生協・コープふくしまの執行役員・ふくしま県本部副本部長をしています。震災当時、コープふくしまの常務理事をしており支援に来る人の窓口対応を行っていました。