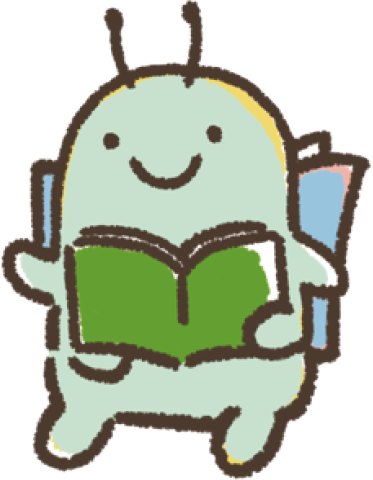今月のナイスコメント(2024年10月)速報
2024年11月23日現在
10月に投稿されたコメント796枚から選考しました。選考は、大学生協の全国学生委員、出版甲子園学生メンバー(特別協力)、書籍担当職員、顧問をお願いしている先生で行いました。
ナイスコメント一覧はこちら
ナイスコメント8点、次点11点でした。おめでとうございます!
ナイスコメントの方には図書カード1000円分をプレゼントします。
ナイスコメント:8件
図書カード1000円プレゼント!
書名クリックで、情報・オンライン注文へ

| ペンネーム: | げっこー |
|---|---|
| 大学・学年: | 宇都宮大学 3年 |
| 書名: | 世界でいちばん透きとおった物語 |
| 著者: | 杉井光 |
| 出版社: | 新潮社 |
ある一文を読んだ瞬間、ゾッとした。自分自身も、この本に隠された仕掛けを当に体験していたからである。小説は物語そのものを楽しむもの。今までそう思っていた。しかしこの本は私のそんな思い込みを、一瞬で消し去ってしまった。物語そのものだけではなく、作者のトリックにも本当に驚いたし、このような形でも読者を楽しませてくれる本があるのだと感動した。電子書籍が普及する現代だからこそ、紙の本の魅力を再確認できる一冊である。読み終わった際にはきっと、心が「透きとお」ったように感じるであろう。

| ペンネーム: | いちごおはぎ |
|---|---|
| 大学・学年: | 熊本大学 2年 |
| 書名: | センス・オブ・ワンダー The sense of wonder. |
| 著者: | レイチェル・ルイス・カーソン 上遠恵子 |
| 出版社: | 新潮社 |
どんなに反対されようと、私はこの小説を「青春小説」と名付けたい。
留年スレスレの三年生、素敵な先輩に憧れて入ったサークルの評判が非常に悪いと知った一年生、学生作家としてデビューしたものの小説が売れない三年生などが主人公の連作短編集。このあらすじからもわかるように、登場人物は皆キラキラキャンパスライフとは程遠い。
しかし、すべての登場人物が懸命に生きている。上手くではなく、強く生きている。そのことに希望を感じられ、すべての大学生を応援したくなった。

| ペンネーム: | 北極星 |
|---|---|
| 大学・学年: | 愛知教育大学 3年 |
| 書名: | ぜつぼうの濁点 |
| 著者: | 原田宗典 柚木沙弥郎 |
| 出版社: | 教育画劇 |
この絵本を読んだ時の感想はまさにその一言であった。
物語の主人公はひらがなの国に住む,「ぜつぼう」の「ぜ」の字に付いた濁点である。主人である「ぜつぼう」が苦しんでいる責任は自分にあると感じたぜつぼうの濁点は,旅に出ることを決意する。しかし,濁点は用途に限りがあると同時に単体では存在できない。自身の存在意義を問われる濁点の様子が愉快な言葉遊びで描かれる。
私たちが当たり前のように使っている言葉がこんなにも面白く,美しい物語になることの衝撃を,ぜひ味わってほしい。
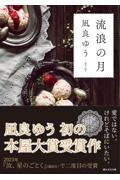
| ペンネーム: | ゆる |
|---|---|
| 大学・学年: | 東北大学 2年 |
| 書名: | 流浪の月 |
| 著者: | 凪良ゆう |
| 出版社: | 東京創元社 |
「小児性愛者」この単語は聞くだけで人を不快にさせる、そんな言葉だろう。さらにここに、「小さな女の子を匿っている」そんな表現を加えたら、不快を超えて憤りさえ感じさせるかもしれない。しかし、この少女にとってこの人が必要な人間だとしたら?生きる上でなくてはならない存在だとしたら?
この本を読んで感じたのは常識とは何かということである。そもそも「常識」「普通」「当たり前」これらの言葉は何が基準なのか。肯定も、しかし否定も出来ないこの2人の関係をあなたはどう捉えるか。「犯罪」か、それとも「愛情」か。

| ペンネーム: | たま |
|---|---|
| 大学・学年: | 京都大学 3年 |
| 書名: | 生殖記 |
| 著者: | 朝井リョウ |
| 出版社: | 小学館 |
あらすじがほとんど公開されていないという、あまりされてこなかった販売方法を取っている理由がよく分かります。とにかくページを開いてみて!きっとあなたも「私」の正体に驚かされます。一人称でも三人称でもない書き方を考えるうちに思いついたという、この語り手。その発明に脱帽です。
小説のようであり、論説のようである内容からは、「生きる意味」「世界の発展」を考えさせられます。あなたも関係ありますよね?と首根っこを掴むように問いただされている感覚。是非他の多くの方にも、打ちのめされてほしいです。

| ペンネーム: | 空飛ぶまめだいふく |
|---|---|
| 大学・学年: | 東北大学 大学院 |
| 書名: | 本は眺めたり触ったりが楽しい |
| 著者: | 青山南 阿部真理子 |
| 出版社: | 筑摩書房 |
本を読む人なら感じたことのある「なぜかこうしちゃうんだよな」。自分だけだと思っていたかゆいところに手が届いたような話が詰まっている。言語化してくれてすっきりし、なぜか小気味良い。本棚をただ見たいだけの男の子と読書家の司書の話が印象的。読んだ後、キャンパス内の書店を2つと駅近の書店を2つ見て回った。なにも買わずにじっくり本棚の背表紙を見て歩きまわるのも楽しいもんだ。この本には、感想を書くとき、感動をべつな感動と結びつけて書くと良いと書いてあった。心の文脈のなかで整理する、っていい表現だな。

| ペンネーム: | 鷽秋かおす |
|---|---|
| 大学・学年: | 東北大学 3年 |
| 書名: | チーズはどこへ消えた? Who moved my cheese? |
| 著者: | スペンサー・ジョンソン 門田美鈴 |
| 出版社: | 扶桑社 |
私のような書痴に言わせれば、「読めば人生が変わる本」などそこら中にある。最早ありふれている。しかしこの本のとびきり良いところは、読み終えた直後から、思考せずにはいられないところだ。簡潔なテーマ、明快な比喩、それらは我々の複雑な人生の精巧な写しである。疑いなく誰もが、これまでの人生をチーズの上で生きている。だから今までの自分を顧みる。そして我々はこれからもチーズの上で生きる。だから自分の未来を考える。数十年後、これを読み返す自分が容易に想像できる。そのとき私は、私をどう解釈するのか。楽しみである。

| ペンネーム: | みゃーり |
|---|---|
| 大学・学年: | 北海道大学 3年 |
| 書名: | 夜と霧 新版 Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. |
| 著者: | ヴィクトル・エミール・フランクル 池田香代子 |
| 出版社: | みすず書房 |
地位も、服も、名前も、何もかもを奪われて、持っているものは自分の身体一つだけになったとき、私には他に何が残っているでしょう。自分の心?強制労働の日々、食事もろくに与えられず、寝ている時だけが、唯一自由でいられる時間。生きる目的を見失いそうになる日々の中で、私たちは今まで持っていた優しさを、人に与えることができるのでしょうか。過酷な環境の中、今までの精神状態でいられるのでしょうか。
生きる意味とは何か。どんな力でも奪えないものはあるか。ナチスの強制収容所に収監された体験をリアルに描く、不朽の名作。
次点:11件
書名クリックで、情報・オンライン注文へ

| ペンネーム: | ぜう |
|---|---|
| 大学・学年: | 西南学院大学 2年 |
| 書名: | 思考の整理学 新版 |
| 著者: | 外山滋比古 |
| 出版社: | 筑摩書房 |
残念なことに、私の脳のスペックでは処理しきれないような情報に出くわすことがある。更に後回し癖も手伝って、「とりあえず明日の朝考え直そう」と次の日に作業を持ち越したこともあった。ところが翌朝になってみると、昨日までの苦悩がウソのように作業がはかどるということも経験してきた。この裏技のような思考法を、経験ではなく知識として早い段階で習得しておきたかったと感じている。その上で、刊行から37年が経ってもなお読まれ続けるこの本は、知のバイブルとして不動の存在なのだろう。

| ペンネーム: | おかず |
|---|---|
| 大学・学年: | 同志社大学 1年 |
| 書名: | 青を抱く |
| 著者: | 一穂ミチ |
| 出版社: | KADOKAWA |
その本の中で特別に重要な場面では無いのに、なぜかコメントを書く時に最初に思い浮かんでくる場面がある。
この本では、主人公が、今は昏睡状態の弟が幼い頃を思い出している場面。海が大好きな弟がバケツに海水をくんで持ち帰ってきたのにバケツの中には海の青がなくて「どうして海は持って帰れないの」と泣くのだ。
キラキラしている大好きなものが、手の中に入ったとたん、別のものになってしまう。
それは、恐らく誰の人生でも1度はあったことで、とっくに忘れていた感情をこの場面は思い出させてくれたのだろう。

| ペンネーム: | 本を読む看護学生 |
|---|---|
| 大学・学年: | 新潟大学 1年 |
| 書名: | わたしの美しい庭 |
| 著者: | 凪良ゆう |
| 出版社: | ポプラ社 |
読んでいると膿んで腐った心の古傷へ雨が降り注いで、新しい花が芽吹くような作品。
「縁切りマンション」なんていう縁起の悪い建物を舞台に、辛いことや嫌なことばっかりで目をそむけたくて、でもたまに幸せな瞬間がやってくる……まるで人生みたいなストーリー展開がされていく。トラウマ級の嫌な記憶もいらない縁を切ってシンプルにしたら、いつか大切な思い出になるかも。そんな予感を読者にもたらす、読むセラピーのような一冊。

| ペンネーム: | えび天天 |
|---|---|
| 大学・学年: | 京都大学 4年 |
| 書名: | センセイの鞄 |
| 著者: | 川上弘美 |
| 出版社: | 新潮社 |

| ペンネーム: | 桐田 |
|---|---|
| 大学・学年: | 龍谷大学 3年 |
| 書名: | エゴイスト |
| 著者: | 高山真 |
| 出版社: | 小学館 |
誰のために行動しているのか?それは行動の主体自身のためかもしれない。エゴかもしれない。でもそれを受け取る側(本書なら龍太の母親)のやさしさがあることを感じられた。
映画版を観た後に読んだ一冊。映画と同様静かな激しさがあって良かった。
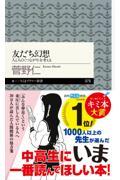
| ペンネーム: | もも |
|---|---|
| 大学・学年: | 富山大学 1年 |
| 書名: | 友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える |
| 著者: | 菅野仁 |
| 出版社: | 筑摩書房 |
今感じるのは、あの時私が本当に求めていたのは、私の定義に当てはまる「友だち」ではなく、(もといそんな定義は意義をなさない。)
自分を否定してしまう理由を受け入れて、そんな自分も肯定できる自分だったと思う。
自分に持っていない要素を相手に本気で求め出したら、それは相手ではなく自身に求めている要素なのかなと思った。
本書は、友だちとの付き合いを通して自分の心の声を改めて聴くきっかけをくれた。
簡潔ですぐ読めるので是非!

| ペンネーム: | さき |
|---|---|
| 大学・学年: | 千葉大学 2年 |
| 書名: | 赤と青のガウン オックスフォード留学記 |
| 著者: | 彬子女王 |
| 出版社: | PHP研究所 |
授業中、窓の外を見て、誰しも思ったことがあるだろう。
「私はなぜ、学ぶのか。」
これは、女性皇族として初の博士号を取得なさった彬子女王がご自身が語った、オックスフォードでの日々の物語である。
皇族の方が書いた、と聞くと、堅苦しい印象があるかもしれない。
しかし、ページを開けば、伝わらない英語に苦悩し、友人とのひと時に心緩ませ、時には愚痴も言う。
時にくすっと笑ってしまうような、私たちと変わらない、大学生である。
読み終わったころには今より少しだけ、学問が楽しくなるだろう。
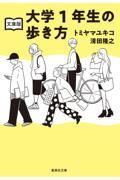
| ペンネーム: | さささ |
|---|---|
| 大学・学年: | 東京大学 1年 |
| 書名: | 大学1年生の歩き方 文庫版 |
| 著者: | トミヤマユキコ 清田隆之 |
| 出版社: | 集英社 |
特に実用至上主義についての部分が印象に残りました。これは、勉強も、インターンも、旅行も、「〇〇のために」するという考え方で、こうなると自由があっても何をすべきかわからず、指示待ち人間になってしまいます。自分にも思い当たる節があったので、もっと遊びをきかせるようにしたいです。大学生によくある悩みを月毎に解説しているこの本は、同じく悩める大学1年生にぜひ読んでほしいです!

| ペンネーム: | リーブロ |
|---|---|
| 大学・学年: | 早稲田大学 1年 |
| 書名: | なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない |
| 著者: | 東畑開人 |
| 出版社: | 新潮社 |
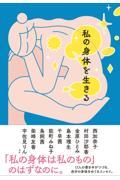
| ペンネーム: | たま |
|---|---|
| 大学・学年: | 京都大学 3年 |
| 書名: | 私の身体を生きる |
| 著者: | 西加奈子 村田沙耶香 金原ひとみ 島本理生 藤野可織 |
| 出版社: | 文藝春秋 |
また、一人ひとり違うのだという認識が広まったとはいえ、多くの人が同じようなことに悩んでいることが分かり安心すると同時に、社会や認識の問題点が浮かび上がった。

| ペンネーム: | おかず |
|---|---|
| 大学・学年: | 同志社大学 1年 |
| 書名: | Q&A |
| 著者: | 恩田陸 |
| 出版社: | 幻冬舎 |