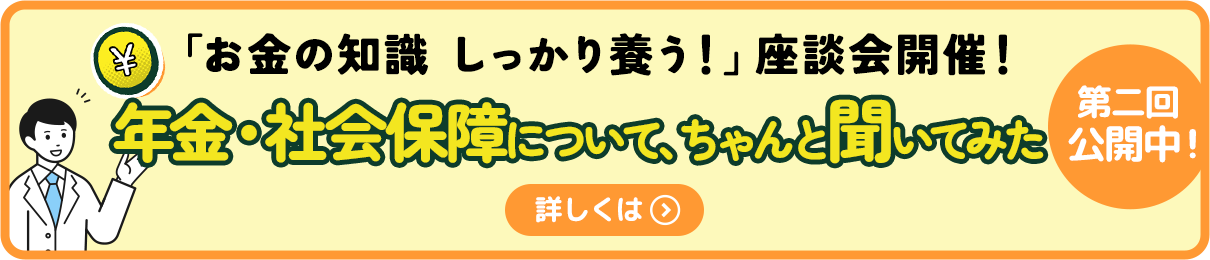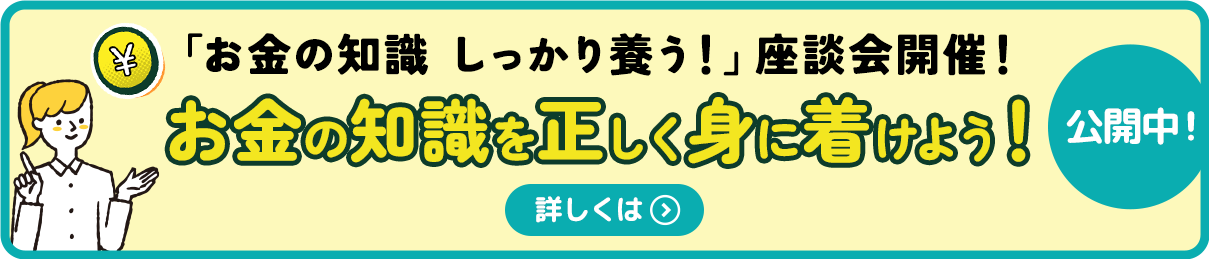「お金の知識 しっかり養う!」座談会 第三回
金融リテラシーを身につける~資産形成と金融商品のお話~
.jpg)
第三回目となる今回の座談会では、自らの生活設計の中で資産形成を考える際に、どのように金融リテラシーを育み金融商品と向き合うべきか、基本的な考え方やリスクと注意すべき点などを教えていただきました。
これを機に投資する・しないも含めて、自分のお金に関する状況を再考してみませんか。
「お金の知識 しっかり養う!」座談会 第三回金融リテラシーを身につける~資産形成と金融商品のお話~
座談会参加者

講師
佐々木 智晴さん
金融経済教育推進機構
(J-FLEC/ジェイフレック)
経営戦略部 経営企画課
経営企画グループ長

浦田 行紘
全国大学生協連
全国学生委員会 副委員長

志村 颯太
全国大学生協連
全国学生委員(司会/進行)

井上 愛理
全国大学生協連
九州ブロック学生事務局
-CONTENTS
(以下、敬称を省略させていただきます)
自己紹介と座談会の趣旨である金融リテラシーとは

志村-
全国大学生協連で全国学生委員をしております、志村颯太と申します。今年の春、富山大学を卒業しました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

浦田-
同じく全国大学生協連学生委員会で活動している浦田行紘と申します。今年の春に奈良教育大学を卒業しました。
投資についてはあまり知らないことが多いので、楽しみにしてきました。どうぞよろしくお願いします。

井上-
全国大学生協連九州ブロックの井上と申します。現在九州大学の4年生です。来年から就職のため上京する予定なので、投資なども勉強して社会人としてのいいスタートを切りたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。

志村-
本日の講師を務めていただきます、金融経済教育推進機構 経営戦略部の佐々木智晴様より、自己紹介と金融経済教育推進機構、金融リテラシーについてのご説明をよろしくお願いいたします。

佐々木-
私は金融経済教育推進機構(以下、通称である「J-FLEC/ジェイフレック」)という、昨年度できた新しい認可法人で経営企画グループという、金融経済教育を広く国民の皆さまに伝えていくための部署で業務をしております。
略歴としましては、2005年に金沢大学を卒業して、日本生命保険相互会社に入社しました。そこで18年ほど勤務した後、2023年から金融庁に出向し「J-FLEC」を立ち上げるための準備室で1年間仕事をし、昨年7月から「J-FLEC」に出向して企画立案や広報活動、また全体執行や監督官庁である金融庁との対応もしております。
簡単に「J-FLEC」の紹介をさせていただきますと、金融経済教育推進機構と漢字で書くと難しいですが、意味合いは文字通り「お金に関する教育を進めていく組織」ということになります。金融機関の販売に関する特別な法律で「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」というものがあり、この中で金融経済教育推進機構というものを作り教育を進めると明記されていて、これにより国の認可を受けて中立・公正な立場から教育を届けていく唯一の公的機関となっています。幅広い年齢層の国民全員に向けて、一人ひとりのニーズに合わせた金融経済教育の機会を提供していますので、皆さんに金融経済のお話をさせていただくことで、少しでも多くの方に知ってもらえたらと思っています。
では金融リテラシーについてですが、端的に言うと「経済的に自立してより良い生活を送るために必要な『お金に関する知識や判断力』」ということになります。大学生活の中でもお金に関する悩みや疑問というのは、アルバイトや仕送りしてもらう中での毎月の生活費の管理や、クレジットカードを持った場合の返済や、社会人になってから支払いをしていく奨学金が自分の生活にどう影響してくるのかなど、いろいろあるかと思います。今日のテーマの中でも投資の話が出てきますが、投資をする前段階として生活費や将来設計をどうしていくのか等のお金に関する知識を学ぶことと、実際に投資をする際に何を買ったらいいのか、手を出してはいけないものを知った上で自己判断できるような教育をしっかりお伝えしていきたいと思っています。
金融リテラシーを育むための学びとしては、自分の収入と支出のバランスをきちんと取るための家計管理、将来に向けてどういう仕事についてどのように成長していきたいか、家族を持つことで将来的に必要なお金を考える生活設計、資産形成を行っていくにあたって必要な金融経済知識があります。このような知識は一人で学ぶには限界もありますので、専門家への相談ということで外部知見の活用を推奨しますし、私ども「J-FLEC」は、この外部知見を提供していることになります。
まず、最初にすべきこと

志村-
実際に自分の周りにも投資や資産運用に興味があるという学生が多いのですが、学生のうちから投資や資産運用について、実際に学んでおくと良いことはありますか。

佐々木-
これは投資や資産運用に限った話ではなく、お金に関する意識を一度しっかり自分の中で持つことが大事なことです。それは自分自身が今置かれている環境、アルバイトでどのくらいの生活費を稼いでいるのか、投資に向けるお金の余裕があるのか、また旅行など自分のやりたいことに対してどのくらい貯金の必要があるのか等、見つめなおすきっかけになります。
また、投資という視点で考えると、社会の状況や今の経済がどのように進んでいるのかを学んでおくという意味での幅広い知識が必要になります。直近では自民党の総裁選挙があり、それを受けて株式市場が大きく動きましたが、そういう市場の流れを読むことも大事ですし、それによって株価が上がる企業もあれば下がる企業もあることを理解しておくことも大事なことかと思います。投資を単純にお金儲けではなくて、自分が生活しているこの日本という国がどのように動いているのか、みんながどう考えているのかを理解できるようになり、幅広い視点で考えられるようになると、投資自体も面白みを持ってできるのではないでしょうか。学生のうちは時間もあるので、このことをきっかけに情報のアンテナを高くして、新聞や経済ニュースなどで興味を持っていろいろなことを学ぶのもいいですね。またその際に、自分が得た情報が正しいかどうか判断できる力をつけることも重要になります。
金融商品の種類とそれぞれの特徴

浦田-
そもそも金融商品にはどういうものがあるのか気になります。手を出してはいけないものという話もありましたが、そこも含めてお話しいただければと思います。

佐々木-
投資に関して注意すべき点は2つあるかと思います。あくまでも将来に向けてお金を増やしていくことなので、生活費以外の余裕があるお金で行うことが大前提です。借金をしてまで投資にお金を回すことは、損をした場合に自分の生活が立ち行かなくなり本末転倒です。
また投資に関しては、おいしい話はありません。SNSなどでよく目にする100万円の元手が5年で1億円になるなどのキャッチーな情報や、著名人が薦めているから安心みたいなものは、そもそも本当に儲かる情報が誰もが目にするSNSに流れてくるはずはないですから、基本的にはないと思ってください。5年で100万円の元手を1億円に増やすには、元手を100倍に増やす必要があり、何か悪いことをしない限りそんな増え方はしません。そこに自分で気づけることがすごく大事ですし、最近では著名人も自身のSNS等で注意喚起をしていますので、そういうものに騙されないようにしてください。資産形成の基本として、運用商品の考え方をご説明しますと、1つ目は株式投資があります。株式投資というのは、いわゆる上場している企業が出している株を皆さんが購入して、それの値上がり値下がりを受けて売買していき、配当金や株主優待などを受け取ることです。株価はここ1、2年上がり調子ですが、それ以前はずっと厳しい状況が続いてきましたので、上がり下がりの波が必ずあると思って運用していくことが大事かと思います。
2つ目の債券投資ですが、満期を迎える時期と利子の受取が債券に記載されており、それを理解した上で満期まで持ち続ければ、約束されていた利子が全て受け取れる仕組みになります。株価みたいな大きな変動はないですが、債券価格というところで少し変動があると思っていただければ結構です。株に比べるとかなりローリスクローリターンですが、リスクが少ない分収益も小さくなります。これも最近は株価の全体的な高まりを受けて利回りが少し上がっているので、昔に比べると収益も上がってきています。
3つ目が投資信託になります。先ほどお話した株や債券を専門家がまとめて運用することをファンドと言いますが、そのファンドを買うという形になります。ファンドが運用する商品としては、株がたくさん入っているパッケージ商品とか、株と債券がバランスよく入っていてリターンもリスクも少し抑えた商品とか、あとは債券だけでパッケージしている商品もあったりします。いろいろな組み合わせがあり、1つの商品を買うよりもプロが分散して運用してくれるところがポイントですし、その分手数料が費用としてかかります。
また株や債券も国内株であったり海外株であったり、世界中のものを買うことができますが、海外株や海外商品を買う場合、例えば日本円でドル建てのものを買うと、円とドルの為替が影響することになります。金融商品を考える際に重要なのは、安全性と収益性と流動性という3つの観点だと言われています。安全性というのは元本や利子の支払いが確実かということであり、収益性というのはきちんと収益が期待できるものなのかというところ、流動性というのは売りたいときにすぐに現金化できるものかということです。株式、債券、投資信託以外に預貯金もありますが、預貯金は金利分しか増えないので収益性が△、株式は収益性の面で儲けは大きいかもしれないけど、安全性に関しては損する可能性もありますので△、債券はバランスがいいですけど満期まで換金できないので流動性としては△、投資信託はパッケージ商品なので、組み合わせによって変動する幅があるということを理解していただければと思います。

浦田-
債券の表の中で、国、自治体、企業などに資金を提供することで債券が発行されるというのは、例えば国債とかになるのでしょうか。

佐々木-
そうですね、社債というものもありますが、いわゆる債券で一番有名なものは国債になります。5年ものや10年物、30年物など満期の設定はさまざまです。満期までの期間が長ければ長いほど、利率が良いのが特徴です。
投資におけるリスクとは?~リスクとの向き合い方~

井上-
投資に興味はあるけど、具体的なリスクがいまいちわからないままで怖がっている部分があります。具体的にどんなリスクがあるのか、何を知ってどのように管理したらいいのか、そういった知識面の話を伺いたいです。

佐々木-
まず、投資におけるリスクの考え方ですが、英単語だとリスクは「危険」という意味合いになりますが、資産運用においては「運用成果の振れ幅」というものを指します。大きく儲かるかもしれないし、大きく損するかもしれないということですね。そのような振れ幅とか不確実性というものを「リスク」と言っています。
その上で、金融商品におけるリスクとリターンの関係を表で表すと、基本的にマイナスにはならないけれど儲かることもあまりないという意味で、ローリスクローリターンの位置に預貯金があります。その右上にリスクが少し上がる分、リターンも上がるという意味で債券ですね。その右側に幅広くあるのが投資信託で、いろいろなパッケージ商品の中でバランスがさまざまなので振れ幅が大きいです。で、少し離れて株式はハイリスクハイリターン、株価が上がるかもしれないし下がるかもしれないという意味になります。
逆にこの表に記載のないものとして暗号資産やビットコインなどがあり、金額の変動の幅が非常に大きいのが特徴です。暗号資産というのは円やドルなどの国際通貨とは違い国の裏付けがなく、多くの取引によって価値が認められるもので、みんなが価値を認めなくなった瞬間に価格は暴落したりします。またデジタル資産なので、紙幣や硬貨として持つことができないのも特徴です。他にもFXや先物取引、オプション取引、あとはバイナリーオプションなどもあります。これらも基本的には価格変動の幅がかなり大きいので、リスクを理解しないままに手を出すのは危険で、きちんと理解した上で選ぶことが必要です。
一方で、ローリスクハイリターンにはバツをつけていますが、これは他の商品とは別物で、全く損をせずに利益がでる商品は、基本的には詐欺に近いものだと思ってください。リスクはないのに儲けだけが出る商品が本当にあるのであれば、わざわざお金を集めて行わないはずなので、基本的にそういう情報が来た時には、明らかに怪しいと思ってください。
先ほどお話したように、投資はリターンとリスクのバランスになりますが、そのリスクとしては主に4つあります。1つめは価格変動リスク、株式や債券の価格変動が起こることです。2つめは信用リスクで、これは投資先の企業が不祥事などで急に財政が悪化するなどの、自分では予期することができないという意味のリスク。3つめは為替変動リスクで、円とドルの関係でいうと最近円安にまた振れてきていますので、ドルのものを買う場合によりお金がかかることになりますし、逆に円高のパターンもあり得ます。4つめはカントリーリスクですね。日本の国内であれば天災など、海外であれば紛争などで、その地域の経済環境に影響がでる場合などが挙げられます。
そういったリスクを抑えるために、長期・積立・分散という3つのキーワードで運用することが推奨されています。長期投資は長い期間で投資を行うこと、積立投資は定期的に一定額を積み立てるように投資していくこと、分散投資は一つの商品だけを買うのではなくて、いくつもの地域や通貨、企業の投資先を散らして投資することです。カントリーリスクや信用リスクなどは急に起こることがあるので、予期せぬマイナスが起きた場合に投資先が一つだとマイナスが大きく影響してしまうため、リスク軽減のためにこれらの視点が重要になります。

井上-
投資信託は初心者でも始めやすいと聞いたことがあったので、お話を聞いて理解できました。やはり投資にリスクはつきものですが、学生のうちは少額でなければ難しいかと思います。そういう時はどうしたらいいのでしょうか。

佐々木-
学生だと投資に回せるお金は限られると思いますが、その限られたお金の中でいろいろな経験をすることも大事なことかと思います。1万円とか、どんなに頑張っても10万円までしか準備できない場合、ある意味マイナスになっても10万円までしか影響しないと割り切れるのであれば、あえてチャレンジしてみることも選択肢のひとつです。いままでお話したように、長期・積立・分散という考え方でリスク軽減をしていただきたいのはもちろんなのですが、明らかに怪しいものに手を出すのではなく、ハイリスクハイリターンと言われている商品であっても自分なりに考えて投資してみることは貴重な経験にもなると思います。

井上-
投資と聞くとどうしても怪しい投資セミナーとか、詐欺まがいのものがあるのではないかと気になります。具体的にどこを見たらいいのか、不安に思った時に逆にどこを信用したらいいのか、相談場所などもあったらお伺いしたいです。

佐々木-
最近はSNSなどにいろいろな情報が溢れていますし、特に生成AIで作られた画像など、見極めが難しいものが多いですが、怪しいと気づくためにも金融リテラシーを身につけることが重要です。成人すると投資はもちろん、いろいろな契約も自分の責任において結ぶことができますが、逆に言うと自分で契約を結んだものは自分で責任を取らないといけませんので、契約を結ぶ前に一度立ち止まって考えることが大事です。
また、不安な時は周りの人や専門家に相談してみましょう。私ども「J-FLEC」は金融庁所管の認可法人であり、国が法律に則って組織を立ち上げています。法律を改正して作った組織でもありますし、公的団体として勧誘等が一切ない状態でお話をさせていただくことができます。国民生活センターや消費生活センター、警察などにも相談窓口はありますが、トラブルが起こってからの相談先が多く、本来はそうなる前の不安がある段階で一度連絡・相談してもらうことが重要です。「J-FLEC」では、「はじめてのマネープラン」として、無料でご相談に応じています。ただ投資商品の銘柄が上がるか下がるかなどの話はできませんのでご了承ください。また、大学生活を終えて社会人になる際には、対面オンラインの無料相談も活用してもらえればと思います。こちらはご自身の情報を事前に入れてもらい、webでオンライン予約をしてもらう形なので、その事前の相談に基づいて私どもの相談員、いわゆるFPの資格保持者が無料で1時間対応いたします。

井上-
投資する時に、どこに相談しても自分のところの商品を勧められてしまうようなイメージだったので、ぜひ何かあった時には相談させていただきたいと思います。
単利・複利の考え方

志村-
資産運用をするにあたり、単利・複利の考え方が少し難しいなと思っています。学生は特にきちんと理解できている人は少ないと思うので、そこを簡単にご説明いただけたら幸いです。

佐々木-
単利は元本にのみ利息がつく計算方法で、毎年投資している金額に対して利息が付きます。複利では1年目は単利と一緒ですが、2年目からは元本プラス1年目の利息の金額に対して利息が付きます。3年目以降も全体の金額に対して利息が付いていくので、いわゆる雪だるま方式に増えていくと言われます。経年で利息の上がり幅が大きくなっていくのが特徴で、投資に関しては複利の考え方が一般的です。
運用とは逆の話になりますが、例えばクレジットカードやローンは1回で払えば利息は付きませんが、分割で支払う場合は決められた利息が付きます。これも期間が長くたくさん借りるほど、元本よりも多く返済しなければいけませんし、利息をたくさん支払うことになります。これが複利の逆バージョンだと考えていただくと、一番シンプルにわかりやすいかもしれません。
あとは資産形成でよく言われる言葉に「72の法則」があります。これは72を実際に自分が運用するときの利率で割ると、お金が2倍になるための必要な期間が割り出せるシンプルな計算方法です。例えば利率3%で運用していくと資産が倍になるまで約24年かかることになり、だからこそ長い時間をかけてコツコツと増やすというのが長期投資の考え方ですね。
続いて、積立投資の方法で「ドル・コスト平均法」というものがあります。特に学生の間はいきなり100万円とか1,000万円みたいな、まとまったお金を準備することは難しいかと思います。そうすると無条件に一括購入ではなくて、一定金額を定期的に購入する「ドル・コスト平均法」が効果的になります。株価は上がったり下がったりするものですが、「ドル・コスト平均法」では一定の金額で買い続けるため、株価が高い時には買える数は少なく、逆に安い時にはたくさん買えるので平均化されて購入していくことができます。株価は波のように変動するものですので、基本的に「ドル・コスト平均法」で買っていくと、一括購入よりも実は多く買うことができて効果的だと言われています。
また分散投資でよく言われるのが「ひとつのカゴに卵を盛るな」ということです。リスク回避を意味し、株式などを一つの企業にまとめて買っていると、その企業に何かあった場合に株価が大きく下落してしまって、自分の資産が大きく傷んでしまうので、分散して持つことで一つがダメでも他のところが良ければ、トータルでは収支に与える問題は少なくなるという考え方です。これは資産においては、株や投資信託や債券などの資産自体を分散しておくことにも当てはまりますし、地域においては日本だけではなく、海外のドルであったり、ユーロであったりに分散しておくことに当てはまります。また「ドル・コスト平均法」にも近いですけど、まとめて買うと何かあった時にマイナスになってしまう可能性もあるので、買う時期を分散しましょうという意味にもなります。これらのように自分の金融資産をバランスよく、さまざまな形で持つことを「ポートフォリオ」と言います。

浦田-
今のお話を聞く限りだと、単利よりも複利の方がお金が増えるようなイメージですが、逆に複利によるリスクみたいなものはあるのでしょうか。

佐々木-
お金を増やしていく時には、複利にマイナスの要素はないと思ってもらって構いません。逆にお金を借りる時には一般的に複利が適用されるので、放っておくとすごいスピードで利息が増えてしまいます。皆さんがお金を借りるときは、何%の利息で借りるものなのかをきちんと理解しておくことが大事です。少し話がずれますが、学生の皆さんが利用する奨学金は、返済期間が20年などの長いスパンなのに貸付利率は低く、借りた金額とほぼ同程度を返済するように設定されています。返済の義務はありますが、皆さんが学習するためにお金を借りる仕組みとしては、すごくいい制度だといえますね。
投資におけるポートフォリオの組み方

井上-
先ほどポートフォリオという言葉がありましたが、実際にどういう組み合わせにするか、株式や債券等を扱う時に何を見てどう判断したらいいのかがいまひとつよくわかりません。投資信託のように何かしらまとまった形で買うにせよ、自分で組むにせよ、どういうところを見て判断したらいいのか、可能な範囲で教えていただけると助かります。

佐々木-
これはなかなか難しいお話ですが、投資のスタイルには2つあると考えています。いわゆるリスクコントロールという形で、リスクをできるだけ抑えて長い目でお金を増やす長期・積立・分散の運用の仕方というところ。あとは株の短期売買や暗号資産・先物などのように、もしかしたら大きく儲かるかもしれないけど大きく損するかもしれないものに投資するリスクテイク型投資です。
よく言われる「投資」と「投機」の線引きは実はすごく曖昧で、これが「投機」だと明確に言えるものはないのですが、「投機」はどちらかというと、大きく儲かるかもしれないけど、損するかもしれないという意味では、後者に近いですね。
株価や日経指数は、例えば今回の総裁選のように、みんなが上がると思っていればもちろん上がります。それは、みんなが株を欲しいと思う状態だからですよね。逆に社会情勢に不安が多いと感じる時は、株価はそれに引っ張られて下がってしまうこともあります。ですから自分の今の生活だけではなくて、社会や経済の動きを学んでおくと、株価の上がり時なども見えてくるかと思います。ただ細かい銘柄で見る時にはまた別の問題になるので、本格的に取り組むのであれば四季報を読み込んだり、企業の決算発表や記者会見をチェックしたり、アンテナを高くしておくといいと思います。株式投資は今日買ったものが明日上がるかどうかはわかりませんし、1カ月後、1年後に上がるのかもしれないことと、買うときも売るときも手数料がかかり、利益に対して大体20%程度の税金がかかるので、それも含めて収益を出さないと利益がでないこと、それらも理解しておく必要があると思います。
できるだけリスクを抑えた投資を考える場合、税制優遇制度として新NISAなどがあげられます。新NISAは基本的には売買手数料がかからない商品なので、そういう意味では大学生の皆さんが始めやすいのではないでしょうか。手数料も税金もなく、そのまま自分の収益になる特徴が周知されたことでやってみようかなと思う人が増え、それに引っ張られて株価も少し上がったのもあるのかなとは思います。

井上-
新NISAに関してiDeCoもよく耳にしますが、よくわからないけど存在は知っているという学生が多いのかなと思います。両者の違いやどういう人にお勧めなのかお伺いしたいです。

佐々木-
NISAは投資の手法の一つで、少額で運用するものについては税金がかからない、税制軽減制度という仕組みです。iDeCoは個人型確定拠出年金という、自分で決まった金額を積み立てていく個人型の年金制度になります。お金を積み立てて増やしておきたいけど、引き出してしまう心配がある場合はiDeCoを選択される方が多いと思います。積立てるお金についても税制優遇があるので、同じ割合で運用していく場合、将来的にもらえる金額が大きくなりやすいのはiDeCoかとは思いますが、iDeCoは年金なので60歳まで引き出せないという特徴があります。自分の将来設計の中で、例えば結婚式のお金を貯めておきたいとか、子供の教育資金にお金を増やしておきたいとか、そういう場合はNISAの方がいいと思います。投資の制度と年金の制度という両者の違いを理解していただくといいですね。
参加者の感想と講師からのメッセージ

志村-
今まで言葉はよく聞くけど、あまり実態はわからないことがたくさんありましたが、今日の話をお聞きして、これからの自分の将来設計において、怖がりすぎて逃げるわけでもなく、かといってあまり怖がらずに手を出しすぎるわけでもなく、適度に怖がりながら投資を行っていく基礎のところを学べました。改めて本日はありがとうございました。

浦田-
私たちくらいの世代までは、学校で金融教育は受けていても投資の学習はなかったので、なんとなく投資イコール怖いものみたいなイメージを持っていました。確かにリスクはあるというお話でしたが、決して投資が危険なものというわけではなくて、上手に使うことによって自分の資産を増やすことにもつながるし、リスクを踏まえ正しい知識を持って資産運用に臨むといいのかなと感じました。
教育大学出身ということもあり、社会科の教員免許を取得しているのですが、在学中に投資についての模擬授業をしなければいけない時に、全くわからずにすごく調べたことがありました。これは幼少期からあまり触れてこなかったことも一因だと思うので、時代の流れに合わせてしっかりと情報を更新していきたいと思いました。

井上-
他の方の感想でもあったように、知識がないと危なくても気づけなかったり、逆に怖すぎて手を出せなかったり、そういった意味でも知識を持つことは大事だと改めて思いました。
手数料や税制度の話も伺えましたが、知らないと損してしまうこともたくさんあるように感じたので、私自身も実はまだ怖くて手を出せていない側でしたが、社会人になって居住地も変わるので、それを機にぜひやってみようかなと思いました。その時には「J-FLEC」に相談させていただけたらと思っています。

佐々木-
浦田さんが話してくれたように、皆さんはおそらく小・中学生の時に金融経済教育があったかと思いますが、文科省が定める学習指導要領の中に投資の話が入ってきたのは2022年度の高校からになりますので、今の大学生は金融経済教育の中でも特に投資については学んでないかと思います。以前の金融教育では貯金や貯蓄についての勉強が多かったのですが、今は投資も含めた資産形成についての学びが一般的になってきています。日本は貯金という概念が強いので、貯金として眠っているお金が2,000兆円あると言われていますけど、それを投資に回すことで、企業は活力になるお金を得てさまざまなことにチャレンジでき、経済が回っていくことにもなります。皆さんが投資を行うことで企業がより良く成長ができていくと、物価の上昇に合わせて企業が経済成長することで給料が上がるという好循環を生むため、投資が勧められています。ただ、そのために皆さんの貯金を全部投資してくださいということでもないので、企業を見極めて投資することで経済も良くなって自分のお金も増えるといいかな、くらいのスタンスでいいのではないでしょうか。一人ひとりの状況に合わせて何をすべきか違いますし、必ずしも全員が投資することが正しいわけでもない中で、自分はどうしたいのか考えてみてください。
「J-FLECはじめてのマネープラン」無料相談では投資の相談のみを掲げているわけではないので、お金に関する疑問や不安を相談することで解消してもらい、より良い生活を送るために活用していただければと思います。
2025年10月9日 大学生協会館にて開催
-CONTENTS