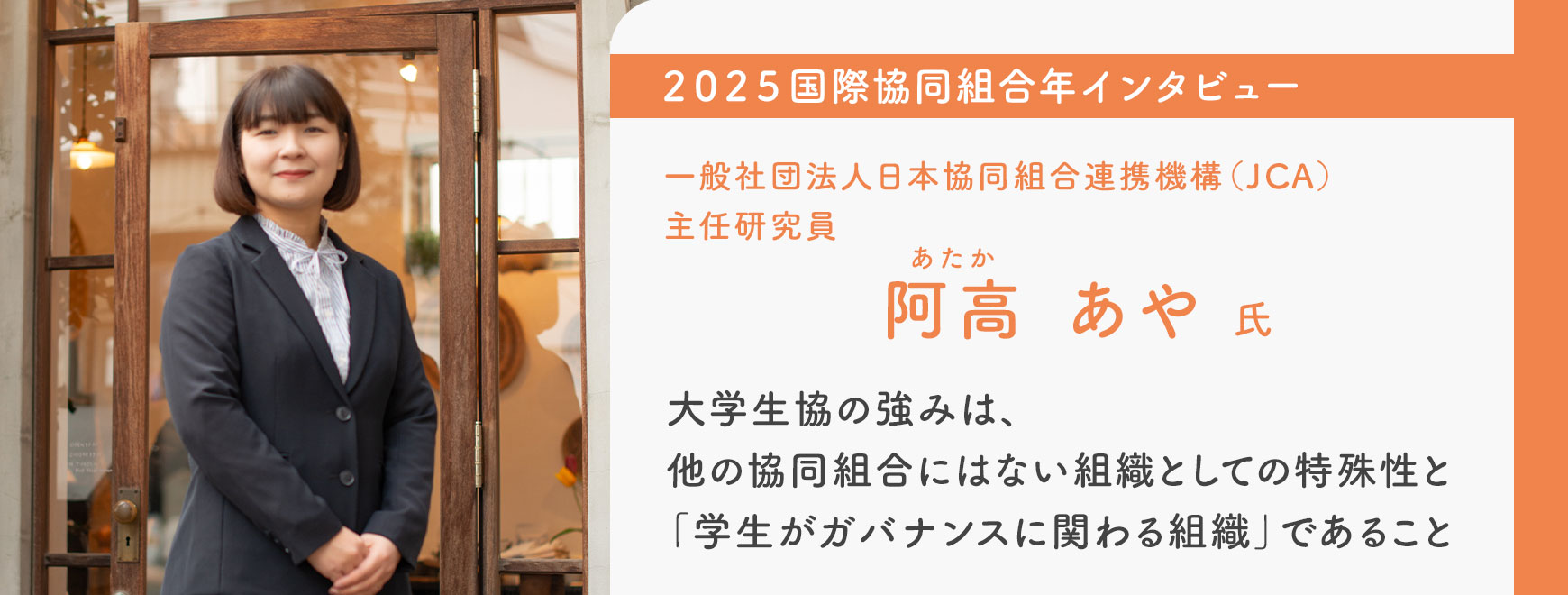2025国際協同組合年インタビュー
一般社団法人日本協同組合連携機構(JCA)主任研究員
阿高 あや 氏
2025年は2012年以来2回目の、国連が定めた国際協同組合年になります。
前回の国際協同組合年の前年にあたる2011年に東日本大震災が起こりました。
当時、福島大学で現代音楽を専攻していた阿高さんが、協同組合の研究へと大きく舵を切ることになったきっかけ、また総代や講師として大学生協に関わっていただく中で感じる課題や、活かすべき特性等についてお話を伺いました。
聞き手

全国大学生協連
全国学生委員会
委員長 高須 啓太

全国大学生協連
全国学生委員会
副委員長 瀬川 大輔
(以下、敬称を省略させていただきます)
はじめに
自己紹介とこのインタビューの趣旨
早速ですが、簡単にインタビューの概要から説明させていただきます。
全国大学生協連は現在約156万人の組合員がいて、 210余りの大学の福利施設を運営している協同組合で、私たちは全国大学生協連の学生常勤という立場で活動しております。
今年が2025年度の国際協同組合年ということもあり、大学生協連のホームページ上に特設ページを開設し、大学生協や協同組合の魅力について、協同組合の研究者の方々にインタビューすることで学びを深めていきたいと考えています。
今回は、共に語れる若年層の協同組合の担い手として、今後の協同組合にどのような社会的価値があるかについて、阿高さんとお話しできたらと思っています。
私は2025年度の全国大学生協連学生委員長を務めております、髙須啓太といいます。昨年の春に岐阜大学を卒業して、既卒の2年目になります。本日はよろしくお願いします。
同じく全国大学生協連で副学生委員長を務めております、瀬川大輔と申します。
北海道にある北星学園大学を、高須と同じく昨年の春に卒業しました。本日はよろしくお願いいたします。
日本協同組合連携機構で、協同組合の研究をするセクションの基礎研究部という、組織で唯一シンクタンクとして残った部署にプロパー研究員として働き、今年で10年目になります、阿高です。よろしくお願いします。
協同組合との出会い
その研究に身を投ずる過程
以前、ワーカーズコープさんのインタビューを受けられた動画がYouTubeにあり、それを拝聴しました。さまざまな経歴をお持ちですが、改めて阿高さんの協同組合との出会いや、関わりについてお話いただければと思います。
15歳くらいから一人暮らしをしていて、働きながら人より3年遅れの21歳で福島大学に入学しました。9歳くらいからずっとオーケストラに入って音楽をやっていた関係もあり、音楽科の作曲研究室で、卒論にあたる卒業制作を終えた矢先に、2011年3月の原発事故が起きて、大学の卒業式が出来なかった世代です。その時点では、全く協同組合とは関係のない世界にいました。
その後、福島大学の体育館や大学生協の食堂などは全部避難所になったので、私たちはそこに演奏に行ったり、大学の中で職員さんやボランティアセンターの学生と一緒に炊き出しをしたり、段ボールやストーブや漫画を運んだりと、線量が高すぎて授業が始められないと言われている建物の中でボランティアを続けるという謎の状況でしたね。大学院に進学したのですが、結局単位のこともあるから短縮してでも授業は再開しなければいけないということで、5月の途中から授業が始まりました。
私は趣味が釣りで、釣り仲間の先生が北海道大学農学部の協同組合講座の出身で、当時経済経営学類の地域経済学の一環で協同組合論、農協論も教えておられた小山良太先生でした。先生は原発事故後に、自治体の首長や生協や農協のリーダーなどの関係者、大学の研究者らで視察団を組み、チェルノブイリ事故後のベラルーシやウクライナの取り組みを学び、戻ってからJA・生協・福島大学を中心に「土壌スクリーニング・プロジェクト」を立ち上げました。1年半ぐらいの間に、延べ300人ほどの全国の購買生協の役職員や組合員の方にご協力をいただきました。私は空いた時間にその方たちと交流する機会を得、作曲研の大学院生であり、音楽で修士副論文を書かなければならない身であるのに、地元の農協や日本中の生協役職による「協同組合論」を耳学問でどんどん吸収するようになりました。
実は、福島には1998年に「大豆の会」という、遺伝子組み換え問題に異を唱えた生協の組合員さんたちの願いを叶えるために、県産大豆を使って生協と農協と農民連という組織とが相乗りで運営している協同組合間協同の事業体みたいなものがあって、それが発展して2008年に私の前職になりますが、地産地消運動促進ふくしま協同組合協議会、略して地産地消ふくしまネットという組織が立ち上がっていて、そこに農協、生協、漁協、森林組合と地元の福島大学の五つが幹事団体となり、県内では業種の垣根を越えてオール協同組合での活動がずっと行われていました。
原発事故のずっと前から地産地消ふくしまネットの皆さんがよく口にされていたのが「絆」という言葉で、原発事故後の復興でも「地元の俺たちがやるしかない」という感じで、淡々と且つ楽しんで取り組む姿勢から、そもそもの働き方、人間としての地元への郷土愛や業務に従事する姿に感銘を受けましたし、理念があり、それが自分の毎日の仕事に反映されていくこと、その接続の良さみたいなものに、「実学とはこういうことか」と身をもって感じました。携わるにつれて、協同組合とは実はとても素晴らしいもので、もっと世界中の人たちに注目してほしいシステムであり、機能美があるものなのではないかと感じるようになり、今は教員免許を取って音楽の先生を目指す時ではない、そんな思いが私の中で沸き起こりました。
結局、大学院を終える頃には協同組合学会の会員となり、大学院を修了した2013年に地元の短大で地域経済を教える先生になり、併せて協同組合論も指導することになりました。ちょうどその年に原発事故後初の2013年日本協同組合学会の福島大会を開催することになって、実行委員として携わることになりました。
もう一つ不思議な縁で言うと、私の出身は、町の一角だけが避難区域に入ってしまった福島県伊達郡川俣町山木屋地区というところで、今はもう統廃合でJAの支店すらなくなってしまいましたが、旧山木屋村農業協同組合を作ったのが私の曽祖父でした。そういう自分に受け継がれるアイデンティティみたいなものもあり、仕事として協同組合研究に身を投じることになったのが、ちょうど12年くらい前、第1回IYC2012の前後ということです。
福島の地には、日本で5番目の早さで消費組合ができています。福島大学は元々師範学校と高商という、2つの学校が合併してできた大学で、高商の先生が賀川豊彦の神の国運動に感銘を受けて始まったのが、福島消費組合、旧コープ福島です。だから福島大学には、大学生と先生で購買生協を作るという流れがそもそもあり、他の国立大学に比して、組合というものへのシンパシーが強い大学に感じました。そういうベースもあるので、社会運動に感度の良い先生たちが伝統的に揃っておられ、先生方が協同組合運動への理解がすごくあった大学であったということも、私が協同組合にたどり着く必然性みたいなものの一つだったと思っています。
私は昨年東北ブロックの担当で、何度か福島大学を訪問しましたが、授業の一環だとか課外活動の中で、さまざまな協同組合的なものを感じました。在籍中に大学生協との関りはございましたか。
それはなかったですが、短大の先生を辞めてJC総研に移るまでの1年間、地産地消ふくしまネットの研究員をしていた時に、福島県生協連に机を構えていたので、会議などで福島大学生協の専務さんとお話をしたことはありました。また、大学生協のキッチンを借りて、地元の農家さんから野菜を集めて調理し、学会のケータリングで出したりもしていたので、そういうご縁はありましたね。
大学生協が抱える課題
他業種協同組合への学び
大学生協は他の協同組合についての学びが足りていないと感じています。どうしたら他業種の協同組合との連携ができるのか、お考えをお聞きしたいです。
例えば、何かイベント等をする場合に、大学生協へ直接リーチすることが難しいということは、一つネックとしてありますよね。また組織内、つまり自大学の中での大学生協の認知とか、普及、理解度を上げるということも、すごく難しい組織だというのを、私自身が現在東京大学で総代をしていますし、福島大学でも学生を経験したからこそ感じることではあります。
打開策としてあげられるのは、むしろ大学が直接いろいろな業種の協同組合と関わっていくことだと思っていて、どちらかというと学生は受け身で単位を取りに来ることになるかもしれないですが、一つは寄附講座の開催だと思います。皆さんの最大の強みは「大学生」であるということ。協同組合の前にトップに持ってこなければいけないのは、やはり「大学の生協」だということだと思うんですね。
例えば、私は法政大学で7年間、協同組合論の授業を持っていましたが、コロナの時に法政大学生協の専務に来てもらって、赤字経営の現状などを話してもらうと、学生は「Amazonで教科書を買っている場合じゃない」、「学食でご飯を食べなきゃ」、となるわけです。それは大学生協にとっても、認知度を上げることになり、なんなら就職にも直結するかもしれない。企業理解、地域理解の点ではいろいろな組織がある中で、非営利組織の中に協同組合という業態があって、理念や歴史を大事にしている「社会的企業だ」と伝えることは、組織論や経営論を学びたい学生にもリーチする部分でもあると思うので、大学であること、そもそも学生がいて授業やインターンができる等、大学生と一緒に組んでできることはたくさんあると思います。まず大学生協から声を上げてもらえれば、事例と事例を結びつけたりでき、お互いの困りごとも解決できるのではないでしょうか。
組合員の帰属意識
各大学それぞれにある大学生協の学生委員会では、組合員のさまざまな要望を形にして企画立案を行い、組合員に参加を促していますが、企画参加という側面が強くて、運営参画や組織参加にはつながりにくいという課題を抱えています。
もっと主体的に組合員の一人として関わってもらう、協同組合という組織として選ばれるために、どのようなことをすべきだと思われますか。
まさに私の2回目の修士論文のテーマが「組合員ロイヤリティ」についてで、何をもって組合員は帰属意識を高めたりするのかについて研究を進めています。一つ確かなことは、世界中の協同組合が、いま皆さんと同じ課題を抱えているということです。
そこには規模という問題もあります。大学生協は一番ミニマムでわかりやすいですが、例えば日本の農協や漁協は県域まで拡大していい、一県一JA、一県一漁協とできるし、生協は皆さんご存知の通り、県域を跨ぐことが法律で許されています。こうなると、自分が協同組合の組合員であるという実感を加入後に持つことは、なかなか難しいことになります。
大学生協のもう一つの特殊性で言ったら、組合員が4年でサイクルしていく、こんな協同組合は大学生協の他にはないし、この新陳代謝の良さというのは、上手く使えばすごいエンゲージメントとかロイヤリティを高めることになり得ます。皆さんにエンパワーしたいのは、実は組織として営利組織でも非営利組織でもなかなかない特殊性を持っていること、そこは非常に有利に使える武器だということです。
ただ、あらゆる協同組合と同じく起こしがちな過ちとして、加入時の説明不足があります。
ここでパソコン買うのかな、車の免許取るのかな、賃貸とかも斡旋してもらえるのかな、と思うけれど、多くの組合員が他の営利企業の商品やサービスと何が違うのか理解できずに加入していることは、唯一で最初の機会を逸しているといえるでしょう。入学の手続きなどは保護者が行う学生が多いかもしれませんが、SNS上のあらゆるところに自己実現のためのアドバイスをもらえるツールがある中で、“大学生協に頼る必然性”が今の学生にはないわけですよね。それを考えると、一番緊張感を持ってわくわくしている時期に、どれくらい新入生に大学生協の特殊性を伝えられるかということが大切で、もうむしろそこしかないのではないでしょうか。
東京農業大学でも協同組合の授業をやってきましたが、最初に生協の組合員かどうか手を挙げさせています。組合員であるのはどういうことかという禅問答から始めて、ネタ明かし後に改めて大学生協の組合員かどうかを聞くと、最初に挙手しなかった学生が手を挙げます。つまり自分が大学生協の組合員なのか、分かってないんですよね。これは企業努力の点では、一番アウトというか、言葉を選ばずに言うと騙して契約していることに近い状態ともいえます。
あらゆる協同組合でも同じことが言えて、医療生協も組合員でなくても受診はできるし、農協だって口座を持ち直売所も利用できる。協同組合加入後にこういうメリットがあるという説明を全部の協同組合が疎かにしているから、世界でも類を見ない国内の協同組合の総組合員数1億500万人にして、ここまでの協同組合離れみたいなことが日本で起きてるのではないかと思っています。
協同組合教育の必要性
広報調査部:他の協同組合でも同じことが起こっているのかもしれないですが、組合員から選ばれた理事は、経営担当者である専務理事に対して、結局委任せざるを得ない構造があるのではないでしょうか。たとえば、大学生協の理事会でいうと、専務の経営方針や経営判断を聞いているだけ、確認するだけになりがちだと思います。それはよくないことだと思いますが、しかし、出資者代表の立場といっても、学生理事はうまく経営について語れないわけです。経営については、専務理事が情報やパワーを持っていて、この差をどう考えるのか。もっと大きなことで言うと、事業連合などの連帯組織が大きな力を持っていて、会員生協が自らできることは結構少ないです。会員生協が大部分のことを事業連合に業務委託せざるを得ないような現実もあるわけです。この問題についてどのようなお考えをお持ちですか。
大前提として、みんなが協同組合と思っていないというところが、まず一番手前にありますよね。職員研修だろうが非常勤理事研修だろうが大学の授業だろうが、必ず最初に話すことはロッチデール公正先駆者組合のことで、始まりは街で石灰入りのパンとか、アヘン入りのビールとか、砂が入った砂糖とかを売りつけられるのが嫌で、自分たちが工場労働をしながら、副業で棚に5品目、小麦粉、砂糖、オートミール、バターとロウソクのみを並べた店舗を構えたこと。その時の営業時間は平日の夜と土曜日のみで、月曜日から金曜日までの日中は工場労働をしていました。この時点では従業員という概念はありません。公正先駆者組合の原則の変更がデイリーニューズに載るほど繁盛するようになると、平日のデイタイムも開店するようになり、従業員が誕生したわけです。余談ですが、協同組合で私が最大の魅力を感じているのは、ビジネスを拡大させていいところで、そこは事業体としてすごく共鳴する点です。綺麗事ばかりの非営利組織もたくさんある中で、儲けることは地域を良くすることだという考えは、理にかなっていることですよね。で、従業員の中には例えばまた混ぜ物をする人が出てくるかもしれない、だから協同組合の職員に絶対にすべきことは、組合員もですがICA第5原則の『教育、訓練および広報』です。教育の原則は1857年にロッチデール原則に追加されて以降、現在及び広報の原則に至るまで一度も外れていません。
職員教育をきちんとしなければ、組合員教育を誰が担うのかという話で、組合員を総代に育て、委員に育て、理事に育てるというのは、専従の職員がリードすべきことなのに、総じて協同組合理解がある人が非常勤理事になっていることは乏しく、いま日本中で組合員教育を真剣に考えなければいけない状況にあります。
それは多分、大学生協の学生委員でもそうですけど、今後違う仕事に就くにしても、世の中にはいろいろな法人形態があって、自分の実現したいことを地域の他の人の困りごとの解決と一致させることを感覚として知っていることは非常に大事なことで、協同組合論を知って損になる人はこの世にいないとまで思っています。それが体の中で実学として仕事に還元できている人にたまに遭遇すると、私はすごく震えるというか感動を覚えますね。
大学生協の強みを活かす
設立して間もないと生協への理解があるところも多いですけど、組合員自身が生協を求めて利用していないと、他の業者でもいいということになるのかなと思います。入学時期に伝えたいことが多すぎて、協同組合がどういうものなのか、きちんと伝えきれていないのかもしれません。
4年で入れ替わるとか協同組合の特殊性とかを排しても、一番わかりやすいのが「若いあなたたち学生がガバナンスに関わる組織だ」ということです。裏を返せば、自分たち組合員である学生が食事も書籍も他の一般業者を使うとなれば、大学生協をたちまち解散させることだってできます。でもまだどんな関係であろうとも、その存在に自分たち学生が関わり続けているということは紛れもない事実で、自分たちが委員や理事になるということが起こり得る。どんなに小さい生協であっても、それなりの予算を持っている事業体です。そこにある意味、何年間かインターンし続けられるみたいなことじゃないですか。社会的企業である協同組合の非営利性を伴いながら、ビジネスを拡大させたり、赤字を改善したり、広報やマーケティングの勉強にもなるようなことに、自分たちが最長4年関われるということ。もちろん今お二人はさらに一歩進んで、全国域のところで大学の垣根を越えて大学生協をどうにかしなければならないという課題意識を持って携わっている、こんな機会ないですよね。だから自分の実利にもなり得るということを伝えていかなければいけないし、これはすごい強みであり、その強みはあなたたち学生自身だということを本来もっと言うべきだと思います。
コロナ禍の2020年に入学した当初、食堂が全く営業できておらず、岐阜大学生協の赤字をどう解消していくかという時に、専務に学生と専務でプロジェクトを立ち上げようと言われて、経営のことは何もわからない状態でしたが、そこに学生として関わることができた経験がすごく貴重でした。
やはり協同組合が窮地に立ったときに、組合員が誰も応援してくれないのは最大の問題だと思うし、もう少しみんな自分ごととして騒いでくれても良かったはずで、そういう意味では広く活躍していくステップに大学生協をどうですかという進め方は、一つ広報のあり方としてはいいのではないでしょうか。一般広報、つまり、ベタですが SNS のような不特定多数の人にローンチしたり、YouTubeとかリールとか何でもいいですけど、もう少し訴求力が高いことをやっていくといいのかなと思います。
大学生協が取り組むべきこと
認知度を上げるために
私は北海道出身で、実家は生協の宅配サービスを利用していましたし、幼少期からサッカーを続ける中でコープ共済にもお世話になっていました。コープ共済はママ友の間で、少ない掛け金で手厚い保障が受けられると話題だったそうで、口コミからコープさっぽろや、コープ共済の加入につながることが多かったようです。
大学生協はそういうことがないと感じていて、地域の中で協同組合としての認知度を上げるためには、どのような活動が必要だと思われますか。
おそらく日本で唯一、協同組合学研究室が残っている大学は、北海道大学です。北海道大学の協同組合研究室では、事業論を大切にする歴史があり、実践的な北海道の人たちの暮らしを守るための協同組合であるというベースがあります。地理的な条件もあり、基本的に北海道の人たちにとって、たとえ理念教育がなくても事業理解があると、協同組合というものは身近に感じられるのだと思います。それを踏まえると、大学生協というのは、組織理解も事業理解もどちらも難しいというか、その妨げとなっているのは例えば組合員証を出さなくても食事ができることですよね。
そして共済に関しては、やはり最大の売りは一律掛け金、一律保障ですよね。面倒なことが少ない代わりに、自分の出した掛け金が共済を通して他者に使われることを是とする人しか入れないということ。これは加入時にきちんと伝えるべきことで、営利の保険会社と同じ土俵で戦うべきではないです。逆に今の時代、少し高額でも非営利性に「いいね」してくれる人もたくさんいるわけですから、SDGsやESD、倫理的(エシカル)消費者みたいなことに興味のある人たちを逃してしまっているかもしれません。
改めて言いたいのは、大学生協の皆さんが抱えている課題のほとんどが、世界共通だということです。物を購入する手段が限りなくある中で、自分たちが何を大事にして運営しているかを伝えなかったら、選ばれる必然性などあるわけがないです。自分たちの強みが何なのか、一度棚卸をして、いま自分たちが使うべき広報のやり方を整理することが、どこの協同組合にもきっと必要です。
大学生協で言うなら、やはり親にパンフレットが届き説明をするだけでなく、組合員である学生自身に語りかけるシーンがそもそもあっただろうかというところです。組合員としてオルグできないことは、普通の民間企業で考えると困った状況です。組合員加入というところが突破できているのに、よくわからないまま4年間過ごしてしまうことは、非常にもったいないと感じました。
協同組合間のつながりを広げ、組織の防災機能の強化へ
大学生協では、福島の今とその想いについて学ぶ「ふくしま」スタディツアーというものを毎年実施しています。東日本大震災と原子力災害による風評被害という、複合災害を経験している世界で唯一の事例ということもあり、福島にしっかりと焦点を当て取り組んでいます。
昨年の能登半島地震でも、大学生協として災害本部を設置したり、日生協と連携しながらボランティア支援に取り組んだりしました。災害時に協同組合として、大学生協として取り組むべきことや、若い学生たちが集う大学生協に対して、期待されることなどはございますか。
これは私の修士論文のテーマに関わることで、非常に難しい質問だと感じています。
生協も農協も単協でオリジナリティを出すことや地域社会への貢献が非常に難しくなってきている中で、有事も平時もオリジナリティを持ち、きちんと思考を続けて組合員への対応ができるところは少ないと思いますが、例えばコロナ禍で福島大学はすぐに農協にお米の提供を要請し、大学の教授たちが袋分けをして寮の学生に配ったり、その動きは茨城大学にも広まったりしました。これは起こりうる自然災害、原子力災害、疾病の蔓延などの不安定な社会に対して、協同組合は絶対的に力を発揮できることに他なりませんし、困っていないところにはむしろ協同組合は必要ないのではないかとも言えます。困りごとの解決のためにあるのが協同組合であり、昔に比べると激甚災害のない地域は今はないわけで、大学生協として有事の際を想定をして平時から動いておくなど、取り組めることがあると思います。
大学というところのみで小さくても協同組合を作れている、規模のコンパクトさ、シンプルさ、集まっている理由がこんなにも強みにできるのは、大学生協以外今はもうないでしょう。とにかく1日1回、みんながそれぞれの住まいから一つの大学に集まってくるという人たちの協同組合です。そこで有事の際に、他の大学生協の人たちとどう結びついて、どんな支援ができるのか、もしくは異業種理解をしながら、自分の地域の他の業種の協同組合の人たちに寄附講座をしてもらうなどの関りを持ち知恵をお借りする。ネットワーキング以上の防災はないと思うので、全国大学生協連という組織がそもそも防災機能みたいなものにもなり得ると思います。お二人の立場だったら、この協同組合のネットワーキングという編み目を細かく広くしていこうと、そういう知見で動かれるといいのではないでしょうか。
みんなの「Better」がつながっていくこと
最後の質問として、 IYC のテーマである「Cooperatives Build a Better World」について、大学生協連としては今年度、全国の組合員と一緒に「Better World」について考えていきたいと思っています。阿高さんの考える「Better World」について、お伺いしたいです。
やはりベースにあるのは、そもそも人間は誰しも何かしらの困りごとを抱えているものであるということ。困っているけど「助けて」と言えない状態は良くないですよね。協同組合の運動癖みたいなものがついてくると、割と日常から「助けて」と言えるようになってくると思うので、それが言えるということがまずBetterであり、みんながBetterになっていくこと、それがつながっていくことが「Better World」に近い状態ではないでしょうか。
例えば、私は今3人の子供を育てていて、夫は海外で協同組合のない場所に協同組合を作る国際協力の仕事をしています。なので、暮らしの中での困りごとは、生協か農協かワーカーズコープ、医療生協でほとんど解決してもらっています。夫の途上国での話を聞くと、協同組合の一番のダイナミズムは誕生する瞬間にあるなと強く思いますが、まず個人レベルで困っていることが言えて、同じ困りごとを持つ人たちが寄り合う、その協同組合のアイデンティティは世の中を良くするために出来たものだから、協同組合があるのに「Better World」になっていないということ自体が、そもそもあってはならないことだ、くらいに私は思って暮らしていますね。
大学生協連も、豊橋創造大学生協(※1)が1年前に設立されましたが、生協ができたことで生活が良くなったという話もお聞きしました。困っていることに声をあげることで、協同組合でそれを解決しその輪が広がり、ひいては世界全体に良くなっていくということですね。
(※1)豊橋創造大学生協 朝元理事長のインタビューはこちらから
やはり世代交代が速い大学生協こそ、理念の継承がすごく大事になってくると思います。設立の瞬間に良さを実感していた人たちは、理念を教えられなくても身をもって体感できますが、年月が経つにつれて営利のサービスがたくさん競合する中で、組合員にきちんと説明することなく加入だけをさせるのは非常にもったいない話で、できれば加入の段階で理念や設立の経緯を、学生たちが頑張ってまだ関わっているのだということも含めて、自分たちらしい言葉で伝える1分程度の動画みたいなもの等、それぞれに作ってみてはいかがですか。
繰り返しますが、経営や運営が傾きそうになった時に、学生の側から要求や請求、説明を求める権利がある組織というのは、大学生協が持つ特殊性です。これはとてもすばらしい機能で、協同組合ライクな社会的企業の認知が高まりつつある今、すごく追い風だと思っているので、そういう意味では、大学生協はすごく現代的な組織運営を先取りしていたとも言えますから、そこを強みとして前面に押し出していけるのではないかと思います。
組織の中にありながら、自分たちが気づいていないことがたくさんありました。
ぜひ多くの生協関係者、学生委員、組合員にこのインタビューを読んでもらいたいと思っています。本日はありがとうございました。
2025年2月21日リモートインタビューにて
プロフィール

一般社団法人日本協同組合連携機構(JCA)主任研究員
阿高 あや 氏
- 2013年
- 福島大学大学院人間発達文化研究科修了 修士(地域文化)
桜の聖母短期大学キャリア教養学科 助教
- 2014年
- 地産地消運動促進ふくしま協同組合協議会 特任研究員
- 2015年
- JC総研 副主任研究員を経て現職
- 2025年
- 東京大学大学院学際情報学府社会情報学コース修了 修士(社会情報学)
<兼務等>
- 2014年〜2025年
- 東京大学農学部 非常勤講師
- 2016年〜2022年
- 法政大学現代福祉学部 兼任講師
- 2022年〜2025年
- 東京農業大学 非常勤講師
- 2025年〜
- 立教大学コミュニティ福祉学部 兼任講師
東京大学大学院情報学環客員研究員
【おもな研究・関心・専門分野】
- ・協同組合間協同
- ・協同組合における理念教育
- ・災害復興と協同組合
- ・社会的連帯経済ほか
【所属学会】
- ・日本協同組合学会
- ・東北農業経済学会
- ・日本災害情報学会