わが大学の先生と語る
「『他者』として沖縄の声を聴く」岸 政彦(京都大学教授)
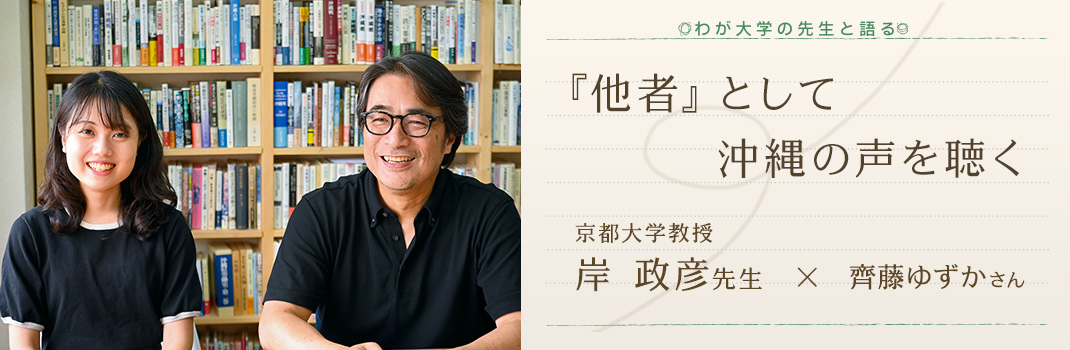
▼ Profile
.jpg)
■略歴
1967年生まれ。
社会学者・作家。京都大学大学院文学研究科教授。
専門は沖縄、生活史、社会調査方法論。
著書に『同化と他者化』(ナカニシヤ出版 2013)、『街の人生』(勁草書房 2014)、『断片的なものの社会学』(朝日出版社 2015/紀伊國屋じんぶん大賞 2016受賞)、『ビニール傘』(新潮社 2017)、『マンゴーと手榴弾―― 生活史の理論』(勁草書房 2018)、『図書室』(新潮社 2019)、『リリアン』(新潮社 2021/第38回織田作之助賞)、『にがにが日記』(新潮社 2023)など。共著に『質的社会調査の方法』(有斐閣 2016)、『地元を生きる』(ナカニシヤ出版 2020)、『大阪』(河出書房新社 2021)。編著に『東京の生活史』(筑摩書房 2021/紀伊國屋じんぶん大賞 2022、第76回毎日出版文化賞受賞)、『生活史論集』(ナカニシヤ出版 2022)。監修に、沖縄タイムス社編『沖縄の生活史』(みすず書房 2023)などがある。
 齊藤ゆずか
齊藤ゆずか
(大学院文学研究科修士1年生)
1.社会学との出会い
齊藤
社会学に関心をもった理由を教えてください。

岸
昭和の頃の家って、百科事典とか全集がなぜか揃っていたんですね。僕は幼稚園にも行かず本をずっと読んでいる子どもだったんだけど、社会問題の本を中学生くらいから読むようになった。貧困とか差別とか。特に管理教育の本に衝撃を受けて。当時は教師が生徒を殴るのが当たり前だった。それが身近な人間関係の問題じゃなくて、制度とか構造レベルで間違っている、という考え方に触れた。本来社会学と社会問題は違うものだけど、社会学的なものに関心が傾いていきました。
スタッズ・ターケル(※)って知ってる?聞き書きをただ並べるだけの本を作った人。あと、「ポンプ」(『おしゃべりマガジン ポンプ!』)っていう、全部読者投稿欄だけでできた雑誌がありました。人々の声がざわざわーっと集まっているのが、リアルだし美しい。もともと、人々の声がただ並んでいるような、ざわざわとしたものに反応する子どもだった。海の水面とか葉っぱとかが揺れているのに反応するんだよね。自分でも、こんなふうに「声をあつめること」をやりたいなって思っていたけど、人見知りが激しくて。そこらへんの人をつかまえて話を聞くのは無理だった。フリーのジャーナリストになって人の話を聞くのはできないと思ったから、中学・高校の早いうちに「社会学者になろう」と決めてた。
社会学者になるうえでは、音楽を諦めたのがいちばん大きかったかもしれない。大学生のときは梅田やミナミの繁華街で生演奏をして稼いでいて、ジャズミュージシャンになろうかなと思っていたけど、才能がないので諦めたんです。そこから大学院を受けるんだけど4年も浪人して、日雇いで建築現場で働いた。高校のころから哲学の本を読んでいたけど、ピエール・ブルデューにはまって、社会学理論そのものも好きになったなあ。
(※)スタッズ・ターケル:アメリカの作家。オーラルヒストリーの聞き書きを行い、ピュリツァー賞を受賞している。
齊藤
なぜ社会学理論から社会調査に研究の軸足を移されたのですか。
岸
修士論文は理論だけで書いたんですけどね。大学1回生のある日、大学に向かう阪急電車の千里線の電車が満員電車で、こんなのに乗って授業に行くのが嫌やなって思って、降りなかった(笑)。関大前の駅を過ぎたら急にがらっと空いて、なんとなく山田という駅で降りたんです。するとそこに万博記念公園があって、その中にある民族学博物館にはまって、人類学に興味をもつようになった。
それと大学を卒業してすぐに、たまたま観光で沖縄に行って、はまった。博士課程に入ってから沖縄のことをやろうと。ブルデューに憧れていたのも大きい。理論も調査もやるのがかっこいいなと思っていた。
最初は沖縄に通うお金がなかった。大阪には大正区を中心に沖縄からの移民が多かったので、そこで調査していた。あと、博士課程から通っていた大阪市立大学(現・大阪公立大学)は代々フィールドワーカーを養成していて、尊敬するフィールドワーカーが多い。今の連れ合い(社会学者・齋藤直子先生)ともそこで出会った。彼女は被差別部落で調査をしている。
ただ、最初に理論をやっていてよかったなとは思いますけどね。
2.「沖縄」という他者

齊藤
講義ではたびたび、沖縄に対する感情が難しいという話をされていました。
岸
直接言われたことはまったくないんだけど、「ナイチャー(沖縄の人が本土の日本人を指してこう呼ぶことがある)に何がわかるんだ」という問いは、常に突きつけられていると感じています。社会学の勉強を本格的に始めた1990年代は、当事者性とかポストコロニアル批判、実証主義批判の議論が出ていた。スチュアート・ホール、フランツ・ファノン、エドワード・サイードなんかをよく読んでいました。そのなかで、「沖縄に向き合う」とはどういうことか、と深く考えたんです。
もともと基地問題や平和運動にはあまりつながりがないんです。それより僕は沖縄の「普通の人」の話が聞きたかった。お酒を飲んで自然に友達になって。でも、そういう友達でも、日常的な会話のなかですごい壁を感じることがある。当たり前なんだけど。
最近の話だけど、琉球新報でエッセイの連載をしていて、感想を送ってくれた方がいた。「岸先生は名誉ウチナーンチュですね」って。ほんとのウチナーンチュのひとには「名誉」はつけないでしょ。心から褒めてくださっているんだけど、「ナイチャー」は「ナイチャー」なんだなと。そういう感覚について、ちゃんと理解したいと思っています。
歴史や政治構造を学ぶと、日本が沖縄をずっと踏みつけにして、アメリカに媚びて沖縄を売ってきたとわかる。自分が直接の加害者の一員だということは、沖縄の研究をしていると日々突き付けられるわけで。沖縄の人にインタビューして本を書くのも、ほんとのところはどうなんだろう、とは思いますね。最初の本(『同化と他者化:戦後沖縄の本土就職者たち』(ナカニシヤ出版))は、出すまでに10年かかった。
僕はずっと社会学は実証的であるべきで、思想になってはいけないと思っている。そういう意味で、「ポストコロニアル」とか「当事者性」の議論には最初から違和感があった。そういうこと言っているやつらはまともな調査をしていない(笑)。でも、同時に、沖縄で日々感じている非対称性も書かなきゃいけない。オーソドックスな社会学で実証的にやると同時に、メタレベルで政治的な非対称性の問題もちゃんと書かないと。単にインタビューやアンケートをしてこういう結果が出ました、ということにはできない。いろいろな課題をクリアするのにずっと苦労しているんです。単に立場性とか当事者性に悩んでいることを書くだけじゃなくて、社会学者として実証的な調査をしなければならない。
3.沖縄について書くということ
齊藤
それでも本を書き進められたことには、何かきっかけがあるのでしょうか。
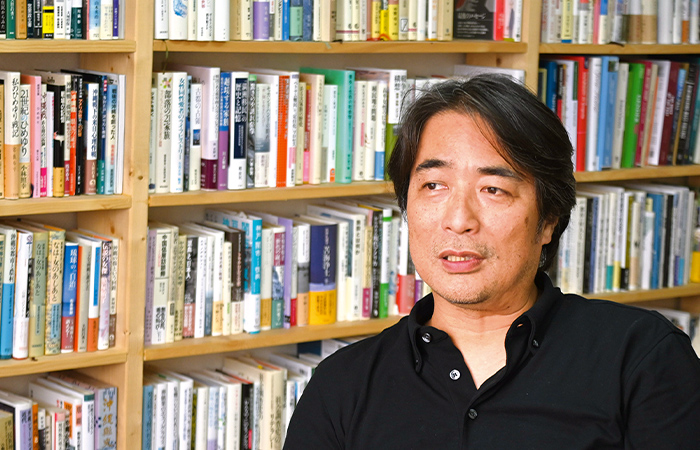
岸
『同化と他者化』の最初と最後に出てくる、大城勲さんをはじめとして、たくさんの語り手の方がたと出会ったことが大きいですね。それから、上間陽子さんや打越正行さん、あるいは連れ合いの齋藤直子のような研究仲間からも、たくさん力づけられています。もう20年以上前ですが、「都市下層問題研究会」というのをやっていて、そこでの議論とか、研究仲間から教わったのも大きいかな。いろんな人に助けてもらいました。
最初の本をまとめるうえでいちばん大きかったのは、語り手の女性から手紙をもらったことですね。博士論文を送ったら「本になるのを楽しみにしています」と書かれていて、本にしなきゃなと。調査って、データを集めるとそれが借金になる。負債みたいな感じ。(集めたからには)「ああやんなきゃ」という感じです。沖縄の人のことで「ナイチャー」が本を書いていいのかなって悩んだけど、沖縄の人から「早く書いて」と手紙をもらったのは大きかった。
その次の大きなプロジェクトとして『地元を生きる―― 沖縄的共同性の社会学』(ナカニシヤ出版)という本を書いたんだけど―― これは4人で書いたんですが―― 僕が出版を4年止めたんだよね。沖縄のなかに階層格差があることを「ナイチャー」が書いていいのかなと思って。これは、沖縄の中でも公務員とか教員は安定しているという、当たり前なんだけど誰も書いてこなかったことを書いた本なんですが。
だから僕はあんまり前に出ちゃいけないと思って、沖縄の人たちに語ってもらう『沖縄の生活史』を作ったときは、単独の編者にはしなかったんです。沖縄タイムス社編として、尊敬する社会学者である沖縄の石原昌家先生と共同で監修という形にしました。
10年で本を20冊以上出していて、「強気で書いている」みたいに思われるのだけど、沖縄の本に関しては出す前にうじうじして、「やっぱりやめよう」とか言って編集者から叱られたことも何度もあります。SNSで沖縄のことを書くのも怖い。沖縄のことで何か言うのはかなり覚悟がいることなのです。
いかに沖縄を語ることが難しいか。たとえば基地を容認する沖縄の人も多いわけです。だから、そこにちゃんと向き合わない内地の人たちにも違和感がある。「沖縄を踏みにじるな」ってそれはそうなんだけど、沖縄には基地容認派もたくさんいるし、保守派の知事もたくさん出ている。必ずしも辺野古のことだけが争点じゃない。そのへんの複雑さをすっとばして、とにかく基地反対だって訴えることで沖縄の声を代弁したつもりになるような議論にも昔から違和感があります。大事なことは、そういう沖縄の多様な声を拾い集めながら、その上で基地に反対するロジックを作っていくことだと思います。単純なことはほんとに言えない。
けど、もう、やりだした以上は、僕はライフワークとして一生関わりたいと思っています。
齊藤
私の関心は台湾やパレスチナにあるのですが、相手が共感も想像もしえない状況にいて、当事者になりきれない中で当事者の話を聞いているということがあります。「沖縄戦の本を書くのを最後の仕事にしたい」とおっしゃっていた岸先生は、当事者ではない立場の人が、当事者の声をどう書き残していくべきだと思われますか。
岸
とにかく私は社会学者なので、社会学の本を書かないといけないということには潔癖なんです。単に沖縄戦はひどかった、悲惨な思いをした、では社会学にならない。沖縄の社会を実証的に分析しないといけないのです。それと同時に政治的な立場性も組み込んでいかないといけないので、難しい作業にはなる。
当事者性だけを考えて何とかなる時代ではないだろうと思う。当事者になれないのは当然なので、社会学者なり歴史学者としてまっとうな仕事をするにはどうしたらいいかを考えるべき。研究者にはまずデータを残す使命がある。地べたをはいずりまわって人の話をきいて、公文書館にこもったりしてまとめていく。そのほうが長い目で見て役に立つと思う。「あなたの研究で基地が減るんですか」と言われたらなんも言えない。けど、『同化と他者化』はデータを集めたところがすごく評価されている。まずはデータを集めるということがいちばん大事なんだと思う。
若い大学院生でも当事者性について悩んでいるひとが多くて。当事者じゃないと語っちゃいけないと思っているから自分の中に当事者性を探そうとするんだけど、それよりもまずは他者のところへ行って話を聞くほうがいい。そこで苦労してデータを集めて後世に残す仕事をしたほうがいいんちゃう、と思う。「当事者しか語ったらあかん」みたいなことを突き詰めるとオートエスノグラフィーしかできなくなっちゃうけど、もし研究者になるなら、自分の中の物語ばかり書いてもよくない。
沖縄戦でもそうなんだけど、最近は余計「残さなきゃ」という気持ちが強くなっていて。『沖縄の生活史』も、100人が個人で自分史を書いて本にするのは難しいから、それはノウハウや資源をもっているこちらがやらせてもらうという感じで。聞き手も語り手も沖縄の人たちです。この本がなかったら残っていない語りがある。「復帰の日に何をしていましたか?」って聞いても、ほとんどの人は「覚えていない」って。仕事とかをしていてね。そういうリアルな感覚を、これまで誰が記録してきただろうって思います。
社会学者として地道にやってきたことで、語りを集めるお手伝いをさせてもらうことはできるようになった。これが沖縄の役に立つとか豪語するつもりはないけど、良い本を作ったなと思います。
4.『沖縄の生活史』の美しさ
齊藤
3冊の『生活史』の目次を見て驚きました。普通は語り手の年齢や属性を書くと思うんですけど、発言が引用されているだけ。
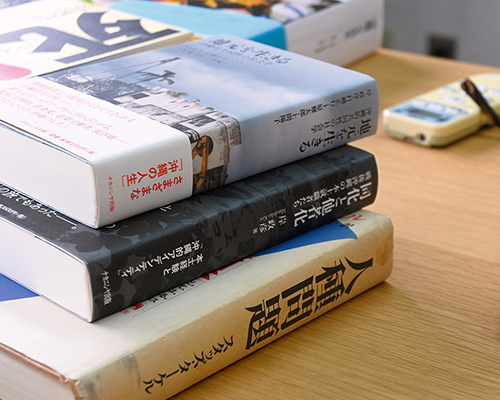
岸
まとめたくないんですよね。そのまま残したい。この本には、「社会学者として本を書かなきゃいけない」という使命と、「語り手の声をそのまま残したい」という思いが同居している。だって、「50代・ゲイ・自営業」っていう人はいないからね。例えば『東京の生活史』のなかに入っているある語り手は、50代でゲイだけど、奥さんが家族を連れて出ていってしまい、一人で家に住んでいる。それが人生でいちばんショックだったという、そんな人に「50代・ゲイ・自営業」というラベルを貼ることはできない。
最初は編集や営業の人と喧嘩しましたけどね、彼らはわかりやすくしたいから。でも「要らん」って。安易な、凡庸で陳腐なまとめ方が嫌いで。「20代女性」っていう人はこの世界にひとりもいないんだから。だれひとりとしてそんなふうに要約できない。
それに、たぶんそういうところを削った方が読まれるとも思った。『同化と他者化』でもいちばん面白いと言われたのが(生活史の語りを書いた)真ん中の150ページ。「自分の親父と同じだ」って泣きながら読んだ在日コリアンの友達もいて。みんな自分のこととして読んでくれた。だから2作目の『街の人生』(勁草書房)はいきなりこのスタイルになって。このスタイルが面白いという確信がありました。
齊藤
講義で「『沖縄の生活史』は美しい本だと思う」とおっしゃっていましたね。
岸
読んでいくと一緒に体験できます。80年の人生を理解するには80年かかるわけだよね。だからこの1万字も一部でしかないんだけど、僕らは普通、1万字も他人の人生を読まない。だけど世界はもっと膨大。1万字切り取っただけでもいろんな人生があるのに、この本には100人しかいない。沖縄には140万人が暮らしています。その頭の上にオスプレイを飛ばしているんだということを想像してほしい。それを促せるのが「美しい本」ということだと思う。『東京の生活史』は、『大阪の生活史』『沖縄の生活史』を「大阪や沖縄の本」ではなく、「生活史の本」として受け入れてもらうために先につくったんだけど、『大阪の~』と『沖縄の~』はほんとにいい本をつくったなと思っていて。初めて自分の目標がなくなりました(笑)。もう普通のひとの10倍くらい仕事したからね……。
生きてきた街・大阪
齊藤
作家・柴崎友香さんとの共著『大阪』(河出書房新社)を読みました。大阪出身で大阪を出て行った柴崎さんと、大阪にやってきた岸先生のエッセイ。岸先生にとって大阪とはどのような街ですか。
岸
僕は大学があるからではなくて、明確に「大阪の街で暮らしたい」と思ったんです。受験で大阪に初めて来たときに、面白いことがたくさんあった。人がよく話しかけてくるし、小学生が電車の中でぼけたりツッコんだりしているし。濃い街に来たなあと思って、面白かった。好きやなあ、と思う。大阪の、世界からほっとかれてる、中央の目が届いてない感じが面白い。政治も経済もしょうもないけどね。一人暮らしを始めたのが上新庄でした。日当たりのいい家で、カーテンがなくてすぐ目が覚めちゃうんだけど、窓をがばっと開けて、「今日何しようかな」って、自由で孤独で、「ひとりで生きるんだよ」という感じ。スティーブン・キングや『指輪物語』にはまって、家から一歩も出ずに本を読む、ということをずっと下宿でやったんだよね。
淀川の河川敷とも出会った。僕の小説には必ず淀川の河川敷が出てくるのだけど(笑)。あと音楽をやっていたからね。梅田とかミナミとかの繁華街でいろんな人の人生を見て、いろんなことを学んだ。自分で稼いで、友達をつくって、彼女をつくって、っていうのが楽しかった。大阪のおかげで生きてこれたなという感じ。この街で生きてきた、暮らしてきたってことやんな。
齊藤
私も京都に来て最初はさみしかったんですけど、最近は家族から「帰省しなさい」と言われます(笑)。
岸
学生さんはだんだん帰らなくなるよね(笑)。僕は地元とは切れているんだけど、沖縄でもそういう、ひとりで出稼ぎに行ったり、地元と縁が切れていたりする人から話を聞くことが多くて、自分を投影しているのかもしれない。
齊藤
ふるさとってなんだろう、と思うことがあります。地元のほうが実家という生活基盤があるし、気候的にも物価的にも、いま暮らしている京都より住みやすいのは確かなんですけど、京都や関西が好きすぎて、「京都に帰りたい」って思ってしまうことがあります。
岸
地元でずっと暮らしている人もいるから「そういう人ってどういう気持ちなんだろう」と思いますね。僕は大阪に来てから、ずっと大阪で生きてきた。京都や滋賀の大学に務めていても遠距離通勤してね。でもやっぱり大阪人にはなれないわけ。アウェー感は消えないですね。僕の大阪弁ってネイティブじゃなくて、大阪人にはばれますからね(笑)。でもアウェー感をもったまま生活するのはできる。アウェー感を持ちながら好きな街に暮らすっていうのはありだと思う。
小説を書く
齊藤
小説も書かれていますよね。
岸
編集者に口説かれた(笑)。SFは好きだったけど、純文学はほとんど読んだことがなかった。最初は断ったんだけどわざわざ新潮社の編集者が大阪まで来て。それ以降トークイベントにも毎回来る。それが2~3年続いて、「やっぱり書くわ」と折れました。最初はホラーSF小説を考えたんだけど、「向いてない。岸さんは自分のこと書いて」って言われて。ちょうど大阪のエッセイを書いていて、これを一歩進めていくと私小説になりそうだという感覚があった。
齊藤
『ビニール傘』(新潮社)を読みましたが、いろいろな人生が重なりあったりずれていたり。同時に出てくるのは二人ほどで、閉じた世界にも見えるのですが、そういう個々人の小さな世界が集まって、この世界ができているんだという感覚になりました。
岸
『ビニール傘』に出てくる一人称の「俺」は、いろんな「俺」がいるように見えるけど実はひとりで、世界のほうが変わっているんだよね。記憶ごと変わるから「俺」自身には変わっていることがわからない。それを世界のほうから書くと、「俺」がたくさんいるみたいに見える。日雇いのときやジャズミュージシャンのときの、毎日違う現場にいるという不安定さというか、寄る辺なさが原点です。日雇いの俺、ジャズミュージシャンの俺、社会学者の俺、「全部同時に存在しているかもしれん」みたいなことを考えて。書いているうちに自然にそうなったんだよね。街を歩いていていつの間にか海になっているという場面があるけど、それは僕に世界がそういう感じに見えているということです。
齊藤
書いてみてどうでしたか。
岸
面白かったですね。全然違う海に連れてかれてそこで遊んだ感じ。文章書くって、どんな文章でも、素潜りみたいな感覚なんですよ。息を止めてがばっと潜るんだけど、それを普段とは違う海でやる感じ。
次はもうちょっと話をつくりたいな。「クアトロ」という小説は、河出書房新社の『文藝』に連載途中で止まっています。男性性のこと、男性の「キモさ」に興味があって。めっちゃ書きたいけど、「社会学っぽい小説を書きに来たな」と思われるのが嫌で止まっている。
齊藤
最近読んでよかった小説はありますか。
岸
柴崎友香さんの『百年と一日』(筑摩書房)はめちゃくちゃ名著です。好きすぎてずっと読めなかった(笑)。最初の何ページか読んで、良すぎて読むのがもったいない感じ。柴崎さんはいいなあ。彼女は『あらゆることは今起こる』という、医学書院の「ケアをひらく」シリーズでご自身のことも書いている。子どものころからの脳の中で起こっていることをADHDの当事者として書いているんだけど、芥川賞作家が書くとこうなるのかっていうね。とてもいい。
インタビューを終えて
.jpg)
齊藤ゆずか
大学生になってから世界が広がり、関わる人が増え、そのバッググラウンドも多様になりました。その分、「他者」をわかろうとすることはとても難しいという実感があります。しかし、「他者」を理解するためにデータを真摯に積み上げて研究することの大切さをお話いただいて、目の前がぱっと開けたような感覚がありました。生きていくために大切な言葉を受け取ることができました。本当にありがとうございました。
▲ Profile


