あの頃の本たち
「走る読書部屋」名取佐和子
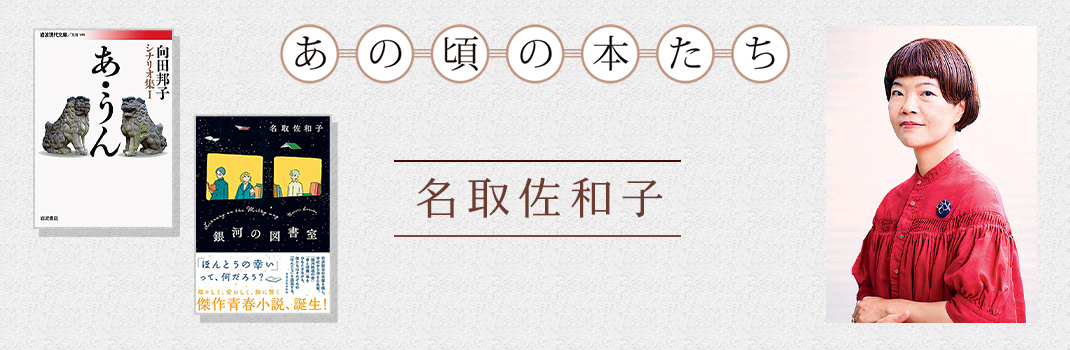
走る読書部屋
名取佐和子 Profile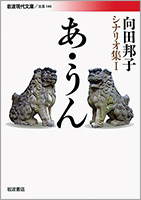
向田邦子/岩波現代文庫
定価1,320円(税込)
よほど分厚い本でなければ、行きと帰りの車内で読み終わった。薄い文庫本なら2冊読めた。本に夢中になって降車しそびれることもままあったし、吊革につかまって読んでいる最中にしおり紐が外れてしまい、前に座っていたおじさんに「釣り糸たらすな。俺は魚じゃねえ!」と怒られたこともある。巧いこと言うなあと感心しつつ、平謝りした。
こんな体たらくのせいか、花の大学生のはずが勉強もサークル活動もアルバイトも恋愛もスベり散らかし、気づけば、時間つぶしの〈読書部屋〉が生活の中心を占めるようになっていた。「なんて地味な毎日だ」とぼやきつつ、私は電車で読む本を常に探し、書店と図書館を巡りに巡った。大学生協は本が定価より安く買えたので、重宝したものだ。
本を選ぶ時は自分の勘を頼った。書棚をうろつき「目が合う」本を探すのだ。絶対にかぶれそうと予感しながら読んだ太宰治にまんまとかぶれて、三鷹まで墓参りにいった。笙野頼子『タイムスリップ・コンビナート』や松浦理英子『親指Pの修業時代』は出オチのようなかっこいい設定にまず痺れ、そこからジャブのように効いてくる文体や緻密な構成に圧倒された。高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』は何度も読み返し、そのたび電車の中でこっそり泣いた。北村薫「円紫さんと私」シリーズは、作中の「私」が同世代だったので、友達に会いにいく感覚で『空飛ぶ馬』『夜の蝉』『秋の花』『六の宮の姫君』を大学在学中に味わい、卒業後に刊行された『朝霧』と『太宰治の辞書』も追いかけた。
〈読書部屋〉で過ごすようになって1年も経つと、本が本を呼んでくる現象が起こりだした。たとえば仏文学科の授業でランボーの詩を原文で読む機会があれば、日本語に訳された『ランボオ詩集』も読みたくなって買う。その翻訳者である中原中也の詩集も読んでみる。言葉ひとつひとつに魂が滲んでいるような詩に感動し、中原中也という人が知りたくなる。評伝や研究書を読む。すると中原さんの親友で恋敵でもあった小林秀雄の存在を知り、今度は彼の評論も読みはじめる。小林さんがものすごい熱量で論じていたベルクソン『笑い』にも手を出す。難しくて読みこなせない本もたくさんあったけれど、知らない言葉を目にするだけで嬉しかった。
向田邦子『あ・うん』は図書館で目が合い、〈読書部屋〉に持ち込んだ。表紙をひらいた瞬間、会話だらけのページに面食らい、電車の中で声が出たことを覚えている。
小説とばかり思って借りたその本は、テレビドラマのシナリオだったのだ。セリフとト書きで綴られる物語をはじめて目にして、読みづらさを感じたのは2ページまで。生きた言葉が使われるテンポのいい描写に、落語好きな私はすぐ馴染み、どんどん読み進んだ。
物語の舞台は、戦争の足音迫る昭和十年代の東京。アラフォー夫婦と夫の親友が織りなすプラトニックな三角関係が、夫婦の十八歳の娘の視点から描かれていく。綺麗事か露悪的かに偏りがちな題材を、しみじみとした味わいに仕上げられるのが向田さんのすごさだ。冷静さと繊細さが両立した観察眼で生活を描き、物語の土台にきちんと据えてある。その生活を表現する手段が、セリフだった。
向田さんの書くセリフは、発声する会話ならではの省略とリズム、何よりユーモアがあって、登場人物の解像度がとびきり高い。そして向田さんのト書きは、文字を追っただけでセリフまわりの状況や人物の感情や動作がパッとイメージできる簡潔な文章ながら、その流麗な文体によって読み物単体としても楽しめた。のちにエッセイや小説に活躍の場を広げて名文を遺された向田さんだが、その素地はシナリオからも十分匂い立っている。
『あ・うん』の読書体験が今までと違っていたのは、読んだあと自分でも書いてみたくなったことだ。どこかにいる誰かの生活を考えると、ワクワクした。小説でも詩でもなく、シナリオの形式で物語を書いたのは、向田さんに憧れたからに他ならない。シナリオは仕事になり、やがて「小説を書きませんか」と誘われた時も、向田さんも進んだ道だから楽しく挑戦できた。走る〈読書部屋〉とそこで読んだ本たちが今の私を作り、小説を書かせていると考えれば、スベり散らかした大学時代も浮かばれるというものだ。
P r o f i l e

兵庫県生まれ。明治大学卒業。ゲーム会社に勤務した後、独立。2010年『交番の夜』で作家デビュー。
●
著書に第5回エキナカ書店大賞を受賞した『ペンギン鉄道なくしもの係』、『金曜日の本屋さん』『江の島ねこもり食堂』『逃がし屋トナカイ』『ひねもすなむなむ』『図書室のはこぶね』『文庫旅館で待つ本は』ほか多数。県立野亜高校が舞台の『図書室のはこぶね』(2022年刊行)は、各地の司書が選ぶ「イチオシ本」に選定されるなど、幅広い世代から愛読されている。最新刊は、高校生たちが宮沢賢治作品と出会う『銀河の図書室』(実業之日本社)。

実業之日本社/定価1,870円(税込)購入はこちら >


