読書マラソン二十選! 181号
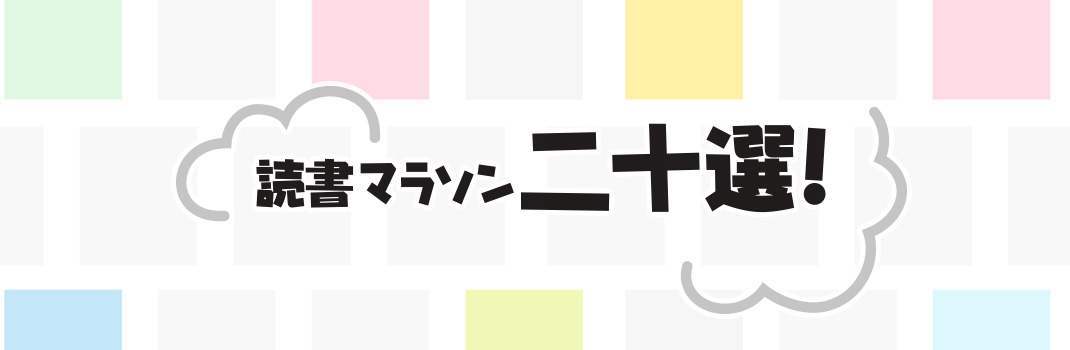 第19回全国読書マラソン・コメント大賞のナイスランナー賞作品のなかから20点、今回もあたたかいお部屋の中で、移動中の電車の中で楽しめる本をセレクトしました。
第19回全国読書マラソン・コメント大賞のナイスランナー賞作品のなかから20点、今回もあたたかいお部屋の中で、移動中の電車の中で楽しめる本をセレクトしました。
-
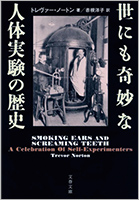 『世にも奇妙な人体実験の歴史』
『世にも奇妙な人体実験の歴史』
トレヴァー・ノートン〈赤根洋子=訳〉/文春文庫購入はこちら > この本は危険な感染症に自ら罹患してみたり、自分の心臓にカテーテルを通したり、といった危険な人体実験を自ら行い医療、科学を発展させてきた勇敢な科学者達のエピソードを集めたものである。彼らの生きた時代に医療の常識とされていたことを今読むと思わずゾッとするが、それは今の時代が豊かになっているという証拠である。勇敢な自己実験者らには感謝してもしきれない。彼らパイオニアが最後まで報われないことは珍しくない。しかし彼らは人生をかけて自分の興味のあることに向き合った。そんな生き方をしてみたいと憧れてしまう。(京都橘大学/わかば)
-
 『私の最高の彼氏とその彼女』
『私の最高の彼氏とその彼女』
ミン・ジヒョン〈加藤慧=訳〉/イースト・プレス 購入はこちら > 読書は新たな世界に自分を導いてくれる。
恋愛は人生に彩りと成功を与えてくれる。
そんな常識を正しいと信じていたのに、この本を読んだ後には不自由さだけが残っていた。
現実よりもリアルな困難ばかりがそこにあって、登場人物たちは自由を求めてタブーなロマンスに奔走する。ただ誠実さと勇気を武器にして。
正直に言うと、彼らに必ずしも理解を示せるわけではない。時には嫌悪さえ感じられた。しかし、それは息が詰まるような常識への揺らぎなのだと気づかされた。不自由さが新たな自由へと生まれ変わっていく感覚がした。(関西学院大学/赤城 漢字)
-
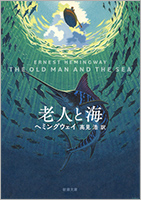 『老人と海』
『老人と海』
ヘミングウェイ〈高見浩=訳〉/新潮文庫 購入はこちら > 要約すると老人が巨大魚を釣り上げようとするだけの話である。だがそれだけで痺れるのだ。広くて深くて、時代を経てもこの物語に船出する人が絶えることはないだろう。男のロマン、というだけではない。巨大魚と対峙し、格闘し、最後には親愛の念さえ抱く老人の姿は、自然の中で太古から生きてきたありのままの人間の姿に見え、自然と距離を置いて生活している私は圧倒され、はっとした。「だが人間ってやつ、負けるようにはできちゃいない」。真の敵はきっと自然ではない。この言葉は、闘うべき時の灯火として、今はそっと胸の底に沈めておく。(京都大学大学院/あらぶゆ)
-
『先生はえらい』
内田樹/ちくまプリマー新書購入はこちら > 大学に入るまでは、丁寧に舗装された道の上を、他人が運転する車で走っているような気分だった。でもきっとその車を降りて自分の足で自分だけの「先生」を探す方が良いのだと、この本を読んで思った。良くも悪くも大量の情報の中を生きなければならない我々にとって、自分だけの主体的な問いを持ち、その答えを知っている「先生」を見つけ出すことは、一筋の光になるかもしれない。他でもない私自身を求めている「先生」のあたたかな眼差しを見逃さないようにしたい。(北海道大学/牛肉の手羽先)
-
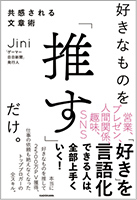 『好きなものを「推す」だけ。
『好きなものを「推す」だけ。
共感される文章術』
Jini/KADOKAWA購入はこちら > 大好きな推しを布教したい!……でも上手く文章にまとめられない。そんな“同士”の皆に読んで欲しい一冊です。推しを語ることの大切さや、「推し文」の書き方、推しを推す為の心構えなど、現代のオタクに必要なコトがギュッと詰まっています。私は本書を読んで、改めて推しの尊さを実感すると共に、オタクである自分に自信が持てたような気がします。そして推しの魅力をもっと多くの人に知ってもらう為に、積極的に「推し文」を発信していこうと思いました。……待って。私は本書を「推し」ているのだから、今書いている文章ってもしかして!?️(立命館大学/おかゆ)
-
 『神時間力』
『神時間力』
星 渉/飛鳥新社
購入はこちら > 漫然とスマホを見てしまう。行きたくない場所、したくないコトに従事してしまう。こんな煩わしさを抱えることはないでしょうか。本書はそんな、現代を忙しく生きる私たちが忘れてしまいがちな「時間」についての視座を得られる本です。
世の中は便利になったけれど、人間の心は荒んだのではないか。一見、更に世界は自由になったけれど、不自由な思考を用いてはいないだろうか。こんなことを痛感させられた一冊でした。
今、不安や悩み、やり場のない思いを抱えている人。この本を通して、限りある人生を謳歌しようではありませんか。(関西学院大学/Big Happiness)
-
 『死に至る病』
『死に至る病』
キェルケゴール〈斎藤信治=訳〉/岩波文庫購入はこちら > 私は、どんなに頑張っても一向に実を結ばない絶望と虚無を、心密かに誇るようになっていたが、これはまさしく、求道精神とルサンチマンの結託、社会に馴染めない自分を誇った腐れ大学生のメンタリティそのものであった。惨めで堪らない人生を特別でかけがえのないものだと思えるようになるためには、「神」の問題と向き合わなくてはならない。
「死に至る病」とは絶望の謂いであり、絶望は弁証法的なもの、また信仰の反対であるとともに信仰の入口ともなり得るものである。(福井大学/緑)
-
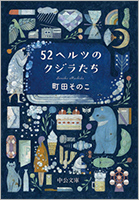 『52ヘルツのクジラたち』
『52ヘルツのクジラたち』
町田そのこ/中公文庫購入はこちら > 「わたしは、あんたの誰にも届かない52ヘルツの声を聴くよ」
孤独な主人公が、虐待を受ける少年にかけた言葉。この言葉に、私は涙がとまらなかった。
周波数が違うために苦しくても仲間に声を届けられない、52ヘルツのクジラ。そんなクジラが主人公と少年をつなぐ、切なく、温かい物語。
自分は一体何者なのか。誰も教えてはくれない答えを見つけようと、もがき続ける青年期。その最中にいる私に勇気をくれるのは、いつもあの言葉だ。毎日不安で、寂しい。それでもあの言葉が、この物語が、私に伝えてくれる。あなたはひとりじゃない、と。(愛知教育大学/北極星)
-
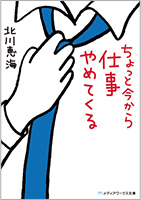 『ちょっと今から仕事やめてくる』
『ちょっと今から仕事やめてくる』
北川恵海/メディアワークス文庫購入はこちら > 追い詰められて、死んでしまいたくなっても、それは本当に「楽になる」方法なのだろうか。「頑張っても、どうしようもなくなってしまったときは逃げてもいい」「生きてさえいれば、案外なんとかなる」この二文を読んだときは、気持ちが楽になり、涙が出そうになった。苦しみを乗り越えたときにはきっと、『人生って、それほど悪いものじゃない』と思えるのだろう。人の命はひとりでは生まれないし、必ず誰かとのつながりがある。そんな命を、今の自分が楽になるかもしれないといった軽い気持ちで使いたくない。そう思った。(宇都宮大学/げっこー)
-
 『ライオンのおやつ』
『ライオンのおやつ』
小川糸/ポプラ文庫購入はこちら >「生きることは、誰かの光になること」。
人生は一本のろうそくのようなものだ。その身をすり減らしながら、お互いを照らし合っている。舞台は瀬戸内海に浮かぶレモン島のホスピス。毎週日曜日の「おやつ」をはじめ、「ライオンの家」の人々との交流や、恋というには曖昧な関係、愛するペットの存在など……。様々な出会いの中で、着実に「死」に近づいていた主人公が、かえって生き生きとしていく姿に、読者は心を打たれることだろう。「死」を描いているのに、明るくてあったかい。きっと、身の回りの「当たり前」を大切にしようと思えるはず。(早稲田大学/キキ)
-
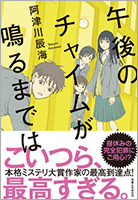 『午後のチャイムが鳴るまでは』
『午後のチャイムが鳴るまでは』
阿津川辰海/実業之日本社購入はこちら > くだらない事に全力な高校生たちの物語。一つ一つの謎がとても面白く、推理小説としての完成度が非常に高かった。しかし、それ以上に青春の輝かしさを強く感じた。一般的に青春といえば友情、努力、涙のようなイメージがある。一方本作では、何でもない日の昼休みを生徒たちが好きなように過ごしているだけだ。それなのに何故こんなにも惹かれるのだろう。私の高校生活はコロナにより多くの行事が無くなっていたが、沢山くだらないことをして沢山笑っていた。本作を読み終えた今なら分かる。あれこそが青春だったのだ。(名古屋大学/メルカトル)
-
 『真昼の悪魔』
『真昼の悪魔』
遠藤周作/新潮文庫購入はこちら > 医者は、人の命を救う職業だ。しかし、医者に良心がなかったら?
医者のフリをした悪魔の願望は「自己弁護の余地のない動機のない悪」である。手始めに子どもをそそのかし、二十日鼠を溺死させる。ボーイフレンドの掌に、興味本位で針を刺す。あまつさえ、人体への影響が不明な薬を「迷惑をかけるしかない虫けら」の患者で実験する。それでも、彼女は「医者」なのだ。今風にいえばサイコパスだが、本作の上梓は昭和55年であることに驚きを禁じ得ない。身近に潜む悪魔によって、医療とは人間の良心のもとに成り立つことを再認識させられる。(早稲田大学/K)
-
 『凍りのくじら』
『凍りのくじら』
辻村深月/講談社文庫購入はこちら > どこにいてもそこを自分の居場所だと思えず、自分や他人をどこか俯瞰的にみてしまう主人公の理帆子を物語に溶け込んだドラえもんの秘密道具が助けてくれる。薄暗い闇の中に一筋の光が差し込むような美しさを持った「少し・不思議」な物語。自分が一歩踏み出せば、少し手を伸ばせば、世界と繋がることができる。世界と繋がっていたことを思い出せる。何者にもなれなくて焦っていたあの頃の私へ教えてあげたい、本はいつだって私たちの味方だ。(帯広畜産大学/ぴち)
-
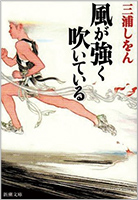 『風が強く吹いている』
『風が強く吹いている』
三浦しをん/新潮文庫購入はこちら > 風には2種類ある。それは、自分に困難を与える向かい風と、自分を前へと進めてくれる追い風だ。人間は楽をしたい生き物だ。だから、楽な追い風の方へと逃げていく。しかし、いずれは向かい風が吹くため、前へは進めない。一方、自ら困難な向かい風に立ち向える人は、向かい風の時はあまり進めないかもしれないが、追い風の時には一気に進める。このように向かい風は自分に成長を与える。困難な状況になったとき、追い風に逃げてしまうのではなく、立ち向かう強さが私は欲しい。(信州大学/脳筋の神)
-
 『本日は、お日柄もよく』
『本日は、お日柄もよく』
原田マハ/徳間文庫購入はこちら > この本は「言葉を操る」とは何かを教えてくれる本だ。言葉は魔物である。扱う言葉一つで願いになったり武器になったりもする。つまり、どう言葉を操るかで自分の人生も他人の人生も変えてしまう。日々、私たちの口から発する一音一音に意識を向ける人なんていないだろう。だからこそ、私は私自身や他人が発する言葉の意味・つながり・想いに重点を置いてみようと思う。きっと、それが「言葉を操る」ための第一歩になるから。(千葉商科大学/たか)
-
 『あいのかたち』
『あいのかたち』
辻村七子/集英社オレンジ文庫購入はこちら > AIの発展が目まぐるしい昨今。アンドロイドと人間のさまざまな形が描かれた物語たちは少しほろ苦く、でも、本当に大切なものについてそっと伝えてくれている気がする。この物語を読むと、未来には今以上に多様なアンドロイドと人間のかかわりがあると思うけれど、それがきっと優しいものであればいいと願わずにはいられなくなる。現実世界でアンドロイドが人間を超えるのか、はたまたそうでないのかはわからない。未来は誰にもわからない。けれど、願わくは、多くの人がこの物語の中で素敵な出会いを見つけられたら、と思う。(岐阜大学/sora)
-
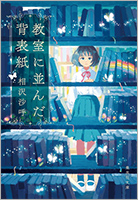 『教室に並んだ背表紙』
『教室に並んだ背表紙』
相沢沙呼/集英社文庫購入はこちら > 作品のキーとなるのは本と司書のしおり先生。それぞれの短編に登場する少女たちは、さまざまな悩みを抱える中で図書室を訪れ、しおり先生と出会う。少女たちの心情は、中学生の等身大の言葉で、ストレートに、そして繊細に描かれており、それがこの作品の魅力なのだと思う。だからこそ、物語の中の彼女たちに感情移入しやすいのだ。
現実はこの作品のように「優しくない」と言う人もいるかもしれないが、現実が少しでも優しい世界に近づくように、私にもできることから行動を起こしていきたいと思えた。(名古屋大学/弥生)
-
 『本を守ろうとする猫の話』
『本を守ろうとする猫の話』
夏川草介/小学館文庫購入はこちら > 「あなたにとって本を読むとはどういうことですか」と問われた気がした。この作品を読んで、自分にとって「本を読むとは」、「なぜ本を読むのか」という読書の原点を考えさせられた。自分にとって読書は言葉との出会いだと思っている。何万字という文字で構成された一つの作品の中で自分にとって素敵だと思える言葉、文章に出会い、新たな視点を得て、自分の世界を広げていく。それが本の素晴らしさであり、自分が本を好きになった理由の一つだと改めて感じさせてくれる作品であり、心の底から本が好きだと叫びたくなった。(広島修道大学/にゃら)
-
 『女に生まれてモヤってる!』
『女に生まれてモヤってる!』
ジェーン・スー、中野信子/小学館購入はこちら > 最高のラジオパーソナリティ、ジェーン・スーと最高の脳科学者中野信子の共著。社会を生きていくときにどうしようもなく押しつけられる「女らしさ」を検証し解体し、「女らしく」ではなくて「自分らしく」生きようと背中を押してくれる本です。日々感じているモヤモヤを言語化し、「そんなのおかしい。相手にする必要ないよ! 人生楽しも!」と言ってくれる二人が頼もしく、本当に勇気がもらえます。頭キレッキレ舌鋒鋭い女たちのトーク、大好きだ―― !!(お茶の水女子大学/M.)
-
 『世の中は偶然に満ちている』
『世の中は偶然に満ちている』
赤瀬川原平=著、赤瀬川尚子=編/筑摩書房購入はこちら > 人生において多くを占めるのは運命ではなく、偶然ではないだろうか。私たちの人生そのものは「偶然の集まりでできている」と言っても過言ではないと思う。しかし現在多くの人々は多くの時間を、手元の携帯電話と過ごしており「偶然に溢れている現実の世界」を見ることができていない。インターネットの社会に「偶然」は転がっていない。なぜならそれは完全に人間が作った世界だからだ。少し目線を上げて、偶然に満ちた毎日を生きて、毎日に特別感を与えてみてはどうだろうか。もしかすると、より充実した日々が過ごせるかもしれない。(松山大学/ももくぅ)




