駒込先生の推薦図書
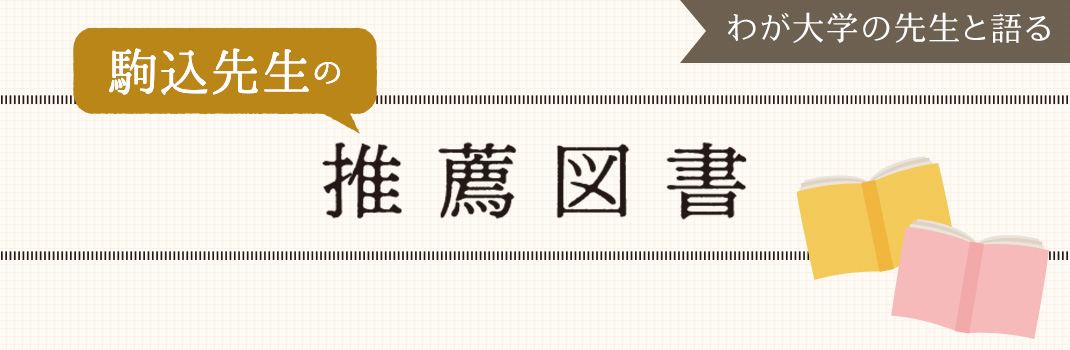
『陳澄波を探して 消された台湾画家の謎』
柯宗明<栖来ひかり=訳>
岩波書店/定価3,300円(税込)
購入はこちら >戒厳令下の台湾で若い男女のカップルが謎の画家・陳澄波の足跡を追うという推理小説仕立ての設定のなかで、日本統治時代に台湾人芸術家たちが直面した苦難と、そのなかで追い求めた夢を浮き彫りとする。

楊双子<三浦裕子=訳>
中央公論新社/定価2,200円(税込)購入はこちら > 1938年の台湾を舞台とした百合小説であり、鉄道小説でもあるのだが、植民者の独りよがりな「善意」への告発がコアとなっている。赤松美和子『台湾文学の中心にあるもの』(イーストプレス)とあわせて読みたい。
『誰の日本時代 ジェンダー・階層・帝国の
台湾史』
洪郁如
法政大学出版局/定価3,080円(税込)
購入はこちら >台湾といえば「親日」とイメージされがちだが、「親日台湾」という場合の「台湾人」とは誰なのか?「日本時代」に学校教育から排除された女性、農村漁村民の視点から歴史を見直し、彼女ら/彼らの経験を紡ぎ直す。
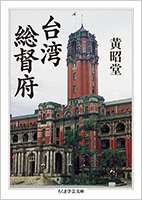
黄昭堂
ちくま学芸文庫/定価1,330円(税込)購入はこちら > 台湾史研究の開拓者による概説書の復刊。大陸では中華民国が成立したのちに「中国人」意識が形成されたのに対して、それより早く日本に植民地化された台湾では「台湾人」意識が形成されたとする歴史像は今なお新鮮。
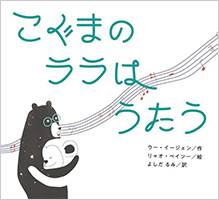
うたう』
ウー・イージェン=作/リャオ・ペイツー=絵/よしだ るみ=訳
国土社/定価1,650円(税込)
『こぐまの ララは うたう』特設サイト
https://note.com/kogumanolala/n/n88c1d78d3d1e
『台湾のアイデンティティ 「中国」との
相剋の戦後史』
家永真幸
文春新書/定価1,210円(税込)
購入はこちら >なぜ台湾では、同性婚の合法化など社会の多様性を重んじる思想が広く共有されているのか? その根底に「国家暴力に怯えなくてもよい社会への渇望」が存在することが、台湾戦後史に即して明らかにされる。
『隙間(全4巻)』
高妍
KADOKAWA/定価808〜968円(税込)
購入はこちら >女子大生・楊洋(ヤンヤン)は、同性婚など社会的イシューにかかわるなかで希望と絶望のあいだを揺れ動き、留学先の沖縄でその振幅はさらに激しいものとなるが、迷いのなかに新しい未来がひっそりと浮かび上がる。

問い』
駒込武(編)
みすず書房/定価3,300円(税込)購入はこちら > 台湾・沖縄からパネリストを招いたシンポジウム、往復書簡、座談会などを通じて、台湾も沖縄も犠牲にしない、東アジアにおける「平和」の可能性を問いかけるとともに、「帝国の狭間」から世界を見る重要性を訴える。
P r o f i l e
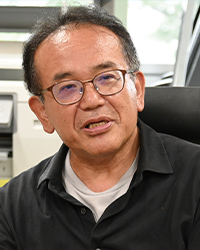
■略歴
1962年東京都生まれ。
京都大学大学院教育学研究科教授。
東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。1992年4月 お茶の水女子大学文教育学部専任講師、1994年1月同文教育学部助教授、1995年3月 博士(教育学)、1999年10月京都大学大学院教育学研究科助教授、2007年4月 同准教授を経て、2012年10月同教授(現在に至る)。専攻は、教育と学問の歴史、台湾近現代史。
●
■主な著書『世界史のなかの台湾植民地支配―台南長老教中学校からの視座』(岩波書店 2015年)、編著に『生活綴方で編む「戦後史」 〈冷戦〉と〈越境〉の1950年代』(岩波書店 2020年)、『台湾と沖縄 帝国の狭間からの問い』(みすず書房 2024年)、訳書に呉叡人著『台湾、あるいは孤立無援の島の思想』(みすず書房 2021年)など多数。
▼ Profile


