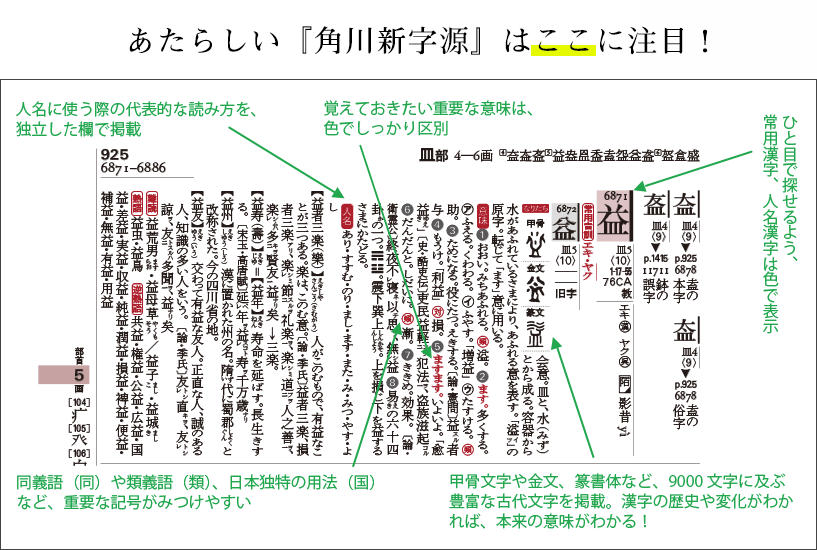いざ、漢和辞典の世界へ
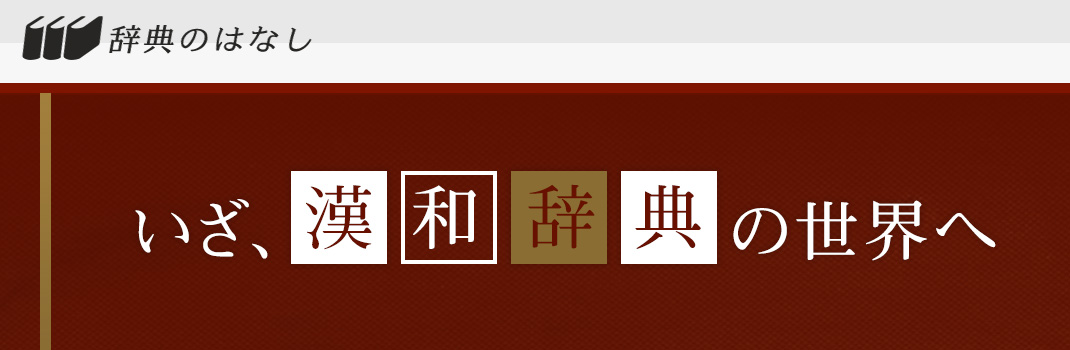
『角川新字源』改訂新版校了間近の辞書編集部へ潜入!
取材・文=田中美里
大学生協売上No.1の漢和辞典。23年ぶりの全面改訂

『角川新字源 改訂新版』
角川書店
本体3,000円+税
2017年 10月30日刊行予定!!
世の中にはパソコンやスマートフォン……文字を入力すればピンポイントで調べることが出来てしまう便利なツールがたくさんありますが、紙の辞書はそれよりももっと深くて大切なことを教えてくれます。当たり前のように使っていた文字文化をもう一度見つめなおそうと、今回、辞典編集に携わる人たちにお話をうかがってきました。
遠足の前夜のような期待感
5月某日。昼下がりの大学の講義は私の頭になかなか入ってこない。この原因はご飯を食べた後の眠けでも、5月病だからでもなく、辞書を作っているKADOKAWAの辞書編集部にお邪魔できるわくわく感によるものだった。私が辞書に興味を持つようになったのは、大学1年のときに「早稲田大学辞書研究会」と出会ったからだ。大学内で独自に使われている「早稲田語」を集め、『早稲田大辞書』を作るということをきっかけに「辞書作り」の面白さを感じた。山積みの原稿にある熱い思い
.jpg) ゲラの山
ゲラの山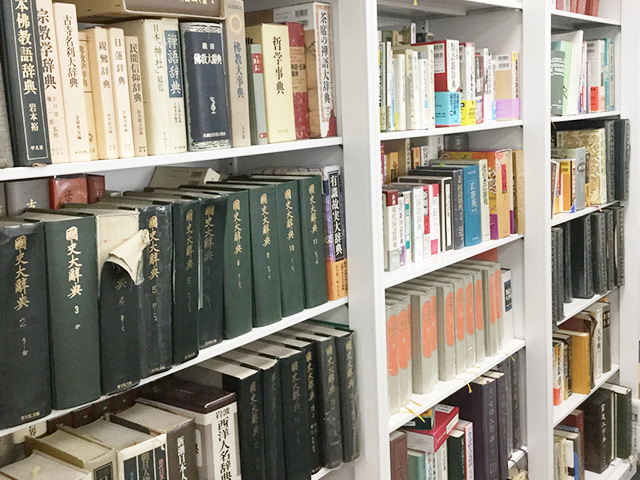 資料棚の辞典類(お宝♪)
資料棚の辞典類(お宝♪)
私と『izumi』編集部の大塚さんが辞書編集部の坂倉さんに案内された部屋で、最初に目に入ったのは紙の山。思わず目を見張ってしまった。さらに向かい側壁面の資料棚には所狭しと辞典類が並んでいる。でもこれは氷山の一角にしかすぎないようだ。ここに入り切らない漢籍の資料等は別の場所にもあるとか。
では今秋発売となる『新字源』の改訂の流れを見ていこう。
23年ぶりの改訂に至った『新字源』。「ゼロ」からのスタートではないものの、最初から作り直す気持ちで臨んだという。というのも、改訂に至るまでに漢字業界では様々なこと(例えば常用漢字の改定など)が起こっていたからで
ある。
全体の流れとしては、まず誰を対象にし、どの文字を、どう載せるかの方針を話し合う。そしてそれが決まったら辞書編集部の重鎮、高野さんが親字表を作る。
親字表って何?と思った読者のみなさん。私も「何?」と思ったのでご安心を。親字表とは常用漢字や人名漢字、JIS漢字の他、漢文を読むのに必要な漢字など、改訂新版に載せる漢字を一覧表にしたものである。ふむふむ、なるほど。この作業を高野さんがお一人でなさったというのだ。そしてなんと高野さんは半世紀以上辞書に関わってこられた。ここまで続けてこられたのは言葉が好きだから、とご自身で振り返っていたように、本当に言葉への愛を感じた。
親字表ができたところで、編者の先生方に原稿を依頼して、ゲラが出たら誤りを修正したり読みやすくするなど手を加え続けたりして、完成に至るということだ。
編集に当たっては一人ひとり担当する箇所(語釈なのか、由来なのかなど)が割り振られて流れ作業のようなやり方で行っていく。
改訂作業をすること十数年。小学校から成人するまでの期間と思うと初めは驚いたが、編集の過程や編集部の思いを知るうちに決して長いとは言えなくなってきた。
こうして出版されたら終了、と思っていた読者のみなさん、ちょっと待ったー!!!
辞書は出版されたら終わりではなく、その時点から重版や次の改訂に向けて作業が始まっている。 「完璧なもの」を目指していてもミスはつきもの。気づいたミスを重版で直すように校了した瞬間から次に向かっている。
デジタルv.s.アナログ
はてさて、みなさんは辞書を作るとき、紙媒体とコンピュータのどちらで作られていると思うだろうか。答えは両方! コンピュータでデータベースを作り、文字自体にナンバリングやラベリングをし、流れ作業を行う。一方細かい手直しは見落としがないように紙で行う。デジタルとアナログの両方のいいとこ取りで辞書は作られているのだ。印刷作業においてもデジタルとアナログの戦いは繰り広げられていた。
印刷は字が重なるということはありえないが、その代わり修正が効かない。一方コンピュータ編集は修正はしやすいものの、数ミリの誤差により、字と字が重なってしまうことも。
デジタルVSアナログ論争はこの辺でさておき、辞書作りに話を戻そう。
「神(紙)は細部に宿る」
私が辞書を引くときにひそかな楽しみにしている、あの手に吸い付くような触り心地。漢和辞典の紙質にも何かこだわりがあるのか聞いてみたところ、漢和辞典は複数の箇所を引き比べることが多いので、開いたときにページが戻ることがないように、どこまで開いていられるかというところを研究しているそうだ。初耳! 紙だけでなく字体や配色に至るまで細部にまでもこだわっていて、辞書は内容だけでなく、辞書を構成する要素すべてに力を注いで作られているのだなぁとしみじみ。
漢字の魅力
場所を移動して辞書編集部の高野さんと福永さん、坂倉さん3人のお話をうかがうことに。お話をうかがっていると辞書編集部の方は本当に本当に言葉を愛しているんだなぁと痛感した。福永さんが「日本には漢字とひらがな、カタカナがあって、すごく言葉に恵まれているからこそ表現が豊かになる」とおっしゃっていたのが印象的だった。
「ひとつひとつの文字にさまざまな由来や歴史的な変遷があり文字そのものに文化がくっついていて、漢字の歴史を辿っていくと当時のことがかいま見えてくる」と坂倉さん。例えば日本の「菊」という文字。皆これは訓読みが「きく」だと思っていないだろうか。しかし、「キク」は音読みであり、元々は中国から入って来たものとなる。中国から入って来たものが日本の国花になる。日本の文化と中国の言葉は切っても切り離せない関係なのだ。漢字って奥深いし、面白い!と感じた。
漢字と向き合いすぎるあまり…
「一点、一角が大事」とおっしゃった福永さん。校正の作業を重ねるあまり、ゲシュタルト崩壊を起こすこともしばしば。また、 新聞記事を読んでいる際、誤字に気をとられ過ぎて内容が入ってこないこともあると高野さんは笑いながら話してくださった。さらに長時間パソコンを見ることから肩こりにも悩まされているそう。大塚さんにも共通しているようで、4人は肩こり解消法トークへ。漢字の一字あたりの単価を計算すると…
辞書の値段を高いなぁと思ったことはないだろうか。私も実はそうだった。祖母に辞書を買ってもらったとき、レジに表示された値段が、本や漫画に比べて遥かに高く、幼心にも驚愕したのを覚えている。辞書が出来上がる過程を知った私のなかで、この印象は次第に崩れ始めた。坂倉さんが「一文字の単価は安いですよ」とおっしゃったのに納得。辞書は高いどころかむしろお買い得!だったのだ。
「先生方の英知と編集部の費やした時間を考えたら、開けばそこに自分の知らない世界のことがいっぱい載っている辞書はすごくお得なものだと思います。だからみなさんに活用していただきたいですし、色々な辞書を読んでもらいたいですね」と福永さん。
大学生になって辞書をほとんど使っていなかった自分を反省した。実家に帰ったら、机の右端に眠っているやつらを久しぶりに開いてみることにしよう。
言葉好きが集まり出来上がる一冊
今回辞書編集部を見学してたくさんの新しい発見ができ、ますます言葉に対する思いが深まると同時に、辞書に対する考え方が変わった。こんなにも言葉を愛しているこんな素敵な方たちと将来一緒に言葉に向き合えたらいいなぁとこっそり胸の内でつぶやきながら出版社を後にした。
 左から、辞書編集部の福永さん、高野さん、私、同・坂倉さん。みなさんありがとうございました。
左から、辞書編集部の福永さん、高野さん、私、同・坂倉さん。みなさんありがとうございました。
(取材日:2017年5月7日)
P r o f i l e
田中美里(たなか・みさと)早稲田大学文化構想学部3年。旅行にいく計画を立てているだけで気がついたら2、3時間経っていることもしばしば。こういう時間を過ごせるのもきっと大学生の醍醐味だといい聞かせ、今日も今日とてネットサーフィン。