いずみ読者スタッフの 読書日記 162号
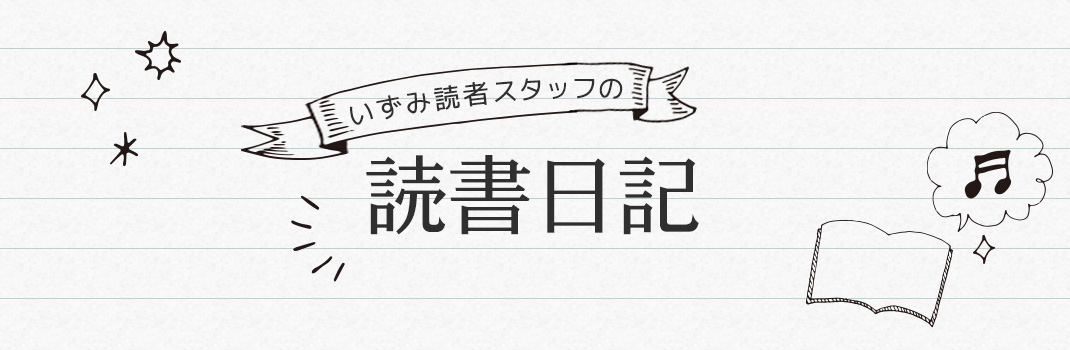
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
同志社大学4回生 畠中美雨
12月下旬 ため息も白くなる頃
 帰省中、皆が寝静まったあとに、自分の本棚よりハードカバーが多い実家の本棚をしげしげと眺め、適当に読んでいた。その中の一冊が呉明益さんの『歩道橋の魔術師』(天野健太郎=訳、白水社)。
帰省中、皆が寝静まったあとに、自分の本棚よりハードカバーが多い実家の本棚をしげしげと眺め、適当に読んでいた。その中の一冊が呉明益さんの『歩道橋の魔術師』(天野健太郎=訳、白水社)。舞台は忠孝仁愛信義和平の八棟からなる中華商場。大人、子供、寝静まった建物。場所や時が変化しながらゆるやかに繋がっていく。切り取る枠が異なるのに重なりあうこの感じ、短編小説の醍醐味だ!と胸が高鳴る。色のついたネオン、昼間の象、歩道橋の魔術師。信じれば本当になる、そう信じて、だから嘘なんてなにもなかった頃を思い出した。この本の中のように、そんな時間はいつかの私にも流れていた。
1月上旬 雪を待っていた頃
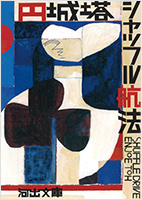 学部4回生故に何かと忙しく、腰を据えた読書の時間が取れない。そんなとき持ち歩くのはエッセイや短編小説。瓢箪柄の赤地のブックカバーにこの日忍ばせていたのは、円城塔さんの『シャッフル航法』(河出文庫)。円城さんの本は集中して読まないと置いていかれる。いやそもそも追いついたこと、全貌が見えたことがあっただろうか。表題の「シャッフル航法」は散文と短編の狭間で弾けているし、ほかの話も異物感と面白さが混在して、気づけば読み終わっていたり、はたまた何度も読み返していたり。読了感があるようでないような。でもいつも考えてしまう物語の意味やメッセージが分からずとも、書く人がいて読む人がいる、それだけで充分ではないか、そう思ったりした。
学部4回生故に何かと忙しく、腰を据えた読書の時間が取れない。そんなとき持ち歩くのはエッセイや短編小説。瓢箪柄の赤地のブックカバーにこの日忍ばせていたのは、円城塔さんの『シャッフル航法』(河出文庫)。円城さんの本は集中して読まないと置いていかれる。いやそもそも追いついたこと、全貌が見えたことがあっただろうか。表題の「シャッフル航法」は散文と短編の狭間で弾けているし、ほかの話も異物感と面白さが混在して、気づけば読み終わっていたり、はたまた何度も読み返していたり。読了感があるようでないような。でもいつも考えてしまう物語の意味やメッセージが分からずとも、書く人がいて読む人がいる、それだけで充分ではないか、そう思ったりした。
1月中旬 三寒四温、たまに雨
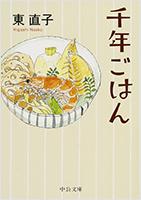 図書館で制限いっぱい借りていた本を返却しに行く。本を返却して空いた手で、本棚から気の赴くままに本を手にする。ふと目についた東直子さん、前号で対談なさっていたっけ。数冊めくり、あまのじゃくな私はあえて短歌だけじゃない一冊『千年ごはん』(中公文庫)をもってカウンターへ。
図書館で制限いっぱい借りていた本を返却しに行く。本を返却して空いた手で、本棚から気の赴くままに本を手にする。ふと目についた東直子さん、前号で対談なさっていたっけ。数冊めくり、あまのじゃくな私はあえて短歌だけじゃない一冊『千年ごはん』(中公文庫)をもってカウンターへ。料理や食材について数ページの思い出、最後に一首という構成の本書。黒豆、春の天麩羅、そうめん……。包丁で小気味の良い音をたててトントンと野菜を切るようにリズムよく読める。そんな中にも、一話ごとの短歌がまるで箸休めの箸置きのように置かれていて、ただ読むだけではなく一息ついて自分の思い出と照らしながら読める。
読み終えて本を返す。あと何回ここで本を借りるのだろう。少しセンチメンタルになりながら、でも自分が通わなくなったとて整然と並んで誰かを待つ図書館のことを思うと、少しも寂しがる要素はないのだ。

.jpg)
.jpg)