読書マラソン二十選! 164号
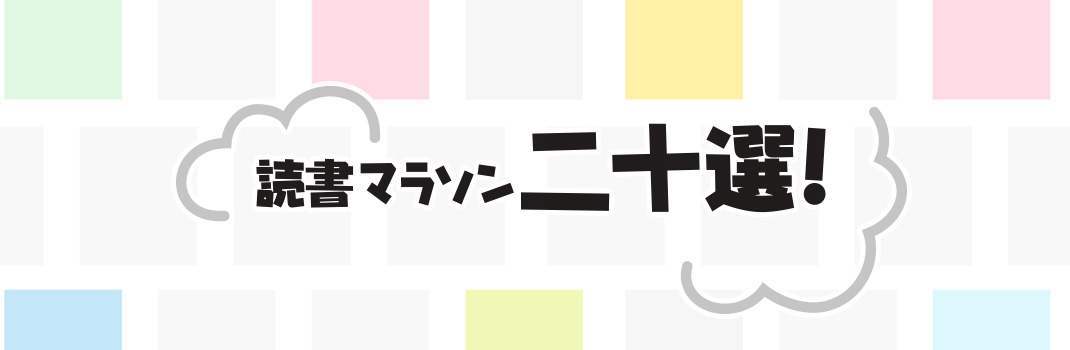
今年度の読書マラソン・コメント大賞が始まりました。
コロナ禍で生協書籍コーナーや書店にゆっくり足を運べない間にも、素晴らしい本が続々と発売されています。この機会に名著とあわせて様々なジャンルの本に触れ、あなたの言葉で、たくさんの本を、ぜひ同世代の仲間に紹介してください。今年のコメント大賞は、Webサイトでも応募ができますよ!
全国読書マラソン・コメント大賞のご案内
-
 『ピクニック——宇都宮敦歌集』
『ピクニック——宇都宮敦歌集』
宇都宮敦/現代短歌社
面白いより“楽しい”と言いたくなる本にときどき出会う。『ピクニック』もそうだ。「パンダTシャツを着ている日はパンダ好きとだいたい間違えられる」って、そりゃそうだよ。「棚にのぼったネコを棚からおろす これを棚おろしという うそ いわない」ってどうしてそんな嘘ついちゃうの。「のばしかけの髪がちくちくするけれど アフロはでかいほうがいいから」って、だから『ピクニック』もでかいの? 正直めっちゃかさばるけど、それでも連れ歩いちゃう『ピクニック』(←「少年ジャンプ」サイズ)をどうぞよろしくお願いします。(広島大学/甘蛙)
-
 『改訂新版 ロボットは東大に入れるか』
『改訂新版 ロボットは東大に入れるか』
新井紀子/新曜社
何かと話題の人工知能。よく耳にはするけれど、ロボットと一緒に暮らしている訳ではないし、日常の中でその仕組みを知る機会はない人も多いと思います。この本は、大学入試という観点からAI・人工知能について知ることができる入門書です。自分も学んだことのある科目や経験したことのある試験だからこそ考えさせられるし、人工知能がどんな風に問題を解くのか興味深かったです。(慶應義塾大学/ピンクの水玉)
-
 『文系と理系はなぜ分かれたのか』
『文系と理系はなぜ分かれたのか』
隠岐さや香/星海社新書
私は理系と文系という分け方が好きではない。「自分は○系だから」と自分が他分野に精通していない言い訳によく使われるからだ。なぜわざわざ分けたのかを知ろうとして読んだが、歴史的にある程度必然性はあったようだ。しかし、私はこの本において学問の歴史ではなく、職業やジェンダー論などと絡めた記述が印象的だった。文系と理系の違いが決定的に大きなものだと考えている人は価値観が変わるだろう。(神戸大学/アップル)
-
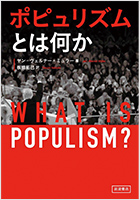 『ポピュリズムとは何か』
『ポピュリズムとは何か』
ヤン=ヴェルナー・ミュラー
〈板橋拓己=訳〉/岩波書店
ポピュリズムという現象が注目されている。簡単に言えば「真の人民」を作り出すことだ。 なんとなく「人気者」くらいに考えている人もいるのではないだろうか。しかし、それは危険だ。ポピュリストを政治的レッテルで退けることは寧ろ彼らを利することになるからだ。ゆえに本書では精緻な分析が行われている。日本にも同様の問題があるとするのは早計だろう。しかし、民主主義が抱える問題の一つとして考えることは意義があるはずだ。(立命館大学/アカデミック賞が欲しい )
-
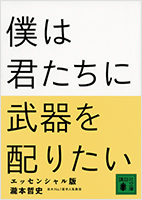 『僕は君たちに武器を配りたい
『僕は君たちに武器を配りたい
エッセンシャル版』
瀧本哲史/講談社文庫
少子高齢化と労働人口の減少という現実が迫る中、自分はどういう仕事に就き、どう生きていけば良いのか悩んでいた。究極的な答えは、自分自身で見つけていくしかないとわかっていても、何かヒントが欲しかった。そんな時、この本と出会った。弱肉強食のグローバル資本主義が進み、日本の有名企業でさえ外国企業に買収されていく中、何かにしがみつく守りの姿勢ではなく、主体的な攻めの姿勢で生きていこうと思った。(首都大学東京/雨と砂)
-
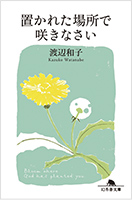 『置かれた場所で咲きなさい』
『置かれた場所で咲きなさい』
渡辺和子/幻冬舎文庫
この本を読んだことで、苦しいことや辛いことに遭遇しても、「これよりもっと苦しい思いをしている人がきっといる。これっぽっちのことで辛いと思えるなら まだ幸せな方だ」と考えられるようになった。また、どんなに苦しいことでも、自分は耐え得ることができると信じることができるようになった。苦しい時の薬として常備しておきたい、いわゆる常備薬ならぬ常備本である。(埼玉大学/きみまる)
-
 『「超」集中法』
『「超」集中法』
野口悠紀雄/講談社現代新書
暑いな! 暑いとやる気なんて出ないよな! 今のやる気は4滴くらいだ! もはや“%”ですら表せないって感じ。きっと汗と一緒に流れて気化して消えてしまったんだろう…。これはもう再呼吸不可能だな。うん、寝よう。……というわけにもいかないんだよな。試験もレポートも研究もあるし。誰だ「大学は人生の夏休み」とか言ったの?? 思いっきり補習とかに追われてる感じじゃないか。何かこう、ガーッと集中して、ガーッと終わらす方法ないものかね……。(岡山大学/n-supra)
-
 『余計な一言』
『余計な一言』
齋藤孝/新潮新書
ああ、今日もまた相手を怒らせてしまった。どうして私はいつも人を嫌な気分にさせてしまうのだろうか。自分が嫌になる。そんな時、私はこの本に出会い、無意識のうちに「余計な一言」を発しているのだと気づかされた。この本では「余計な一言」を具体的な会話の例を通して紹介しているため、実生活に投影しやすい。いわばコミュニケーションの参考書である。人間関係がうまくいかずコミュニケーションに悩んでいる人に、ぜひ読んで欲しい。(関西学院大学/くじら)
-
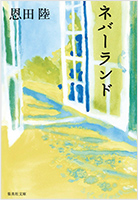 『ネバーランド』
『ネバーランド』
恩田陸/集英社文庫
自分は、向き合っているだろうか──気がつくと、美国と同じことを自問自答していた。周りの人と話していると、みんなそれぞれ、自分の将来や現実とちゃんと向き合っていることがわかって、それにひきかえ自分は──と情けなくなる。一方で、自分と同じように、みんな何かしら抱えているものがあるんだろう、と思うと、少しだけ勇気づけられたような気もした。(早稲田大学/なんでもや)
-
 『星に願いを、そして手を。』
『星に願いを、そして手を。』
青羽悠/集英社文庫
子供の間は、何も考えることなく無邪気に自らの夢を叫ぶ。小学生の卒業文集を見ると、こそばゆい気持ちが湧いてくる。しかし、大人になり年をとって、ある人は夢にすがり、ある人は夢を捨て、ある人は夢を諦め、ある人は夢に敗れ、ある人は夢を叶える。そんな美しくも儚い夢について、もう1度考えさせてくれる小説だった。主人公たちが“子供”から
“大人”になる過程には、青春の香りを感じさせる。(東京大学/グランド・ニーニョ)
-
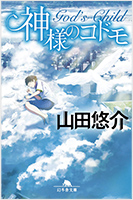 『神様のコドモ』
『神様のコドモ』
山田悠介/幻冬舎文庫
ショートショートでも山田悠介ワールドは健在である。最後の2行程で背筋が冷たくなる作品も少なくない。私のオススメは「肉」だ。大岡昇平「野火」などで大きく取り上げられるカニバリズムの問題を、現代ではこうも短く描くことができるのかと衝撃を受けた。現代は戦争を現実視しなくても生きてしまえる程、平和ボケした世の中なのだろう……。(法政大学/Maria)
-
 『ジェリーフィッシュは凍らない』
『ジェリーフィッシュは凍らない』
市川憂人/創元推理文庫
久々に“刺さる”感覚を覚えた。本書は非常にスタンダードでストレートに美しい推理小説だ。しかし、それだけでは終わらない。ラストシーンにて犯人が「〇〇です」と現れたとき、まるで今まで毒に犯されていたことを唐突に自覚させられたような衝撃を感じた。決して一撃じゃないけれど、確実に殺してくる感覚。あくまで静かな余韻を残して終結する物語は、淡く美しい。(お茶の水女子大学/水月真臣)
-
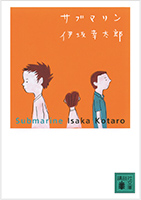 『サブマリン』
『サブマリン』
伊坂幸太郎/講談社文庫
何が悪で何が正義か。世の中には白黒つけられない問題が山ほどある。そんな社会で葛藤する少年たちは、抱えている問題にこそ大小はあれ、自分と重なる部分があった。頑張ることがダサい。必死なことが恥ずかしい。そんな思春期から人はどう変われるのか。物事の見方を少しだけ変えてくれる、そんな本でした。(横浜市立大学/umepeko)
-
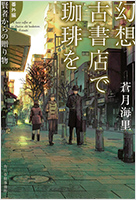 『幻想古書店で珈琲を 番外編』
『幻想古書店で珈琲を 番外編』
蒼月海里/ハルキ文庫
見たまえ、この、鳥の行進を!
言葉は私達を幸福にも不幸にもする。ネガティブな言葉ばかり呟いていると、人生にも陰りが出てくる……。日本では言霊と言うけれど、確かに言葉が持つ力は大きくて、人との縁を強固にするのも、人との縁を断ち切るのも言葉だったりする。言葉の使い方を今一度考えて欲しい。あなたの言葉にはどんな力があるだろう。(東京農業大学/カトリーヌ)
-
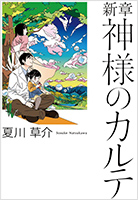 『新章 神様のカルテ』
『新章 神様のカルテ』
夏川草介/小学館
大学病院で難病の患者や後輩の教育、研究をこなし、双葉やお嬢に好かれ、家族とのひとときや久兵衛のお酒で癒される栗原一止がとても好きです。『神様のカルテ』を読んだ後は人に優しくなれるし仕事に真面目になれます(“真剣勝負”の意味で)。
第一班の班長になった一止の次回作が楽しみです。(公立はこだて未来大学/ハル)
-
 『キネマ探偵 カレイドミステリー』
『キネマ探偵 カレイドミステリー』
斜線堂有紀/メディアワークス文庫
取り返しのつかない悲劇が起こっても、死なない限り人生は終わらない。終わってくれない。 この小説の主人公達は取り返しのつかない愚かな失敗を、あるいは理不尽な悲劇を経験した。しかし、だからこそ二人は出会い、互いにかけがえのないものを得るのである。まだ終わっていないから、今、もう一度生きていける──。これは確かな救いの物語である。(奈良女子大学/チカ)
-
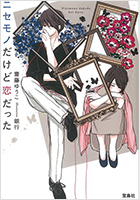 『ニセモノだけど恋だった』
『ニセモノだけど恋だった』
齋藤ゆうこ/宝島社文庫
寝る前に流し読みするつもりだったところ、気がつくと最後まで熟読していました。最初は「レンタル彼氏」と客の禁断の恋物語を予想していたのですが、二人の男女の夢と現実が描かれるあたりからどんどん引き込まれ、ただの恋愛モノにとどまらない印象を受けました。レンタル彼氏カオルや周囲をきっかけに大きく成長するヒロインの姿には、共感すること間違いなしです! 恋する人、夢追う人におすすめの一冊です。(愛媛大学/山猫)
-
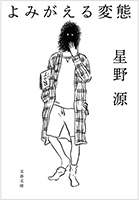 『よみがえる変態』
『よみがえる変態』
星野源/文春文庫
星野源によると 僕たち人間は皆、変態らしい。意味不明だが、僕はその言葉で心が笑った気がした。ちょうど辛い時期に読んだせいもあるが、星野が書く文章は心を笑わせる力があると思う。これは星野源という男のエッセイだが、まるで自身が体験したかのようなリアルがここにはある。今をときめくこの男性を知ることは、今を惑うあなたの心に一閃の光をもたらすことになる。きっと、よみがえるさ。(東京学芸大学/Tao)
-
 『健康で文化的な最低限度の生活』
『健康で文化的な最低限度の生活』
斉藤壮馬/角川書店
本が好きだから読書をしているのに、本当は読書している自分を自慢したいだけなのかもしれない。読書が好きだと誰かに伝えるたびにそう悩んでいた時期があった。この本のある章に、同じ悩みを抱えた著者が心から本が好きだと言えるようになった経歴が書かれている。ありきたりな感想だが、感動した。そして私も心から「本が好きだ」と嘘偽りなく言えるようになった。本が好きならこの章だけは読んでほしい。そう強く思わせるようなエッセイであった。(桜美林大学/たつる)
-
 『おやつが好き』
『おやつが好き』
坂木司/文藝春秋
この本を楽しむ条件はたった一つ。「おやつが好きだ」ということだけである。著者がこよなく愛するおやつは 、キラキラしているものからどこか懐かしくてあたたかいものまで多岐に渡る。ちょっと疲れて息抜きしたいとき、ぜひ手にとってみてほしい 。色々なおやつが詰まった、とっておきの宝箱を開けるような気持ちで一読できるエッセイだ。ただし、ダイエットをしている方は気をつけて 。読めば読むほど、おやつが好きになります。(信州大学/絲)
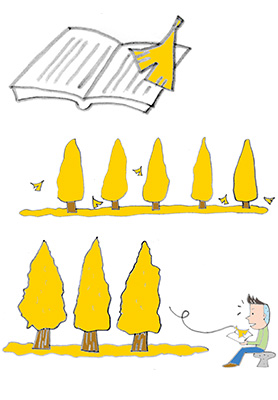
※表記の所属大学は応募時(2019年)の名称です。


