いずみ読書スタッフの 読書日記 165号
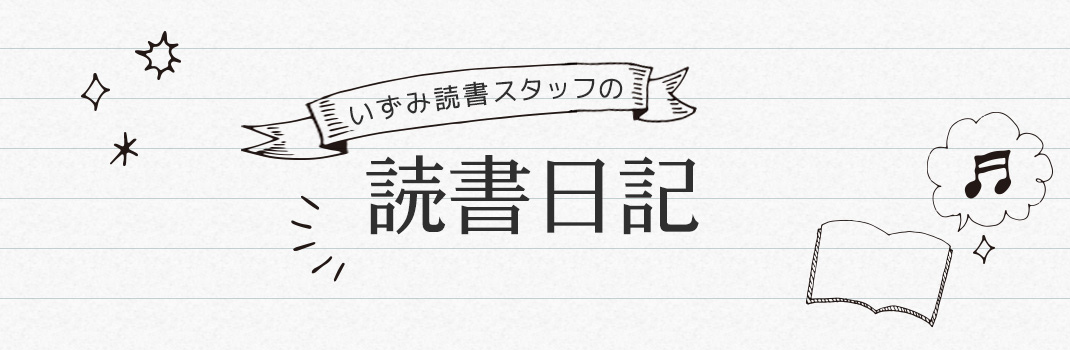
レギュラー企画『読書のいずみ』読書スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
岡山大学4回生 末永 光
九月
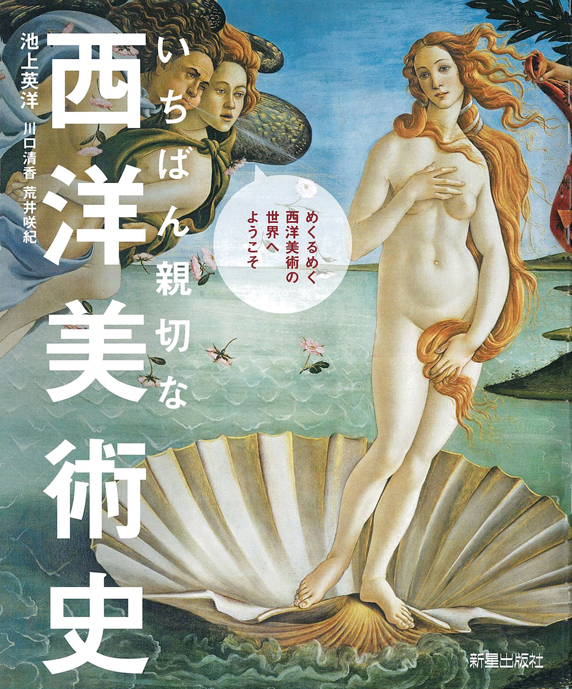 「芸術の秋」をすっ飛ばして生きてきた。小中高とスポーツ三昧、九州の辺境の島暮らしで美術館やその他諸々の文化的施設に縁がないまま生きてきたせいか、大学生になってもその勢いのまま生活が続いた。秋といえば、飯だけが楽しみな季節だった。ところで、通っている岡山大学には素敵な制度がある。なんと、倉敷市にある大原美術館に無料で入れるというではないか。行くしかない!と意気込んだのが二年前の夏である。
「芸術の秋」をすっ飛ばして生きてきた。小中高とスポーツ三昧、九州の辺境の島暮らしで美術館やその他諸々の文化的施設に縁がないまま生きてきたせいか、大学生になってもその勢いのまま生活が続いた。秋といえば、飯だけが楽しみな季節だった。ところで、通っている岡山大学には素敵な制度がある。なんと、倉敷市にある大原美術館に無料で入れるというではないか。行くしかない!と意気込んだのが二年前の夏である。美術館を訪れてみると、ふむ、美しい。うつくしい……。非常にボヤッとした感想を持ったのを覚えている。しかし、たいして勉強するわけでも、理解しようとするまもなく、普段の生活に戻ってしまい二年の月日がたった。
今回、一念発起して美術を勉強してみようと読んだのが『いちばん親切な西洋美術史』(池上英洋ほか/新星出版社)だ。いちばん親切な、と謳うだけあり、イラスト解説や作品の画像もふんだんに使われている。わかりやすい。
読了してからは、まだ大原には行けていない。知識の眼鏡をかけて、もう一度美術館を回れば、芸術のより深い部分へ触れられるはず。楽しみである。
十月
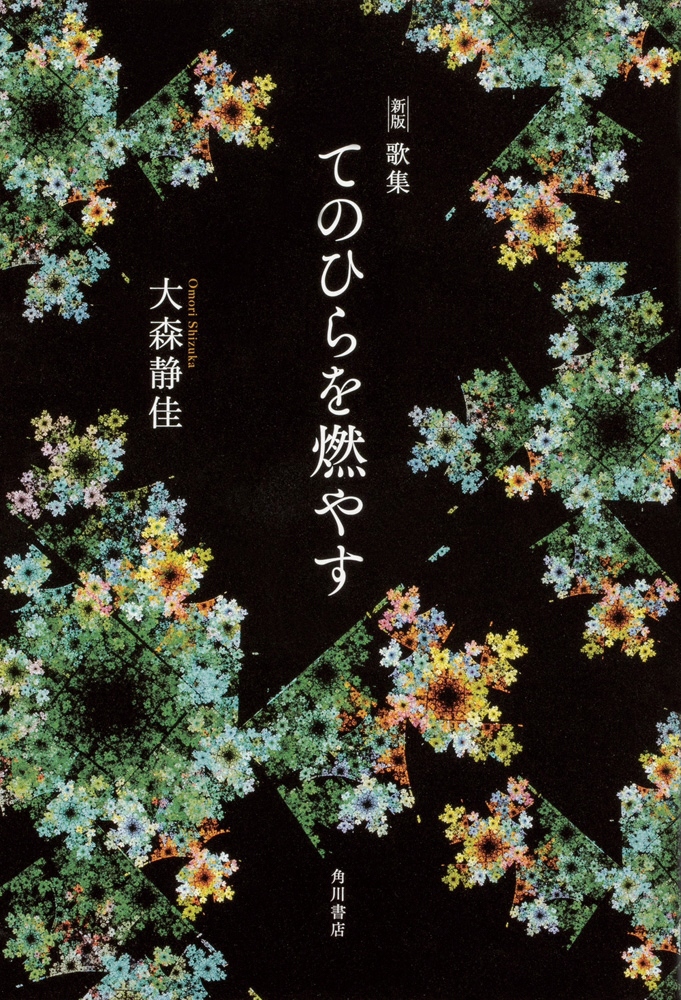 塗り絵のように暮れてゆく冬 君でないひとの喉仏がうつくしい
塗り絵のように暮れてゆく冬 君でないひとの喉仏がうつくしい冒頭の一首は『てのひらを燃やす』(大森静佳/角川書店)のなかに載っている短歌。大森静佳さんの歌の中でも、最も好きなものの一つ。好きな理由を言語化するのは、ムズカシイ。あえて言葉に表すならば、幻想的な冬の様子からの、視点の移動、イメージが完璧にちかい場所でおちついている様子、語彙のうつくしさに惹かれるのだろう。
すぐれた短歌を鑑賞する行為は、歌を通して、歌人の視点を借りることだ。
「塗り絵のように暮れていく冬」という表現をみることで、そんなふうに世界が映るようになる。今までになかった色彩の表現だ。きっとこの歌を知ってからの冬は、より白くて柔らかい。
そして勉強するまでは気づいていなかったが、絵画や彫刻を観ることもかなり近い効果をもつはずだ。モネやシニャックの眼を通して当時の光のようすを感じることや、ゴヤの絵で人々の怒りや哀しみに触れることも、また作者の視点を通して世界に触れることだと言えると思う。
自分ひとりだけの眼だけで生きていたらもったいない。表現者たちの視点を借りながら、世界のうつくしいものにもっと触れていきたい。そう思った十月であった。
最後に大森さんの短歌で好きな一首を紹介して、筆を置く。
比喩としてしか燃えない空に生かされて眼の高さまで沈める帽子
京都大学大学院M1 畠中 美雨
9月上旬 眠れぬ秋の夜長に
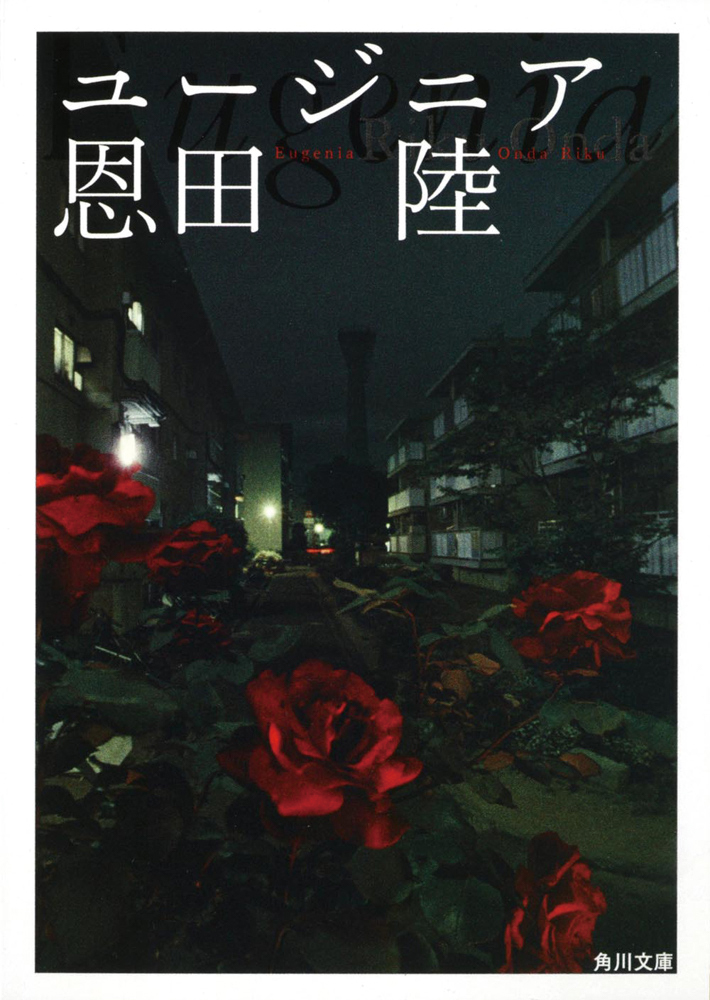 163号の「BLUE」特集を読み恩田陸さんの『ユージニア』(角川文庫)を思い出した。 寝付けない夜に、そうだ読み返そうと開く。
163号の「BLUE」特集を読み恩田陸さんの『ユージニア』(角川文庫)を思い出した。 寝付けない夜に、そうだ読み返そうと開く。旧家で起きた未解決の大量毒殺事件。その真相と犯人を突き止めるべく様々な人物の視点から事件が語られるが、犯人や事件の真相は明記されず、その後の事件についても言及されないまま物語は終わる。こう書くと途中で消化不良になりそうだが、飽きさせず読ませるのが恩田さん。
読み終えて、たてた自分の仮説を何年も前のブログ内の仮説と比較するのも楽しい。時間を越えて顔も知らない誰かと読みあえる幸せ。……おっと、空が白みはじめた。
10月初旬 読書の秋、積読の秋
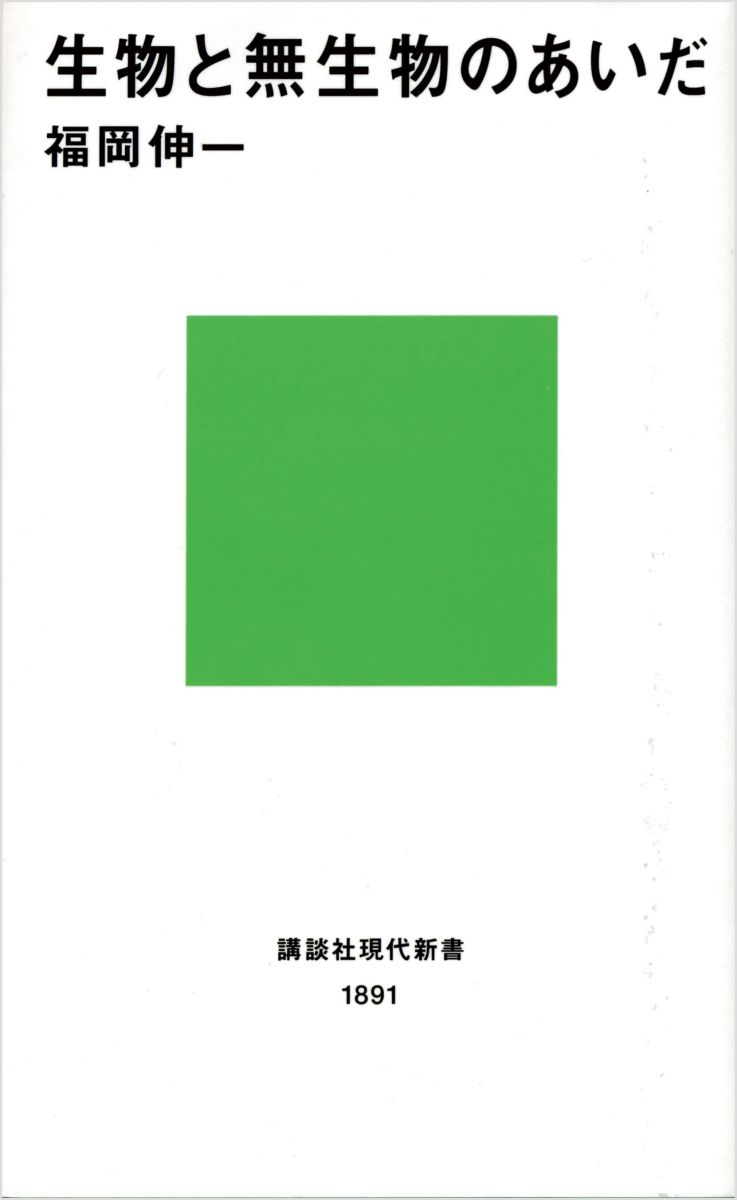 ひとくちに積読といっても、認識している本としていない本がある。後者の彼らには、ある日棚を整理したり、はたまた今回のように勧められたりしてようやく再会する。この度相見えたのは福岡伸一さんの『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)。
ひとくちに積読といっても、認識している本としていない本がある。後者の彼らには、ある日棚を整理したり、はたまた今回のように勧められたりしてようやく再会する。この度相見えたのは福岡伸一さんの『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)。「生命とは何か」を追求するノンフィクションミステリーとでも言おうか。推理小説よろしく、裏の駆け引きなどハラハラする研究者らのダークな一面や、研究手段を砂遊びに擬えられるその文章力、ストーリーが飽きさせない。読み物として楽しめ、折しもウイルスが蔓延している現在引き込まれやすさ満点、かつ新しい知識も学べて誰かに話したくなる一冊。
こうして、自分にとって最適なタイミングで出会えるから、やっぱり積読肯定派。
10月下旬 暖房をつけるか悩む頃
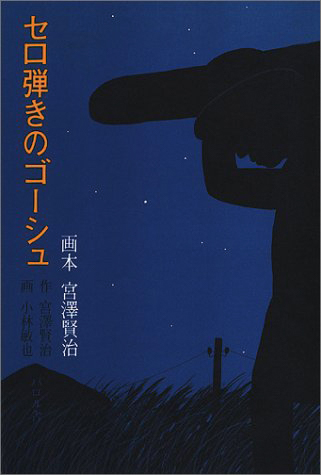 こんな話だったっけ? 宮澤賢治さんの『セロ弾きのゴーシュ』(パロル舎)を読んで驚いた。 “真夜中に動物たちがやってきて演奏を聴き、そのおかげで演奏会も成功する” という和やかな話だと記憶していたが、実際はゴーシュの姿を通して、やってきた猫やかっこうに八つ当たりをする人間の残虐さ、すべて上手く終わってから、ひとりごちて謝る狡さが描かれていた。国語の授業のようにして心理描写を事細かく追いたくなったのは久しぶりだった。
こんな話だったっけ? 宮澤賢治さんの『セロ弾きのゴーシュ』(パロル舎)を読んで驚いた。 “真夜中に動物たちがやってきて演奏を聴き、そのおかげで演奏会も成功する” という和やかな話だと記憶していたが、実際はゴーシュの姿を通して、やってきた猫やかっこうに八つ当たりをする人間の残虐さ、すべて上手く終わってから、ひとりごちて謝る狡さが描かれていた。国語の授業のようにして心理描写を事細かく追いたくなったのは久しぶりだった。また絵本から遠く離れて何年も経つが、こんなに強く語りかける力を持っていたとは。絵の力にも圧倒された。
*****
振り返ると、この秋は再読ブームかも。呼び出して手にとれば、いや忘れていても何度でも自分に語りかけてくれる本。本っていいなぁと再確認した秋でした。
京都大学3回生 徳岡柚月
サツマイモの日

今日はお目当ての本があるので、まずはパソコンで蔵書検索。最近よくお世話になっているウェブサイトで紹介されていて、気になっていた『鳩の撃退法』(佐藤正午/小学館文庫)。結果は……「貸し出し中」。やっぱり人気があるんだな~、もしかして同じウェブサイトを見た人が借りてるのかも。仲間だな。まあそれはともかく、今回は佐藤さんの別の本を借りてみよう。佐藤さんの作品、まだ読んだことがないんだよな~。初めましての作家さんの本を読むのはすごくわくわくする。どれにしようかな。
統計の日
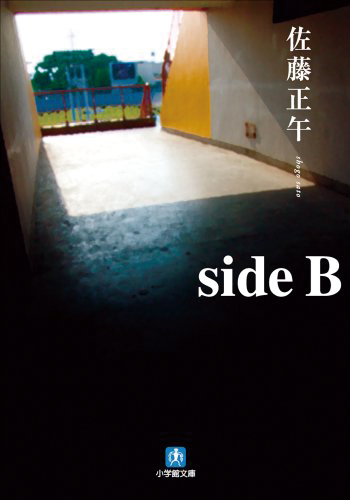 『side B』(佐藤正午/小学館文庫)読了。 この前図書館で借りた中の1冊。佐藤さんの競輪ファンとしての顔が見られるエッセイ集。あの日は結局少し考えて、佐藤さんの本はまずエッセイからスタートしようと決め、エッセイ集を2冊借りた。いきなりB面(競輪ファンの面)から入るのもおもしろいけど、A面(もう1冊のエッセイ集)→B面という王道ルートを取った(エッセイから入っている時点で王道ではない気はするけど)。わたしにとっては競輪も未知の世界なので、少しどきどきしながら読み始めたのだけど、文章のおもしろさと好きなものを語るときの熱量に引き込まれ、気づくと夢中でページをめくっていた。いつか生の競輪を見てみたいなぁ。
『side B』(佐藤正午/小学館文庫)読了。 この前図書館で借りた中の1冊。佐藤さんの競輪ファンとしての顔が見られるエッセイ集。あの日は結局少し考えて、佐藤さんの本はまずエッセイからスタートしようと決め、エッセイ集を2冊借りた。いきなりB面(競輪ファンの面)から入るのもおもしろいけど、A面(もう1冊のエッセイ集)→B面という王道ルートを取った(エッセイから入っている時点で王道ではない気はするけど)。わたしにとっては競輪も未知の世界なので、少しどきどきしながら読み始めたのだけど、文章のおもしろさと好きなものを語るときの熱量に引き込まれ、気づくと夢中でページをめくっていた。いつか生の競輪を見てみたいなぁ。
世界パスタデー
.jpg) 『毒きのこに生まれてきたあたしのこと。』(堀博美/天夢人)読了。これも『side B』と一緒に借りた本。夏に菌類の研究室見学に行って以来、わたしの中では菌類がアツイので、図書館で背表紙が目に入った瞬間すっと手にとってしまった。表紙のヒグチユウコさんのかわいらしいけどどこかぞっとする画もすてきだ。毎年毒キノコを食べてヒトが亡くなったというニュースが絶えないことが示すように、毒キノコにはヒトを引きつけて止まない魔力を持つ。生きていく上でなんの得もないはずなのに、なぜヒトは危険とわかっているものに神秘的な美しさを感じるんだろう。不思議だなぁ。
『毒きのこに生まれてきたあたしのこと。』(堀博美/天夢人)読了。これも『side B』と一緒に借りた本。夏に菌類の研究室見学に行って以来、わたしの中では菌類がアツイので、図書館で背表紙が目に入った瞬間すっと手にとってしまった。表紙のヒグチユウコさんのかわいらしいけどどこかぞっとする画もすてきだ。毎年毒キノコを食べてヒトが亡くなったというニュースが絶えないことが示すように、毒キノコにはヒトを引きつけて止まない魔力を持つ。生きていく上でなんの得もないはずなのに、なぜヒトは危険とわかっているものに神秘的な美しさを感じるんだろう。不思議だなぁ。

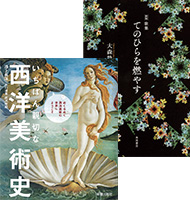 岡山大学4回生 末永 光
岡山大学4回生 末永 光 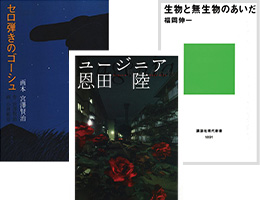 京都大学大学院M1 畠中 美雨
京都大学大学院M1 畠中 美雨 .jpg) 京都大学3回生 徳岡柚月
京都大学3回生 徳岡柚月 
