読書マラソン二十選! 169号
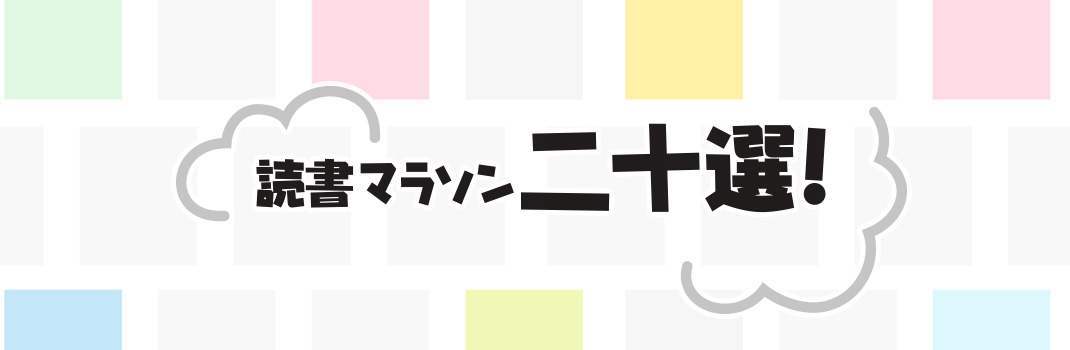
今年もまた、寒〜い冬がやってきましたね。年末年始は何かと賑やかなイベントが目白押しですが、お部屋の中で温かいお茶でもすすりながら静かに読書に浸るのもいいでしょう。今回も2020年の全国読書マラソコメント大賞受賞作品のなかから、よりすぐりの20作品をお楽しみください。
-
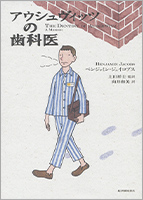 『アウシュヴィッツの歯科医』
『アウシュヴィッツの歯科医』
ベンジャミン・ジェイコブス
〈上田祥士=監訳、向井和美=訳〉/紀伊國屋書店
今まで自らユダヤ人迫害の歴史について触れることはなかったが、タイトルに対して可愛らしいイラストに惹かれ手に取った。残酷な非日常だけではなく、彼なりの奇跡、そして恋。それまでは、迫害の歴史には残酷というイメージしかなかった。しかしそこには今、私たちが送っている日常と変わらないものもあったことに驚く。そして、「あのようなことが自分に、一度しかないこの人生に起こったことは、いまだに信じられない」終盤に書かれているこの一文に私は胸を衝かれた。簡単に相槌なんて打てない。忘れられない一文になった。(法政大学/朔)
-
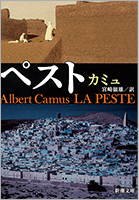 『ペスト』
『ペスト』
カミュ〈宮崎嶺雄=訳〉/新潮文庫
「自分でそれを望もうと望むまいと。この事件はわれわれみんなに関係のあることなんです」−−突如降って湧いた不条理によって今までの日常から切り離され、過去の幻想と今の孤独との対比に懊悩する。ペストによって閉鎖された町の市民たちのこの苦悩は、今の我々にとっては想像に難くないだろう。愛する者との別離、忍び寄る死の病の足音。それらの苦しみの中で懸命にペストと闘う者たちの姿は、我々が今直面する状況にどう向き合うべきかを雄弁に訴えかけているように思われる。ペストは繰り返す。この言葉が、時代を超えて心に深く突き刺さって離れない。(名古屋大学/ふずりな)
-
.jpg) 『センス・オブ・ワンダー』
『センス・オブ・ワンダー』
レイチェル・カーソン〈上遠恵子=訳〉/新潮文庫
本書を読んで改めて思ったのは、著者であるレイチェル・カーソンが如何に地球を愛していたかということである。そして何か別のことにも気づかされた。そう、私は今まで、子どものように豊かな感性、好奇心を持っていた大人を無意識に慕っていたのである。おそらくこれは、こういう大人でありたいという私の願望でもあるのだろう。やはり思うのは、大人は決して「子どものこころ」を忘れてはいけないのだ。私も、「センス・オブ・ワンダー」を一生涯失わずに生きていきたいものである。(慶應義塾大学/桑原 茂夫)
-
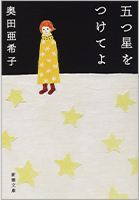 『五つ星をつけてよ』
『五つ星をつけてよ』
奥田亜希子/新潮文庫
自分が「好き」と信じたものを、貫き通すのはこんなにも難しくなったのか。SNSの普及で、考えなくてもいい心配が増えた気がする。誰が決めつけたかわからない評価を気にして、買い物も、友好も、恋も、全て面倒くさく感じてしまう世界になった。第三者の声なんかいらない。私は私のまま、自分の意見に自信を持たなくてはいけない。誰がなんと言おうと、他人からの評価を気にせず、自分の気持ちを一番に信じようと思った。(愛知大学/ゆずもも)
-
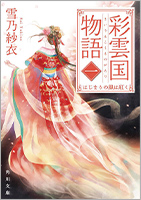 『彩雲国物語 一 はじまりの風は紅く』
『彩雲国物語 一 はじまりの風は紅く』
雪乃紗衣/角川文庫
王が全く政治しようとしないことを知り、主人公は「期限付きの妃」の仮面を被って教育係を引き受けるところから物語は始まる。一見「ラノベ出身作品」という偏見を持ちそうになるが、読んでみると、世の中の男女の格差を知ってなお、女の自分に出来ることを模索するその姿は同性の私にとても響いた。そして後に彼女は妃を辞め、女性初の官吏となる。数々の苦難が待ち受けるが、よりよい世の中をつくりたいと願う彼女がこれからどんな人生を歩んでいくのか、まるで自分も彼女と一緒に生きているような気持ちになる。個人的に、是非女性に読んで欲しい作品だ。(甲南大学/ゆずこしょう)
-
 『小さき者へ/生れ出ずる悩み』
『小さき者へ/生れ出ずる悩み』
有島武郎/岩波文庫
私はある職業に就くために大学で勉強をしている。しかしその職業とは別に、「こんなことをして生きていけたら」と思う職業がある。
この本に登場する「君」は、画家を夢見る貧しい漁夫である。彼は自分の夢と貧困、己の才能に対する不安の中で揺れる。
夢を持つことは生きる希望にもなるが、呪いにもなり得る。迷い続け、何者にもなれぬままの人生かもしれないのだ。夢を追うにしても追わないにしても、心残りは生まれる。
これからきっと何度も他の道を思う私への戒めのようだった。(北海道大学/木口了一)
-
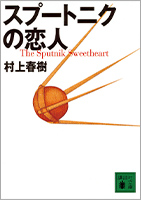 『スプートニクの恋人』
『スプートニクの恋人』
村上春樹/講談社文庫
初めて、村上春樹の本を手に取った。なぜ村上春樹が世界でも評価されているのか、その答えはこの本にあると感じた。あまりにも描写がリアルで読んでいて何度赤面したことか。物語は恋愛ファンタジーにして、最大のミステリー小説だ。一体誰がスプートニクの恋人なのか。主人公すみれか、すみれが恋心を抱くミュウか、それとも語り手の僕なのか。もしかしたら、この本に夢中になっている私自身なのかもしれない。村上春樹に恋してしまった。(日本女子大学/いちご)
-
 『本日は大安なり』
『本日は大安なり』
辻村深月/角川文庫
この物語を担う語り手達には共通点がある。それは、同じ日同じ場所で、それぞれの思い込みを誰かに解かれたという点だ。結婚式という、人生が変わる一大イベントを舞台に、「主役」でない人達が人知れず誰かに出会い、己の価値観を変えていく。人生を本当に変えるものは大きなイベントではなく、小さな出会いの積み重ねなのかもしれない。事実、後日談では少しずつ語り手たちの人生が動いているようであり、さらに先の未来を想像せずにはいられない。この物語は、ハラハラする展開の裏に、人間の愛おしさが溶け込んでいる尊い物語なのだ。(早稲田大学/y0d)
-
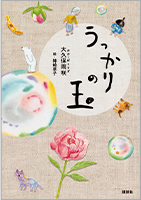 『うっかりの玉』
『うっかりの玉』
大久保雨咲〈陣崎草子=絵〉/講談社
年を重ねることをネガティヴに捉えがちだ。物忘れが多くなるかもしれないし、顔にシミやシワが増えるかもしれない。でも、それらが全て愛おしいものに変わった。うっかり物忘れをした時は、小さなかわいい女の子がそれをしゃぼん玉に替えて集めているかもしれない。もし大切な人と離れ離れになっても、死後小さくなって一緒に孫の顔を覗いているかもしれない。年をとることが何より素晴らしく、楽しみに満ちていることに気付いた。毎年誕生日を迎えるごとに、この本を読み返していきたい。そして、私はその幸せをじっくり噛み締めるのだ。(大阪大学/光岡諒彦)
-
 『熱帯』
『熱帯』
森見登美彦/文春文庫
一冊の本を巡って様々な年代の、全く違う人たちが集まり、繋がる。読書は決して孤独ではないと感じました。同じ本を共有し、語ることができる。たとえ語らなくても、一冊の本の向こう側には多くの人がいる。そんなことを教えてくれました。大学生になってから「本をたくさん読まなくては」と焦っていた私に、改めて読書することの楽しさを思い出させてくれました。「面白い小説が読みきれないほどあるということはそれだけで無条件に良いこと、それだけでステキなこと、みんなよく頑張った、人類万歳!」(早稲田大学/めんたいこ)
-
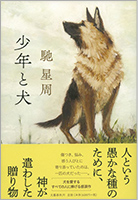 『少年と犬』
『少年と犬』
馳星周/文藝春秋
少年と犬までのすべての物語は、多聞の、光を想うきもちからの壮大な旅路であった。この世に実体がなくなっても、生きているものは亡くなったものを心の中で生かすことができる。最後の最後、光の一言で気づかされ、物語に登場したすべての人も誰かの心の中で生き続けているのだろうと思い、救われた気がした。私自身も、幼い時ずっと一緒だった飼い犬が亡くなってからもう15年たったが、今でも、いるな、見てくれているなと思う瞬間がある。物語の中で多聞に出会ったすべての人も多聞のことを忘れないだろう。もちろん、読者の私も。(麻布大学/meer)
-
 『先生と私』
『先生と私』
佐藤優/幻冬舎文庫
大学に行く価値の一つは尊敬できる先生と出会うことにある。もし大学の4年間を費やして尊敬できる先生に出会えなかったとしたら、控えめに言って大学での学びの半分は放棄している。
本書は著者である佐藤優が人生で出会った、尊敬できる先生たちとの交流を描いている。教育と聞くと、カリキュラムやら参考書の内容の充実度などに目が行きがちだ。しかし教育の本質は人から人に影響されて学ぶことだ。そんな影響されるべき先生に出会っている人も、まだ出会っていない人も目標を見つけられる一冊だ。(東京経済大学/内田充俊)
-
 『仕事としての学問
『仕事としての学問
仕事としての政治』
マックス・ウェーバー〈野口雅弘=訳〉
/講談社学術文庫
今から100年以上前、ウェーバーが残した言葉は現代日本の政治に問を投げかける。政治と行政の境目は何か。「政治主導」と叫ばれるようになってから久しいが、未だに国会答弁では官僚が大臣の答弁を考え、常に後ろに控えている。政治を行なっているのは一体誰であるのか。
昔の人の言葉を知ることは新しい考えを知ることにもなる。100年経った今だからこそ、その言葉の重みを感じるのだ。(名古屋大学/みらい)
-
 『青の数学』
『青の数学』
王城夕紀/新潮文庫
真っ白な紙に一行の数式。これを解けと言われても、情報が少なすぎないか……? 私の頭も真っ白になり、何もできずに解答時間が終わる。私は数学が苦手だ。正直、数学が好きな人の考えが理解できなかった。この本に出合うまでは。
真っ白な紙に数式が一つ。そこからただ一つの答えに向かって突き進んでいく。登場人物たちが解答を導き出す時間は宇宙を彷彿させるほど美しく、自由で、神秘的だ。数学の美しさを垣間見て、今は少し、ほんの少しだけ数学のことを好きになれた気がする。(立命館大学/ゆず)
-
 『君の悲しみが美しいから
『君の悲しみが美しいから
僕は手紙を書いた』
若松英輔/河出書房新社
震災によって大切な人を亡くし、耐えがたい悲しみに直面している全ての人に向けて、著者が送る11通の手紙。愛する人との別離は、身が砕かれるほど苦しく悲しいものですが、著者である若松氏はその悲しみの中に、決して損なうことのできない貴さがあると述べています。若松氏が紡ぎだす温かい言葉の数々は、不安や悲しみの淵に立つ私たちにそっと寄り添い、また道を指し示す光のように感じました。若松氏の綴る日本語の美しさに感動すると同時に、私もまた若松氏の言葉に救われ、今日もまた愛しみの中で精一杯生きていこうと思いました。(東京農工大学/kei)
-
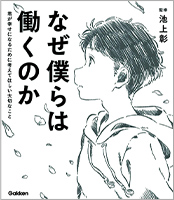 『なぜ僕らは働くのか』
『なぜ僕らは働くのか』
池上彰、佳奈、モドロカ/学研プラス
大学に入学してから約半年経ったが、再来年には就職活動を控えていることを早くも考え始め、不安になっていたときにこの本を見つけた。大人になったらなぜみんな働くのか、みんな楽しくてその仕事をしているのか、働かずに生きる方法はないのか、毎日汗水垂らして働いている大人たちをみて自分の将来について、不安な気持ちや戸惑いを感じていた。しかしこの本を読んで今まで抱いていた未来へのマイナスな気持ちが少し軽くなり、将来が楽しみになった気がした。同じようなことを感じている学生がいたら是非読んでみてほしい。(東京理科大学/わんわん)
-
 『原因を推論する』
『原因を推論する』
久米郁男/有斐閣
普段生活している中で目にする様々な現象やデータに対して、私達は自然とその原因を推論し、時に自分にあてはめてみようとしているものだ。「ピアノを習っている人は成績がいい」と初めて聞いたときは、自分もピアノを買ってもらおうと思ったのを覚えている。しかしピアノと成績に因果関係があると考えるのが早計であるということが、本書を読むことでより明確になってきた。「個人的なことは政治的だ」という言葉もある通り、身の回りには政治的現象が転がっている。これらの原因を推論する時、本書の方法論を実践してみたい。(東京大学/3days ago)
-
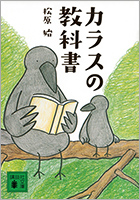 『カラスの教科書』
『カラスの教科書』
松原始/講談社文庫
犬が好き、猫も好き、私は動物が大好きなのだという人は多い。だが、「カラスは好き?」と聞くと多くの人は首を横に振る。
もったいないことだと思う。犬や猫と同じくらいカラスは愛らしくて、人間味があって、面白いのだから。からいものは苦手、好きだった相手にフラれて元気が出ない。これは人間にだけでなくカラスにもあてはまるのだ。どこか人間臭いカラスの姿がこの本の中にある。読み終えるその瞬間、あなたはカラスの魅力に気付くだろう。(千葉大学/きぃ)
-
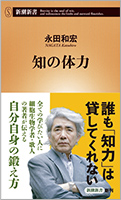 『知の体力』
『知の体力』
永田和宏/新潮新書
私は今まで問題を解くとき答えが合っているかばかりを気にしていた。だから、「社会には答えのある問題はない」という言葉は衝撃的だった。高校までの試験は、答えが必ずあって、その答えに導いてくれる教師がいる。しかし、社会に出ると答えのある問題というのは、実は何一つないと言ってもよい。大学は、この高校と実社会のひずみを埋める役割があると知った。これからは、問題を型にはめたり、答えを他人から与えてもらったりするのではなく、自分の中で考え、答えを見つけられるよう、大学生としての時間を過ごしていきたいと思った。(東京薬科大学/ちー)
-
 『すごい物理学講義』
『すごい物理学講義』
カルロ・ロヴェッリ
〈竹内薫=監修、栗原俊秀=訳〉/河出文庫
シンプルな題名だ、というのが私の第一印象だった。内容に関する表記はなく、ただ表紙から宇宙に関する話であることが予想できるのみだ。その私の予想は半分正解で、たしかに宇宙の話もあった。しかし、この本はそれだけに止まらない。時間と空間に関する本だ。
この本は世にも珍しいループ重力理論の一般向けの本だ。物理の話は数式を用いた方が説明しやすい。しかし、一般向けのため、式をほとんど使わず説明している。それでも著者は物理の難問を分かりやすく紹介することに成功している。ベストセラーになったことも十分うなずける。(神戸大学/アップル)
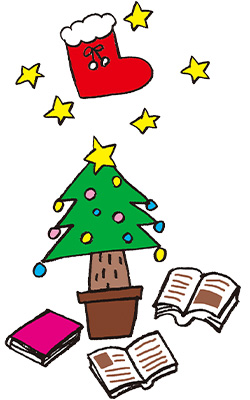
※予告……次号は2021年第17回全国読書マラソン・コメント大賞の選考結果をお届けします。


