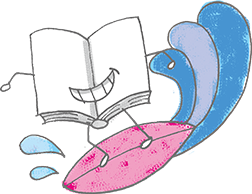読書マラソン二十選! 171号
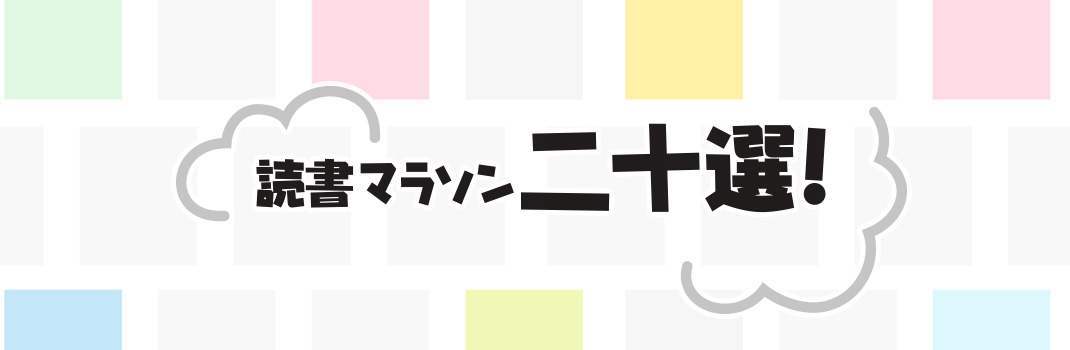
第17回全国読書マラソン・コメント大賞のナイスランナー賞受賞作品の中から、エッセイ、小説から、ノンフィクションまで、この夏におすすめの20作品を受賞コメントとともにご紹介します。
-
 『うっかり鉄道』
『うっかり鉄道』
能町みね子/幻冬舎文庫 旅に出たい!!
この本は鉄道旅エッセイです。著者の能町みね子さんと、担当のイノキンさんの旅の記録です。
古い無人駅を目指したり、ぞろ目の切符を買い求めたり、景色を楽しんだり……一冊読むだけでこんなにたくさんの鉄道旅の楽しみ方が分かる本は、あまりないのではないでしょうか。
特に印象に残ったのは江ノ島電鉄の話。線路が通学路になってしまっています! 江ノ電はそこそこ本数があると思うのですが、大丈夫でしょうか?
とにかく鉄道旅がしてみたくなります!(東京農工大学/ぺんぎん)
-
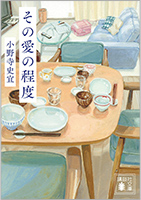 『その愛の程度』
『その愛の程度』
小野寺史宜/講談社文庫 結婚、浮気、離婚、再婚、新しい恋愛、家族愛など、結構内容としてはヘヴィなのに、なぜこんなに淡々としていて柔らかで、暗くもくどくもないのだろう。まさにチーズみたいだ。決してチョコケーキやモンブランではない。でも、あっさりしていても後味は濃厚。愛とは何か、相手の何を好きでいるのか、その愛の程度はどれほどかを色んな場面、側面から考えさせられる。チーズケーキが食べたくなった。(宇都宮大学/みるきー)
-
 『ライオンのおやつ』
『ライオンのおやつ』
小川糸/ポプラ社 残された最期の時間を瀬戸内のホスピスで前向きに過ごす雫や、彼女を温かく囲む登場人物たちは、毎日忙しく走り続けている私に、人生について考える大切な時間をくれた。特にマダムの「こちら側からは出口でも、向こうから見れば入り口になります」という言葉は印象深い。すっと私の心の中に染み渡り、死に対する恐怖を肯定的なものに変えてくれた。良い死に方をするには良い生き方をしなければならず、QOLも QODも変わらないということである。私も雫のように、この豊かな瀬戸内の町で体と心を大切に生きようと思う。(広島修道大学/友愛数)
-
 『エレジーは流れない』
『エレジーは流れない』
三浦しをん/双葉社 「普通」って、誰が決めたことなんだろう? 当たり前のように学校に通って、進路を決めて、気がついたら社会の誰かに決められたようなレールにのって生きている人生。私は私のなりたい姿があるのに、それをあえて遠ざけながらやりたくないことをやっていく人生。きっとこんなの、本望じゃないって分かっているのに。はみ出すことを恐れる多感な時期に、まるで生き急ぐかのように自分のやりたい事を精一杯探す。そんな時に少しでも笑って、このもどかしさを分かってくれる人がいるなら、それは幸せな事だと思った。(愛知大学/りんごぱん)
-
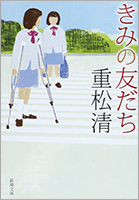 『きみの友だち』
『きみの友だち』
重松清/新潮文庫 「わたしは『みんな』って嫌いだから。『みんな』が『みんな』でいるうちは、友だちじゃない、絶対に」
大学に入学した際、多くの人がたくさんの友だちを頑張って作ろうとしているように見えた。しかし多くの友だちと絡めば絡むほど一人一人との繋がりは薄くなってしまう。そのような考えを私はもともと持っていたためにこの言葉に深く共感を覚えた。大学で大人数で固まって話したりしている人たちよりも、二人で話している人たちの方が充実していて楽しそうに見えるという私の感覚は間違ってなかったのだと、この言葉を受けて確信した。(山口大学/りん)
-
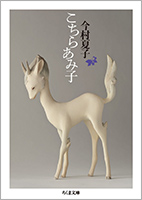 『こちらあみ子』
『こちらあみ子』
今村夏子/ちくま文庫 収録されている3つの作品の中で、一番おもしろいと思ったのは「ピクニック」です。一回読んだだけでは、私はこの物語を理解することができませんでした。しかし、ある視点に気づいて、もう一度読み直してみると「そういうことか」となりました。淡々と叙述されていく物語の中で、一回目には見えなかったニュアンスが浮かび上がってきたり、物語の輪郭自体が変化したりしました。これはちょうど、ミステリー小説を一度読み終えて、犯人がわかった上でもう一度読み返すのと似たような感覚かもしれません。新鮮な読書体験でした。(早稲田大学/ふう)
-
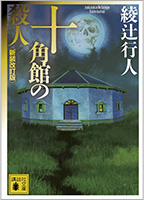 『十角館の殺人』
『十角館の殺人』
綾辻行人/講談社文庫 この本を読んで本当に良かった。大学生の今だからこそ、面白さが倍増して感じられました。何故かというと、登場人物がほぼ大学生だからです。感情移入出来たり、あるいは「同年代なのに!」と行動力に感銘を受けたりして、登場人物の友達感覚で読み進めていました。こんなとき自分ならどうするだろうか、と想像しながら読んでも面白いと思います。また、物語の謎が終盤になって解き明かされるときには恐ろしさで震えてしまいました。犯人の狂気を理解すると途端に怖さが増してきて、今までの親しみやすさが一変、不気味な小説に変化します。(埼玉大学/かもちゃん)
-
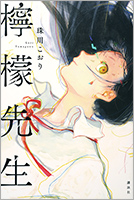 『檸檬先生』
『檸檬先生』
珠川こおり/講談社 とにかく美しかった。この物語は音や数字、人までもが色に見えてしまうという共感覚を持つ小学生の男の子が、同じ共感覚を持つ中学生の女の子「檸檬先生」に出会い、優しくない世界を生きていく話なのだが、色の描写が非常に多い。何せ共感覚を持つ二人にとって世界は色に溢れているのだ。共感覚が原因で二人は異質な存在とされてしまうが、私はこの色に満ち溢れた二人の世界はとても美しいと感じた。(名古屋市立大学/ココア)
-
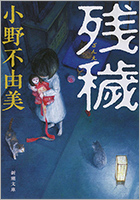 『残穢』
『残穢』
小野不由美/新潮文庫 読み進めるほどに恐怖がじわじわと積み重なっていった。どこまでも果てしなく先が見えない恐怖に逃げ出したいという気持ちがありつつも、それ以上に、読み手の好奇心を掴んで先へと誘うような、物語に引き込む語りの力を感じた。予測のつかなさ、際限の無さの恐ろしさもさることながら、一番の恐ろしさは「もしかしたら自分の身の回りにも存在しているのではないか」と思ってしまうような曖昧さと現実感だと思う。そしてそれは小説という媒体だからこそ成し得る、読み手の想像力を最大限引き出す表現にあると思った。(弘前大学/猪鹿蝶)
-
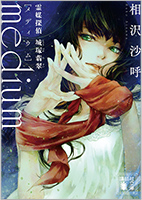 『medium 霊媒探偵 城塚翡翠』
『medium 霊媒探偵 城塚翡翠』
相沢沙呼/講談社文庫 「すべてが、伏線。」いや言い過ぎだろうと。小説のキャッチコピーには少しうんざりしていた。しかし読んでみて実際そうなのだから驚くほかない。日常の謎、ミステリーはすぐ身近にある。ほんの少しの違和感に気づく力、それを自分で考える力、私たちに足りていないものに思える。
なぜ分からないの? この小説は作者からの挑戦状だ。思考停止して検索に走っていては何にもたどり着かない。なんかこの人好きじゃないな、なんて思ったら、そこからよく考えてみる。それが一歩だ。(立命館大学/ひのとみこ)
-
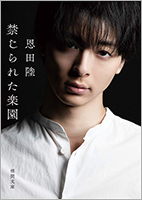 『禁じられた楽園』
『禁じられた楽園』
恩田陸/徳間文庫 著名な芸術家が山奥に造ったという、まるでテーマパークのような美術館に招かれた男女たちは、そこで自らの心の奥底に閉じ込めていた悲劇を目の当たりにすることになる。禁じられた楽園へと足を踏み入れた者たちの心理を描いた幻想ホラー作品。体を突き抜けるような突然の恐怖に駆られるというよりむしろ、歪んだ世界に登場人物たちとともに少しずつ呑み込まれていくような不気味さに耐えられず、つい本から意識をそらして自分の周囲を見回してしまった。巧みな情景描写で読者を物語の世界へと引き込む恩田陸氏の作品を、ぜひご一読いただきたい。(電気通信大学/ポム)
-
 『ニューロマンサー』
『ニューロマンサー』
ウィリアム・ギブソン〈黒丸尚=訳〉/ハヤカワ文庫 ニューロマンサーは詩とハイテク技術が狂暴に絡まり合ったサイバーパンクSFの代名詞に恥じない傑作である。……ただいっておきたいのは、決して読みやすい作品ではないということだ。電脳空間に代表される、現実の延長線ではあるものの、非物質的かつ形而上的なものの描写は、文章で表現するということの極限に挑んでおり、そのパラノイアともいえそうな情報量はまるで雪崩か洪水のようだ。そして、その困難を無事乗り越えられた読者だけが、これまでになかった新しい文学表現の領域を認識することができるのである。(山形大学/千田美咲)
-
 『「普通がいい」という病』
『「普通がいい」という病』
泉谷閑示/講談社現代新書 コロナウイルス感染症の蔓延によって、大学一年時から準備していた交換留学が中止になりました。それ以来私は、留学をする自分を想像するたびに、胸が締め付けられるような喪失感を感じていました。しかし本書175ページを読んだとき、思わず顔を上げて「なるほど!」と声を上げました。自分が感じていた苦しみは、留学が中止になったこと自体ではなく、留学のことだけを考えようとする執着心から来るのだと気づいたからです。本書を読んで、自分の内面を一歩引いて見つめることの難しさと大切さを学びました。(北星学園大学/高岡賢人)
-
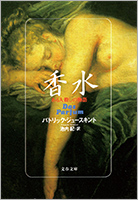 『香水 −ある人殺しの物語−』
『香水 −ある人殺しの物語−』
パトリック・ジュースキント〈池内紀=訳〉/文春文庫 引っ越しで全ての本を譲ることになった時、本作だけはどうしても譲ることができなかった。それほどまでに、本作は私自身を構成している要素のひとつである。
読み終えた瞬間、周りに溢れていた「匂い」が一斉に私に存在を主張してきた。「匂い」には、それぞれ鮮やかな色がついている。粘度もあれば温度もある。飲んで味わうことさえできる。本作を読み終えたあの日から、私にとって「匂い」は嗅覚だけでとらえきれるようなものではなくなった。
今は、日常生活に当たり前に漂っている「匂い」の色や感触を想像するのが、この上なく楽しい。(松山大学/500ml烏龍茶)
-
 『掃除婦のための手引き書』
『掃除婦のための手引き書』
ルシア・ベルリン〈岸本佐知子=訳〉/講談社文庫 愛、宗教、暴力、アルコール、美しいもの、悲しいもの、私のなかのカテゴライズがふにゃっと曲がり融合してだんだん分からなくなる。
あまりに沢山のものを抱え込んだ物語から一つ確かなものをみつけたわけではないけれど、決して何も残らなかったわけではない。
ただ私の心の大きな網目では掬えなかったさらさらとした感情が溜まってきらきらと光っている。
時に高速列車のように恐ろしく、時に溺れるような静けさで、物語は停滞することなく進む。私はその行き先に怯えるが、思いがけない軽やかな衝動で物語は幕をとじていく。(下関市立大学/すやこ)
-
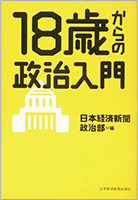 『18歳からの政治入門』
『18歳からの政治入門』
日本経済新聞政治部=編/日経BPM 一票じゃ何も変わらない……そんな考えが変わった。このように考えていた原因は「政治を知らなかったこと」だと思う。政治家、政策、政党……。どれも授業やニュースで聞いたことはあるものの、説明を求められたら答えられない。
この本は、遠い存在だった政治を身近なものに感じさせてくれた。そして選挙とは、様々な立場の人がそれぞれの望む生活を主張できる唯一の機会であることに気づけた。選挙は2〜3割の票が動けば、政治が「変わる」ような仕組みになっているらしい。変わらないと言う前に、ちゃんと考えて投票してみようと思う。(愛知教育大学/すもも)
-
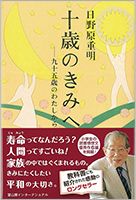 『十歳のきみへ』
『十歳のきみへ』
日野原重明/冨山房インターナショナル 『十歳のきみへ』に出会ったのはちょうど10歳の夏。そして今年、20歳を迎えた私は再びこの本を手に取った。本には10歳の私が引いた鉛筆の線が残されている。これを見ながら「こんな風に考えていたのか、今とはちがうな」と思いをはせる。一方で、10年前と全く変わらない印象は日野原先生の優しくて温かい言葉。先生のメッセージがストンストンと心に刻まれる。
何年経とうと変わらない気持ちもあれば、思いが変化することもある。10年後、20年後の私はこの本を読んで何をどう感じるのであろうか。節目節目に読んで心の変化を味わいたい。(愛知教育大学/えりす)
-
 『戦争は女の顔をしていない』
『戦争は女の顔をしていない』
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ〈三浦みどり=訳〉/岩波現代文庫 戦争と女性。私の中でこの二つはほど遠いものだった。髪の毛を切り落とし、男性と同じ服装をし、戦地に赴く女性たち。そこには、決して一括りにできない一人ずつの戦争体験がある。名前を持った一人一人が語る彼女たちの戦争は、果てしなく重く、終わりがなかった。終戦後もひたすら口を閉ざし続けた彼女たちの叫びが、声が、事実が、つまりノンフィクションが、物語になることをこの本を通して知った。(早稲田大学/めんたいこ)
-
 『パンセ』
『パンセ』
パスカル〈前田陽一、由木康=訳〉/中公文庫 「人間は考える葦である。」中学生の時から人間とは何かということをぼんやりと考えていた私にとってこの言葉はまさに青天の霹靂であった。この言葉を求めて『パンセ』を読み始めた結果、今までにない人間の捉え方に出会った。人間の偉大さと矮小さ、精神と身体といった相反する二つの観点から人間を捉えることによって正解や不正解は表裏一体であり、全てがあり得る解であることを教えられた。この本を読んだことで今までに認められなかった考え方などを容認できるようになったため、この本に出会えたことを非常に嬉しく思っている。(愛知教育大学/愛知)
-
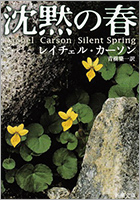 『沈黙の春』
『沈黙の春』
レイチェル・カーソン〈青樹簗一=訳〉/新潮文庫 59年前に書かれた本は今も警鐘を鳴らしていると感じました。人間が生み出した化学薬品によって人間だけでなく多くの生命が命を落としました。当然科学によって人間が有利に立ち、駆除などによって暮らしやすい世の中になりました。しかし、その代償として自然環境を崩壊させた事実も残ります。現在も自然環境の保護へ全力を尽くす人たちがいます。この本によって科学が起こす悲劇を知り、少しでも自分でできる事を行動につなげるべきと感じました。私は文系ですが科学の知識をつけて環境問題に関心を寄せることから始めたいと思います。(法政大学/シャンシャンシャン)