いずみスタッフの 読書日記 173号 P2
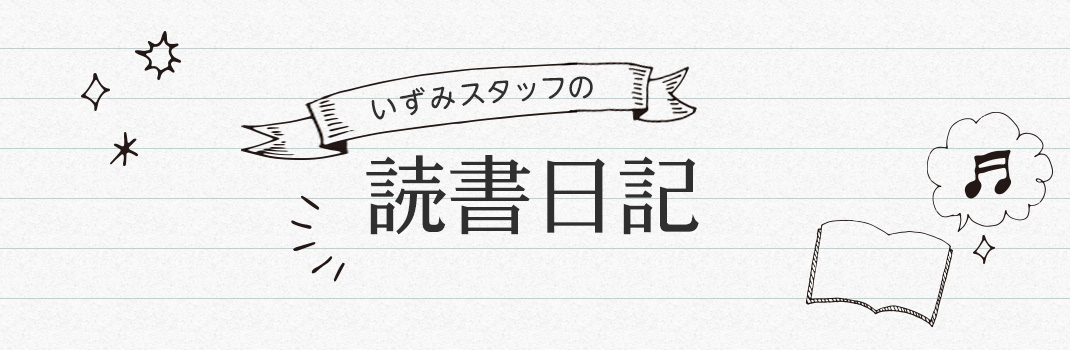
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
東京工業大学2年 中川倫太郎
十月初旬
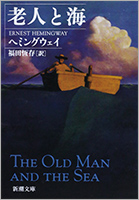 カポーティなりカフカなりドストエフスキーなり、海外文学を語る上で欠かせない作家は幾人もいるだろうが、読書習慣を後天的に身につけた僕はそういう素養がすっぽりと抜け落ちている。基礎のない応用ほど頼りにならないものはないので、とりあえず『老人と海』(ヘミングウェイ〈福田恆存=訳〉/新潮文庫)を読むことにした。
カポーティなりカフカなりドストエフスキーなり、海外文学を語る上で欠かせない作家は幾人もいるだろうが、読書習慣を後天的に身につけた僕はそういう素養がすっぽりと抜け落ちている。基礎のない応用ほど頼りにならないものはないので、とりあえず『老人と海』(ヘミングウェイ〈福田恆存=訳〉/新潮文庫)を読むことにした。日本人にとって一番身近で一番厳しい自然、海。海は少しの油断も見逃さず、あっという間に僕らを飲み込み、自然に還してしまう。有島武郎の『生れ出づる悩み』は、日本語の美しさ難しさを駆使することで海の存在感を誇示した。対してヘミングウェイの『老人と海』は、単純な表現を極めることで人間の(無)意識を浮き彫りにした。ふたつの作品の焦点の違い。
十月中旬
 東工大の一年生は全員「立志プロジェクト」という文系教養科目を取らされる。賛否はあるけど、僕はこの授業が好きだった。文系を知らない理系はつまらないから。この講義の最終課題は指定図書の書評で、図書ラインナップの中に『苦海浄土』(石牟礼道子/講談社文庫)があったのを覚えている。単位関係ないけど読もうか。
東工大の一年生は全員「立志プロジェクト」という文系教養科目を取らされる。賛否はあるけど、僕はこの授業が好きだった。文系を知らない理系はつまらないから。この講義の最終課題は指定図書の書評で、図書ラインナップの中に『苦海浄土』(石牟礼道子/講談社文庫)があったのを覚えている。単位関係ないけど読もうか。五体満足、公害とも無縁で生まれてきた僕らは、水俣病患者の言葉にならない気持ちを一言一句正確に理解することはできない。理解はできないけれど、共鳴はできる。「魂の文学」とも評されるこの本は共鳴の本だ。一人の小さな主張も千人が一同に発すればそれは大きな声となる。共鳴は共鳴を呼び、優しい響きが全球を包んだまさにそのとき、象は微笑み、太平の世が訪れるだろう。
十月下旬
.jpg) 別役実から本格的に演劇の世界にのめりこんだ僕からすると、アングラ演劇の旗手たる唐十郎は外せない。テント劇場の内部で繰り広げられるエネルギッシュな演劇は唯一無二。今度演劇部の有志で唐組の紅テント公演を観に行く予定だ。
別役実から本格的に演劇の世界にのめりこんだ僕からすると、アングラ演劇の旗手たる唐十郎は外せない。テント劇場の内部で繰り広げられるエネルギッシュな演劇は唯一無二。今度演劇部の有志で唐組の紅テント公演を観に行く予定だ。演劇は「観る」以外に、戯曲を「読む」ことでも楽しめる。『唐十郎Ⅰ 少女仮面/唐版 風の又三郎/少女都市からの呼び声』(唐十郎/ハヤカワ演劇文庫)で僕は唐戯曲をはじめて読んだ。小便臭い下町と詩的な幻想世界がクロスオーバーする世界観、ダイアログは四方八方に空中浮遊、たまの言葉遊び。とにかく難解でも、読み進めるうちに慣れるのは語学留学みたいなもの?
千葉大学2年 高津咲希
9月下旬
.jpg) ああ、美術館に行きたいなあ。『妄想美術館』(原田マハ、ヤマザキマリ/SB新書)は私をそんな気持ちにさせた。表題の通り、お二人の妄想がどんどん膨らんでいくのがとても面白かった。ティツィアーノ・ヴェチェッリオの「手袋をもつ男」から当時と今のファッション事情にまで話が広がったり、自分が美術館をつくるなら、誰のどんな作品を集めたいかを熱く語ったり……読んでいるだけでワクワクが止まらない。これを機にアート巡りを始めようかしら。
ああ、美術館に行きたいなあ。『妄想美術館』(原田マハ、ヤマザキマリ/SB新書)は私をそんな気持ちにさせた。表題の通り、お二人の妄想がどんどん膨らんでいくのがとても面白かった。ティツィアーノ・ヴェチェッリオの「手袋をもつ男」から当時と今のファッション事情にまで話が広がったり、自分が美術館をつくるなら、誰のどんな作品を集めたいかを熱く語ったり……読んでいるだけでワクワクが止まらない。これを機にアート巡りを始めようかしら。
10月上旬
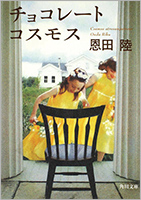 「演劇」がテーマの小説を読みたくなり、『チョコレートコスモス』(恩田陸/角川文庫)を手に取った。夢中になって読み終えると、演劇がもっともっと好きになっていた。演劇は、夢を見ることに似ている思う。芝居が始まると、舞台上には全くの別世界が突如として現れ、観客はいつの間にかその世界観にぐっと引き込まれている。幕が下り、気づいた時には舞台上にはもう何もない。でも確かな心の震えと簡単に冷めそうもない興奮が現実なのだと教えてくれる。この不思議な緊張感は演劇の醍醐味だと私は思う。
「演劇」がテーマの小説を読みたくなり、『チョコレートコスモス』(恩田陸/角川文庫)を手に取った。夢中になって読み終えると、演劇がもっともっと好きになっていた。演劇は、夢を見ることに似ている思う。芝居が始まると、舞台上には全くの別世界が突如として現れ、観客はいつの間にかその世界観にぐっと引き込まれている。幕が下り、気づいた時には舞台上にはもう何もない。でも確かな心の震えと簡単に冷めそうもない興奮が現実なのだと教えてくれる。この不思議な緊張感は演劇の醍醐味だと私は思う。この小説では、とある演劇のオーディションが描かれているが、そのオーディションの課題がまったく奇想天外なのである。自分だったらどう演じるか、登場人物たちはどの様にやってのけるのかを考えながら読み進めるのが何とも楽しかった。
10月中旬
 朗読は面白い。視覚の情報は何もないはずなのに、心地よく発せられる言葉の一つ一つに耳を傾けていると、段々と情景が見えてくる。同じ文章でも読み手や読み方によって全く違った印象を与えるのだから、まるで魔法だ。
朗読は面白い。視覚の情報は何もないはずなのに、心地よく発せられる言葉の一つ一つに耳を傾けていると、段々と情景が見えてくる。同じ文章でも読み手や読み方によって全く違った印象を与えるのだから、まるで魔法だ。自分でも朗読をしようと思い立ち、約十年ぶりに本棚から金子みすゞの詩集を引っ張り出した。小学生の頃、先生が音読カードにシールを貼ってくれるのが嬉しくて、毎日読んでいた詩集だ。懐かしい。当時は、シール欲しさにただひたすら元気よく音読をしていたが、今改めて読んでみると言葉の一つ一つが胸に沁みた。心地よい言葉の響きとテンポの良さはあの時感じたそのままだった。
母が素敵な詩集を教えてくれた。『生命は 吉野弘 詩集』(吉野弘/リベラル社)。生き急いでいたら簡単に見過ごしてしまうような、何気ない日常の一瞬を作者は丁寧に綴っている。時には小さな幸せを噛みしめ、時には素朴な疑問を抱き、時にはじっくり考える。そんな豊かなひと時を大事にしたい。
前のページへ

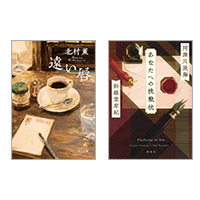 京都大学大学院
京都大学大学院.jpg) 名古屋大学4年
名古屋大学4年.jpg) 東京工業大学2年
東京工業大学2年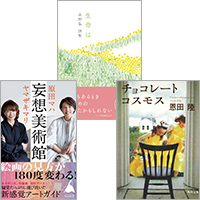 千葉大学2年
千葉大学2年
