日本保険学会の学会誌『保険学雑誌』に大学生協共済連職員藤本昌氏の論文が掲載されました
今年で創立75年を迎える日本保険学会は、1895年設立の「保険学会」を前身としており、 その学会誌『保険学雑誌』は、同年刊行が開始された『月刊保険雑誌』をルーツとして、創刊120周年を迎えます。 このような日本の社会科学系学術研究会の中でも最も古い歴史と伝統を誇る学会の一つである 日本保険学会の学会誌『保険学雑誌』に、大学生協共済連職員の藤本昌氏の論文が掲載されました。 今回、日本保険学会監事で前理事長であり、大学生協共済連理事でもある早稲田大学教授の江澤雅彦先生に、 執筆者である藤本氏よりインタビューを行い、この論文そのものや共済制度などの価値や意味、 今後の方向性などについてお話していただきました。

大学生協共済連職員
藤本 昌 氏
1962年 兵庫県生まれ
1989年 神戸大学経済学部卒業
1989年 大学生協神戸事業連合就職
1999年 全国大学生協連移籍
2010年 大学生協共済連移籍

早稲田大学商学部教授 日本保険学会監事(前理事長) 大学生協共済連理事
江澤 雅彦 教授
1960年 東京都生まれ
1983年 早稲田大学商学部卒業
1991年 早稲田大学大学院商学研究科博士
後期課程満期退学
1995年 八戸大学商学部助教授
1999年 早稲田大学商学部助教授
2001年 早稲田大学商学博士
2004年 早稲田大学商学部教授
藤本 大学生協は大学の中の協同組合で、共済も協同組合保険と言えるものですが、金融商品でありながら大学に属するメンバーが助け合いながら学び合っているというところに特徴があり、「学」というキーワードがあると思います。今後に向けて私をはじめ大学生協、共済団体や実務家のメンバーに対するメッセージをお願いします。
江澤 まず大学生協共済連で、藤本論文に続くものを書いていただく。実際にお仕事されている中で切り口はいろいろある、それはやはり実務家の強みなのです。地に足が着いて、実際の経験にもとづく論文はそこに強みがあるので、実務で思っていることを雑誌に載せてみよう、みんなの前で報告してみようということで続いてもらいたい。
さらに規模の大きいJA共済連や全労済、コープ共済連など、それぞれの特徴や抱えている問題、今後の自分たちの課題などを学会の場で議論していただければと思います。
保険法改正により、契約上は保険も共済も基本的には一緒という時代が来たのです。保険と共済は一つのいわゆる保障マーケットの中で、競争したり補完したりはあっても、共済という協同組合保険と株式会社や相互会社の保険が並立して、保険会社と共済団体とのいろいろな関係性なども、堂々と学会で議論していく時代になった。その皮切りを今回、大学生協共済連の藤本さんがやってくださった。学生に近い、学びに近い方が先頭を切られて、本当にいいきっかけになりました。
藤本 もう一つ忘れてはいけないのは今年1月に急逝した小野寺正純さん、前の専務理事です。ずっと私の論文にお付き合いくださり、何度も何度も読み返して感想や助言を頂きました。小野寺さんとずっと話していたのはやはり「学」というキーワードです。小野寺さんの遺志を引き継ぐためにも、微力ですが私自身も、大学生協のメンバーはもちろん、他の共済団体の皆さんとも連携していきたいと考えています。また、一緒に実務をやっている仲間という意識で、こんな論文でも何かのきっかけになれば嬉しく思います。
江澤 藤本論文の次は、共済推進に関する論文も期待しています。保険学会で行うことに意義がありますね。 協同組合保険は、株式会社・相互会社保険とは違う共済というブロックとして、日本では存在している、ということを学会の場で行なっていただけると、理論面から考える我々研究者と、実務から機能的にやれる皆さん方との協力により、学問的にも進みます。
藤本 日本保険学会の立場で大学生協あるいは学生に対しての期待、メッセージがありましたらお願いします。
江澤 共済や協同組合では、教育、リテラシーの問題があります。自分の入っている共済の内容がよく分からない学生が多いということをお聞きして、まだまだ努力する余地がある、まずみんなに分かってもらう、理解してもらうことをまずやって欲しい。
さらに学生にとっての生活保障全体の問題です。共済金の支払いだけでなく予防の問題、あるいは後遺障害を被った後に就職のサポートができないかという提案を藤本論文でされていましたが、大学生協ならではと思っています。実際に就職の斡旋ができないまでも心配してあげる、共済金給付後どうなっていますか、卒業後のご予定はどうでしょうかということを危惧してあげられることができたら、それは保険会社などの生活保障とは全く違う。事前の教育、給付金の支払い、そして事後のサポートもできたら、本当に総合的な大学生の生活保障制度の構築になるんだと思いました。
保険学会の賛助会員として共済関係の皆さんがせっかくお金を出しているわけですから、今度はアカデミックな面での意見表明もしていただき、その結果をこの保険学雑誌にまとめていただく。保険学会のこれからの歴史を、保険会社、共済団体、そして我々研究者が、それぞれの立場でこれからもさらに刻んでいく、その一つの有力なプレイヤーとして、共済団体の皆様にも活躍してもらいたいと、学会の元代表者として思います。

藤本 大学と一緒に何ができるかも大切なポイントだと思っていますが、そのあたりはいかがですか。
江澤 学生どうしの連携、たすけあいがいかに大切かということを、まずご理解いただくことが重要です。
例えば、病気入院が事故入院の3倍もある、死亡の一番は自殺、メンタルによる入院は女子が多い、など共済団体として給付にもとづくデータがあるので、それを大学幹部の方に「こういうことですよ」と実態をフィードバックして、予防提案として「こういう手が考えられますね」ということで、本当に学生のために共済団体と大学が協力すると、心と体の病の点については情報が集まってくる。そのことを通じて、大学の中での生協の存在、ポジショニングができるのでしょうね。
自転車事故が起きたときに学生がそのルートを調査して、大学に教えたというとりくみのことを聞いたときにああ素晴らしい、地味だけどすごくいいことをしているんだなあ、そういうことがまさに大学生協の共済の役割期待に沿っていることで、本当にいいことだなあと純粋に思いました。
藤本 現役の先輩が、「ヒヤリ、ハッと」した、あるいは実際にケガや病気に遭ってしまった体験をもとに、仲間意識をもって後輩に「気をつけてね」と言うことがまさに参加の本質だと思うのです。
江澤 そうした日々の日常活動の中で、「こういうことが保険会社との違いだ」ということを一つひとつ実証していく、行動に示していくということの積み上げで、生協の共済のアイデンティティが主張できる。各論であり実行、機能的にそれを組み立てていく時代なのかなと思いますね。本当に眼を凝らして大学生協の共済の資料を読むと、ああ、こんないいこともやっているのかと気付いて感動します。
地味ですけどね。実は地味なことが一番大事です。それをやってこそ、大学も動いてくれます。自転車事故の実態を背景に、大学に対し通学路整備等について意見を申し上げる。生協は非営利団体だからこそ、そういうことを大学に堂々と提案されるといいと思います。
藤本 大学の皆さんと本気で一緒になって取り組み、全構成員に同じ意識をもってもらうことが理想です。入学した学生は全員無事に卒業していく、毎年大学と一緒にその繰り返しを実践していく、その一端を担えるような共済団体、協同組合でありたいと思っています。
江澤 大学にたくさん学生が集まって活動する以上は、必ずリスクはあります。だから共済が必要なのですが、そういう生活の中で出てくるリスクを分析して、防止できるものは、学生どうしあるいは大学と協力していくのが生協の役割でしょうね。
藤本 起こってしまったことは、二度と起こらないために、支払事例は必ず有効に活用していく。
江澤 そうすれば掛金を下げられるかもしれない。また共済が普及するかもしれない。
藤本 学生が本当に自立した形で、何らかの役割を果たせるように社会に出ていく、就職するということまでサポートすることが大学や生協の役割だと思います。
大学生協共済連は全国大学生協連とともに2015年6月、「学生の生活リスク講座」を始めました。今後は消費者教育の視点でそれをさらに深めていきます。また、学生の危険やリスクについて、さまざまなテーマにもとづき、学生のために活動されている方々とネットワークを広げていくとりくみとして、実践していきます。
江澤 消費者教育の原点として大学生への保障あるいはリスクの問題で、教育や情報提供をやっていただく、それは大学生協の大きな役割、大きな期待ですね。
藤本 ありがとうございます。消費者教育の原点の役割をも担えるように、頑張っていきます。今後とも、大学生協をよろしくお願いいたします。
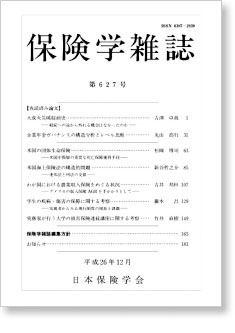
保険学会と『保険学雑誌』

藤本 昌 氏
1962年 兵庫県生まれ
1989年 神戸大学経済学部卒業
1989年 大学生協神戸事業連合就職
1999年 全国大学生協連移籍
2010年 大学生協共済連移籍
藤本 今回初めて私の論文を掲載いただきましたが、日本保険学会とその学会誌である『保険学雑誌』について、学会の前理事長の立場で江澤先生よりご紹介願います。
江澤 日本保険学会は1940年にできて、今年慶應義塾大学で75周年の記念大会を行います。大学で教えている研究者と、その数をはるかに上回る保険の実務家の皆さんからなる学会で、年次大会と関東、関西、九州の各部会で活発に研究報告を行い、そこで報告されたものを原則として『保険学雑誌』に掲載しております。 藤本さんの論文は2014年12月発行の627号に掲載されました。この雑誌も年4回発行や増刊号で号を重ねて、日本の社会科学系学会では一、二を争う古い伝統ある学会です。
1984年入会の私も約30年の会員歴ですが、この雑誌に論文が載って「研究者として一人前になったなあ」と感じたものです。もっと実務家の方の論文もどんどん掲載して、実務家の観点から保険学の研究をやっていただきたいというのが願いで、藤本さんにもしつこいくらいお願いをしたという経緯があります。
江澤 日本保険学会は1940年にできて、今年慶應義塾大学で75周年の記念大会を行います。大学で教えている研究者と、その数をはるかに上回る保険の実務家の皆さんからなる学会で、年次大会と関東、関西、九州の各部会で活発に研究報告を行い、そこで報告されたものを原則として『保険学雑誌』に掲載しております。 藤本さんの論文は2014年12月発行の627号に掲載されました。この雑誌も年4回発行や増刊号で号を重ねて、日本の社会科学系学会では一、二を争う古い伝統ある学会です。
1984年入会の私も約30年の会員歴ですが、この雑誌に論文が載って「研究者として一人前になったなあ」と感じたものです。もっと実務家の方の論文もどんどん掲載して、実務家の観点から保険学の研究をやっていただきたいというのが願いで、藤本さんにもしつこいくらいお願いをしたという経緯があります。
藤本論文の意義

江澤 雅彦 教授
1960年 東京都生まれ
1983年 早稲田大学商学部卒業
1991年 早稲田大学大学院商学研究科博士
後期課程満期退学
1995年 八戸大学商学部助教授
1999年 早稲田大学商学部助教授
2001年 早稲田大学商学博士
2004年 早稲田大学商学部教授
藤本 今回いろいろな方のサポートをいただき本当に感謝しております。神戸大学時代の恩師である水島一也先生はじめ諸先生方のご指導も踏まえて、共済・保険は、事後の保障に加えて、事前の予防サービスも備えることが重要であるという問題意識をもって書かせていただきました。
江澤 今まで学生の生活保障、疾病・傷害の保障について論じられたものがなかった、そういう点でまず大きな意味があります。さらに大学生協の共済以外に学研災や付帯学総と比較をして、それぞれの特徴を論じて、これから補充すべき点はこういう点がありますということを主張されていることは、他の共済団体や保険会社にとっても、我々研究者にとっても、非常に示唆に富む論文であると思いました。
また大学生協の共済は学生が対象ですから、組合員の特定性、同質性という点で、共済の中でもモデルになる一番純粋なものです。JA共済や全労済などはその不特定性が出てきて、現実に近いのですが、参考にする場合にいろいろ付随して考えなければいけないことが多くなってしまいます。大学生協の共済はかなり純粋モデルに近いので、〝理論の学校〟として、研究者としてもこの団体は共済と保険の境界を考えるのに非常にいい題材です。
江澤 今まで学生の生活保障、疾病・傷害の保障について論じられたものがなかった、そういう点でまず大きな意味があります。さらに大学生協の共済以外に学研災や付帯学総と比較をして、それぞれの特徴を論じて、これから補充すべき点はこういう点がありますということを主張されていることは、他の共済団体や保険会社にとっても、我々研究者にとっても、非常に示唆に富む論文であると思いました。
また大学生協の共済は学生が対象ですから、組合員の特定性、同質性という点で、共済の中でもモデルになる一番純粋なものです。JA共済や全労済などはその不特定性が出てきて、現実に近いのですが、参考にする場合にいろいろ付随して考えなければいけないことが多くなってしまいます。大学生協の共済はかなり純粋モデルに近いので、〝理論の学校〟として、研究者としてもこの団体は共済と保険の境界を考えるのに非常にいい題材です。
実務家へのメッセージ
藤本 大学生協は大学の中の協同組合で、共済も協同組合保険と言えるものですが、金融商品でありながら大学に属するメンバーが助け合いながら学び合っているというところに特徴があり、「学」というキーワードがあると思います。今後に向けて私をはじめ大学生協、共済団体や実務家のメンバーに対するメッセージをお願いします。
江澤 まず大学生協共済連で、藤本論文に続くものを書いていただく。実際にお仕事されている中で切り口はいろいろある、それはやはり実務家の強みなのです。地に足が着いて、実際の経験にもとづく論文はそこに強みがあるので、実務で思っていることを雑誌に載せてみよう、みんなの前で報告してみようということで続いてもらいたい。
さらに規模の大きいJA共済連や全労済、コープ共済連など、それぞれの特徴や抱えている問題、今後の自分たちの課題などを学会の場で議論していただければと思います。
保険法改正により、契約上は保険も共済も基本的には一緒という時代が来たのです。保険と共済は一つのいわゆる保障マーケットの中で、競争したり補完したりはあっても、共済という協同組合保険と株式会社や相互会社の保険が並立して、保険会社と共済団体とのいろいろな関係性なども、堂々と学会で議論していく時代になった。その皮切りを今回、大学生協共済連の藤本さんがやってくださった。学生に近い、学びに近い方が先頭を切られて、本当にいいきっかけになりました。
藤本 もう一つ忘れてはいけないのは今年1月に急逝した小野寺正純さん、前の専務理事です。ずっと私の論文にお付き合いくださり、何度も何度も読み返して感想や助言を頂きました。小野寺さんとずっと話していたのはやはり「学」というキーワードです。小野寺さんの遺志を引き継ぐためにも、微力ですが私自身も、大学生協のメンバーはもちろん、他の共済団体の皆さんとも連携していきたいと考えています。また、一緒に実務をやっている仲間という意識で、こんな論文でも何かのきっかけになれば嬉しく思います。
江澤 藤本論文の次は、共済推進に関する論文も期待しています。保険学会で行うことに意義がありますね。 協同組合保険は、株式会社・相互会社保険とは違う共済というブロックとして、日本では存在している、ということを学会の場で行なっていただけると、理論面から考える我々研究者と、実務から機能的にやれる皆さん方との協力により、学問的にも進みます。
日本保険学会の立場から
藤本 日本保険学会の立場で大学生協あるいは学生に対しての期待、メッセージがありましたらお願いします。
江澤 共済や協同組合では、教育、リテラシーの問題があります。自分の入っている共済の内容がよく分からない学生が多いということをお聞きして、まだまだ努力する余地がある、まずみんなに分かってもらう、理解してもらうことをまずやって欲しい。
さらに学生にとっての生活保障全体の問題です。共済金の支払いだけでなく予防の問題、あるいは後遺障害を被った後に就職のサポートができないかという提案を藤本論文でされていましたが、大学生協ならではと思っています。実際に就職の斡旋ができないまでも心配してあげる、共済金給付後どうなっていますか、卒業後のご予定はどうでしょうかということを危惧してあげられることができたら、それは保険会社などの生活保障とは全く違う。事前の教育、給付金の支払い、そして事後のサポートもできたら、本当に総合的な大学生の生活保障制度の構築になるんだと思いました。
保険学会の賛助会員として共済関係の皆さんがせっかくお金を出しているわけですから、今度はアカデミックな面での意見表明もしていただき、その結果をこの保険学雑誌にまとめていただく。保険学会のこれからの歴史を、保険会社、共済団体、そして我々研究者が、それぞれの立場でこれからもさらに刻んでいく、その一つの有力なプレイヤーとして、共済団体の皆様にも活躍してもらいたいと、学会の元代表者として思います。
学生参加の良さ

藤本 「自分たちの共済とは? 」を考えたときに、私は「自分たちが出し合った掛金が給付などで必ずみんなに返ってくる、それが実感できる素晴らしさ」、「自分たちで知恵を出し合ってどんな制度にもできる、それを実現できる素晴らしさ」の二点に確信をもっています。江澤先生からご覧になる大学生協の共済はいかがですか?
江澤 組合員からの意見を吸い上げて、それを仕組みに反映させるスピード、その確実性も共済のアイデンティティを発揮する局面です。そこが大規模の保険会社にはなかなかできない迅速性があります。
また学生は発想が新鮮で自由なので、共済制度の改定の際に「どんな共済を望みますか」と意見を出し合ってもらい、いいものは採用していく。「こんな意見が出ました。どう思われますか」とまたフィードバックする。みんなで共済を考えることが、組合員参加になっていくのです。
あとは情報の共有ですね。給付ボードのとりくみはこのように役立っていった、こういう方のために機能したということをみんなで分かち合うということが重要でしょうね。
モデルとしては、保険会社は個々の契約者とは実線で結ばれていますが、契約者どうしの関係は点線です。大学生協の共済は、まず学生どうしが実線で結ばれていて、その活動の中でお金を出し合って、お世話役としての事務局があって、たすけあいとして実現していきます。だから学生が表に出て徹底してやっていくことが、名実ともに大事でしょうね。それがほかの団体にとっても、参加の問題を考える場合、いいお手本になっていくと思います。
大学の方々とともに 学生の実情から
藤本 大学と一緒に何ができるかも大切なポイントだと思っていますが、そのあたりはいかがですか。
江澤 学生どうしの連携、たすけあいがいかに大切かということを、まずご理解いただくことが重要です。
例えば、病気入院が事故入院の3倍もある、死亡の一番は自殺、メンタルによる入院は女子が多い、など共済団体として給付にもとづくデータがあるので、それを大学幹部の方に「こういうことですよ」と実態をフィードバックして、予防提案として「こういう手が考えられますね」ということで、本当に学生のために共済団体と大学が協力すると、心と体の病の点については情報が集まってくる。そのことを通じて、大学の中での生協の存在、ポジショニングができるのでしょうね。
自転車事故が起きたときに学生がそのルートを調査して、大学に教えたというとりくみのことを聞いたときにああ素晴らしい、地味だけどすごくいいことをしているんだなあ、そういうことがまさに大学生協の共済の役割期待に沿っていることで、本当にいいことだなあと純粋に思いました。
藤本 現役の先輩が、「ヒヤリ、ハッと」した、あるいは実際にケガや病気に遭ってしまった体験をもとに、仲間意識をもって後輩に「気をつけてね」と言うことがまさに参加の本質だと思うのです。
江澤 そうした日々の日常活動の中で、「こういうことが保険会社との違いだ」ということを一つひとつ実証していく、行動に示していくということの積み上げで、生協の共済のアイデンティティが主張できる。各論であり実行、機能的にそれを組み立てていく時代なのかなと思いますね。本当に眼を凝らして大学生協の共済の資料を読むと、ああ、こんないいこともやっているのかと気付いて感動します。
地味ですけどね。実は地味なことが一番大事です。それをやってこそ、大学も動いてくれます。自転車事故の実態を背景に、大学に対し通学路整備等について意見を申し上げる。生協は非営利団体だからこそ、そういうことを大学に堂々と提案されるといいと思います。
藤本 大学の皆さんと本気で一緒になって取り組み、全構成員に同じ意識をもってもらうことが理想です。入学した学生は全員無事に卒業していく、毎年大学と一緒にその繰り返しを実践していく、その一端を担えるような共済団体、協同組合でありたいと思っています。
江澤 大学にたくさん学生が集まって活動する以上は、必ずリスクはあります。だから共済が必要なのですが、そういう生活の中で出てくるリスクを分析して、防止できるものは、学生どうしあるいは大学と協力していくのが生協の役割でしょうね。
藤本 起こってしまったことは、二度と起こらないために、支払事例は必ず有効に活用していく。
江澤 そうすれば掛金を下げられるかもしれない。また共済が普及するかもしれない。
学生のリスクリテラシー
藤本 学生が本当に自立した形で、何らかの役割を果たせるように社会に出ていく、就職するということまでサポートすることが大学や生協の役割だと思います。
大学生協共済連は全国大学生協連とともに2015年6月、「学生の生活リスク講座」を始めました。今後は消費者教育の視点でそれをさらに深めていきます。また、学生の危険やリスクについて、さまざまなテーマにもとづき、学生のために活動されている方々とネットワークを広げていくとりくみとして、実践していきます。
江澤 消費者教育の原点として大学生への保障あるいはリスクの問題で、教育や情報提供をやっていただく、それは大学生協の大きな役割、大きな期待ですね。
藤本 ありがとうございます。消費者教育の原点の役割をも担えるように、頑張っていきます。今後とも、大学生協をよろしくお願いいたします。
(編集部)
藤本論文のご紹介
『保険学雑誌』第627号 2014年(平成26年)12月
学生の疾病・傷害の保障に関する考察 ―実務者からみる現行制度の現状と課題―
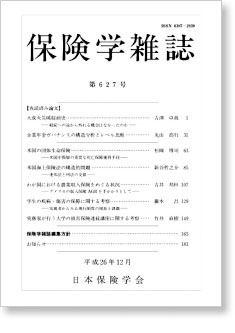
<要約> わが国では,学生を取り巻くリスクに起因する疾病・傷害がもたらす結果に対して,現行の共済・保険(以下,保障制度)が十分に機能していない。なぜなら,現行の保障制度は公的医療保険を補う制度として十分に普及していないと推定できる上,現在の学生の生活実態に保障内容が見合っていないからである。
現在の学生の休学・退学の原因となる身体疾患・精神障害の状況の把握を糸口に,学生生活の維持・充実を妨げる①死亡,②後遺障害,③入院・手術,④通院の実態をみる。それらを踏まえ,国内における日常生活に範囲を限定して現行制度の対応状況をみる。
以上を確認した上で,現行制度の課題を明確にして将来へ向けた改善点を明示する。共済団体・保険会社がそれらをヒントに制度(商品)開発すれば,現在の学生の生活実態に見合う保障制度への発展を期待できる。
現在の学生の休学・退学の原因となる身体疾患・精神障害の状況の把握を糸口に,学生生活の維持・充実を妨げる①死亡,②後遺障害,③入院・手術,④通院の実態をみる。それらを踏まえ,国内における日常生活に範囲を限定して現行制度の対応状況をみる。
以上を確認した上で,現行制度の課題を明確にして将来へ向けた改善点を明示する。共済団体・保険会社がそれらをヒントに制度(商品)開発すれば,現在の学生の生活実態に見合う保障制度への発展を期待できる。
日本保険学会ホームページ
※日本保険学会では、保険学雑誌掲載の論文を、一定期間経過後電子ジャーナル化しており、学会のホームページから閲覧することができます。藤本論文も閲覧可能です。
※日本保険学会に関しましては、同学会事務局(電話:03-3255-5511)に直接お問い合わせください。
※日本保険学会では、保険学雑誌掲載の論文を、一定期間経過後電子ジャーナル化しており、学会のホームページから閲覧することができます。藤本論文も閲覧可能です。
※日本保険学会に関しましては、同学会事務局(電話:03-3255-5511)に直接お問い合わせください。
学生本人のケガや病気にそなえる
たすけあいの制度
たすけあいの制度