- HOME
- 保護者の方へ
- 学生の心と体に寄り添う
- 学生の“こころ”を支える
たすけあい情報室 (大学関係者向け健康・安全情報)
Way of health care center. 新大生の心身の健康を支える保健管理センターの歩み。【新潟大学編】

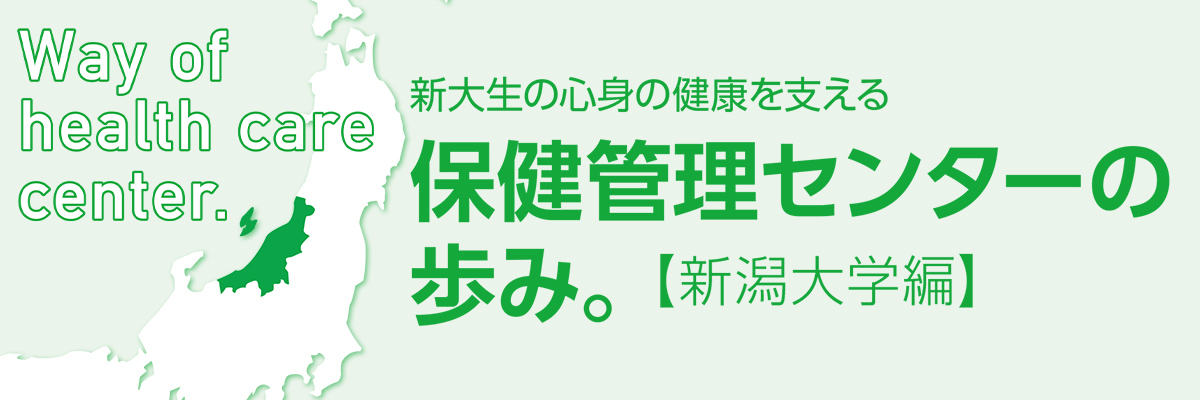
ご協力いただいた方々

新潟大学保健管理センター
黒田 毅 所長

新潟大学理学部3年
二瓶 陽色 さん

新潟大学理学部4年
金澤 妃奈音 さん

新潟大学生協 職員
荒井 望

保健管理センター外観
学生の支援については「学生支援課」や「教務課」「キャリア支援課」などさまざまな部署が関わっていますが、そんな部署の一つに「保健管理センター」があります。病気やけがの応急処置のほかに、定期健康診断の事後指導・健康相談・保健指導・医療機関の紹介・カウンセリングなどを行い、学生の心身の健康を守り、よりよい学生生活が送れるよう支援するのが保健管理センターの役割。そもそも教育基本法の第一条に「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とあり、大学をはじめとした教育機関における健康確保は教育の最も基本的な課題と位置づけられています。1966年には文部省より「学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導の施設」として、各大学に保健管理センターの設置が規定されました。この発令を受けて新潟大学でも学生運動などの困難を乗り越え、1973年にようやく保健管理センターを開設する運びとなったのです。以来50有余年にわたり、新大生の心身の健康を見守り、健全な学生生活を支えてきました。そして、2020年には新型コロナウイルスの感染拡大という開学以来の危機を迎えましたが、適切な対応と人々の連帯、不断の努力によって新たなステップを踏み出すに至りました。新潟大学の保健管理センターは、これからも新大生の心身の健康を見守り続けていきます。

高田分校に学生保健相談所を設置
高田分校(新潟県上越市)にあった教育学部の一室を借りて、保健管理センターの前身ともいえる学生健康相談所を開設。人文学部および教育学部、理学部、教養学部の学生の健康相談に対応しました。ただ、専任の医師はおかず、医学部付属病院の内科医師数名が、週3日間、限られた時間ではありますが相談にあたったといいます。

大学紛争の余波を越えて保健管理センターを設置
文部省令を受けて新潟大学でも保健管理センターの設置が検討されましたが、当時盛んだった大学紛争の余波で頓挫。7年後の1973年になってようやく開設の運びとなりました。開設にあたっては現五十嵐キャンパス内の大学本部の一室に仮設することになりました。その後、現在の本部棟に隣接する場所に現在の保健管理センターが設けられました。

学生の健康管理の要、自動健診システムを導入
学生の健康を管理する上で重要なのが、定期的な健康診断による健康状態の把握です。しかし、1万人を優に超える学生が対象となると、それをスムーズに実行するのは容易ではありません。そこで、新潟大学ではより円滑な健康診断を実施するため、2000年に自動健診システムを導入しました。健康診断はあらかじめホームページから予約を取り、当日受付システムに学生証をタッチすることで待つことなくスピーディーに受けることができます。身長、体重、視力、血圧、尿検査(蛋白・糖)、胸部エックス線検査、健康調査(内科・眼科・耳鼻科・皮膚科)、生活と気分に関する問診など、健康診断の結果は一元的に管理され、自分の健診結果をいつでも閲覧することができます。また、健康管理センターでは、身長、体重、体脂肪率、筋肉量、血圧、視力、聴力、呼吸機能、握力、ストレス度などの健康測定を学生自身がいつでも自由に行うことができます。(黒田所長)

レントゲン車

測定室

新型コロナウイルスの感染拡大による未曽有の危機
未曽有の危機をもたらした新型コロナウイルスの感染拡大の際にも大きな役割を果たしたのが健康管理センターです。2020年の発生当初は、さまざまなメディアを介して次から次へと正誤の判別もつかない情報が溢れかえる中、正しい情報をスピーディーに学内周知していくことに苦労しました。2021年2月から高齢者や医療従事者を先行して新型コロナワクチン接種が全国的に開始されたことを受け、学内での職域接種の実施を決定。保健管理センター主導により、同年7〜11月に1回目・2回目、翌2022年4月と5月に3回目の学内接種を実施しました。会場設営や物品準備、医師と対応スタッフの確保などさまざまな苦労がありましたが、教職員の方々にご協力いただいたおかげでスムーズにワクチン接種を進めることができました。その他にも感染者把握から心のサポートまで、健康管理センターが一丸となって対応しました。(黒田所長)

かぜなどの軽い病気にかかることはありましたが、まさか自分が新型コロナウイルスに感染するとは思ってもみませんでした。その時は本当に苦しくて、1人暮らしをしているので特に助けてくれる方もいなかったですし。それこそ友達にまず電話をして、スポーツドリンクなどの取りあえず必要なものを持ってきてもらって何とかしのいでいました。(二瓶さん)
入学したばかりで友達もそんなにいなくて。このままコロナ禍が続いたらせっかく大学に入ったのに友達もできずに終わってしまうのではないかと。授業でわからないことがあっても一人で頑張るしかないんじゃないかと思っていました。まさに、そういう不安の中で過ごした学生生活だったような気がします。(金澤さん)
CO・OP学生総合共済の共済金支払状況を見てみると、コロナ禍においては、自宅療養の方についても入院扱いとして給付金をお支払いするなど、きめ細かな対応に努めていました。また、授業のオンライン化や外出自粛などによって人とのコミュニケーションが取れず、メンタルに不調をきたす学生が多かったことから「こころの相談テレホン」や「こころの早期対応保障」といったサービスの提供を通じて、学生たちのメンタルヘルスにも配慮していました。(荒井)

ポストコロナへ保健管理センターと共に
長い目で見れば今後も新たな感染症が発生し、人間は再び新たな対応を迫られることになります。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大によって得られた教訓は、新たな感染症が発生した時にきっと確かな支えとなってくれるはずです。そして、そんな新たな局面においても、健康管理センターは学生や教職員の心身の健康を支え、常に心強い味方であり続けることでしょう。(黒田所長)
『Campus Life vol.80』より転載
