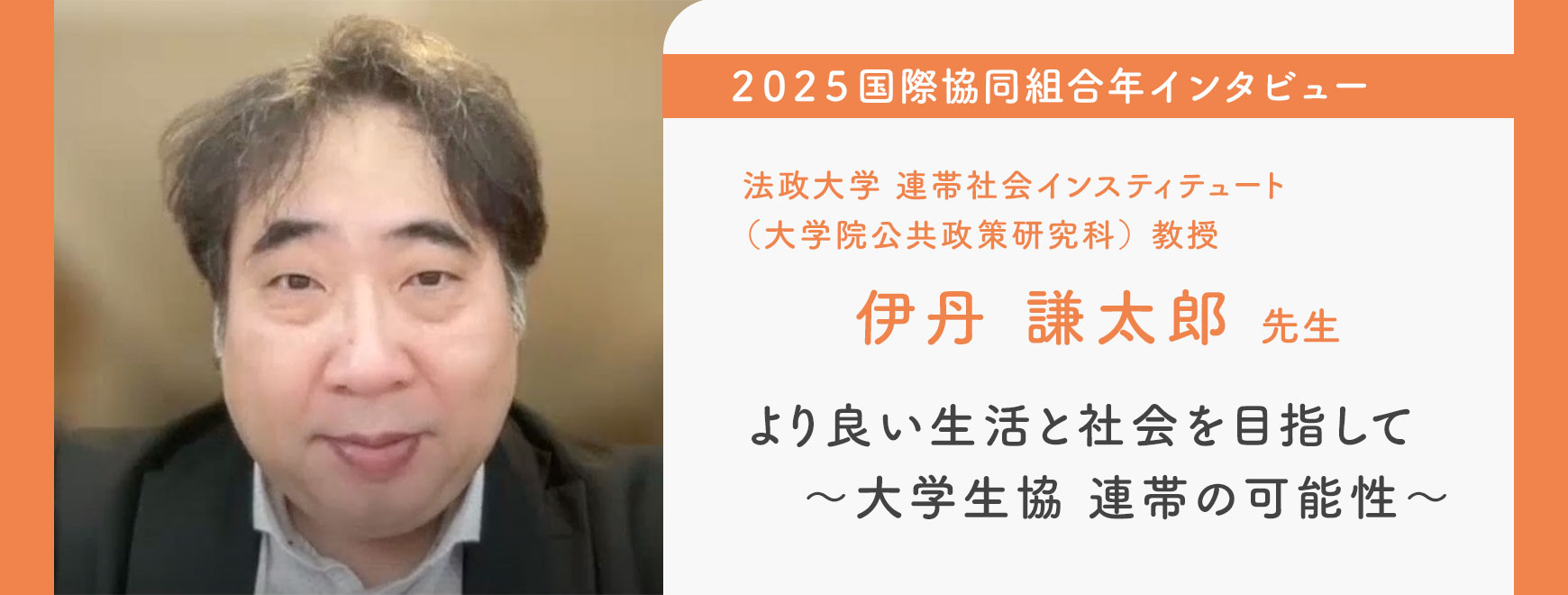2025国際協同組合年インタビュー
法政大学
連帯社会インスティテュート(大学院公共政策研究科)教授
伊丹謙太郎 先生
2025年に国際協同組合年を迎えるに当たり、全国学生委員会では法政大学教授の伊丹謙太郎先生にインタビューをさせていただき、協同組合の意味と意義、大学生協が社会に果たすべき役割等についてお話を伺いました。
聞き手

全国大学生協連
学生委員会
委員長 加藤 有希
(司会/進行)

全国大学生協連
学生委員会
高須 啓太
(以下、敬称を省略させていただきます)
はじめに
全国大学生協連は156万人の組合員(大学生・院生・留学生・教職員等)を持ち、210あまりの大学の福利厚生施設を運営する生活協同組合です。社会的にみれば小さな組織ですが、65年に及ぶ歴史の中で組合員のより良い生活に貢献するべく活動を続けてきました。
私たち全国学生委員会では、協同組合について研究されている伊丹先生に対談の機会をいただき、大学生協が大学の中あるいは外の地域に向かって今後どのような役割を発揮していけるのか考えていけたらと思っています。本日は全国学生委員長の私と学生委員の髙須の2名でインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
法政大学の伊丹です。本日はよろしくお願いいたします。
大学における学生への福利厚生の提供には、大まかに見て三つの枠組みがあります。一つはアメリカをはじめとする、大学そのものが教育のみならず福利厚生も提供するというパターンです。学生はキャンパス内の寮に住み、キャンパスそのものが一つの街になっています。もう一つ、ドイツなどでは主に行政が学生に対する福利厚生を提供します。これにより大学間の格差が生まれにくく、どの大学に通っていても、共通したサービスを受けられます。
この二つに対し日本の場合は、大学生協を通して学生が教職員と共に主体的に福利厚生の制度やサービスを提供するという形をとる大学が多く見られます。学生ニーズの共通性と(各大学における)特殊性をうまくバランスできている点では、先の二者よりも優れたシステムであると思われます。
今先生がおっしゃったことを、最前線にいる専務理事の方々や学生委員の皆さんはなかなか気づきにくいと思います。僕は昨年度、伊丹先生のゼミを訪問していろいろなお話をお聞きしたときに、非常に客観的に大学生協を見ることができ、大学生協の素晴らしさを実感しました。このインタビューが、全国の仲間にも同じように感じていただけるような内容になればと思います。
協同組合の意義
協同組合と賀川豊彦
先生のご経歴を拝見すると、東工大の社会数理系の専門で学ばれたと、非常に特殊な印象を受けました。そこから協同組合を知ったきっかけと大学生協とつながりができた理由をお聞きしたいと思います。
東工大では、今田高俊教授の運営する社会数理講座に所属していました。私が最初に勤務した千葉大学には政治哲学が専門の小林正弥先生がいらっしゃいまして、今田先生と小林先生は共に公共哲学運動の推進に関わっていた関係で、ポスドクとして千葉大学に移り、研究も公共哲学※という枠の中で絞り込んでいくうちに、賀川豊彦や協同組合運動につながりました。自分にとって一番大きな問題意識は「民主的な経済は可能なのか?」ということです。皆さん「Occupy Wall Street※」や「99%」という話はご存じでしょう?
※公共哲学 より善き公正な社会を追求しながら、市民にとって切実な足元で起こっている公共的問題の実態やあるべき姿について考えていく実践的な哲学。公共的問題の具体例としては教育問題、福祉問題、環境問題、地球温暖化問題等。
※ウォール街を占拠せよ(英: Occupy Wall Street) 2011年9月17日からニューヨークのウォール街において発生した、アメリカ経済界、政界に対する一連の抗議運動を主催する団体名、またはその合言葉。"We are the 99%" は、1970年代からアメリカ合衆国において上位1%の富裕層が所有する資産が増加し続けている状況を表わす。
民主的な社会運営や経済運営がなされれば、本来的には99%が苦しむような社会は生まれようがありません。でも実際に我々が目にしているのは、一握りの人間が権力やお金を持ち、人びとは分断され、社会からこぼれ落ちる人口が増えてしまっています。
経済運営において民主主義が実装できるのであれば、今我々が直面している課題の多くが解消できるのではないか。その一つのあり方が協同組合であり、私自身としては、協同組合やその大切さを日本で最初に投げかけた一人である賀川豊彦に非常に興味を持って、協同組合研究を行うようになりました。
いろいろな人間が集まり話し合って自分たちの生活や社会を良くしていくのは、大学生協にも似たところがあると思います。大学生協は理事会や総代会で組合員の代表が集まって議論し、自分たちの生活を改めて決めていくことができる場です。すごく親和性がある分野だったのだなと思いました。
ご指摘の通りです。公共哲学運動は、むしろかつての大学生協や協同組合運動が実現してきたことの意義を再評価し、もう一度そうした方向性を軸に、大学や市民社会の変革を試みようという動きであったと考えています。
大学教育において、学生自身が主体的に自らのニーズを語り合い、福利厚生の提供に関わっていく場が大学生協ですが、大学生協と共に大学そのものも民主的な人格形成の場としてリバイバルさせていくというのが、公共哲学運動が目指していたものです。そういう意味では、既存の協同組合組織の枠を越えて、協同をさらに拡張させる運動であると表現しても間違いではないと思います。
先生はどういうきっかけで賀川豊彦に興味を持たれたのですか。
例えば日本の近代化の夜明けに尽力した渋沢栄一などに比べ、賀川豊彦はまさに産業が急速に発展し、その中で産み落とした闇に対して格闘してきた人物です。その身に近代化や資本主義が生み出した弊害を背負いながら生きた最初の世代だと言えます。こうした困難を克服しようと彼は様々なチャレンジを試みているわけですが、戦後豊かになった日本では忘れられた存在になりました。しかし、ご存知のように90年代以降の長期にわたる経済停滞の下、「貧しい日本」の再来や新しい諸課題が生まれる時代に、もう一度賀川から学ぶべきことがあるのではないか、そういう思いもあって、賀川を研究対象に据えることになりました。


全国大学生協連 第67回通常総会(2023.12.16)
総会はコロナ禍の2020年よりリモートで行われてきた。2024年はつくば国際会議場にて5年ぶりに対面で行われる。
大学生協の役割
先生は大学生協のどういうところに興味を持ってくださったのでしょうか。
実は大学生協に関わる方々も公共哲学運動にコミットされていました。庄司先生※などもその一人です。同時に自分にとっても、大学は一番馴染みの深い組織でもあります。私自身が学生時代に大学生協をしっかりと見ていなかったという悔いもありましたが、大学生協が行っている活動の素晴らしさには注目すべき点があると思っています。
※庄司興吉先生 東京大学名誉教授(社会学)。全国大学生活協同組合連合会会長理事(2005~2015)
大学は、個々の大学が別個に運営する自前主義をとっています。それぞれがオリジナルでユニークな存在になれるので、それ自体は悪くはないでしょう。でもやはり、大学を横断して学生同士を結びつける存在があるかどうかは極めて重要だと思います。
その必要性をはっきりと見せつけてくれたのが、コロナ禍における大学生の声を大学生協が中心となって社会に向けて発信していったときです。大学生協の潜在的な力はすごくありますし、同時に大学の学びや暮らし、学生にとっての生き方やあり方についても横断的に考えることができる存在です。
大学生協は、別々の学部で学んでいる学生が一緒に集って、授業とはまた違った形で自分たちに共通の何かを考えていこう、問題解決に向かって進んでいこうというように、知恵をつなぎ合わせられる場所でもあります。それがただ机上の空論で終わらず、具体的なニーズを叶える実践へと進められるというのが素晴らしいですよね。
考えて学んで知識を得て成長してというだけでなく、やはり実践を通して鍛え直していくというプロセスは絶対に必要です。授業では実践へのルートが十分に用意されていないのですが、大学生協はまさにこの役割も果たしてきたと考えれば、何より期待が大きいですよね。
僕は「大学内に学生の自治的な組織がほとんどなくなっている中で、大学生協がある大学に入れたのはすごいことなんだよ」とさまざまな機会に言われてきましたが、お話を聞いてまさにそれを実感しました。
「連帯」の力
ギフトギビングの精神
僕は2020年度に大学に入学したので、大学に通わない大学生活からスタートしたわけなのですが、コロナ禍でも大学生協の学生委員会が連帯を通じてこの危機を乗り越えてきました。僕たち学生委員にとっては当たり前だと思っている連帯は、外から見た時にどういうふうに見えているのでしょうか。
大学生協の歴史こそ、今の日本社会が思い出し、学び直さなければいけないものだと思います。例えば通常「連帯」や「協同」というと、同じ立場にある人たちが均等にお金を出し合ってギブアンドテイクで助け合うという水平的相互扶助のイメージで捉えられがちです。しかしまだ大学生協が多くなかった時代の大学生協運動では、生協があることで自分たちの暮らしが支えられているたくさんの学生が、生協がないことで苦労している他大学の学生の境遇を思い、義憤をもって大学生協設立運動に関わってきました。「自分の通っている大学にはすでに生協があるから関係ない」という個人主義ではなく、大学が違えど同じ大学生として皆が豊かになるために積極的に他大学の設立運動に関わっていく。それが彼らの「連帯」だったのです。
この中で面白いのは、この連帯運動の成果として、200 を超える数へと大学生協が広がり、大学生協の経営基盤も非常に強くなった。結果として、かつての個々の大学生協がやってきたことよりもはるかに多様で大規模なことができるようになった。戦後早々から続けてきた「連帯」がこうした大きな力を生み出すことにつながったわけです。
戦後の大学生協間の連帯運動から学べるのは、ギフトギビングの精神ではないでしょうか。誰かのために必要だと思うなら、それを実現するためにみんなで汗をかく。直接自分の利益にはならないし、そうした見返りももとめない。しかし、このような動機に基づく行為が積み重なった末に現在の大きな大学生協が生まれています。協同組合はもちろん、これからの日本社会を考えるなら、絶対に覚えておきたい歴史的事実です。
「協同組合の素敵なところはどこなの?」と聞かれた時、まさに戦後の大学生協運動における連帯の歴史が一番しっくりくると思います。今新しい社会をつくっていく上で何が必要なのかと聞かれると、私は「大学生協が培ってきた連帯の歴史をあらゆる場で実装させていくこと」と答えます。
自分自身はコロナ禍でもオンラインで他の大学とつながってというように、コロナ禍を連帯で乗り越えたという認識がありましたが、連帯の力はコロナ禍に限ったことではなかったのですね。
例えば、古い大学生協として東京大学生協、早稲田大学生協がありますが、彼らにとって関西に新しい大学生協を作ることで自分たちが得られる利益は特にありませんよね。また、多くの大学生は4年で卒業していくので、たくさん大学生協ができることによって生まれるスケールメリットを彼ら自身が享受することはありません。だから明らかに無償の贈与というような行為が連鎖していく。その数珠は繋がっていて、大学生協が発展してきた。場合によっては、利益は子どもたちが大学生になる20年・30年後に返ってくるのかもしれません。世代を超えた「大学生の連帯」を確認することができます。
大学生協の価値
僕は福山市立大学生協で活動していました。設立したてで小規模でやれることが少ない中でしたが、周りの仲間と切磋琢磨できるような関係性は思いきり築いてきたと思っています。僕たちが頑張れたという意味で連帯はすごく有難かった。だからこそ僕たちは山口県立大学生協設立の際に当たり前に支援をしてすごく感謝され、立ち会えて良かったなと思えました。そういうことが脈々と受け継がれているのですね。
設立に関わった世代というのはすごいエネルギーを持っているので、携わる機会があったのはうらやましいことでもあります。一方で、設立から何十年も経っている大学生協でも学生が主体的に運営できるという特徴においては違いはありません。大学生協は大学生が活躍し仲間とともに成長できる大きな舞台のひとつです。そういうものが全国的に連帯されているというのは素晴らしいことです。
他方で私もそうでしたが、大学生協の価値や意味、あるいは学生委員会について何も知らないまま卒業してしまう学生が圧倒的に多かったりするわけですよね。だからこそ彼らに対してその魅力を伝えられるような機会を、これから益々増やしていかなければいけない。同時に彼らから「かっこいいよね」と言われるような学生委員会、憧れられるような学生委員であってほしいと思います。
私の指導している学生の一人が大学生協を修士論文の研究テーマに選びました。「入学オリエンテーションの時に先輩方がすごく心強く思えた。それが大学生協学生委員会に入った理由です」という人が多かったと聞いています。でもそれが一部であるのが残念です。大多数の学生に大学生協の意味や、それが必ずしも大学の敷設機関などではなく、学生が中心になって運営している組織なのだということを知ってほしいですよね。
せっかく大学生協のある大学に入ったのに、そういうことに気付かないのは本当にもったいないなと思います。だからもっと広めていきたいなと、中に入っていた人間としてはすごく思います。
大学生協とコミュニティ
「社会連帯経済」
僕は愛知県出身で、岐阜大学に入学して4年間岐阜で一人暮らしをしました。大学生として地域と大学が結びついているフィールドで活動できたのは、そのつながりを実感できたすごくいい経験になったと思っています。今、大学生が「社会連帯経済※」に関わることの意味、地域社会に関与することの意義をお聞きしたいと思います。
※社会的連帯経済(SSE) 「社会的経済」と「連帯経済」を組み合わせた言葉で、Social and Solidarity Economyの頭文字を取って「SSE」とも言われる。行き過ぎた利潤の追求による弊害をなくし、民主的な運営により、人間や環境にとって持続可能な経済社会をつくることを目的とする概念。
誤解を恐れずに言いますと、大学生協の運動に関わっている時点で、すでに社会的連帯経済の担い手であるのだと思います。社会的連帯経済の明確な定義はまだありませんが、その筆頭に挙げられるのが協同組合です。
ただ、一方で SSE(社会的連帯経済)が推進しようとしているのは、必ずしも一つ一つの協同組合を強くしようというものではなく、いろいろな団体が連携して新しい社会をつくっていこうという連帯の精神を軸にした運動です。
ですから皆さんにとっては、大学の中で協同組合として運動を行うだけではなく、そこでこれまで関わってこなかった人たちと一緒に新しいつながりを作っていくのが非常に重要になってきます。今、協同組合原則が改訂に向けて動いている時期ですが、ICA(国際協同組合同盟)が作った1995年改訂原則※の第七原則に「コミュニティへの関与」という言葉があります。
ICAによる協同組合の定義とアイデンティティ
※ICA(国際協同組合同盟)は、1995年の100周年大会で協同組合を定義し、協同組合の価値と7つの協同組合原則を定めた「協同組合のアイデンティティに関する声明」を採択した。
コミュニティとは何なのか。日本では「地域社会」と訳されている文章もありますが、実は地域とともに職域のコミュニティも含まれています。その中でも代表的なものの一つが大学生協です。
キャンパスコミュニティが皆さんの暮らしや学びの土台になっていますが、それは単体で存在しているわけではなく、実はキャンパス自体も周辺にある地域の市町村のコミュニティの中に存在しています。つまり多層的で多重的につながりあっているコミュニティの一つとして協同組合の役割や機能が果たされているわけですが、その全体のあり方をしっかりと見晴らして、連帯の輪をあらゆるところに広げていくことが求められているのです。
当然大学生協だけで、あるいは大学キャンパスだけで成立しているような暮らしというのはないわけですから、まさにそれを支えてくれているというような感覚でキャンパスの外と連携を進めていくことが、 SSE にとっては一つの進め方ではないでしょうか。大学生の皆さんにとってのスタート地点としては、「キャンパスの外へ」という姿勢が一番やりやすいと思います。大学生協はすでに全国連帯のような形で大学生協間の連帯が非常にうまくいっているので、他の協同組合よりもはるかに社会的連帯が進めやすい存在なのかもしれないですね。
社会を変えられる力
僕の母校である福山市立大学は「キャンパスは街、学ぶのは未来」という標語のとおり本当に街の中にあるキャンパスです。この設立したばかりの大学生協があったからこそ、地域に関わっていくことの良さや、自分たちの学びを地域でも実際に活用できるというように、実践を伴いながら成長できていくという大学生協の良さを知りました。だから、今日のお話は自分の中ですごく腑に落ちました。
福山市立大学にせよ、福山市にせよ、すでにそこに自分は関わってしまっているわけですよね。協同組合というのは自分で変えていける組織なので、単に批判したり批評したりするだけでなく、ないものは自分たちでつくればいいし、問題があれば自分たちで改善できる。協同組合で培われた生き方は、自分のアイデンティティの一部でもあるわけです。
そういう意味では、福山市民でありかつ福山市立大学の学生である、というようにアイデンティティは多重になっているといえます。でもそれは自分が何かを変えられる存在であるし、それが自分自身の変化にもつながるものです。だから、何も変えられないと諦めるのではなく、変えられるという道筋を持てるというプライドを育ててくれる大学生協での経験は貴重なものです。皆さんにとっても、それが大学生協での活動が与えてくれた第一歩なんじゃないのかな?
これは企業に入ってもそうですよね。就職先の会社で「ルールが決まっているから、しょうがない」と言ってぼやくよりも、その構成メンバーである以上は自分の意見に対する共感が集まれば、変えられるかもしれないという思いで働けば、働き方も全く違ってくるはずですから。
失敗が許される場所
先日の大学生協連の学生の意識と行動に関する研究会※で、小中高の学校生活において自分の表明した意見が実際に反映されたという経験の有無でその後の生き方が変わってくるという話がありました。
例えば「校則を変えたい」と言っても実際に変わる経験をしていないから「どうせ言っても変わらない」と諦めるのと同じように、大人になって選挙権を得ても「どうせ世の中変わらないから」という理由で選挙に行かない若者がいるのではないか。同じように協同組合の組織にいる大学生も、変えられるコミュニティの中にいるはずなのにそれを知らないから自分の意見を言わないという学生が多くいるのではないかと思います。
※第48回「学生の意識と行動に関する研究会」ネット選挙と若者世代の政治参加意識|全国大学生協連の研究会報告|全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)
そういう学生に、せっかく協同組合という民主主義の仕組みがあるコミュニティにいるのだから、自分のいる組織や地域コミュニティにも変えられる可能性があるのを自覚してもらうためには、どういった関与ができるといいのかなと純粋に疑問に思いました。
そこは結構難しいところですね。昔に比べると現在は、失敗できる機会が用意されていないことが要因の一つかと思います。かつてのようにまずやってみて、でも結局失敗してダメだったというのと、「こうすればいいのに」と思ってもそれを実践につなげる術を持たずに諦めてしまう状況とは、全然違うはずです。
社会そのものが、個人の無力感を強く意識させる方向に動いてしまっている。それは多分、「失敗してはいけない」という一人一人の思い込みがあまりにも強くなってしまっているからでもあります。どんなことでもやってみることが許される環境とそれを通して成功体験が重なることで、次のステージや次の新しい変革へとつながっていくものです。失敗したら怖いからと言って可能性を閉ざしてしまうのはもったいない。
これは、個人の問題だけではなく、社会や組織の側もそうした声に対して「うるさいな」と壁をつくるのではなく、「じゃあやらせてみようよ」というような形でやらせてみたほうがいい。そうした好循環が個人と組織との間でできると、今の日本社会が落ち込んでいる閉塞感が大きく変わっていくはずです。そうした失敗を許容する環境が学生の皆さんが社会に出る前に大学あるいは初等中等教育の間にいかに用意されているのかというのが重要です。
大学生協の学生委員会活動というのはそうした「失敗するかもしれないけど、自分たちでとりあえずやってみようよ」というようなチャレンジやチャンスが用意されている場です。そして、仲間が知恵を出し合ってチャレンジし、失敗しても相互に支え合って問題を解決していく。心強い仲間の存在と、何でもチャレンジしてみようという勇気。これらは体験を重ねることで強くなるわけですが、まったくそういう機会を得られない人もたくさんいる。むしろ多数派は機会をえられていないんじゃないか。
チャレンジできない若者が増える原因は「どうせ自分なんかやっても無駄」という自己肯定感の低下と言われています。自己肯定感が下がると、新しいことやチャレンジはさらにできなくなってくるという悪循環。現状の我々が陥っている悪循環をむしろ好循環に変えていく一つのきっかけというのは、身近に協同組合があることなのかもしれないと考えると、協同組合ってすごく素敵じゃないですか?
僕も大学生協の学生委員会で「やってみようよ」と言ってやってみて散々失敗してきました(笑)。でも大学生協は学生がチャレンジできる場所を作ってあげることをすごく大事にしています。新入生向け講座の中でも、大学生協が「大学4年間の中でこんなチャレンジしてみませんか?」という提案をしているので、誰もがチャレンジできる機会を与えられる大学生協があるのはすごく有難いと思いました。
より良い世界へのチャレンジ(メッセージに代えて)
最後の質問をさせていただきます。国際協同組合の IYC 2025のテーマが「協同組合はよりよい世界を築きます(Cooperatives Build a Better World)」となっており、大学生協連としては全国の組合員と一緒に「学長と組合員が一緒に考えるベターワールド」を集めようという企画を25年度に向けて考えているところです。伊丹先生ご自身が考えるベターワールドをぜひお聞きしたいと思います。
ベターワールドというのは「かなり控えめな表現」でもありますが、これが良い社会、これがダメな社会と特定の価値観の下で定めるものではなく『今日よりも明日が何か改善されているように一歩でも二歩でも次に進んでいける』、運動というのはそういうものなのかもしれません。
「協同組合がより良い社会を築きます」いうキーワードにはいろいろな解釈があると思いますが、大学生協の場合、自大学のキャンパスの中だけで自足してサービス向上に努めればいいだけではなく、むしろ自分たちのコミュニティを超えてより良い社会、より良い世界に向けていろいろな可能性にチャレンジしていくというような意味でもあると思います。
やはりチャレンジできるということは非常に大切なことであって、それが次の時代や次の社会をつくっていくものです。学生の段階からそうしたチャレンジができる機会を与えられている皆さんは本当に幸せだと思いますよ。我々にとっても、今でもチャレンジするのは楽しいですよね、やっぱり(笑)。
チャレンジしていくことでベターワールドを自分たちがつくっていくのだという実感にも繋がっていきます。“チャレンジ”は一つのキーワードですね。
どんな仕事をしていても、それが社会や世界とどうつながっているのかという軸をしっかり持っているか持てないでいるのかによって、その仕事が楽しいか楽しくないか、相当変わってくるはずです。
これは学生さんへのメッセージとして申し上げますが、多分これから社会に出た時に、自分の仕事が社会に対して、あるいは世界に対して、どんなつながりを持ってどんな役割があるのか、広く見られるような視野を確保しながら職業生活に努めてほしいと思います。
本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
(2024年11月21日リモートインタビューにて)
プロフィール
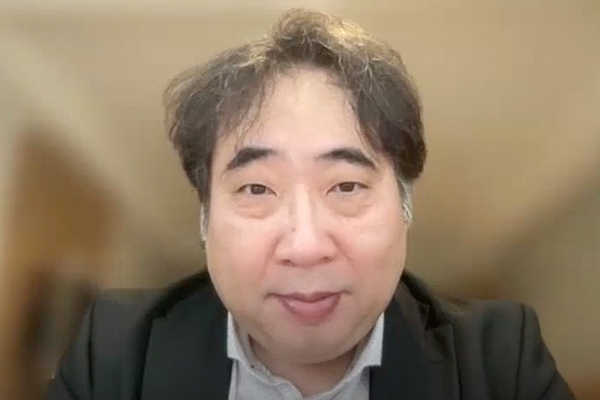
法政大学 連帯社会インスティテュート(大学院公共政策研究科)教授
伊丹 謙太郎 先生
専門は公共哲学/社会倫理学、意思決定科学。研究テーマは、賀川豊彦を軸とした協同組合思想史、非営利組織連携論、社会的連帯経済、プラットフォーム資本主義と協同組合ほか。
1975年徳島県生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科社会数理講座博士課程単位認定修了。千葉大学医学部、人文公共学府特任助教等を経て、2020年4月より現職。協同組合プログラムを担当。
賀川豊彦学校長(鳴門市立賀川豊彦記念館)。ロバアト・オウエン協会理事、公益社団法人教育文化協会理事、公益財団法人生協総合研究所評議員、一般社団法人協同総合研究所理事ほかを兼務。
▼researchmap
伊丹 謙太郎 (Kentaro ITAMI) - マイポータル