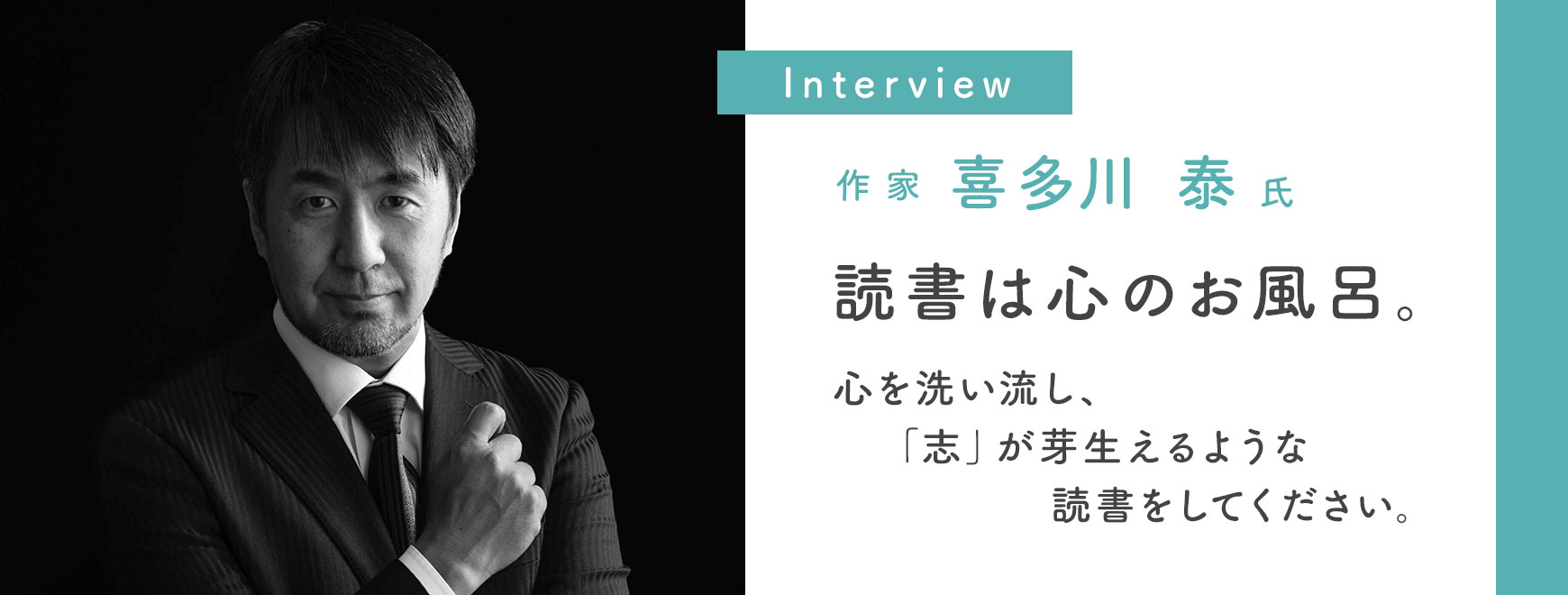- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 喜多川 泰 氏 インタビュー
- 喜多川 泰 氏 インタビュー(大学時代~27歳の起業を通して得たもの)
大学時代~27歳の起業を通して得たもの
人を幸せにする指導者になりたいと思った
先ほど学生の本離れの傾向を指摘されましたが、ご自身は大学時代をどのように過ごされましたでしょうか。
僕たちの頃は今とは時代が違うので、多分皆さんとは全然違う過ごし方だったと思います。人口も非常に多く、大学入試も第1希望の大学は倍率が25倍とかでした。合格後に大学に入学するために上京して都会で1人暮らしをするというのは、やはりすごく大変なわけですよね。
アルバイトもしなければならない、自分が何者かにならなければならない。そのための4年間で、何をしていいか分からないけれども、日々やらなければならないことで忙しい学生生活でした。
喜多川さんが塾の先生を志されたきっかけは何でしたか。
僕が指導者になりたいと思うようになったのは、実は指導者になった後でした。大学時代は僕も自分が何に向いているか分からなくて、それを4年間一生懸命探しながら過ごしたわけです。
自分には何にもないと思っていた。その中で唯一周りの人から褒められたのが、人に勉強を教えることだったんです。確かに知っていることや勉強を誰かに教えると、「すごくよく分かる」「君に向いているよ」と言われたことがありました。誰かから喜んでもらえた経験がこれしかなかったんですよね。僕は本当に自分が指導者に向いているかどうか分からず迷いましたが、僕が通っていた塾の先生からも「お前は向いている」と言われたこともあり、この道に進んでみようと思いました。
自分がみんなに言われて嬉しかったことを職業にされたということだったのですね。塾の先生のことを「指導者」とおっしゃっていましたが、その意図は何かありますか。
僕ももう20何年先生をやりましたが、一生懸命勉強を教えて、生徒がいい成績を取って行きたい学校に進学した後、その子たちが果たして幸せな人生を送っているかというと、勉強ができるのとそれとは別問題だったのです。
そこで、ふと気付くわけです。自分は勉強を教えるのが仕事なのだけど、勉強ができるようになると同時に、その子の生きる力を奪っているのかもしれないと。だから僕がやりたいのは塾の先生として勉強を教えることを含めて、その子を幸せにすることだと思うようになったんですよ。
誰かを導いて幸せにしたいと思う人は、みんな指導者じゃないですか。それは塾に限らず、学校も習い事も同じです。会社で上司が部下の成長を促すためにすることも指導ですよね。そういう指導者でありたいなという思いがありました。
起業を契機に本を読むようになった
喜多川様ご自身はどのように読書をしていらっしゃったのでしょうか。
僕が実際に本を読むようになったのは27歳の時で、皆さんよりも年をとってからです(笑)。27の時に何があったかというと、僕は自分で会社を立ち上げたんです。それまでは大手学習塾に勤務する会社員でしたが、自分のやりたいことが別のところにあると思ったので独立しました。起業をしたということです。
世の中には起業した人は大勢います。起業する人の特徴を1つ挙げるとしたら、やはり自信があるということなんですよ。自分のやろうとしていること、自分の考え方に自信がある。そうでない人は起業なんてしないですからね。
僕も自分の考え方に自信があって、きっとこういうふうに塾を運営したら世の中の人が必要としてくれると思って起業したのですが、いざ立ち上げると全くうまくいかないわけです。自分がイメージしていたとおりのことは全く起こらない。人も集まらないし、かといって蓄えがあるわけじゃない。
一緒に始めたスタッフたちは、そんな僕についてきてくれた。僕が発信した夢や目標や見たい未来、そういうビジョンを聞いて、ついていったらきっと未来はそのとおりになるのだと思ってくれたんですよね。
生徒が来なくて給料も払えないという状況になっても、非難めいたことを言う人が 1 人もいなかったんです。「最初はそんなもんなんじゃないですか」「信じていますよ」「最初からうまくいくなんて思ってないですよ」って、むしろ周りの人の方が僕をすごく励ましてくれました。
僕はその反応を見て、これは絶対何とかしなきゃいけないと思いました。僕は自分の教育理念に自信があって、自分の行動に対する世の中のレスポンスに対しても自信があったのに、そうならなかったわけです。だけど周りには信用してくれる人が大勢いた。だからもうなりふり構わず、こうなったら自分の思っていたことなんか一切関係なく、いろいろな人の学びを取り入れて少しでもいいから前に進んで行かなきゃいけないと思って本を読み始めたわけです。
読書は発見の連続だった
皆さんは読書を通じてご存じなのでしょうけれど、本当にお恥ずかしい話、僕は27まで気付かなかったことがありました。
会社をたくさん興した人、危機を何度も乗り越えた人、会社を作ったけれども潰してしまった人が世の中には大勢いて、その人たちがたくさん本を書いているわけです。そういう本を読んでいると、「こんなこと知らないで人を呼ぼうとしていたんだ、これは絶対つぶれるわ」と思う。そこから学んで実践して、また別の本を買ってきて読んだら、「こんなこと知らないでやろうとしていたらそりゃつぶれるわ」と思う。それをずっと繰り返していくと、何年経っても出会う本出会う本に毎回発見があるわけです。そしていつの間にか、僕はそのまま読書を継続していきました。
当時も今でもそうですけど、経営がうまくいかなくて苦しんでいる人、会社の人間関係で苦しんでいる人、資金繰りで苦しんでいる人、スケジュールが満タンな生活でどうしていいか分からない人が周りに大勢います。それを打破するために、「僕もそれ経験してきたから気持ちはわかるよ。いいからこの本読んでみなよ」と、本を渡します。本を渡された側は、「いや今は日常に隙間がなくて本を読める状態じゃないから、隙間ができたら読むよ」って言うわけですよ。だけど僕は「逆ですよ。僕も隙間がなかったけど、読んだら隙間ができました。だから読んだ方がいいですよ」って話をします。
大学は本を読みに行く場所

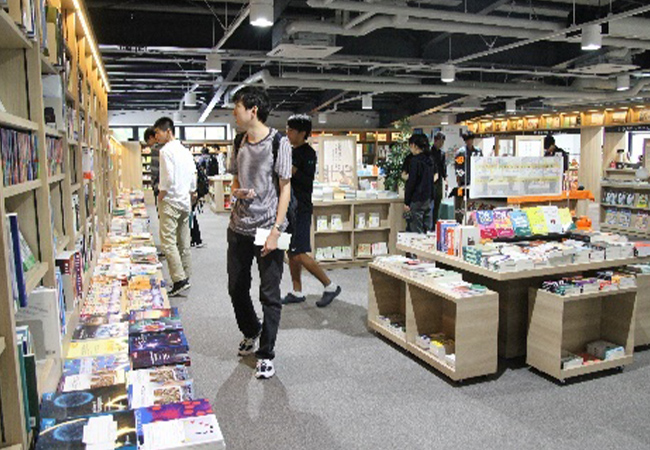

大学生協の書籍部❶ 山口大学生協 吉田キャンパス「FAVO-Books」
各所にテラス席を設け、各種交流イベントなども実施しています。
学生の読書調査では、2017年に初めて「1週間1冊も読みません」という学生が50%を超えました。その時に感じたことをお話しします。
時の流れとともに大学の役割も変わってきました。僕らは「いい大学に入ったら、いい将来が約束されている」と言われながら育った世代なんです。だから、目的はいい大学に入ることでした。ところが、僕らが在学中にそういう時代ではなくなってしまいました。今では「この大学に入ったら将来安泰ですよ」なんて大学は、日本全国どこにもなくなってしまいました。時代がそうじゃなくなったんですよね。
じゃあ大学へは何をしに行くのでしょうか? 僕は間違いなく大学は本を読みに行く場所だと思っています。でも調査では、半分以上の人たちが本を読まない。だから、僕は学生に本を読むことの大切さを知ってほしいなと思って、『書斎の鍵』でも何のために本を読むのかを書かせてもらったんですよ。



大学生協の書籍部❷ 山形大学生協 小白川キャンパス「Porte」
今も昔も、大学生が本を求めて集まる場所です。