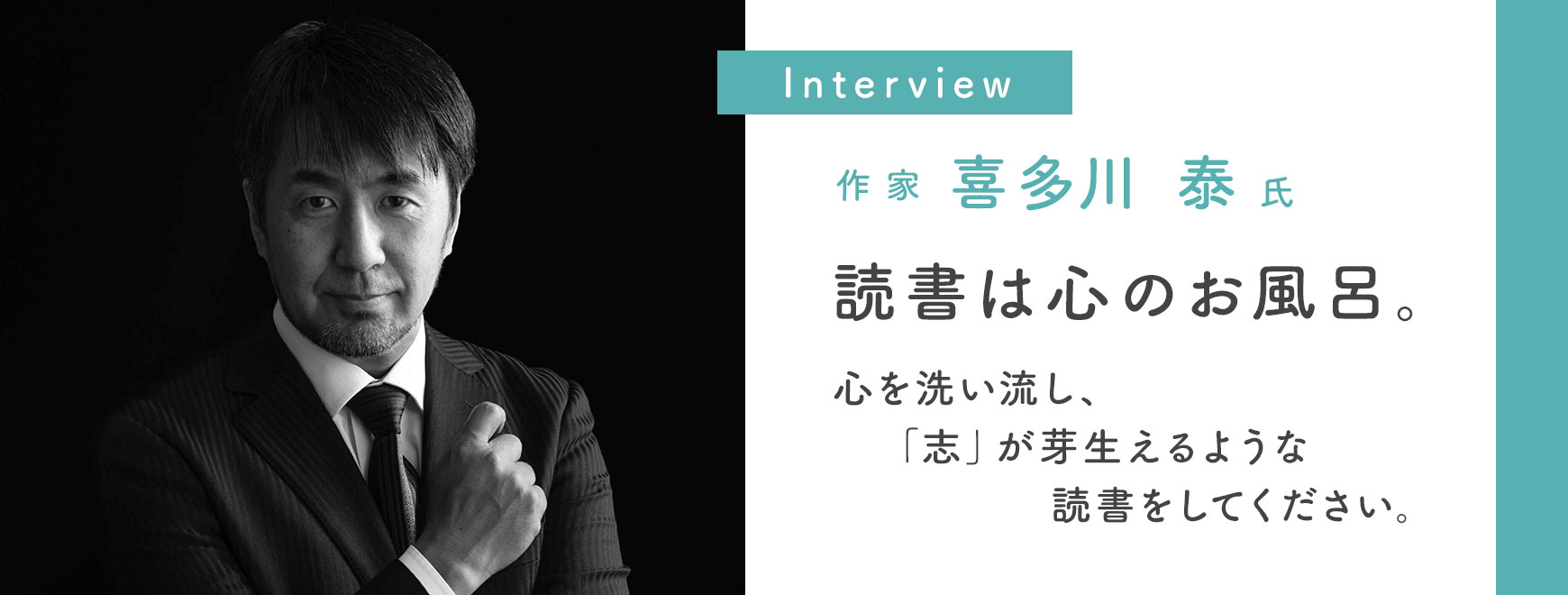- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 喜多川 泰 氏 インタビュー
- 喜多川 泰 氏 インタビュー(何のために本を読むのか)
何のために本を読むのか
読書は心のお風呂です
「忙しくて本を読む時間がないです」、「本なんて読んで、何か意味あるの?」と思っている人たち。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ。就活も面接も行かなきゃいけない。「そこにどうやって本を読む時間をねじ込むんですか?」と聞く人に、「そんなに忙しいんだったらお風呂入らないの?」と聞くと、「お風呂は入ります」って言うんですね。
「お風呂に入るのはなぜですか?」そうすると「だって一日活動したら体が汚れるでしょう?」と言われます。それはそうですね。外出したらいろいろな菌がつくし、人間は内側から新しいものを作って古いものを排出するのが生きるということですから。それをきれいにして寝床に入りたい。これは当たり前の話です。体はそうですけど、じゃあ心はどうするんですか?
『書斎の鍵』の中で、「読書は心のお風呂です」という表現をしました。僕らの時代よりも皆さんの時代の方が、心のお風呂に入らなければいけない時間を必要としていると思います。それは、一日あたりに触れる情報量が桁違いだからです。
例えば手元にスマートフォンがあるとか、いつもPCを持ち歩いているとか、そういったデバイスが近くにある生活環境って、ここ10数年のうちに人類が初めて経験したことです。今やそれが当たり前になっていますよね。
例えば中高生、小学生でも、精神的に病を罹患して病院通いをしているとか、学校に行けてないとかで、継続的なケアが必要な子が当たり前になってきましたよね。それが一概にスマートフォンなどが原因だと結びつけられるかどうか分かりません。でも、スマートフォンが出てくる前の中高生でそうなることが一般的だったかというと、実は非常にマイノリティだったんですよ。
だけど今は逆です。当たり前ですが人間の心というのは、情報に触れることによって動かされるわけです。例えばほんのちょっとした情報でも「あ、どうしよう」と思ったり、「わあ、楽しそうだ」と思ったりして、あっちへ行ったりこっちへ行ったりして心が揺さぶられてしまう。
一日生きるとやはり外からの情報によって自分の心が汚れるし、内側からの情報つまり自分が考えていることによっても心が汚れる可能性がある。なのに、心のお風呂には入らないの? ということを、やはり僕はとりわけ今の時代の若い人たちには伝えたいと思うんですよね。
「心のお風呂」という表現がとても素敵だなと思いました。僕の場合、大学1、2年生はコロナ禍で自粛生活を余儀なくされていたのでなかなか人にも出会えなかったし、課題やバイトで結構いっぱいになってしまったことがありました。そんなとき、ふらっと本屋に立ち寄って、いいなと思った本を1冊手に取って帰って読んでみたら、読んだ時間はそれこそ20分くらいでしたが、荒んでいた心が本当に軽くなり、心が洗われた気がしました。それが、本当に心が洗われた瞬間だったんだなと共感しました。
一日1%の読書で人生は変わる
じゃあ 「一日あたりのお風呂の時間ってどれぐらいですか?」というと、だいたい僕は15分だと思っています。僕が考える読書は、そういった一日15分程度の読書なんです。2~3時間読みたいっていう人を別に止めはしませんが、それはたまに温泉に行ってリフレッシュしたいという感じで、毎日そうである必要はないと思います。
その15分という時間は、一日の大体1%なんですよ。もし皆さんが新しい習慣のために一日1%使えれば、残りの99%は今までと同じ過ごし方をしていてもいいと思う。だから「一日1%を読書に置き換えるだけで、皆さんの人生は100%変わります」と言い続けてきました。それは僕自身がそうだったし、僕が伝えてきた皆さんも実感しています。だから、半分ぐらいの学生が本を読まないというのは本当にもったいないことです。たくさん読む必要はありませんが、一日15分は毎日読むべきだと皆さんにお伝えしたいと思います。
大人も本を読みましょう
ご自身のウェブサイト「読書の広場」を開かれていますが、読書でつながるコミュニティで目指していること、期待していることがあれば、教えていただきたいです。
子どもが本を読まないのは、やはり大人が本を読まないからなんですよね。「自分は読まないから分からないけど、本を読んだ方がいいらしいから本を読む子にしたい。でも、ある程度の年齢になると読書より勉強させた方がいいんじゃないの?」と考えるから、「本を読んでいる暇あったら勉強しなさい」と言いたくなるんですよ。だから僕がコミュニティで言っているのは、「大人たちがまず本を読む人になりましょう」ということ。これが一点です。
もう一点は、本を読んでいる大人が素敵な人生を送ると、若い人達が「あの人の生き方いいな」と思って、憧れの存在になります。だから、本を読むとこんなにかっこいい大人になれるという例をたくさん作ってほしい。そうすれば、「私も本を読んであんな人になりたい」と憧れる人たちが世の中に増えて、若い人たちも本を読みたくなると思います。
そうですね。自分の親も含めてやはり本を読む大人が身近にいると、自分も本を読もうかなという気分になることもあると思います。
全国の大学生へのメッセージ
フラットな気持ちで人と出会おう
僕の場合、3年生になってからは少しずつキャンパスが開放されていって、大学生協の仲間をはじめいろいろな人との出会いがありました。教育実習で一緒に研究授業をしたり指導案を作ったりした仲間たちもいます。今はまだ卒業して1年目ですけれども、大学生活で関わった人たちとの出会いを生涯大切にしていきたいと思っています。
喜多川先生がこれまで出会われた人の中で、大切にしたいと思われた出会いを教えてください。
作家になって19年経つので、いろいろなところでいろいろな人たちと出会う機会は多いです。その中で思うことは、やはりどの出会いもできるだけフラットにしたいということです。
なぜなら、それぞれがそれぞれにしか知らない世界を生きてきた人たちだから。専門分野で活躍している人も専業主婦として何十年も子育てをしてきた女性も、その人しか知らない世界をそれぞれが生きているわけですから、僕もこの人との出会いは大事にしたい、この人との出会いは大事にしたくないというような意識はできるだけ持たずに、1人の人間としてフラットに接していきたいと思います。
読書で志を立てよう
最後に読者の大多数を占める大学生はじめ若者世代にメッセージをお願いします。
ある大人があなたに「いいか、お前は本を読むなよ」「本など読まずに、私の言うことだけ聞きなさい」と言ったら、皆さんはどう感じますか。また、例えばこの日本社会で「もうこちらが指定する本以外は読まないでください」と言われていて、就職した会社が「本を読んだら感化されて会社を批判するようになるから、本を信じないで会社の言うことだけ信じなさい」と言われたら、どう感じますか。
恐らく、何かコントロールしようとしているな、要は自らの決定に隷属する人間をつくろうとしているんだなと感じると思うんですよね。だから、例えば「君たちは受験勉強終わるまで本読まなくていいからね」と言われるのは、同じような危険性を含んでいるということに気付いてほしいと思います。「本を読まなくていいですよ」と禁止するのは、皆さんから自分の人生の決定権を奪って、「私の言うことを聞いてその通りに動く、そういう存在になりなさいね」と言われているのに等しいわけです。
僕は読書をすすめる講座の中で、よく吉田松陰の言葉をピックアップしてお伝えしています。吉田松陰は松下村塾で塾生に『士規七則』を伝え、読書を奨励しました。要約すると「志を立ててください」「良い人々との交流を通じて成長してください」「本を読んでください」と、この3つが肝要なんですね。その序文にはこうあります。
『冊子を
「ページをめくると、素晴らしい言葉がどんどん迫ってくる。そんなに素晴らしい効果が本にはあるのだ。にもかかわらず人は本を読まない。もし読んだとしても、行動に移す人は少ない。本当に本を読んで、そこに書いてあることを実行したら、人生が千回あったとて万回あったとてやり尽くすことのできないぐらいやりたいことで溢れるのに」。
読書の一番の効果はそこでしょうね。つまり本を読むと、自分の人生がやりたいことで満ちる、それに尽きると思います。「読まなくても幸せに生きていけると思います」と言う人もたくさんいます。確かにそうかもしれませんが、読まないで生きる幸せは、やはり目標を追う生き方だと僕は思います。夢が叶いました。ああ幸せ。じゃあ次は何が欲しい? こういうふうに夢を追い求めて幸せになるという生き方には、できるだけ少ない労力でできるだけ多くを得たいという価値観が根底にあるので、どこかで無気力になってしまうんですよね。それは、夢は途中経過でしかないからです。
本を読むことで志が自分の中に芽生えていきます。夢はほっておいても自生しますが、志は自生しないんですね。「志」とは、自分はどんな人になりたいか、どんな人として一生を送りたいかということです。そこにはゴールがないし、成功失敗もない。自分が人生を終える瞬間まで続いていくのが志です。
本を読むことで、志が人の中に芽生えていくのだと思います。自分の中に志が芽生えるような読書をしてほしいというのが一番の願いです。
そのために僕は、心も体と同じで、一日一回体をきれいにするんだったら一日一回心のお風呂(読書)にも入ったほうがいいんじゃないの? というアプローチから入っています。志を高く保つために読書を続けましょう。
お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。また今後もご著書を読ませていただきたいと思っております。
こちらこそありがとうございました。
2024年4月22日リモートインタビューにて
PROFILE
喜多川 泰 氏

1970年生まれ、愛媛県西条市出身。東京学芸大学卒業後、大手学習塾勤務を経て1998年に横浜で学習塾「聡明舎」を創立。人間的成長を重視した教育方法が注目される。2005年『賢者の書』にて作家デビュー。『君と会えたから…』は2作目にしてベストセラーになる。『手紙屋』『「福」に憑かれた男』『ソバニイルヨ』『運転者』など、いずれも反響を呼び、長く読み継がれている。2010年に出版された『「また、必ず会おう」と誰もが言った。』は映画化、舞台化される。“自己啓発小説の旗手”とも謳われ、多数の作品が国内外で高い評価を集める。全国各地で講演やセミナーなども開催。