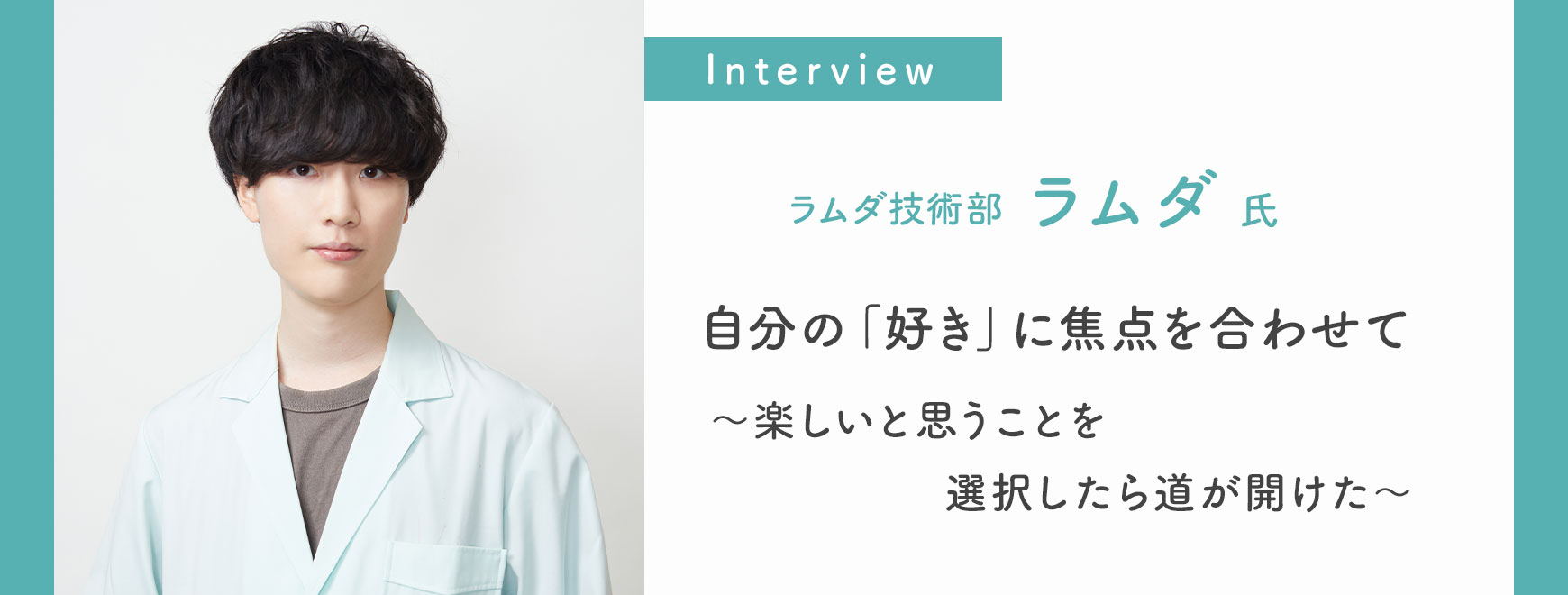動画制作秘話
伝えたいことが企画に結び付く瞬間
現在、講座やプレゼン、YouTubeなどの活動をされていますが、視聴者や傍聴者の共感や興味を引くネタはどのように考え、集めているのでしょうか。
伝えたいことというのはたくさんあります。結構リストとしてストックされていますよ。でも、それをそのまま解説しても、授業と一緒であまり面白くないなと思っているので、じゃあどういう企画とセットにしたらその伝えたいことを楽しく伝えられるかというのは常に考えていて、見つかった瞬間に企画化するという感じです。
具体例では、雪玉を斜面に投げて二次関数を描くという動画を投稿したんですよ。これもたまたま雪山に遊びに行った時にちょっと試してみたらうまくいったので撮ったのですが、二次関数というのはすごく大事な概念なのでしっかり伝えたいと思っていたんです。ただ、その性質を使った面白い例が動画としてすぐには思いつかず、ずっと蓄えていた企画でした。それがつながった瞬間にああいう雪玉の動画となって投稿されたという流れだと思ってもらえればいいかと思います。
普段の勉強の中で、これはみんなにも知ってもらいたいけどどうやって伝えようかなというネタがいろいろある中で、日常生活につながったものが動画として形になるということですね。
そうですね。自分が専門として勉強してきたことに関しては、理想的には全てそれができるといいなと思っています。ただ、今その中でも動画にできている部分は分かりやすい概念の一部だけなので、まだ動画にできてない部分を常にどうしたら企画にできるかと考えて生活しています。
ターゲットを明確に
動画の中の説明がすごく分かりやすいと思います。講演も分かりやすいし、プレゼンも面白いのですが、話す時や動画でポイントを抑えて伝える時に意識されていることがあればお伺いしたいです。
動画に関してはターゲット層を明確に決めていて、それは中3生くらいなんです。もちろんその他の年代の人が見てはいけないというわけではありませんが、中3で一応義務教育を習い終えた人なら完璧に理解できるくらいの目標を決めて、そのレベルに合わせて説明するようにしています。
それは今まで塾講師として、個別指導でも集団指導でも中3生とたくさん関わってきたので、(特定の)この子に話してこの表現で伝わるかなと昔の記憶を辿ってシミュレーションしながら動画の原稿を作っているところはあります。ということは、副次的な効果として中3以上の大人にはもう少し理解しやすいような動画の仕上がりになっているのかなとは思っています。
講演会ではターゲットがその時々だという感じがあるのですが、動画に比べると一発勝負でしゃべらないといけません。僕はそういうのは実はあまり得意ではないので、日々どうするとうまく伝わるか勉強しているところです。
具体的には、もう本当に小手先のテクニックですけれど、フィラー※を入れないとかですね。「えっと」などとあまり言わないようにしています。そういうテクニックを調べて、講演会でどう話せばぶっつけ本番できれいに話せるのかなと考えています。
例えば、細かいところですけれど、主語と述語の対応のように日本語の文法として正しい言葉を発せているかなというのを後から動画で確認するとか、そんな感じですかね。
※フィラー(filler)とは、会話においては「えーっと」「あのー」「ん-」のような、言葉に詰まったときなどにでてくる言葉。
講演の時は話し方を復習して、次はもっとうまく話せるようにという努力もされているということですね。
まあそういうことをしながら、少しずつましにしていっているというところですね。
動画のターゲットを明確に定めているということは知りませんでした。だからこそ、みんなに分かりやすく楽しめる動画にもなっているのですね。大学生もいろいろな場面でプレゼンすることも多いかと思いますので、ターゲットをしっかり意識する姿勢というのは、学ぶべきだと思いました。
ターニングポイントとなった動画
今まで投稿された動画の中で、特にお気に入りの動画があれば教えていただきたいと思います。
これもよく聞かれるのですが、最近投稿した動画に関しては、まあ大体気に入っていますね(笑)。じゃあ何が代表的な動画なのかなと考えた時に、やはりチャンネルとして成長のターニングポイントになった動画というのはしっかり記憶に残っているわけで、それはいくつかあります。
最初にラムダ技術部が誕生したきっかけとしては、高専在学中に投稿した「ワンクリック詐欺を作ろう」という動画ですね。これをニコニコ動画に投稿したら、最初から割とバズったんです。バズったら楽しくて、脳内麻薬みたいなものが出て投稿がやめられなくなって今に至っているという感じなんですけど(笑)、これがきっかけです。
それからもう一つ、大学に入ってから投稿した「ダサいスライドを作ろう」という動画。これがまたちょっと再生回数が伸びたんです。これは分野を拡大する理由にもなった動画です。もともとはプログラミング一択でやっていたのがアプリを使ったものに拡張していくことができた。活動の幅を広げることができたきっかけになった動画ですね。
そして就職してすぐに投稿した「フリーWi-Fi盗聴してみた」という動画。これは単純に数字がすごく伸びて、初めて200万回再生に達したという動画です。2020年ぐらいに年間の所得が20万円を超えたので確定申告しないといけない、職業YouTuberと言っていいのかなと思ったそのタイミングで投稿した動画です。
そこからは大きなターニングポイントになった動画はないかなという気はするのですが、だんだんもう少し理系っぽい感じで分野を広げながら拡張していって、水素水から水素を除去してみたり音姫を改造してみたり。その辺りで「あ、こういう動画でもいいんだ」と悟った動画はいくつかありますね。
自分も「ダサいスライドの作り方」という動画がすごく面白いなと思っています。学生委員会の活動では結構プレゼンをする機会があります。例えば交流会のスライドを作ったり、店舗のポスターやポップを作ったりするときに、どうしたら組合員に見てもらえるかと考える中で、逆にダサいスライドにならないように頑張ろうと、学生委員のみんなで見たのを思い出します。
私は「フリーWi-Fi盗聴してみた」という動画がきっかけでラムダ技術部と出会いました。その頃から高校の受験期にかけて、自分が憧れていた分野というのもあって、授業や勉強の休憩にYouTubeを見る機会がすごく多くなりました。
ITリテラシーに関して
情報社会での注意喚起を目的とした動画や講座などにおいて、ラムダ様が重要視されていることをお聞かせください。
ワンクリック詐欺や架空請求など、いつ自分が被害に遭ってもおかしくありません。情報系の注意喚起に関しては、基本的には全ての動画企画と同じようなコンセプトでやっています。特にITリテラシーのような動画は政府や関連団体、フィッシング対策協議会、日本サイバー犯罪対策センターなど公式団体が被害を減らしましょうと呼び掛けていて、自分もコンセプトとしてそういう被害を減らせるようなことができればと思っています。
ただソーシャルグッド※みたいな動画は、面白くないと広く伝わらない。だからこれも、どういう企画とセットにすると ITリテラシーが向上するような企画として楽しく伝えることができるのかなというのを重視して、常に考えていますね。
※ソーシャルグッドとは、社会(Social)に対して良い(Good)インパクトを与える活動・サービス・製品などの総称。SDGsや気候変動対策など地球規模課題の解決が注目されるなかで、多くの企業が自社の利益を確保するだけではなく、社会に貢献して自社の存続意義を示すことが必要になっている。