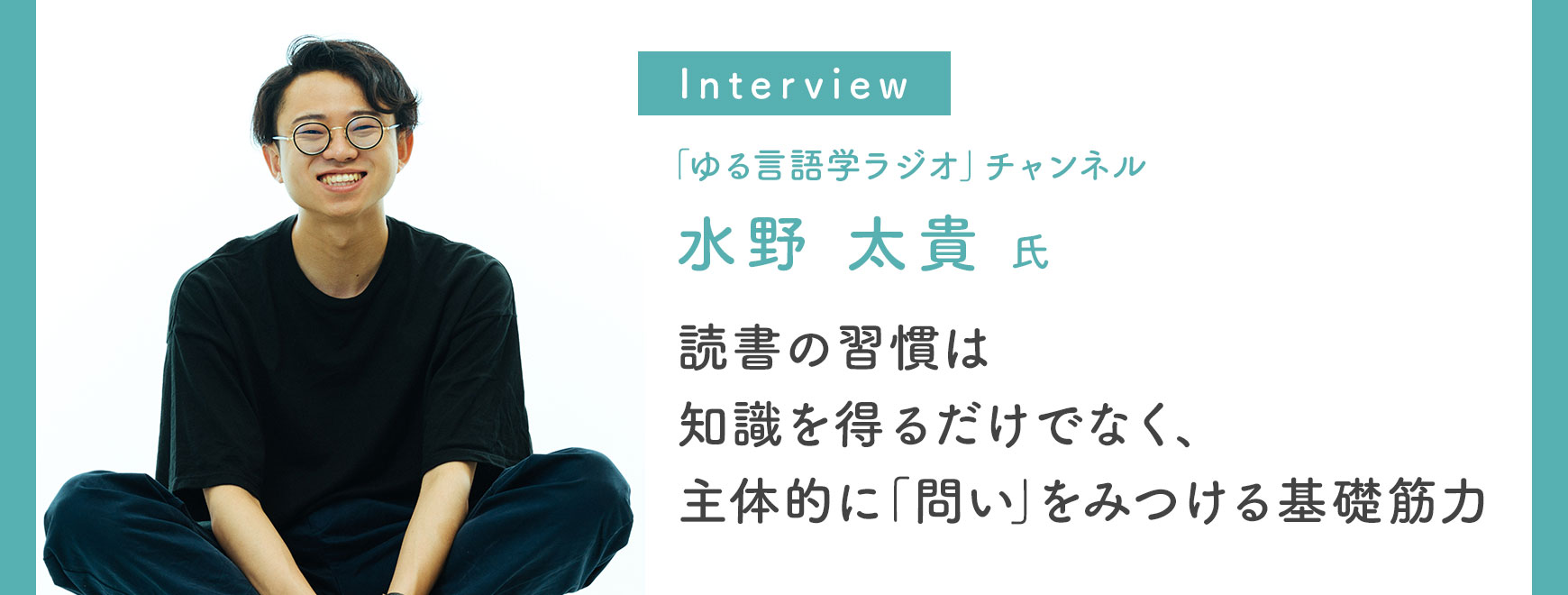- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 水野 太貴 氏インタビュー
- 水野 太貴 氏 インタビュー(読書を手段とする興味・関心の広げ方)
読書を手段とする興味・関心の広げ方
知識をインプットするコツ
「ゆる言語学ラジオ」では、自分の興味・関心にのめり込むタイプなのかなと拝見しています。学術書や専門書を読み込んでいたり、辞書なども通読されたりしていますが、主体的になりにくいという大学生が多い中で、ご自身がインプットする際の手法や考え方はどのようなものですか。
大学生に一つ伝えられるのではと思うのは、研究者にならずに消費だけするという生き方もあるということです。
まず、難しい本を丹念に正確に読むようなことはしてないですね。順に解きほぐしていくと、学術書や専門書は読み込んではなく、つまみ食いという感じが近いと思います。例えば専門書などは研究者が読むことを想定して書いているから、結果に至る過程が詳細に書いてあるわけです。でも仮に、研究者にならずに消費者でいるのであれば、結論だけ読んでもいいわけですし、読み方は自由なわけです。僕は割とそういう感じで、例えば論文が8本入っている書籍を買った時も、興味を持った論文はじっくり目を通しますが、難解な箇所を一生懸命に理解しようとしていません。それはある意味では怠惰とも言えますが、そういう読み方をしたらいけないわけではないからです。でも、読書に慣れていない人は、書いてある内容を全部理解しないといけない、全部自分のものにしないといけないと思い込んでいて、それによって不幸なミスマッチが生まれている気がします。
インプットは「この時に使うかもしれない」と思うと定着しやすいという、一般的な傾向があると思うので、その前提で興味・関心を広げるために僕が大学生の頃によくやっていたことは、人に会う予定から逆算して、その人が研究していることについての本などを読み、理解しておくことです。具体的には、来週会う後輩が生物学科だったら何か進化論の本でも読むことにします。そうすることで話が盛り上がるし、話が広げられて深堀りもできるじゃないですか。だから出版社の人にOB訪問する場合は、出版業界に関する本や編集者が書いた本を読んだりしていたので、就活の時は大量のインプットが欲しくなりました。大学生の頃は受動的だけど、関連した勉強というか、本を選んで読むことによって視野を広げることができると思います。自分の専門と関係ない本をたくさん読むことになるというのが、結果として一番大きかった気がしますね。
あくまでも体系的に学ぶことを意識しすぎるわけではなくて、過程と結論をつまみ食いみたいな感じで読んでみて、それで興味がでて学びたい、研究したいと思ったら、それを読み込んでいくということですか。
そうですね。真剣に読み込むことをやっていないわけではなくて、たくさんつまみ食いのように読み進めるなかで、この理解だけでリターンが大きそうだぞ、となると勉強するみたいな感じ。だから結果的には、そのつまみ食いのように読み進めていくと、コスパが悪くなるタイミングというか、知りたいことが全部ここにつながっているのではないか、というところにあたるようになります。例えば、YouTubeを作るなかで、言語学の意義について考える時に、論理学の基盤が必要のようだし、堀元さんがやっているコンピューターサイエンスの方でも、どうやら述語論理という概念が出てくるようだとか、論理学につながることが多くなると、リターンが大きそうだから勉強するという感じですね。
読書で「問い」を見つける筋力をつける
大学生の頃は受動的に、勧められた本を読むこともよくやっていました。例えば人に会う時にお勧めの本を尋ねると、自分では絶対読まない本が返ってくる場合が多くて、相手も勧めた本を読んできてくれる相手だと嬉しいし、読んだ感想を喋れば盛り上がるわけだから仲良くもなれるわけですよね。そうして読書の幅が広がったと思います。ある程度のインプット量があると、気になるテーマみたいなものが自然と出てくるようになるので、自分が興味あるもの、知りたいことを自分で主体的に見つけられるようになったのは、もしかしたら社会人になってからかもしれないですね。
確かに大学生にとって自分で問いを見つけることは、多分卒論とかですよね。そう考えると、問いや定義を出し、仮説もした上で先生が一緒に手伝ってくれる小・中・高校の教科書での学びはすごくよくできているし、主体的に問いを見つけられるようになるために読書をしていくことは大事なことだと思いました。
問いの見つけ方とか、自分が興味を持てることの探し方などを教えてくれる本はもちろんありますが、そういうリサーチクエスチョンの始め方みたいな本にほとんどの人はアクセスすることが難しいし、実際僕は大学生の頃に本を1,000冊くらい読んだのですが、大量のインプットをしてようやく問いが見つかるようになった感じです。知りたいことについて調べるためにはどのような本を読めばよさそうかという勘が働くとか、面白そうな本かどうかをパラパラ見ただけで判定するなどのスキルは、ざっくり1,000冊読むことである程度身についた感じでしたね。
でも、一つは僕の学科が比較的時間に余裕があったというのも大きいと思うので、毎週のように教科書を読み込んで勉強しなければいけない学部の学生さんには、同じようにできるとは思わないですね。
読書の変遷は人生の変遷
小説を読まなくなった理由
学術書や専門書の話はすごく多いですが、逆に文芸書や小説を読むことはありますか。
大学生の頃はありましたね。だから社会人になって小説を読めている人はすごいと思っています。
僕が小説を読まない理由は、単純に自分に今必要だと思っていないからというのが大きいです。書評家の三宅香帆さんが著書で「小説は自分の人生のテーマと重なるとすごく面白い」というようなことを書かれていて、例えば恋愛で傷ついた時に失恋物の小説を読むと共感できるし、就職活動をする時に朝井リョウさんの「何者」を読むとすごく印象に残ったり。社会人になってからそういうテーマがあまりないから、どちらかというと教養書みたいなものの方が入ってくるというだけで、人によっては小説の方がいいという人がいると思いますけどね。
確かに、中学校の時にずっと「都会のトム&ソーヤ」という本を読んでいて、いま大学生になったら読まなくなったことを考えると、自分を投影していたことはあったと思いますね。
そうだと思いますよ、多分。だから悩みとか自分が直面している大きなものと、その本のテーマが重なるとすごく自分に入ってくるはずで、実際に自分はそうでした。そういう本の選び方ももちろんあるし、大学生のうちに読書に対する力を鍛えておけば社会に出てからも使えるので、例えば悩んだ時に対処する方法を模索する一助になると思いますけどね。
大学生の時こそ読書を
読書の話と関連して、今の大学生が置かれている状況として、なかなか主体性が持てないという声もあったりする中で、大学生にとってどのような学びや、学びの機会が必要だとお考えですか。
社会に対する提言みたいなものがあまり自分の中にないので、繰り返しになるかもしれないですけど、社会人になってから新たなスキルを身につけたり、資格を取ったりするのは、結構大変で面倒なことで、最近出た「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という本とか、「ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち」という本を読むと出てくるのは、明確にこれくらいのリターンがありそうだという見積もりがとれるもの以外を社会人になってからやるのは結構大変だということです。
社会に出ると、3時間を投下したけど自分に何も得るものがなかったというものに耐えられなくなることが多くて、とりわけ平日ずっと仕事をして、特に激務だと土日を心身の回復のためにあてる生活をしていると、そういう無駄にしたことに対して落ち込むことが増えてきます。だからそういうマインドになる前に、例えば必要な失敗をしておくとことも重要だと思っていて。
僕の場合は読書でしか語れないので読書に関していえば、読んだけど面白くなかった本をある程度読まないと、面白い本を探すことはできなかったりするし、あと読書は苦手な人にはものすごい負荷がかかる行為なので、忙しくなってから読書の習慣を身につけるのは更に負荷がかかりますが、僕みたいに大学生の頃にある意味サボりながら読むということ、一生懸命全部を身につけるのではなく、自分に引っかかる部分を見つけて読むことが早くできるみたいな能力をつけておくと、忙しくても読書ができるから、そういう感覚で大学生の時間を使っておくと、もしかしたら大学生の頃にはできなかったけど、社会人になってからそういう主体的なテーマ設定を見つけるみたいなことはできるかと思います。
今はそれを簡単に発信できるテクノロジーがいろいろ整っているので、YouTubeでもいいし、ブログでもいいし、Podcastでもいいし、そういうデバイスはいっぱいあって、それをやるのは楽しいから、大学生のうちにそういう基礎筋肉みたいなものをつけておくといいかなと思いますね。
私は国語教育専修に通っておきながら大学の勉強が忙しく、なかなか本に向かうことができていない状況ですけど、社会人になる前にできる失敗をしておくことも大切だというお話、いますごく身に染みて感じました。大学生活が少し残っていますので、これから少しでも意識を向けていきたいと思いました。
別に読書じゃなくてもいいですが、比較的読書の方が何か知識を得るときに転がっているものが多いと思います。今の日本だと論文のオーディブルなどはあまりないので、時代が追い付けばそういう形でのインプットも可能でしょうが、現状だとやはり本しかないという意味では、僕は一番効率がいいと思うので、大学生の頃の時間に余裕のある時に習慣つけておくだけで、今後の人生で大きなリターンが返ってくると思うので、ぜひ頑張って身につけてもらえると、自身が出版関係者でもあるので嬉しいなと思います。最初から難しい本を読まずに、自分が読み通せそうだと思える、例えば1週間で読めそうだと思えるような薄い本から始めてくださいね。