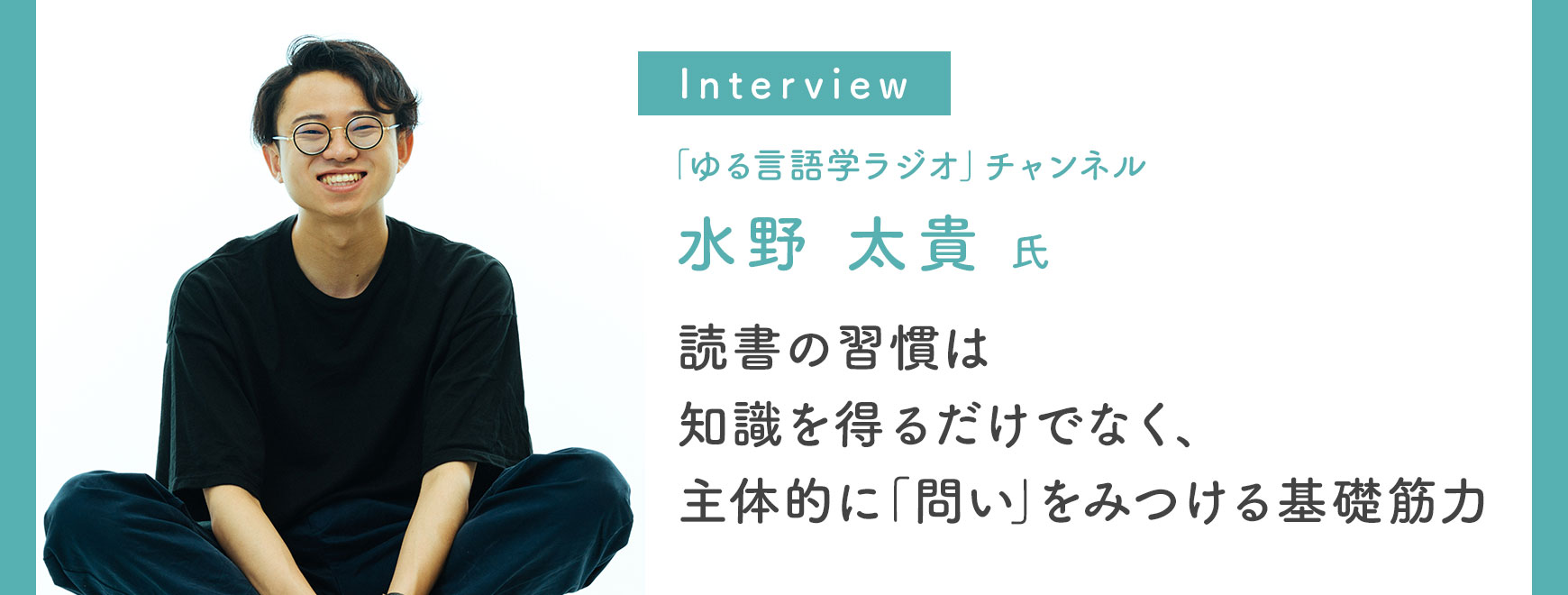- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 水野 太貴 氏 インタビュー
- 水野 太貴 氏 インタビュー(好きな書店のタイプ)
好きな書店のタイプ
南部購買の思い出
読書を再開するきっかけは南部購買で本を買って、というお話がありましたが、生協の書籍コーナーの印象はいかがでしたか。また、どんな書店がお好きですか。
全く面白くない話ですけど、まずやっぱり安く買えるのがありがたかったですね。書籍は基本的には割引では買えないので、新刊が出ると必ずそこで買うように気をつけて漫画を安く買っていました。あとは、普通の書店にはあまりない言語学のコーナーがちゃんとあるから、いい本に出会ったことはありましたね。難点としてはもちろん、あまり書籍の入れ替えがないというか、大きくガラッと中身が変わることがないから、最初の衝撃をあまり更新されることはなかったですけど、それでも身近なところで簡単に言語学、言語関連の書籍を見られるのは大きかったですかね。
あと大学生協の書店は、岩波文庫がたくさん置いてあるから嬉しかった覚えがありますね。岩波の書籍は買い切りなので、一般の書店はリスクが高くて仕入れにくいですけど、大学生協は岩波のラインナップの比率が、売り場面積に対してすごく高いことが嬉しかったですね。それって学生を尊重しているというか、岩波なんて読まないだろうではなくて、大学生協の強気が見て取れますよね。それは嬉しかった覚えがありますね。
テンションが上がる書店とは
好きな書店でいうと、僕は一つのテーマについて、いろいろな角度の研究者の本を読むのが好きで、例えば「なぜあの人のジョークは面白いのか」という本は進化生物学者がジョークについて研究した本で、それとは別に「限界芸術『面白い話』による音声言語・オラリティの研究」という専門書は言語学者が面白い話を分析した本、つまりそれぞれはジョークや面白い話を言語学の観点と進化生物学の観点から見ている本で、普通のジャンル別で分けると重ならないようなこういう2冊が横に並べてあると、気の利いた書店だなと思いますね。
例えば似た話で、最近「Mine!」という所有に関する書籍が出て、それは法学者が所有権をめぐる面白話を集めた本ですけど、それと例えば持つという動詞についての分析の本が横に並んでいたりすると、この2冊を読むといろいろな角度で「持つ」について知ることができるという並べ方をしてくれている書店だと感じて、やっぱりテンション上がりますよね。それはやっぱり個人の、それこそ独自の仕入れをしているような書店さんに多いかもしれないですね。県外の皆さんに全然通じなくて申し訳ないですけど、愛知県だったら「ON READING」という東山の書店さんとか、「TOUTEN BOOKSTORE」という金山にある書店などが、今の例に該当するのかなという気がしますね。
もしかしたら、それは少し上級者向きかもしれないですけどね。初心者の方には売れている本や面白い本がドーンって置いてある方が親切なのかもしれない。ただ若干慣れてくると、そういう並べ方に工夫がある方が書店として個性が出るので面白いかなとは思います。
自身のアウトプットから広げる未来
知識を得る楽しさの芽を自分で育てる
「ゆる言語学ラジオ」や「ゆるコンピュータ科学ラジオ」などのコンテンツを通して、どのような人が増えていけばいいなと思われますか。
これは堀元さんというより僕の意見ですけど、一つはさっきも言ったように「研究はしないけど、学問は面白い」人たちがいてもいいと思うのです。どうしても学問となると最終的には研究をする、だから研究をせずに学問を消費している人は、研究をしている人に比べて劣っているという考え方をしている人もいると思いますが、僕個人としては消費しているだけでも、全員が作り手にならなくても、むしろその方が、競技者人口が増えるのではないかと思っています。
僕も堀元さんも学部卒なので専門的な知識は全然ないですけど、社会人になってから、こうやって研究とは関係なく無責任に勉強して、ある意味無責任に研究について語り合う趣味があっても別にいいと思います。その様子をYouTubeで見せることで「研究者になるわけではないけど、学問は面白いから消費する」みたいな人が増えてくれたら嬉しいと最近は思っていますね。
私も最近発信された「ビジュアルシンカー」のような、そういう知識を得られるだけで楽しいと思うことも非常に多いので、自分から発信していくのではなくても学問の世界に入り込めるという環境はすごくいいなと思いました。
浦田さんが「知識を得るのが楽しいと思った」と言われましたが、その気持ちを自分でうまく育てると大きくできると思います。僕の場合は、本を読んで「やっぱり、これは面白いな」というのを確認し続けることで、その気持ちが相当大きくなり今がありますが、多分その芽は逆に放っておくと忙しくなることで消えてしまうこともあるので、大学生のうちにそれを大きく育てておくと社会に出て忙しくなった時でも、仕事のことだけを考えるようなことがなく、趣味の世界に逃避することができるのではないかと思いますね。
読者の皆さんへ
おそらく読者の大多数が大学生などの若者世代になると思うので、その世代に向けてのメッセージをお願いします。
あまり自慢できる大学生ではなかったのですが、就職活動自体は割とうまくいって、友達と一緒に始めたYouTubeも多くの人に見てもらっていて、大学生時代だったら絶対にアクセスできなかった言語学者と対等に話したり、あるいは褒めてもらったり、サポートしてもらったりすることに驚いている日々を送っています。だから授業をサボって研究に向いていないとか、大学を選択したことに迷いが生じても、いろいろなことが確定するのは少し後だなというのが、ここ最近実感していることです。僕の場合は読書を大学生の頃に頑張ることで、ある意味逆転することができたので、自堕落な大学生にこそ、こういう生き方もあるのだというのを、一つの参考にしていただければ嬉しく思います。
2024年4月30日リモートにてインタビュー
PROFILE
水野 太貴 氏

1995年 愛知県生まれ。
名古屋大学文学部卒業。大手出版社勤務。
主に言語学をテーマとした「ゆるく楽しく言語の話をする」をコンセプトとする「ゆる言語学ラジオ」というPodcastやYouTubeチャンネルを堀元見氏と共に、製作・出演している。
YouTubeチャンネル登録者数26.5万人(2024年5月現在)
2023年4月7日、番組初の著書『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』を刊行した。
▼受賞歴
・JAPAN PODCAST AWARDS「ベストナレッジ賞」、「リスナーズチョイス」
・INDIE Live Expo 2022「さっさと続きを遊んでほしいで賞」、「実況アワード大賞」
▼公式HP https://yurugengo.com/
▼YouTube https://www.youtube.com/channel/UCmpkIzF3xFzhPez7gXOyhVg/featured
▼Podcast https://podcasters.spotify.com/pod/show/yurugengo