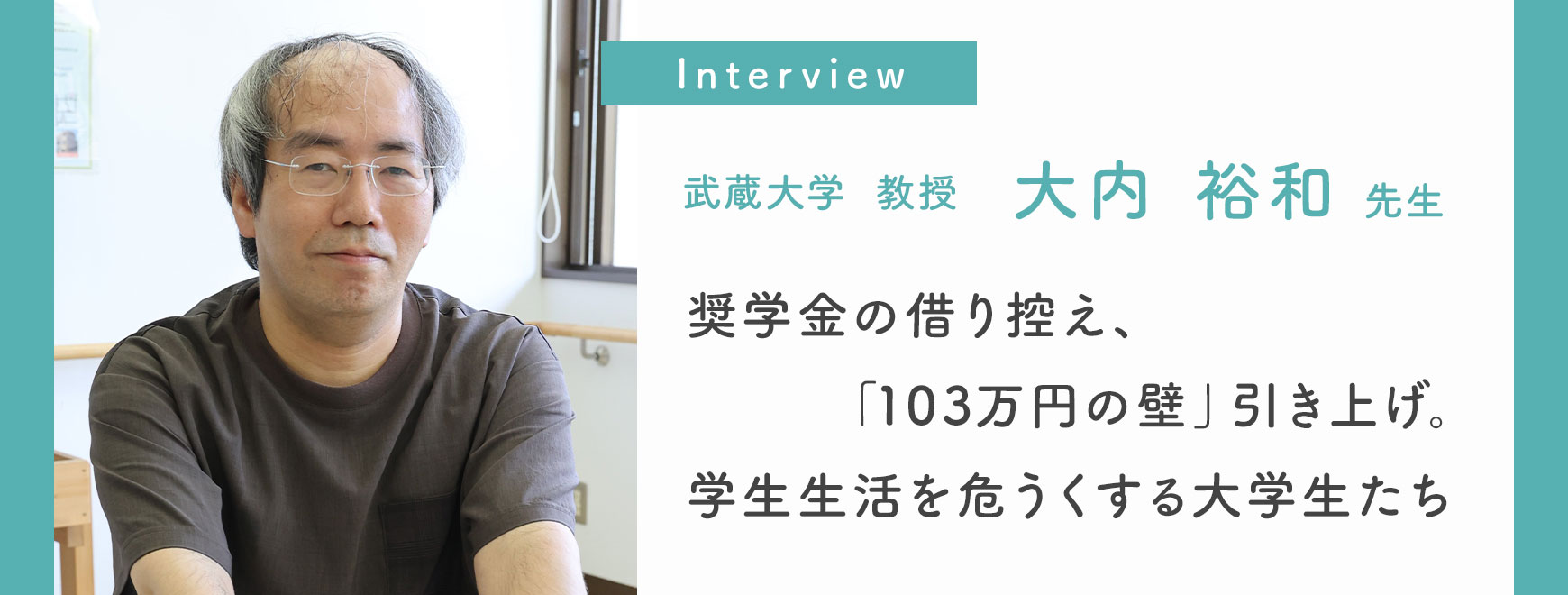- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 武蔵大学 教授 大内 裕和 先生 インタビュー
- 充実した大学生活のために
充実した大学生活のために
奨学金制度の改善点
私自身も貸与型奨学金を借りる際に親戚に連帯保証人になってもらったので、親にとって奨学金は借金という認識が強いと思います。
先生は給付型奨学金の拡充や学生の奨学金返済減免措置などの対応について、どのような対策が必要だと思われますか。
これは私自身ずっと取り組んでいることで、2012年当時と比較すれば、給付型が導入されてその利用人数が増えてきたことは大変良いのですが、まだ不十分だと思います。高等教育の修学支援新制度(※)でも当初は標準4人世帯で年収380万円までが対象でしたが、多子世帯と理工農系という条件で支援を拡大しています。しかし、多子世帯でない人や文系の人は対象から外れています。
(※)高等教育修学支援新制度
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
現在、貸与型奨学金を9割以上の学生は返済していますから、返済できなくなっている割合はそれほど高くないのです。でも卒業後の仕事や収入が分からないというリスクがあることからも、奨学金を給付型中心へと抜本的に切り替えなければダメだと思います。早急に給付の大幅拡充をしなければ、利用した人は不安を感じるし、利用すべき人が利用を忌避する傾向は変わらないと思います。
私が運動を始めた頃と違って返済猶予も5年から10年に延びたし、減額措置も月の返済額を減額することができるので、その制度を知っていれば延滞を回避できます。
ただ、これも月額が減るだけで返済総額や利息が減るわけではありません。他の国のように本人の所得に応じて返済額が減額される制度にはなっていないのです。
日本以外の諸外国の所得連動型の返済制度は、本人の所得が少なければ返済総額そのものが減るという制度です。それを導入すれば、すでに利用しても苦しまなくて済む人もいるでしょう。ここまで若い人の未婚化や少子化が問題になっているのに、なぜ給付の拡充と所得連動型の返済制度に踏み出さないのか、私には分かりません。
「103万円の壁」
先生は今回の都議会議員選挙の結果をどのように受け止めていらっしゃいますか。
私は奨学金を給付にし返済額を減額するためには、若い人が苦しまないで済むような税の取り方と配分の仕方を提案してきました。しかし、若い人たちは「税と社会保険料そのものを減額する」という政策を今回は支持しましたね。税・社会保険料の減免と手取りを増やすと言った国民民主党の支持率が20~30代に圧倒的に強いのはそのためですね(※)。
(※)24年の衆議院議員選挙においても国民民主党が「年収103万円の壁引き上げ」を公約に掲げ、議席が4倍増になった。比例区投票では若年層の支持率が高く、20代では26%と単独トップと多くの若者の支持を得た。
そうすると、実際には所得の再分配(※1)が行われず、格差が広がることになります。その事実が若い人にちゃんと届いていないので、あのように103万円の壁(※2)を壊すと言えばワッと票が入るのですね。彼らがそこに引っ張られるのは、税や社会保険料が若い人のために使われていると思えないような状況だからでしょうね。
(※1)所得の再分配:高所得者がより多くの税金や社会保険料を納めるように調整して所得格差を抑えること。
(※2)103万の壁:給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める。学生やフリーターなどが家族の扶養に入っている場合、年収103万円を超えると扶養を外れ、親など扶養者の所得税と住民税が増える。
だから奨学金が完全に給付になり、返済が減額され、さらに学費が大幅に下がるということに税金が使われれば、その世論は一気に変わると思います。それができなければ、税金や社会保険料そのものを払いたくないという方向に流れ続けるでしょう。
私たちの運動は奨学金制度の改善を着実に進めてきたのですが、若い人たちの深刻化する困難のスピードには追いついていません。私たちの運動の成果が不十分だから、「税と社会保険料を減らせ」という分かりやすい主張に若い人たちが引っ張られてしまうのでしょう。そのことに重い責任を感じています。
アルバイト優先の学生たち
学生のアルバイトの現状
学生が学業とアルバイトを両立する上で、どのような課題があるとお考えでしょうか。また、学生にはどのような大学生活を送ることが望ましいと思われますか。
これは私が2013年からブラックバイト問題に取り組んだ理由と関わります。私の学生時代は、アルバイトに苦しむとかアルバイトを辞めたいのに辞められないなんてありませんでした。アルバイトというのは基本的に働く側には責任がなく、休みたければ休めるし辞めたければ辞められる。まして試験前に休むのは当然でした。私たちは学生生活を優先し、その上で仕事を調整したからです。
友達と自由に集まれるのが学生生活のいいところですよね。ところが今の学生は、アルバイトのシフトが調整できなくて一斉に集まることができないのです。今年の1年生からも『友達と会えない』という相談がありました。バイトのシフトを調整できないので4人で集まれるのは2カ月半後ですって。社会人みたいな話です。私はアルバイトを簡単に調整できて友達のある学生生活を過ごしたから前提が違うわけで、今の学生は可哀想で仕方がないですね。
また知りあいの学生たちは、興味で授業を選ぶのではなく「木曜日はバイトを入れるから空けておく」。せっかく望んだ大学に入ったのにバイト優先で、取りたい授業があっても取らないのです。もちろんそうでない学生もいますよ。でも私の知る多くの学生は、自分の興味を持った授業よりもバイトを優先しているのです。
ブラックバイトって?
“ブラックバイト”って、一般にバイト先で酷い目に遭うことだと思われています。でも私は、『学生であることを尊重しないアルバイト』をブラックバイトと定義しました。でも私の教える学生たちはブラックバイトが当たり前で、前の日に深夜のシフトがあるから次の日の午前中の授業は取らないとか、シフトがあるから友達と会えないとか。大学生活は4年間しかない貴重な時間なのに、それが普通になっているのはおかしいでしょう?
さらに、バイトにのめり込んでバイトにやりがいや手応えを感じるという学生もいます。そうした学生は、バイトはとても充実していると言い、むしろメインは働く方でその合間に大学に来ているような生活を送っています。でもそれは、学ぶ中心でなくて稼ぐ中心の生活になっているのですよね。
それはやはり望ましくない。学生が悪いのではありません。授業・ゼミよりもバイト、大学よりもバイトになってしまっている学生が大勢いますが、それによって学生同士が大学での人間関係を深められないとか、充実したゼミ活動ができないという弊害が生じています。つまり徹頭徹尾学生生活がないがしろにされているのです。
だから「学業とアルバイトを両立する上での課題」「両立させる上で望ましいこと」という漆崎さんの質問に対して、そういう状況になっている背景には、学生が経済的に困窮しているという事情がありますし、その責任は学生にはありませんから、私は学生たちにこうしなさいなんて答えられる立場ではないと思います。
私が答えられる立場ではないということは前提の上で、私は学生が充実した学生生活を送れるように奨学金制度の改善や学費の引き下げに向けて頑張っていますから、学生の皆さんにはその当たり前になってしまっている今の状況を疑ってもらえたら嬉しいですね。何を言いたいかというと、「バイト先に過度に組み込まれることであなたの学生生活が奪われていませんか?」ということです。お金がなくて大変なのですからとても難しいですが、自分たちの学生生活をメインに考えて、自由な学びを奪っているものは何かを見つめてくれると嬉しいです。学生の自由な学びを奪っているのは、高い学費とダメな奨学金制度だと私は思います。