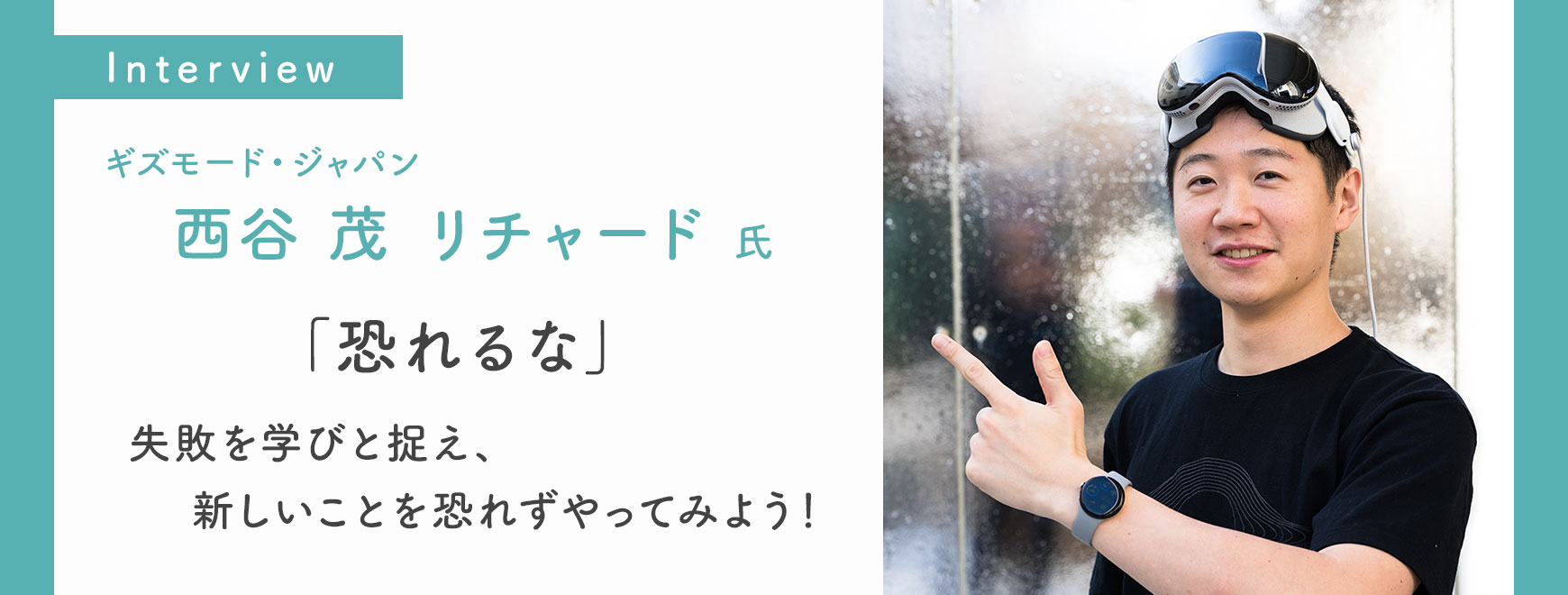- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 西谷 茂 リチャード 氏 インタビュー
- 世界における日本企業の特性
世界における日本企業の特性
主にこれから日本の工業や理工学の企業を担う学生に向けて、お答えいただきたいと思いますが、リチャードさんから見た海外企業と日本企業の差であったり、日本企業の強みだったり、逆に課題と思われる部分をお聞かせください。
これはですね、非常に難しい質問だなと考えていまして。というのは、製品の大小もありますし、それを全般踏まえてとなると、割と無難な答えしか出ないからなのですが。
日本の強みはやはり、いくつかあるうちの優先度が高いものを言うと、サプライチェーンがある程度備わっているというのが強みかなと。例えば、特殊な鋼材とか、金属の張力が強いもの、曲がりにくい硬い金属などは、製造にかなりの技術が必要らしく、日本はそういった素材を作るのが得意なので、それを使った製品、自動車などは得意分野ですよね。
もう一つ次の強みとしては、そこがあまりDXされてないというところですね。そういった企業にこれから就職するという人は、その会社に対して自分が持っているデジタルの素養が大きく貢献できると思うんですね。もしくはそのライバルのベンチャー企業とか、中小企業に入るという方も、大きな企業に対してのそこがエッジになり、DXの面で勝てるということがあるはずなので、日本という市場で見たときにそこが強みになると思います。
逆にそれはグローバルにおいては弱みなので、課題かなという感じがしますね。ハードウェアは過去の遺産がたくさんあるけど、ソフトウェアは一部の業態を除いて、日本はもう少し伸びしろがあるのではないかと思います。
それから、社会課題と先進性というのがあります。大きなもので言うとやはり少子高齢化で、これに対する製品やサービスは、やはり少子高齢化が進んだ国じゃないと作りにくいということがあるんですね。どんな国もいずれは少子高齢化に突入すると言われているので、日本で先にいいものを作ることができれば、海外展開もしやすいのかなと。さらにそういったものを作る時に、言語の壁や文化の壁がまだあるので、海外の企業が日本に参入しにくいので、ある程度グローバルにおいては守られた環境で、そういったサービスや製品作ることができるのはチャンスです。
日本のDXされていない部分というのが気になるのですが、もう少し具体的にこう変わればみたいなことをイメージされていたりしますか。
特定の例は挙げにくいので、曖昧な言い方で言うとインフラ周りなどですね。例えばアプリがあったとしても、すごく多くのステップを踏まなければいけないとか、特定のやり方でないと何かが達成できないとか、ユーザーとして使いづらいことがあります。やはり本当の意味で、ユーザー目線で物事をDXしてほしいというところです。
言い方を変えると、物事の優先順位をすごく意識してほしいんです。ユーザーがそのアプリやサービスを使うときに、その人が達成したいことがすぐに明確に手順がわかるようなデザイン、それができていれば、問題ないのかなと。すべて一挙に対応しようとすると、すごく難しいシステムになってしまうので。
学生時代の過ごし方
自分のやりたいことを見つけるには
とりあえず大学に入ってみたけれど、自分のやりたいことを見つけられない人が結構多いと感じるのですが、どうしたら自分の興味って見つかるのかなと思うのですが。
これはね、恋愛に例えるとしたら、とにかく「たくさん当たって砕けろ」ですね。
大学に入り、いろいろな課題やレポートを書いてみて合わないなと思ったら、それは自分の興味は他の部分にあるのではないかという学びだと思うんですよ。なので、そこで立ち止まるよりも、次に何か新しいことをやってみようと、どんどんチャレンジできれば、多かれ少なかれどこかで自分のやりたいことに出会うのではないかと思います。
それでも出会わなかったら、将来自分がやりたいことに出会った時にすぐ行動ができるように、お金なり、資産なり、友達を増やしておくなり、そういったアクセスできるリソースを増やしておくことが、直近のゴールじゃないでしょうか。
僕は理工学部のソフトウェア系のコースだったんですけど、大学2年生の頃にコース選択に違和感を覚えて、作るというよりも活用して何かをすることの方が好きだと感じて、そこから職業の選択を考え始めた経験があるので、すごく共感しました。
たぶんそこの知見は無駄にはなってなくて、絶対やって良かったと実感できる人生になると思うんですよね。全部やってみていい。いろいろやりたいですよね。
経験は無駄じゃない
やってみないと、自分に合うか合わないかは分からないと思うので、まずやってみる、手を伸ばしてみることはすごく大事だと思いました。
過去にやったことが意外な形で活きた経験はありますか。
学生時代の長期の休みに、不健全なほどゲームにのめり込んでいたことがあって、日常生活でゲーム操作をしてしまうほどに、ゲームの中と実際の自分の体の感覚が密接につながっていた時期があったんですよ。
ただ、そのゲームに勝つためにアイテムを比べて勝率を計算したりしていたことは、ある種のデータ分析力として後ほど活きてきましたし、のめり込んだ経験というのは、これ以上やったら危ないなというストッパーとして機能してきていたりとか、あとはゲームをやっていたからこそできた友達がいたりとか、そのゲームの経験がギズモードでのゲーミング PC のレビューで活かされたりしましたし、あまり調子に乗らない程度に、色々試してみればいいんじゃないかなと思います。
若者世代へのメッセージ
最後になりますが、このインタビュー記事の読者の大多数を占める今の若者世代、大学生世代に向けてのメッセージをお願いいたします。
事前に企画案をいただいて、ここだけずっと答えが出なかったんですよ。
今も正直出ていないんですが、自分が学生の頃に聞きたかった言葉で言えばいいのかなと、このインタビュー中に思いつきました。
一言で言うと「恐れるな」ということですね。
もちろん、本当に怖いものは正しく恐れなければいけないですけど、大抵の新しいことや新しい人、アクティビティであれなんであれ、やらないから、知らないから怖れを感じるのだと思うんです。挑戦してみて本当に嫌だったらそれは学びですし、若い頃の失敗って、その後の自分から見ればありがたく思えるものです。その学びあるから、もう似たような失敗はしないというのもありますし、そこにずっと興味を持ち続けなくなるので頭がクリアになります。あの頃あれをやっていたらとか、今からやってみようかな、やめとこうかなって、3年前も今も3年後も悩んでいるなんてもったいないじゃないですか。だったら、やればいいですし、失敗したらそれはそれで面白いエピソードになる。そう考えると失うものはあまりないし、得るものばかりなので、とにかく新しいことを恐れずにやってみたらと当時の自分に伝えたいです。
本日はたくさんの質問に答えていただき、本当にありがとうございました。
2025年4月3日 リモートインタビューにて
PROFILE
ギズモード・ジャパン 西谷 茂 リチャード 氏
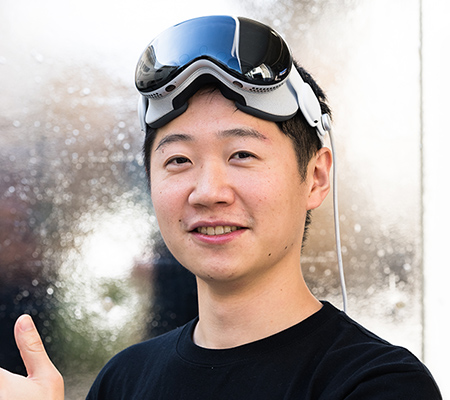
アメリカの人気テクノロジーサイト「GIZMODO(ギズモード)」のライセンスのもと、株式会社メディアジーンが運営する「ギズモード・ジャパン」編集部に所属。編集者・レビュワーとして、最新ガジェットの紹介をはじめ、多様な情報発信を担当。記事執筆に加え、動画やメディア出演、SNSでの発信など、マルチな形でテクノロジーの魅力を伝えている。
(公式サイトより一部抜粋)
ギズモード・ジャパン https://www.gizmodo.jp/