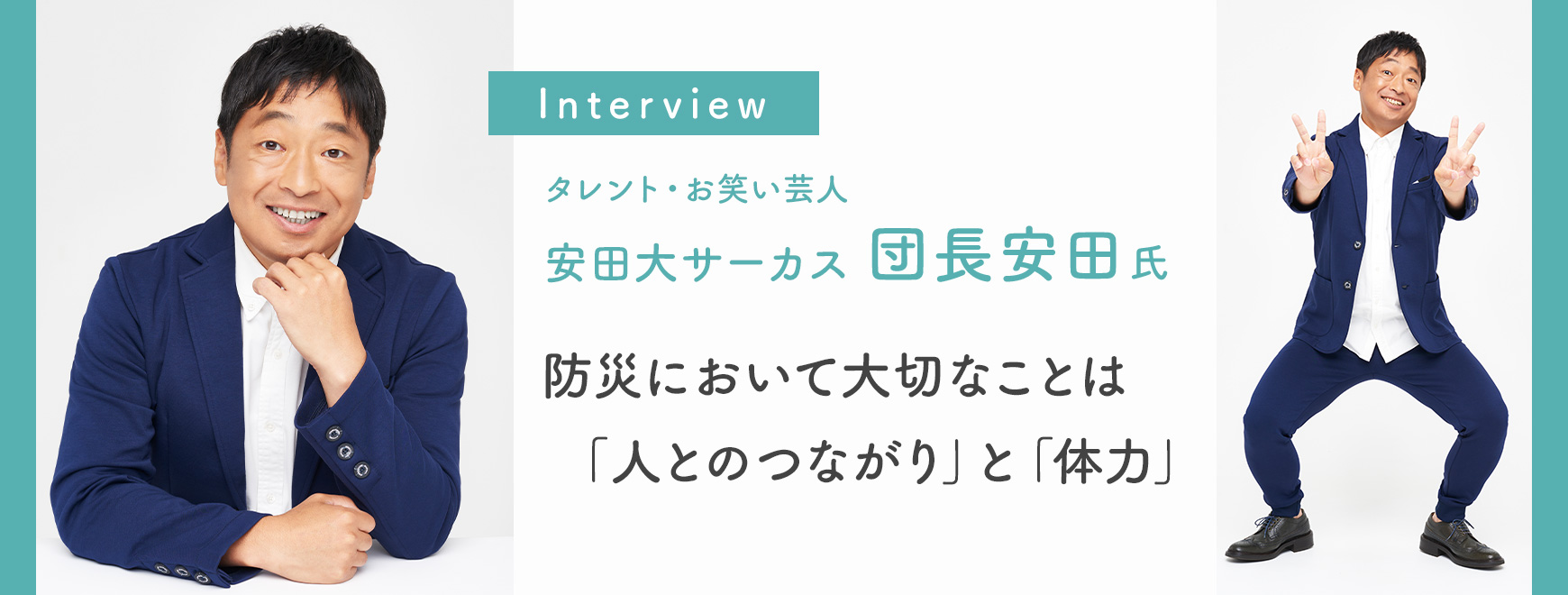阪神・淡路大震災
1995年(平成7年)1月17日
まず、阪神・淡路大震災当時はどのような生活をされていたのか、あとは実際に当時から防災の面で意識されていたことはありましたか。
震災時は、成人式の2日後の朝5時で、僕は寝ていました。当時、関西は地震が全然ない地域で、備えというよりも地震なんて起きないと思っていたので、何も用意はしてなかったですね。揺れはじめると、ベッドの上でもトランポリンのように飛んでいる感じで身動きが取れず、お皿やガラスが割れる音がバリバリして、あとから見たら水槽が割れていて。でも眠たいし収まったから寝ていたら、部屋に来た母親が、寝ている自分を見てびっくりして「大丈夫か?」と。でも母親も動揺していたのか、固いスキーブーツが壁に刺さっていたのを見て「見てみ、スキーブーツあるで。あんたこれ、探していた奴やん」っていうのが第一声でした。
その後、父親の車で祖母の家を見に行くと、甲子園口の辺りから家が倒れていて進めず、逆に戻ろうとしても戻れずに揉めたり、あちこちで火事があったり、当時は信号も止まっていて混乱していました。なんとか祖母宅に行き、安否を確認してから帰宅したら、マンションの予備電池で一旦電気が普及したらしく、割れた熱帯魚の水槽の中のヒーターが漏電して火事になりそうになっていましたね。家電はまずコンセントを抜かないといけないと、それで火事になったお家もたくさんあったというのは後で聞きました。
当時は慌てて外に出て足の裏を怪我した人たちが何人かいたので、今はなるべく寝ている枕元にスリッパなどを置くようにしています。他のケガもそうですけど、足の裏の怪我は一度経験しましたが本当に辛いです。
当時の被災地の実情
もちろん水道も止まったので、洗いものができないから、お皿にサランラップ等の食品包装用フィルムを巻いて食事をしたり、人によっては寒い時期だったので体に巻いている人もいたような気がします。これが意外と役立つと覚えたのと、あとは給水が来ても水を入れるタンクがなくて、タンクを買いに行くと通常よりも高い金額を取られたりしました。
それこそ体育館の日当たりがいい・悪いでいがみ合うとか、給水が来ても手伝わないとか、カップラーメンを取りすぎだとか、もう小さなことでみんないろいろ揉めるのよ。そういうところはあまり表に出ないし、みんな一致団結して頑張っているみたいなことが報道されるけど、そんなのは本当に申し訳ないけど一部でしたね。
公園とかの和式トイレを排泄物が超えていたし、思い出すと未だに気持ち悪いよね。でも早めに自分たちの地域は食事も届いて、被災地にしては恵まれた環境ではありました。
問題はあるとこにはあって、ないとこにはないみたいなことが、当時はスマホもないので起きていることがもう口伝えや噂だけで、みんなの不満になっていたりしましたよ。そもそも目の前で起きていること、甲子園口の駅前のビルや阪神高速が倒れるなんて想像もつかなかったし、なぜ助けに来てくれないのかという感じでしょう。火の手はあがる、銀行のATMはブザーが鳴りっぱなし、自動車に電柱が倒れてクラクションも鳴り続けるとか。僕は車を盗まれましたし、近所の女の子は車の中に引きずり込まれそうになったと聞きました。治安も非常に悪くなっていたんじゃないかな。当然、電気も街灯もあまりついてないから暗くて、女の人は暗い中をあまり歩かないほうがいいと言っていましたね。
第一に自分のこと、余裕ができて人のこと
被災した時は、マラソンと一緒でペースを保たないと無理なんですよ。マラソンはゴールがあるから頑張れる、だけど被災した時ってゴールがないでしょう。いつまで頑張れば自分の家に戻れるのかわからない。被災した友達を自宅に呼ぶと、仲が悪くなることもあります。家庭のルールってそれぞれ違うから、靴の揃え方、トイレの使い方ひとつとってもイライラするわけで、その小さいことがどんどん積み重なって仲が悪くなる。被災した時に、人のためにも自分のためにも頑張るというのは身が持ちません。それができる人はいいですけど、僕はできないと思うので、自分のことだけ考えるとまでは言わないけど「第一に自分のこと、余裕ができて人のこと」くらいにしないと、精神的に辛くなってくると思います。
大学生協は協同組合では、その価値の一つに「自立」ということがあり、自分自身がある程度自立していないと誰かを助けることはできないというところで、今のお話に通じるものがあり、共感できました。
また、先ほど洗い物ができない時の食品包装用フィルムの活用法をお聞きしましたが、実は最初にお話した大学生協のリサイクル容器は、食べ終わった後にフィルムをめくって容器を回収するもので、それは阪神・淡路大震災当時の皆さんの経験から生まれた取り組みだと聞いているので、つながりを感じました。
全く協力し合わなかったというわけではないけど、そういうリアルな一面を見てきた人は話すべきかと思っていて。ドラマチックにいいことや専門的なことは他の人にお任せして、リアルなことにちょっと笑いを入れて聞きやすくして話すことが僕の役目だろうと思っています。
今まで話すことをお断りしてきた時期もありましたが、スキーブーツの話みたいな、芸人のスタイルで話すようにしています。
経験を語るきっかけ
友人の死と掲載された写真
話したくないと思っていた理由が、ご自身のなかにあったということですか。
お笑いって楽しいもので、悲しい話をするのは、自分にとってマイナスだと思っていたところがあります。だけど、きっかけはコロナ禍に僕も周りも仕事が減っている中で、阪神・淡路大震災から何年も経つのに取材が来たりしたことです。震災直後の読売新聞に写真が掲載されたことがあって、その写真の僕の目の前の倒壊したビルで「お笑い芸人をやれ」と言ってくれていた友達の恵介が亡くなりました。あの写真は不思議で、ビルに向かってずっと「恵介、恵介、頑張れ、頑張れ」って言っていたのに、たまたま写真は横を向いているので僕とわかります。すごいタイミングと奇跡だし、たくさんの写真の中から選ばれたということは何か意味がある、“まだまだお前、頑張れよ”っていうことだろうなと思って。
人の「死」って二つあると聞いたことがあって、一つは肉体が死ぬ時、もう一つは人の記憶からなくなった時。僕は恵介に二つ目の「死」を与えないために、語り部としてこの経験を話すようにしています。