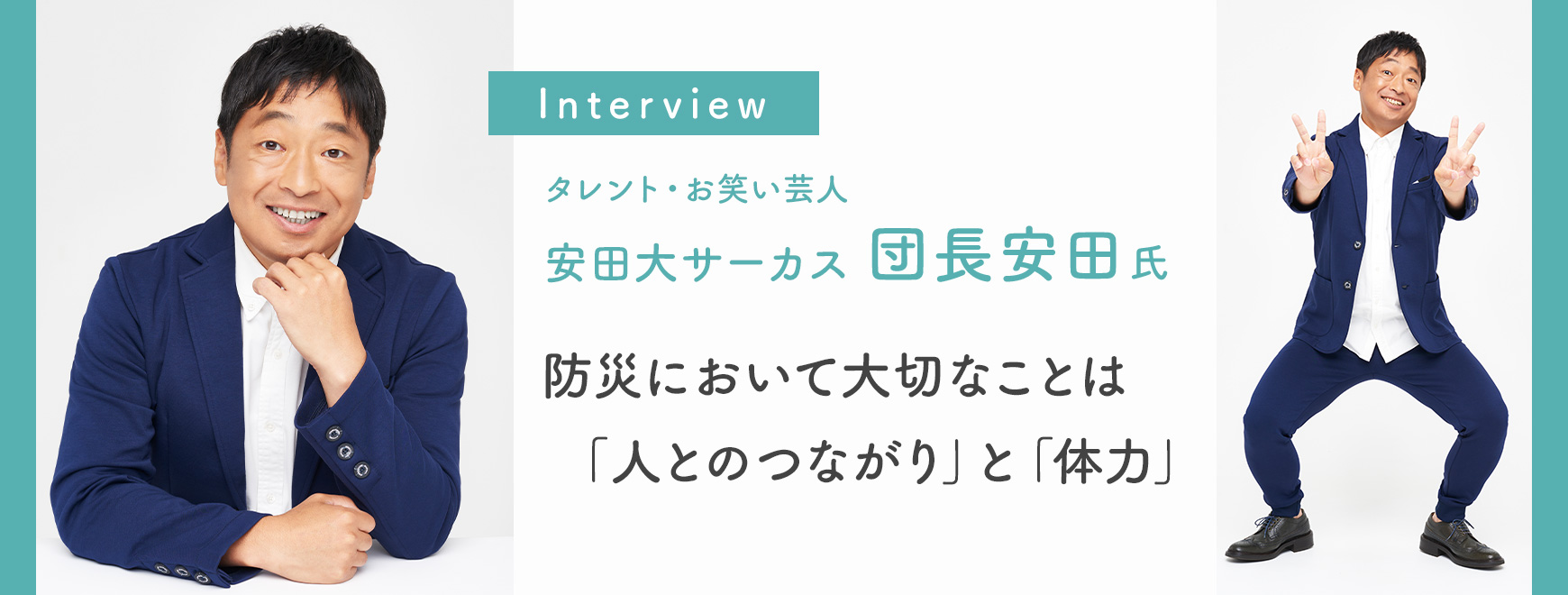- HOME
- 学生・教職員の活動
- 全国学生委員会の活動
- 学生委員会のインタビュー
- 安田大サーカス 団長安田 氏 インタビュー
- 被災後に学んだこと
被災後に学んだこと
人と人とのコミュニケーションの大切さ
実際に被災した人は必要な情報を求めて、デマや噂に左右されることがあると思いますが、ご自身が情報源の選び方などで気を付けていたことはありますか。
当時はスマホもなかったので、拡散される情報もなかったですし、デマに対する対策はなかったですね。そもそもどれがデマでどれが真実かは、今となってはもうわからない。被災地のどこで物が手に入るのか、給水はいつなのか、被災した時に役立つ知識などは、結局のところ「人」でした。人と人とのコミュニケーションが最終的には大事になるので、今思い返してみても、人から教えてもらう情報が正しいか正しくないかは人を信じるしかなったし、悪いことをしたのも、助けてくれたのも、教えてくれたのも人でした。だから常日頃から会うと会釈くらいはする間柄じゃないと、非常時に声をかけにくいと思うんです。
先日も、近所の高齢女性に連絡がつかないと近隣の人たちで声をかけあった時に、今まで話したことがない人と話す機会があって、やっぱりその時に普段会釈や挨拶だけでもしている人の方がコミュニケーションを取りやすかったですしね。やっぱり結局「人」なんですよね。
今からすぐにできることは、もう「にこっ」ですよ。ちょっと気持ち悪いと思われるのかもしれないけど、よく会う人に「にこっ」と会釈すること。結局、防災の原点の一つは「人」だと思います。
それぞれの「助け合い」のかたち
自分自身は東北出身で、東日本大震災を小学校3年生から4年生にかけての時期に経験しましたが、内陸の出身なのでひどい被災もなく、年齢的に情報もあまり入ってこなかったので、こうして著名な方が実際の経験をリアルに語ってくださることに感謝しています。
阪神淡路大震災を経験されて29年経ちますが、それ以降も東日本大震災や今年の能登半島地震など、さまざまな災害が起こっています。災害が起こった時にどう捉えられているのか、意識や災害支援の取り組みなどがあれば、教えてください。
助け合いは人それぞれで違うと思っています。お金での支援は募金等できる範囲でやりますが、震災直後に行くことが正義みたいな感じもあれば、直後に行く人を攻撃する人もいて、何もしない人よりはした方がいいと思うくらいで、どちらが正解かは正直わからないです。ただ、売名行為のように見受けられる人もいるので、直後はとりあえず見守ろうと、ひとまず自分の現地の知り合いに連絡を取り、その人に何が足りないのか確認することに重きを置いてきました。
やはり個人で全員は守れないから、落ち着いてきたら観光に行くとか、友達が能登にいるので会いに行こうかなと思っています。落ち着いてからだと目立たずに行けると思うし、災害時にタレントとして注目されることは必要ないと思っています。なので、東北も落ち着いてから自転車を持っていって走ったり、仮設のお店で買い物したり、目立ったことはやってないですけど、それも一つの復興ではあると思うので。
お友達の自転車屋さんが能登にいますが、「もう今はいいから、大丈夫だから。落ち着いて自転車で走れるようになったら、その時に来てくれることが嬉しいから」と言われたので、そうしようと思っています。だんだんやっぱり薄れていくんですよ、みんな。時間が経てば経つほど。だから自分の武器としては、自転車でいくらでも走れるので、サイクリングを楽しみに行くというのは一つ、やろうと思っています。それが人助けになるかどうかはわからないですけど、そういうやり方もあるんじゃないかなと思っています。
今のお話で、二つ大事なポイントを感じました。一つは、被災した側からすると連絡をくれるのが知り合いだと安心するんですよね。もう一つは風化させないというか、現状を伝えていくことです。その地域の人たちの一年後、二年後がリアルに伝わるように、発信する側は行動していかないといけないと強く感じました。
経験で得た知識を伝えること
だから自分の身を削るだけが正義じゃないとは思うので。ちゃんとこっちも楽しんだ方が「やりに来ました」「やってあげますよ」みたいなことよりはいいし、だからそこに住んでいる知り合いに連絡することだけでもできると思います。
国の政策についてもいろいろニュースが出ますけど、復興が遅れているような報道を見て絶望的になる人もいるのではないかと心配になります。騒ぎすぎることは少し危険で、被災した人たちの不安を煽っているような気もするし、一方で声をあげてくれる人がいないと本当に支援が行き届いているか分からないところもあるし、難しいですね。
だから正しい知識が必要で、例えば家が「半壊」だと言われた後に、もう1度見てもらったら「全壊」になった人もいるし、納得がいかない場合は2回、3回と見てもらえることを知らない人も多いじゃないですか。みんな1回目の経験だと思うんです、多分1回しかないと思うんですよ、あんな経験は。
先日、日本銀行のツアーで貨幣博物館に行った時に、震災で焦げたり焼けたりした原形を留めていないお札を持ち込むと、新しいお札に交換する取り組みがあることを知りました。そういう経験や知識を伝えていくことで、被災した人たちの生活がより良くなることはあると思います。
あとは、復興は長い目で見るというか、その場に日常を取り戻すまでがやはり復興なのだと改めて感じたので、支援はもちろんですが、自分たちの防災も改めて確認するべきだと思いました。
若い世代の皆さんへ
それでは最後に、読者の大多数は今の若者世代になるので、今までのお話を踏まえてメッセージをお願いします。
ピンチの状態になった時に頑張りすぎないということと、自分のできる範囲でやるということが大事なので、その範囲で頑張ってくれたら、頑張ってもらった側は本当にありがたいと思っていますので、皆さんのその勇気とか頑張りとか、いま大学生でできることをやってくれたら嬉しいなと思います。
僕も被災したのが20歳なので、無責任だったんですよね、正直。実家暮らしだったし。だから、今もしあの状況になったらプレッシャーはとんでもないですよ。お金の問題や、家族を守らないといけないとか。20歳って、そういう背負っているものは親世代ほどないと思うので、だから学生だからできることを自分で考えてやってくれたら嬉しいなと思います。でも無理はしないでほしいですね。
それと、一番鍛えておくといいのは体力です。自分の身を守るのも走れることが一番とよく言われますけど、体力はつけていた方がいいと思います。そういう意味で、一番の防災は「体力」と言えるかもしれません。
現在、全国学生委員会の中で、激甚災害支援防災の分野を推進していくリーダーを務めていますが、今まではいろいろな大学生協や学生たちが防災に前向きに取り組むことを推進していく立場として、実際に何か起きた時の行動につながるような情報を発信することが多かったのですが、お話をお聞きするなかで、防災において「人とのつながり」や「体力」も大切であるという、自分としても今まで考えられなかった新しい視点に気づかされましたし、勉強になりました。
これから大学生協連の学生委員会として、防災や激甚災害支援について推進していく上で、参考になる情報をたくさんいただけたと思うので、これからも学生が前向きに考えて行動していくことができるように、頑張っていきたいと思います。
2024年7月12日リモートインタビューにて
PROFILE
安田大サーカス 団長安田 氏

1974年 兵庫県西宮市出身。
HIRO、クロちゃんと共にお笑いトリオ「安田大サーカス」を結成。
リーダーでツッコミ担当、ニックネームは「団長」。
お笑い芸人にとどまらず、俳優、声優やナレーターとしても活躍。
スポーツ万能で自転車のロードレースを趣味とし、自らを「自転車芸人」と名乗り、著書も出版している。
(公式サイトより一部抜粋)
▼ 所属事務所HP
安田大サーカス |松竹芸能株式会社 (shochikugeino.co.jp)
▼ Instagram
https://www.instagram.com/dancyoyasuda/
▼ X
https://twitter.com/dancho_yasuda
▼ YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCl8AJj6Qxktq82x-PnOg40A