いずみ読書スタッフの 読書日記 164号
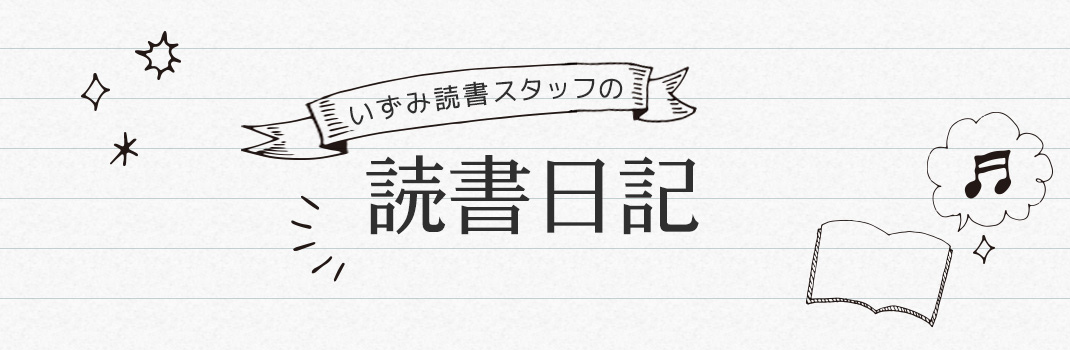
レギュラー企画『読書のいずみ』読書スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
京都大学大学院M1 畠中美雨
6月初旬 気付いたらなんとなく初夏
 自粛期間が明ける直前、滑り込みで読みはじめた一冊がG.ポリア〈柿内賢信=訳〉の『いかにして問題をとくか』(丸善出版)だ。ジュンク堂書店京都店の閉店前、最後に立ち寄った日に購入した一冊。本書は、解法や目的達成への手段を自分で発見する思考過程の指南書である。はじめは学生と教師の対話形式で算数の簡単な問題を例に、徐々に複雑で抽象度が高い問題を扱っていきつつ、各ステップでやるべきことが書かれている。個人的にその道筋はもとより、“数学”を言語化していく工程に目を見張った。数学を嗜む人以外にも支持されているという表紙の帯文句にも納得。数学以外の一般的な問題解決の一助にもなる一冊。
自粛期間が明ける直前、滑り込みで読みはじめた一冊がG.ポリア〈柿内賢信=訳〉の『いかにして問題をとくか』(丸善出版)だ。ジュンク堂書店京都店の閉店前、最後に立ち寄った日に購入した一冊。本書は、解法や目的達成への手段を自分で発見する思考過程の指南書である。はじめは学生と教師の対話形式で算数の簡単な問題を例に、徐々に複雑で抽象度が高い問題を扱っていきつつ、各ステップでやるべきことが書かれている。個人的にその道筋はもとより、“数学”を言語化していく工程に目を見張った。数学を嗜む人以外にも支持されているという表紙の帯文句にも納得。数学以外の一般的な問題解決の一助にもなる一冊。
6月中旬 雨音が聞こえはじめた頃
 久方ぶりに本屋に出向く。いつもだったら気の済むまでうろちょろするけどもこの御時世だ、一直線に詩・短歌のコーナーへ向かう。本は時代の鏡でもあるけれど、このコーナーは流行りに構わない普遍性が光っていてなんだかほっとする。
久方ぶりに本屋に出向く。いつもだったら気の済むまでうろちょろするけどもこの御時世だ、一直線に詩・短歌のコーナーへ向かう。本は時代の鏡でもあるけれど、このコーナーは流行りに構わない普遍性が光っていてなんだかほっとする。購入したのは千種創一さんの『千夜曳獏』(青磁社)。表紙の手触り、透度、不揃いな裁断面、その内にある祈りのような短歌たち。「千夜も一夜も越えていくから、砂漠から獏を曳き連れあなたの川へ」心が洗われる、とはこんな心地を指すのだろうか。何かと気詰まりしそうな日々に呼吸を取り返せる短歌集。味わって読み進めよう。
7月中旬 立ち止まる梅雨前線
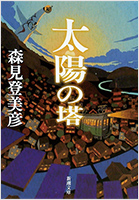 この本を読むのは実に6年ぶり、森見登美彦さんの『太陽の塔』(新潮文庫)を生協にて購入する。主人公「私」の元恋人水尾さんが惹かれる太陽の塔、そして「ええじゃないか騒動」の起点、四条河原町の交差点は如何なる場所か……。広島に住んでいた私は、森見作品を読んでは空想したものだ。
この本を読むのは実に6年ぶり、森見登美彦さんの『太陽の塔』(新潮文庫)を生協にて購入する。主人公「私」の元恋人水尾さんが惹かれる太陽の塔、そして「ええじゃないか騒動」の起点、四条河原町の交差点は如何なる場所か……。広島に住んでいた私は、森見作品を読んでは空想したものだ。京都で学生生活を送っている今は、読み進めながらその場所を思い浮かべることができる。そして思い出す、太陽の塔をはじめて見たときの圧倒される思い、四条河原町の交差点で信号を待つ時間ですら楽しかったことを。これらの森見作品、虚構や妄想が現実を面白おかしくしてくれたのだ。ただ空想にかまけて読んでいた頃と比べて少しは成長できただろうか。
読了後、ところで森見さんが本作である大賞を受賞したのは修士在学中だっけ、それで私はいま……と急に現実に立ち返る。この長い梅雨が明けたら、祇園祭も各地の花火大会もないけれど、もう夏がきてしまう。
千葉大学2年 磯部美月
7月中旬
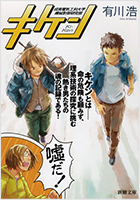 雨がいつも降っている。課題に追われ、友達には会えない毎日。思いっきり楽しい気分になりたくて本棚から手に取ったのは、『キケン』(有川浩/新潮文庫)だった。普通の工科大学の、普通(?)の大学サークルの物語。主人公の冴えない理系男子・元山くんがとにかくハチャメチャな先輩たちにぶんぶん振り回される姿は、一息つく暇もないほどの笑いを提供してくれる。学内でバイクを乗り回し、爆破実験まで行ってしまうU先輩と、そんな先輩さえ恐れる寡黙なO先輩。
雨がいつも降っている。課題に追われ、友達には会えない毎日。思いっきり楽しい気分になりたくて本棚から手に取ったのは、『キケン』(有川浩/新潮文庫)だった。普通の工科大学の、普通(?)の大学サークルの物語。主人公の冴えない理系男子・元山くんがとにかくハチャメチャな先輩たちにぶんぶん振り回される姿は、一息つく暇もないほどの笑いを提供してくれる。学内でバイクを乗り回し、爆破実験まで行ってしまうU先輩と、そんな先輩さえ恐れる寡黙なO先輩。狭いサークル部屋の中で、たぶん相当量の唾を飛ばしながら、彼らにツッコミを入れる元山くんの姿を想像してみよう。ついさっきまでの寂しさはどこかへ飛んでいき、パワフルな気分になってくる。
ただ、この本には仕掛けがあって、読後にはほんの少しの切なさが訪れる。この愉快な物語は、あくまでも「あの頃」の物語なのだ。私はこんな風にゲラゲラ笑えるほどの「あの頃」を作れているかなぁ。なんてセンチメンタルちっくになってしまう。でも、大丈夫。物語の中盤に戻れば、またその悩みを吹き飛ばすほどの笑いがいくらでも詰まっている(この無限ループから抜け出せない……)。
8月上旬
 やばい。いよいよやばい。テストが迫りくる。精神がやられる。そんなときは、まず読書。すぐに読める短編集で一息つこう。そう思って、『できればムカつかずに生きたい』(田口ランディ/新潮文庫)のページを開いた。この本は、エッセイ集だけど、とっても言葉が重い。読んでいる間は、曇り空の下で強烈なボディブローを何発も食らっているような気分になる。
やばい。いよいよやばい。テストが迫りくる。精神がやられる。そんなときは、まず読書。すぐに読める短編集で一息つこう。そう思って、『できればムカつかずに生きたい』(田口ランディ/新潮文庫)のページを開いた。この本は、エッセイ集だけど、とっても言葉が重い。読んでいる間は、曇り空の下で強烈なボディブローを何発も食らっているような気分になる。それでも何度も読み返してしまうのは、雲の切れ目から、これ以上透明なものはない、と言えるような透き通った言葉が降ってくるからだ。どんな言葉をそう感じるかは人によって異なるだろうから、詳細は書かない。でも、確かに、この本の中にはそんな言葉が点々と存在していて、ついついクセになってしまう。曇り空さえ、この光を引き立たせるための背景として、愛おしく思えてくる。
あれ、おかしい。「すぐに読める」から短編集を選んだはずなのに、ふと気がつけば1時間は余裕で経っていた。本日の勉強量はほぼゼロである。いつも本は私の時間を奪う。だけど憎めないのは、なんでなんだろう。そんなことを考えると、さらにテスト勉強は進まなくなっていく。
北海道大学3年 長田幸子
6月中旬 カッコウのなく夜に
 ぱったり出会った古本屋で本を買ってしまった。数ヶ月前の引っ越しの時に「これ以上本を買っては引っ越しの時にとても苦労する。今後本はなるたけ買わないようにしよう」と決意したはずだった。けれど古本屋が数か月ぶりであったが為に耐えきれず店内に入り、見つけた素敵な本の値段が昼飯代を犠牲にすれば買える値段だと気がついてしまったとき、その決意ははかなく消えた。
ぱったり出会った古本屋で本を買ってしまった。数ヶ月前の引っ越しの時に「これ以上本を買っては引っ越しの時にとても苦労する。今後本はなるたけ買わないようにしよう」と決意したはずだった。けれど古本屋が数か月ぶりであったが為に耐えきれず店内に入り、見つけた素敵な本の値段が昼飯代を犠牲にすれば買える値段だと気がついてしまったとき、その決意ははかなく消えた。最近は課題が増えてきて(溜めたともいう)、鳥を見に行くこともできていない。
本の中でくらい、思いっきり自然に触れたかったのである。古本屋で買った本の一冊である『野の鳥の生態1』(仁部富之助/大修館書店)はすこし年季が入っていた。発行は1970年代らしい。浪漫が詰まっている気がしてならない。古本屋で本を買うのは、色々想像が働いて楽しいから、きっとまた買うに違いない。
本の中ではいくつかの種類の鳥が紹介されていて、夜になると我が家の近くで独唱しているカッコウも載っていた。
専門書ではなく、読み物としての要素が強いのでそれなりに楽しめた。ただ、「このころはきっと自然が豊かなのだなあ」と思ってしまってタイムスリップしたい気分に駆られた。それに著者の観察力。見習いたいものである。色々と。
7月 溶けて海にでも流れ込みたい日に
 おかしい。おかしい。私は何のために北国にやってきたのか。涼しい場所へ行きたかったのではなかったか。それだというのに、暑い。今私はまさしく溶けている。屋外に出たくない。机に冷えた飲み物をおいて、手に取ったのは辻仁成の『海峡の光』(新潮文庫)。辻仁成の作品は小学校以来読む機会がなく、久しぶりの再会であった。函館を舞台にしているからひょっとして見知った地名が出たりしないかしら……そんなことを考えていた最初の自分は読み終えるころには消えていて頭には「?」が残っていた。人生経験が足りていないのかしら。この話の根底にあるものが私にはまだつかみ取り切れていない……く、くやしい。人の行動は説明が毎回付けられるわけではないものだけれど、その描写が本当に上手かった。心情が読めるような読めないようなこの雰囲気。おそるべし……。
おかしい。おかしい。私は何のために北国にやってきたのか。涼しい場所へ行きたかったのではなかったか。それだというのに、暑い。今私はまさしく溶けている。屋外に出たくない。机に冷えた飲み物をおいて、手に取ったのは辻仁成の『海峡の光』(新潮文庫)。辻仁成の作品は小学校以来読む機会がなく、久しぶりの再会であった。函館を舞台にしているからひょっとして見知った地名が出たりしないかしら……そんなことを考えていた最初の自分は読み終えるころには消えていて頭には「?」が残っていた。人生経験が足りていないのかしら。この話の根底にあるものが私にはまだつかみ取り切れていない……く、くやしい。人の行動は説明が毎回付けられるわけではないものだけれど、その描写が本当に上手かった。心情が読めるような読めないようなこの雰囲気。おそるべし……。

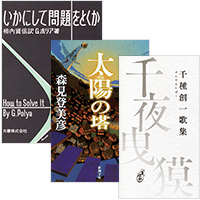 京都大学大学院M1 畠中美雨
京都大学大学院M1 畠中美雨 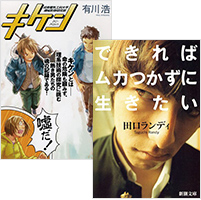 千葉大学2年 磯部美月
千葉大学2年 磯部美月 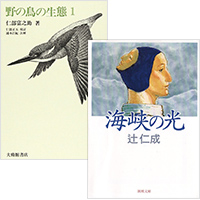 北海道大学3年 長田幸子
北海道大学3年 長田幸子 
