いずみ読書スタッフの 読書日記 164号 P2
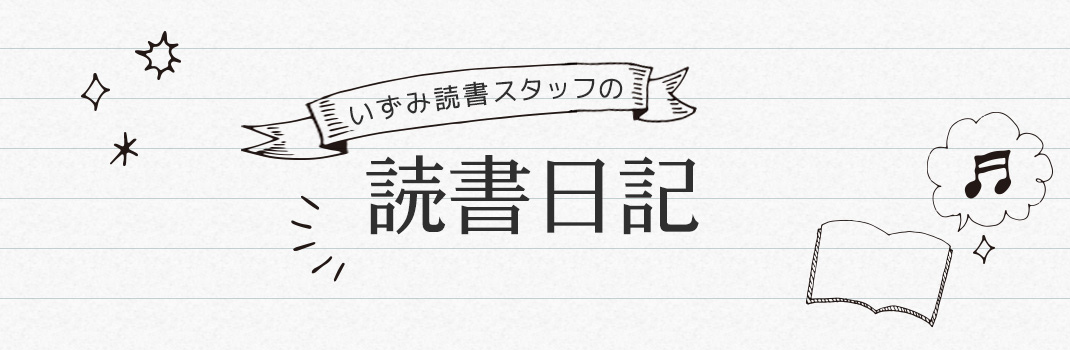
レギュラー企画『読書のいずみ』読書スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
金沢大学3年 光野康平
6月上旬
 目を背けたくなる現実が書き記されたルポルタージュ、悲惨すぎるラストをむかえる小説等々。思い出すだけで苦しくなるトラウマ本が何冊かある。その中の一つが『死にがいを求めて生きているの』(朝井リョウ/中央公論新社)だ。この小説では、他人の評価や時代の変化にばかり目を向けて、自分自身を見失った人々が描かれている。その姿は、上手く大学になじめないことを他者や環境のせいにしていた当時の私にそっくりだった。登場人物に共感するたび、「今の生きづらい状況を作りだしているのは、お前自身だ」と作者に言われている気分になり、私はページを進めることがとても苦しかった。読み終わってからの数日間は、気が付いたら自分の嫌な部分を考えていた。そして、未読の本のストックがつきた休日。一年ぶりくらいに勇気を出してその本を読むことにした。すると、不思議なことに今回はあまり苦しくない。代わりに、登場人物たちの成長過程や作者がこの本に託したメッセージを感じることができた。この一年間で自分が成長したとか、悩みがなくなったわけじゃない。だけど、何かの変化を感じられたこの休日は、少しだけ自分のことが好きになれた気がする。
目を背けたくなる現実が書き記されたルポルタージュ、悲惨すぎるラストをむかえる小説等々。思い出すだけで苦しくなるトラウマ本が何冊かある。その中の一つが『死にがいを求めて生きているの』(朝井リョウ/中央公論新社)だ。この小説では、他人の評価や時代の変化にばかり目を向けて、自分自身を見失った人々が描かれている。その姿は、上手く大学になじめないことを他者や環境のせいにしていた当時の私にそっくりだった。登場人物に共感するたび、「今の生きづらい状況を作りだしているのは、お前自身だ」と作者に言われている気分になり、私はページを進めることがとても苦しかった。読み終わってからの数日間は、気が付いたら自分の嫌な部分を考えていた。そして、未読の本のストックがつきた休日。一年ぶりくらいに勇気を出してその本を読むことにした。すると、不思議なことに今回はあまり苦しくない。代わりに、登場人物たちの成長過程や作者がこの本に託したメッセージを感じることができた。この一年間で自分が成長したとか、悩みがなくなったわけじゃない。だけど、何かの変化を感じられたこの休日は、少しだけ自分のことが好きになれた気がする。
7月上旬
 金欠の日曜日、今日は見るだけと言い聞かせて、行きつけの本屋に向かった。何回通っても、何度眺めても、本棚の中には新たに見つかる本があるから、週末の本屋通いはやめられない。正面入り口の前にある新刊コーナーにたどり着くと、平積みされた本の中から『夢を叶えるゾウ4 ガネーシャと死神』(水野敬也/文響社)というタイトルを見つけてしまった。うだつの上がらない人生を過ごしていた主人公のもとに突如象の神様「ガネーシャ」が現れて、夢を叶えるための様々な課題を主人公に出していく、コメディ小説と自己啓発本が合わさったシリーズの4作目。この「夢を叶える象」シリーズは、小学生の時に、初めて読書の楽しさや有意義さを私に教えてくれた大切な存在だ。
金欠の日曜日、今日は見るだけと言い聞かせて、行きつけの本屋に向かった。何回通っても、何度眺めても、本棚の中には新たに見つかる本があるから、週末の本屋通いはやめられない。正面入り口の前にある新刊コーナーにたどり着くと、平積みされた本の中から『夢を叶えるゾウ4 ガネーシャと死神』(水野敬也/文響社)というタイトルを見つけてしまった。うだつの上がらない人生を過ごしていた主人公のもとに突如象の神様「ガネーシャ」が現れて、夢を叶えるための様々な課題を主人公に出していく、コメディ小説と自己啓発本が合わさったシリーズの4作目。この「夢を叶える象」シリーズは、小学生の時に、初めて読書の楽しさや有意義さを私に教えてくれた大切な存在だ。「いま金欠だけど、この本はいずれ買うことになるから買ってよし」と何十回も使ってきた言い訳を自分にして購入。帰りのバスでさっそく読み始めると、わがままで人間臭いガネーシャの行動にマスクの中の口は緩みっぱなしで笑い声をこらえるのが必死だった。そして、読み終わったあと心に刻まれる、夢を叶えることの難しさと大切さ。久しぶりに「読書は楽しい!」と心の底から思うことができた。
広島大学3年 倉本敬司
8月 締め切り……
暑い。読書日記の原稿の締切が来て、優に5日は過ぎていることだろう。レポートが忙しいと言い訳はしているものの、そういつまでも引き伸ばせるものではない。そもそもレポートを書く気が起きない。『太陽の塔』(森見登美彦/新潮文庫)でも読もう。よし、まだ俺は大丈夫だ。6月 日常は戻らず、本は増える
 緊急事態宣言が解除され、対面の授業も出てくるだろうと意気揚々と実家から舞い戻ったのだが、授業はすべてオンラインのまま。いや、図書館が開いたから、良しとすべきなのかもしれない。しかし、こうして今の生活に慣れていくのは何となく嫌だ。と、コープショップを悶々と徘徊する私はきっと瘴気を放っていただろう。そんなとき目に止まったのは、『三体Ⅱ』(劉慈欣〈大森望ほか=訳〉/早川書房)である。ときめく話題の中国SF第2弾、上下巻2冊で約3,300円、金がないのはさておいて、即刻買った。このときの私はきっとカナブンしか止まらない小学校の桜の木にミヤマクワガタを見つけた少年のように、目を輝かせていたことだろう。
緊急事態宣言が解除され、対面の授業も出てくるだろうと意気揚々と実家から舞い戻ったのだが、授業はすべてオンラインのまま。いや、図書館が開いたから、良しとすべきなのかもしれない。しかし、こうして今の生活に慣れていくのは何となく嫌だ。と、コープショップを悶々と徘徊する私はきっと瘴気を放っていただろう。そんなとき目に止まったのは、『三体Ⅱ』(劉慈欣〈大森望ほか=訳〉/早川書房)である。ときめく話題の中国SF第2弾、上下巻2冊で約3,300円、金がないのはさておいて、即刻買った。このときの私はきっとカナブンしか止まらない小学校の桜の木にミヤマクワガタを見つけた少年のように、目を輝かせていたことだろう。
7月前半 言い訳
久しぶりに市内に行った折に、ついつい調子に乗って、何冊も本を買ってしまった。本棚はパンク寸前であるが、5時間に渡るお喋りで気分は昂揚していたのだから仕方ない。何事にも例外というものはある。仕方ないんだ。それに『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー〈芹澤恵=訳〉/新潮文庫)は『批評理論入門』(廣野由美子/中公新書)で取り上げられていたので以前から読みたかったのだ。7月後半 梅雨・弁明
 Amazonのほしいものリストは7年に渡って読みたい本を積み上げてきた我が生の痕跡である。その中から今回消化したのは、『ソクラテスの弁明』(プラトン〈納富信留=訳〉/光文社古典新訳文庫)である。哲学は役に立つと本気で思っている。その理由は、考える枠組みを提供してくれること、自分の小ささを思い知らされることにある。俗に「答えのない問い」と呼ばれる問題には、ほとんど何らかの解答が与えられていると思う。
Amazonのほしいものリストは7年に渡って読みたい本を積み上げてきた我が生の痕跡である。その中から今回消化したのは、『ソクラテスの弁明』(プラトン〈納富信留=訳〉/光文社古典新訳文庫)である。哲学は役に立つと本気で思っている。その理由は、考える枠組みを提供してくれること、自分の小ささを思い知らされることにある。俗に「答えのない問い」と呼ばれる問題には、ほとんど何らかの解答が与えられていると思う。私はこの人間よりは知恵がある。それは、多分私たちのどちらも立派で善いことを何一つ知ってはいないのだが、この人は知らないのに知っていると思っているのに対して、私のほうは、知らないので、ちょうどそのとおり、知らないと思っているのだから。どうやら、なにかほんの小さな点で、私はこの人より知恵があるようだ。つまり、私は、知らないということを、知らないと思っているという点で。(31〜32頁より)
「無知の知」として知られるこの一節が示しているのは、人間が知恵という点でどのように謙虚であるべきか、ということらしい。そうであれば、「答えのない問い」が本当に答えがないのかどうか問うてみる必要はあるのではないか。そう思案していたら、長い梅雨が明けた。なお、ほしいものリストは増えた。
前のページへ

.jpg) 金沢大学3年 光野康平
金沢大学3年 光野康平 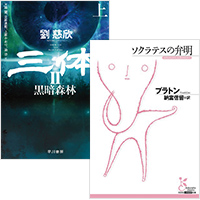 広島大学3年 倉本敬司
広島大学3年 倉本敬司 
