わが大学の先生と語る 拡大版
「うたう文章、交わす言葉」藤原 辰史(京都大学准教授)

▼ Profile

■略歴
1976年生まれ、北海道生まれ、島根育ち。
京都大学 人文科学研究所 准教授。
1999年、京都大学総合人間学部卒業。2002年、京都大学人間・環境学研究科中退。同年、京都大学人文科学研究所助手(2002.11-2009.5)、東京大学農学生命科学研究科講師(2009.6-2013.3)を経て、現在、京都大学人文科学研究所准教授。博士(人間・環境学)。2019年2月に、第15回日本学術振興会賞受賞。
『ナチス・ドイツの有機農業―― 「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』(柏書房 2005年)、『カブラの冬―― 第一次世界大戦期の飢饉と民衆』(人文書院 2011年)、『稲の大東亜共栄圏―― 帝国日本の<緑の革命>』(吉川弘文館 2012年)、『ナチスのキッチン―― 「食べること」の環境史』(水声社→決定版=共和国 2012年→2016年)、『食べること考えること』(共和国 2014年)、『トラクターの世界史―― 人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中公新書 2017年)、『戦争と農業』(インターナショナル新書2017年)、『給食の歴史』(岩波新書 2018年)、『食べるとはどういうことか』(農文協 2019年)、『分解の哲学―― 腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社 2019年)、『縁食論―― 孤食と共食のあいだ』(ミシマ社、2019年)、『農の原理の史的研究―― 「農学栄えて農業亡ぶ」再考』(創元社 2020年)、『歴史の屑拾い』(講談社 2022年)、『植物考』(生きのびるブックス 2022年)。
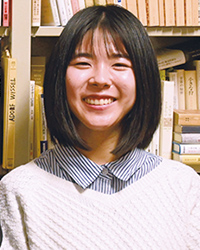 関根 美咲
関根 美咲
(文学部2回生)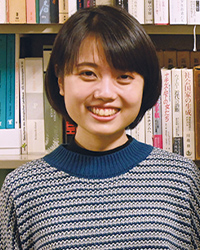 齊藤 ゆずか
齊藤 ゆずか
(文学部3回生)
1.読書との出会い

関根
先生の研究室にはたくさんの本がありますし、新聞で書評も書かれています。豊かな読書体験をお持ちかと思いますが、先生と読書の出会いについて教えてください。
藤原
大変恥ずかしいんですけど、僕の読書との出会いは、極めて不幸なものでした。というのも、本を読むことに全く喜びを感じない中高生でした。せっかく外が晴れているのに、何が面白くて読書なんかするんだ、って。実際に読んでも、ある言葉で立ち止まって思考が別の方向に行ってしまう。文に脈があるという意味がわからなかったんですね。
高3の時、読書感想文を書くために本を探したんですよ。すごく小さな町の、一軒しかない本屋で。薄いほうがいいと思って、大岡昇平の『野火』(新潮文庫)を選んだんですね。これが僕にとってすごく大事な出会い、でしたね。「人間は人間を食べる」ということを初めてそこで知りました。『野火』では、フィリピンの戦線で主人公たち日本兵が軍に見捨てられる。生きるためにとにかくあらゆるものを食べる。海水も飲むんだけど、大岡は「甘い」って書くんですよ。喉が渇きすぎて、甘く感じたって。「なんだ、この海水を飲む場面は」と不遜だけど、心が躍ったんです。なんだかすごく生々しいものを『野火』から感じ取りました。
大学に入って、ゼミではみんなが気の利いた「ゼミっぽい」発言をするので気おくれしてね。そこはとにかく「一週間に一冊本を読め」っていうゼミでした。最初の半年間は本当に地獄だったけど、徐々に読んでるフリができるようになりました。一冊とりあえず読み終えてみる、読み終えた気になる。すると自分が本を読み終えたことが嬉しくなっちゃってね。記録に残そうと、「本カード」というのを貯めていくようになりました。
結局100%読み切るってことはありえないんだよね。人間同士もそうだけど、本も出会ったものを100%わかりましたってことはありえない。でもやっぱり、出会いが大事だということを大学1年生で学びました。それ以来、わからないところはわからなくていいんだ、って気が楽になって。それから本との幸せな付き合いが始まりましたね。
齊藤
今では幅広く読まれていますよね。
藤原
本屋はやっぱり出会いの場所なんですよね。ほしい本を買うだけならインターネットで済むわけですけど、自分の感性とか知性とか興味とかをはみ出ているものと出会えるのが本屋。大学院生のときに自分でルールを決めました。とにかく関心のある本は最後まで読もうと。たとえ辛くても一度手をつけてしまったら最後まで読もう、そして、あらゆることに興味をもとうと。そうやって手広く学びながら自分の専門を築いていこうとしていました。
2.枠を越えて行け
齊藤
先生の著書は、縦横無尽に学問の領域も飛び越えて、エッセイを読んでいるように感じて素敵でした。執筆の心構えといいましょうか、気をつけていることとか意識していることとかがあれば……。
藤原
僕が入ったドイツ語の先生の研究室は言語運用に関しては厳しかったけれど、学問を越境することに対して極めて寛容だったのは幸運でした。僕は今の学問の、ルールを守ることを何よりも自分に課して本を書いているような事例とか、先達たちの学説だけでなく彼らの人格までにも自分の研究人生を捧げている事例をすごく残念に思っていました。学問の喜びというのはもっと自然な発露なはずで、もっと破天荒に、自分の関心の赴くがままに研究する人が一人ぐらいいてもいいんじゃないかと思いました。僕は偶然、学会に入らないまま就職しているので、学会に気遣うこともなく研究できるという幸せな環境にあります。執筆のとき何に気をつけているかということですが、変な言い方をすると、まず越境した先のジャンルの方への猛烈な敬意を抱くことですね。思想哲学を学べば、言葉一個であらゆる現象を一応は説明できます。でも、これを安易に用いてしまうと、越境先の人に対して上から目線になってしまい、つまらない。越境する以上は、越境した向こうの住人の皆さんとちゃんと会話をする。もう一つは基礎的な入門の本をできるだけ読むことですかね。立花隆さんの本を読んで学びました。立花さんは全ジャンルを入門書から読みはじめている人なんだよね。全部くまなく読んでいくんです。基本的な知識を得てようやく専門家に会いに行く、ということをやってらっしゃった。『植物考』(生きのびるブックス)を書くときも、植物学入門といったものをかなり読みこみました。その二つはやっぱり、越境する時の重要な点というか最低限のマナーというかな、そういう感じがするよね。
齊藤
『植物考』を書かれようと思った経緯を教えてください。
藤原
ある出版社の編集者が連載を持ちかけてくれました。その時に何がいいかなあと考えて、これまで農業とか食の研究をしてきた自分の原点をちゃんと確認しようと思って。植物とは何かを文系的に考えてみたくなった。昔、アリストテレスやベーコンのような哲学者も、植物を論じていました。文系理系という枠もなく関心を持ってたわけです。だけど今は拒否されていて、高校まではそういうことに関心を持たないでくださいって言われているかのよう。で、成人式では自由に主体性を持って取り組みましょうとか言うんだけど「遅いわ」って思う。主体的に学問を取り込めるようなものがあってもいい。悩んでいる学生たち、高校生中学生に、こういうふうなことを書いているおじさんがいるんだ、物理の法則に関心を持ちつつ夏目漱石に惚れていてもいいんだって思って欲しい。そういうふうなのが二つ目の理由かなと思います。
3.話して書いて

関根
先生は対談とかでいろんな方とお話しされると思うんですけど、お話しされる時と本を書く時で何か違いを感じているかということについてお聞きしたいです。
藤原
それは初めての質問ですね。全然違うジャンルだと思います。僕は書くことから始めてるから書くことが先に来るんですよ。院生時代にいろんなところで発表する機会があって、僕の先生から「とにかく君は発表は下手だ」って怒られたことも多々ある。聞いてる人の身になってみろって。話してる相手を見ながら臨機応変に対応できる喋り方を身につけなさい、って注意を受けてトラウマになった記憶があるんですね。やっぱり論文を書いたり、本を書いたりレポートを書いたりって、区切られた時間で作品を完成させることと似てるかな。職人が時計を作る感じ。対談はスポーツに似てると思います。動作をした瞬間に次どんな動きが返ってくるかを予測している。スポーツは常に先を読んで成り立っています。対談というのは、その場に緊張感が漂う、ライブみたいなものなんですね。ジャズのセッションにも似てるよね。ジャズってある程度ルールやコードは決まってるけど、途中でアドリブがたくさん入るのが素敵ですね。ドラムを聴いたりサックスを聴いたりして、「そろそろ合わせよう、はい」って始まるのがたまらないわけですよね。お互いのリズムというか、身体だけで会話になっている瞬間というのがあります。対談もそうで、その場に合わせて臨機応変に自分の答えられるものを答えていくんです。スリリングだし、書いたものにはない発想があったり思いつきが浮かんだりするんですよ。これは、実は将来的にものを書く時のヒントになり続けてきているんです。僕にとって対談、会話のやりとりと執筆ってすごくいい循環になっていて、両方必要だと思いますね。仕事をする上でも、例えば、プロジェクトに合わせてものを書く時間と、自分の同僚と議論していくっていう両方がないと、面白いアイディアは生まれない。この二つは本当に重要だと思いますね。
僕の講義で学生の参加を求めたいのは、そういうことなんです。僕は学生が反応してくれないと毎年同じことをしゃべり続ける。それは自分にとってもつまんないし学生にとってもつまんない。学生に何か言われて、「はっ」て驚いて必死になって言葉を紡いでいきながら、このことについてはこういう本があるね、とか言って本に頼りながら逃げているのを見てほしいんです。でも、これは本のあり方として必要ですよね。今後何が起こるか分からない、その時に自分が持っている知識を総動員させて、知を発動させるという行為も知的な行為のはずですよ。
それと、とにかくそういう外界を遮断して、沈思黙考、自分の世界で、こうでもないああでもないって考える時間も重要で、その両方が往復であるっていうのがポイントだよね。
4.文章でうたう
齊藤
『植物考』の中で「文章は思想という種子を発芽させる酵素であり、音や拍子でもある」と書かれています。先生の著書を読むと、ことばが自分の中にすっとはいってくる感覚があります。文章がもつ酵素としての力とか音楽性が発揮されていると思いました。
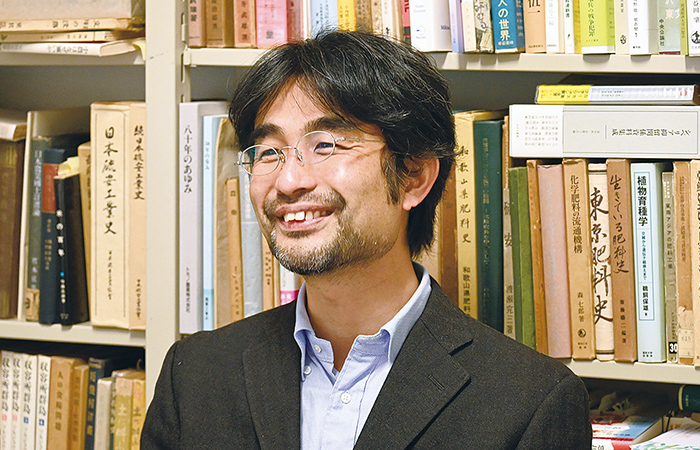
藤原
僕は勉強を始めたばかりの若い人たちにそう言ってもらうのが目標のひとつ。拍子という話をしましたね。ことば自体がひとつの歌であるということ。できているとはとても思えないけど書くうえで注意していることですね。もちろん内容がなくてリズムだけの文章ってつまらない。だけど文章って元々は音調がついていたはずなんですよね。今しゃべっている言葉だって、イントネーションとアクセント、そして間があるから伝わってると思う。間が重要なんです。要するにいったん読者に考えさせる。段落を分けるっていうことだよね。
句読点も本当に重要で、変なところについていると直したくなります。句読点っていうのは「うん・たたた」の「うん」っていう瞬間を読者に与えて「たたた」をちょっと待っていてくださいっていう感じ。音楽ではそれが形式化されていて、音符は休符があるから成り立ちます。「単にだらだらと書いていたら伝わるものも伝わらん」とわかってきました。それに気付いたのは、子どもに絵本の読み聞かせをしてからです。読みやすい絵本とそうじゃない絵本があるんですね。読みにくい本は休めないのよ、どこに呼吸を入れていいかわからないからつっかかるんです。リズムよく読めないので、子供に心地よく聞こえないんですよね。いくら訓練してもつまずいたり噛んだりしてしまう。
僕が好きなのは、かこさとしさんの『まさかりどんがさあたいへん』(小峰書店)。かこさんが亡くなる前に、『現代思想』の「かこさとし特集」で文章を書かないかと僕に声をかけていただいて、かこさんが書いている絵本の文章の勢いで論文を書いたんです。「まさかりどんがさあたいへん」でしょ。なんとかかんとかやってきて、どんどんどんどんなんとかする……なんとかかんとかやってきて、こうこうこうこうなになにする……ってノリで書くわけ。論文だけどリズムを大切にして書いてみたら、史上最強に読みやすい日本語になったんだよね。
声に出してつっかえない文章というのが、やっぱりいい文章。本を読む行為は体力を使うし、音読はそれ自体すごく演劇に近い。声は心身の状態を媒介して出てくる空気の振動じゃないですか。だから文章も、声に出したときに人に伝わってほしいと思って書くことを意識するようになりましたね。だけど全然僕にはまだ足りないなという思いのほうが強いです。僕自身は研究者ですから、理屈屋なんですよね。理屈をちゃんと伝えなきゃって思うとリズムは消えていく。だけど、人の心に届くためのリズムも、学問から奪ってはならないだろうと思っています。
僕は石牟礼道子さんの文章に影響を受けました。『椿の海の記』(河出文庫)が好きで、彼女の文章を読んでいた時に「無料食堂試論」というエッセイを書いたんですね。そうしたら『婦人の友』の編集者からお手紙が届いた。「あなたはこの文章を書くときに石牟礼道子さんの本を読んでいませんでしたか。『椿の海の記』のイメージが私に浮かびました」と。この方は敏腕編集者で、エッセイには石牟礼道子の「い」の字も出てこないのにばれちゃった。そしてびっくりしたんだけど、「一緒に石牟礼さんに会いに行きませんか」って書いてあって。大ファンの人に会いに行けるってことでめちゃくちゃ緊張しました。
齊藤
先生が授業で紹介されていたので読んだのですが、『椿の海の記』は本当に、こんなに豊かな世界が言葉で作れるんだって。
藤原
でしょ?彼女は主婦で、廊下に置いてある小さな台で書いていたの。当時は女性が文章を書くなんて許されないことだったわけだけど、こっそり書いていた文章ですよね。
関根
(持っていた本を取り出す)『食べごしらえおままごと』(中公文庫)にも……。
藤原
ああ、持ってきていたんだ!
関根
「おいくつでっか、おしゃまやなあ、これはこれはめでとうおさめつかまつる」……いいですよね、これ。
藤原
いいよね、その文が。石牟礼さんとともに活動した渡辺京二さんが言っていたのは、これは熊本弁でも天草弁でもなくて道子弁だと。
石牟礼さんはお会いしたときすでにご病気で入院されていて、2時間が限度と言われていたけど3、4時間くらい話してくださいました。最後に、「私は歌いたい」って石牟礼さんが言ったんだよね。で、僕は「歌いたい?」って尋ねると、同席していた渡辺さんが、「この人は歌ってるんだよ。書くんじゃなくて、全ての文章を歌っている」と。「歌う」と「書く」を分けていないというあり方が僕にはしっくりきた。学問の世界で書かれた文章を見ても、やっぱり歌ってる人とそうじゃない人がいるの。僕は歌う側で書きたいと思っています。試行錯誤状態ですが、それで最初に言われたような書き方になっているのかもしれません。
5.かけあう言葉
斎藤
石牟礼さんの『椿の海の記』もそうですが、昔の日本の人たちの話し言葉にはリズムがあって、だから話し言葉と結びついた文章にもリズムがあるのかなと思うようになりました。
藤原
ラップのように言葉を音楽表現として伝える動きは今もあるけれど、昔は踊りや歌う場面がもっと日常的に、目の前にあったよね。でも、リズムやダンスを解放する場が生活と切り離されてきた。そういう意味で、小説や詩は、人間の本来的な言葉の向き合い方を残しているのかもしれませんね。
関根
最近、民族音楽学のレポートで沖縄の島唄について調べました。島唄は、昔は集落の人たちにとってのコミュニケーションツールとして存在していたけれど、今は技術面が重視されて、コミュニケーションツールとしての役割は弱くなった。文体にあるリズムも、感情を共有するみたいな側面と結びつくのではないかと。
藤原
その話を聞いて思いついたのが、各地にある労作歌ですね。島唄というのは詳しく知らなかったけど、コミュニケーションツールだったっていうのは大きな発見で。例えば農村の労作歌に「稲扱き歌」というのがあります。穂についた米粒を落とす作業を、男性と女性が一緒にするんですね。その作業の動きのリズムに合わせた労作歌が各地にあるんです。歌を歌うことと働くことは、昔は一緒のものでした。農業だけじゃなくて、漁業とか土木工事とかで、労作歌がわたしたちの身体の延長として各地に存在しています。面白いのは「田植え歌」。村の女性達が集団となって一列になって、太鼓の音に合わせて綺麗に植えていく。田植え歌ってエロティックなんだよね。理由は、一つは女性たちが田植えをすることで大地の神様が喜ぶということを伝えている、もう一つは女性たちの服の裾からのぞく艶めかしい足を男たちがからかう。その掛け合いが一つの労作歌をなりたたせているんです。稲扱き歌とかでも、途中で替え歌になって、こっそりと愛の告白をいれて気持ちを探ったりするんだって。歌を聴く人、歌う人に分けるのは近代の発想、わたしたちの暮らしの中ではそうじゃない。聞く人も歌う人も相互乗り入れ状態。歌う人がいたら、反対側には聞きながら踊る人がいて、入れ替わり自由なものだったと思うんですよね。文章の話に戻せば、文章を書くときは、私たちが過去にあった古層とどう対応するかというのが大事だと思います。
関根
音楽でいうと、コロナ禍で、コンサートとかでの演者と観客の応酬が減って、聞く側、観る側と演じる側の分離が進んできたと感じます。
藤原
歌舞伎の「成駒屋!」とか、コンサートの「ブラボー!」とかね。最近は代わりに拍手を勧められるね。声を出したくなる気持ちわかるよね。それが本来の芸術っていうか。僕が講義でやりたいのはそういったコール・アンド・レスポンス。ジャズと一緒で、何か返ってくるというのを意識しながらやってるほうが、やってる本人も聞いてる人達もスリリングでいいんだよね。
6.文学は手紙である
齊藤
『歴史書の愉悦』(ナカニシヤ出版)は様々な研究者による研究書の書評アンソロジーで、昔の研究者との対話だなと思いました。『言葉をもみほぐす』(岩波書店)は民俗学者・赤坂憲雄さんとの往復書簡。すごく素敵で、手紙っていいなぁって。
藤原
手紙っていうのはある意味の切なさを伴いながら交わされるコミュニケーションツール。本来そばにいれば必要ないわけですよね。「あなたが不在だ」っていうことを前提に、ことばでそれを埋める作業が手紙だと思うんですね。『歴史書の愉悦』での書評は、会えない、しかし尊敬する歴史家の書いた本と対話することによって、同時代を生きられなかったギャップを埋めようとする行為だと思います。
ものを書くということは、基本的に誰かとの不可能な対話をイメージせざるを得ません。埋められないギャップを埋めようとするけど埋められない、切ないと感じる。あらゆる文章には手紙的な要素があると思います。
往復書簡をすると、自分が意図していないことが伝わって話が発展することが往々にしてあるんですよね。たとえば赤坂さんとの時、僕は「デフォルト」という言葉を使いました。「あらかじめ決められたひとつの制限」って意味でしか使っていなかったけど、赤坂さんは最初「負債」という意味でとっていらっしゃった。意味がちょっとずれて伝わるとか、会えばすぐ伝わることがずれながら伝わっていくっていう、言語行為のひとつの宿命。そのもどかしさが僕にとってはすごく楽しい。
歴史書を書くということは、過去の歴史を生きた人との対話でもあり、こういう人に読んで欲しいなと思い描く厳しい顔をした人との対話でもある。いちばん厳しい批評家を頭の中に置くんです。「こんなこと書いたらこいつに絶対批判されるわ」と思いながら書くと良い文章になるんですね。特に論文はそう。
齊藤
『分解の哲学』(青土社)ではまさにある人を思い浮かべながら書いたとおっしゃっていましたが。
藤原
『分解の哲学』では捧げている人のことを書いたんですよね。あれは最初から最後まで掃除のおじさんのために書かれている。僕が東京で住んでいた公営住宅をずっと掃除してくれて、子どもたちの面倒を見てくれた、岩手出身の足を引きずった優しいおじさん。そのおじさんを主人公にしたかったし、そのおじさんに読んで欲しくて書いていました。おじさんだったらどう応えるだろうかと思い浮かべながら書いていたということになります。原則、独りよがりの文章っていうのはありえない。少なくとももう一人の自分が生まれてくる。ドストエフスキーの『地下生活者の手記』という短いけどすごく面白い本があって、あれもひきこもりの男の文章に見えるけど徹底的に自分と対話するんだよね。もう一人の自分を作ってひたすら対話する。文章っていうのは独りよがりにはならないようにできていると思います。

インタビューを終えて
.jpg)
関根 美咲
私は言葉を、思考を文字通りに起こすだけの手段として用いてきたように思います。そうしてできた文章には人間味がなく、感情が流れていった跡が見えるようで気に入りませんでした。今回の対談を通して、言葉は人々の感情にあふれたものであるということ、そして人生の根幹となるような可能性を秘めているということに気付きました。私の中で、言葉に対する意識や世界の見え方が変化したと感じています。ありがとうございました。
.jpg)
齊藤 ゆずか
先生とお話をするといつも、何かを求める気持ちがつよくなります。本を読みたい。どこかへ行って、誰かと話したい。それは先生自身がさまざまな「出会い」を、人一倍楽しんでいるからだとわかりました。先生の書いた本はどれも、わたしに語りかけてきました。「なぜひとは死ぬとわかっていて対話をするのか」―― 在りたい自分で生きるため、というのがインタビューを終えたわたしの考えです。お忙しい中、ありがとうございました。
古本の魅力
藤原
本屋が楽しいと思うようになったのは、大学4年生とか大学院生の時です。新刊を売る本屋じゃなくて古本屋に行くのが楽しかった。高価な本が安く売られているのを見つけると楽しかった。古本屋でとにかく安いのを探しましたね。
関根
古本屋には絶版になってしまった本とか、普通の本屋で売っていない古いものがあっていいですよね!
藤原
ほんとそうで、新刊本の問題点は、古くなった本を売らなくなったってことですね。今絶版になっている本の中には名著がたくさんあるんですよ。1930年代40年代に出された本っていうのは、新本で売ってるわけがない。古本屋に行けばその時代に出された古い本とかが出てくるんです。たとえばここ(藤原先生の背中の本棚から一冊取って)、この日本の有名なプロレタリア作家の前田河広一郎の『火田』っていう小説は、いま手に入らないよ。こういう本は著者の印鑑が押してあったり、旧字体で、ルビがいっぱい振ってあったりします。こういうのを読むとワクワクするよね。100年前の人が読んでたものをまた僕が手に取れるという、古本の喜び。当時の人が触ったものを触ることで、時代を語る許可を得たような気持ちになれます。あと、この時代の日本の本だと例えば、今絶対手に入らない、島木健作の『生活の探求』という本。これは、1938年かな、当時ものすごいベストセラーになりました。90年経って、いまは売られてないわけです。島木健作は、元々は小作の運動とかをしていたマルクス主義者だったんだけど、逮捕されて獄中で転向宣言をするんですね。彼自身はしかし、農民をもとに世界を捉えていくっていう志自体は捨てなかった。マルクス主義を捨てて農村の中で生きて行く自分をみつめる小説、これを転向小説といいます。「戦争によって初めて民衆とか農業とか具体的なことを知ることができました」っていうことを赤裸々につづったフィクションで、これが本当に売れたんですね。
関根
この本が入っている箱もいいですね。
藤原
そう、僕たち箱って買わないよね。箱付きの本、引き出してパカって開くような本を、死ぬまでに一冊書きたいなと思っています。でも箱を作る職人さんって減ってるんだって。重要な技術なので、箱作りはそういう職人さんしかできないんだよね。
関根
何十年も前に作られた箱なのにちゃんとエッジが残っていますね。
藤原
やっぱり、製本技術が優れてるんでしょうかね、すごくいいよね。
一次史料を読む
齊藤
『歴史の屑拾い』(講談社)の中で、文章を読むことは、歴史学で一次史料を読むことと近いという印象を受けました。
藤原
すでに本の中に引用されている文章でも、その「ナマのもの」―― 昔の手紙とかね、そういうのを読んでいくのがすごく楽しい。(紙を取り出す)例えばこれはね、『世界の子ども』(平凡社)という、1955年に出版された全集の一次史料です。世界中の子どもに作文を送ってくれと依頼して、良いものだけ日本語に翻訳して載せた本の、一次史料。つまりボツになったものがここにあるわけ。この前、その共同研究をしている研究者からドイツ篇を見てくれと頼まれたんです。ざっと読んでみると、当時の子どもたちがどういったことを考えていたのかがわかります。
関根
子どもが書いたのですか。
藤原
そう、全部子どもだよ。たとえばこれ、「自分は1939年3月10日にダンツィヒで生まれました」って書いてある。1939年3月だから、あと6か月で第二次世界大戦が始まる時期。ダンツィヒというのは大戦の突破口が切られた場所なので、世界政治的に極めて重要な場所なんですね。作文や手紙を一次史料として読むとき、書いてあることの9割ぐらいは平凡なことですよ、お国自慢とかね。でもそれをどう読むか。子どもたちはなぜそれを日本の少女や少年に伝えたかったのか、それを考えることが、一次史料を読むということだと思います。
いま、大学生にすすめたい本
藤原
最近読んだ本で、衝撃的に感動した本をお伝えしたいと思います。元テレビディレクターで、今ノンフィクション作家をされている堀川惠子さんという方がおられて、この前『暁の宇品』(講談社)で大佛次郎賞をとられました。『暁の宇品』も素晴らしいですが、彼女の本で『教誨師』(講談社文庫)も感動しました。教誨師というのは、罪を犯した人に宗教の教えを伝える宗教者です。伝説の教誨師を描いたノンフィクションが、超絶に面白かった。主人公は死刑囚の教誨師なんですよ。あと何年かでどうせ死ぬことが分かっている。だけど彼は話すんですね。ほとんどの死刑囚が、気が小さかったり自身がずっと被害者だったりするんだよね。あるとき感情を抑えきれなくなってやった行為が死刑に至っている。そういう意味でこの死刑囚と自分との差はそれほどないと主人公は気づいていくんです。『教誨師』は死刑問題を考える上でも、国家が罪を犯した人間を国家や国民の名において―― 僕たちも死刑のボタンを押しているわけですから―― 「殺す」とはどういうことかを考える上でも、ぜひ学生さんたちに知ってほしい。かつ、「対話って何だろう、死ぬとわかっているのにその人と対話するってどういうことか」を考えてほしい。なぜかというと、大学は言葉を交わす場所なんだよね。言葉を振りまいてそれが誰かの芽として出てくるのを待つ。あるいは誰かと丁々発止で言葉を交わす。これが大学であって、前と矛盾するけど本を読むことは二の次なんですよ。『教誨師』を読んで、言葉が交わされるということはどういうことかというのを考えてほしいなと思って挙げました。
▲ Profile


