いずみスタッフの 読書日記 175号 P2
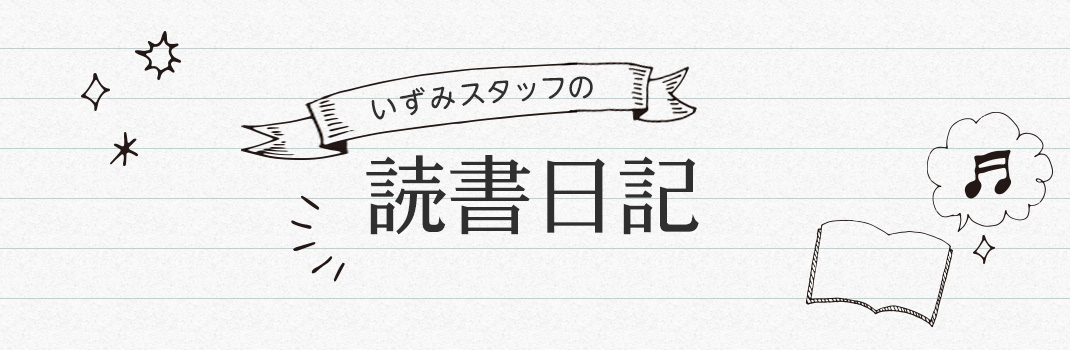
レギュラー企画『読書のいずみ』読者スタッフの読書エッセイ。本と過ごす日々を綴ります。
京都大学大学院M2 徳岡 柚月
3月 ひと月をかけて
 1月から3ヶ月間、コンテンポラリーダンスをしていた。最終的に1時間超の公演を行なうことになっていた。舞台の最初と最後の演目は、中原中也の詩の世界の中で、そしてそこから私たちの生きる世界へじわじわ滲み出しながら、やろうと決まった。
1月から3ヶ月間、コンテンポラリーダンスをしていた。最終的に1時間超の公演を行なうことになっていた。舞台の最初と最後の演目は、中原中也の詩の世界の中で、そしてそこから私たちの生きる世界へじわじわ滲み出しながら、やろうと決まった。開幕は「月夜の浜辺」。ドビュッシーの『月の光』を背景に、私は詩を朗読する。全面黒の舞台、真ん中にブルーシートの海。琥珀色のスポットライトに淡く照らされている。波打ち際を歩きながら、文字を追う。顔を上げる。月夜の晩に、浜辺に落ちていたボタンを拾った彼らがそこにいた。なぜだか捨てるに忍びないそのボタン。この時彼らは何を思いながら「月夜の浜辺」に立っていたのか、その答えを私はこれから先も聞くことはないだろう。
終幕は「ピチベの哲学」。外套を着た男が横たわっている。ゆっくりと足を垂直に持ち上げる。「チヨンザイチヨンザイピーフービー!」奇っ怪に叫び、足を地に叩きつける。目が虚ろだ。泥酔、陶酔? 舞台が暗転する。狂ったように転がる男はある時は道化のような声音で、ある時は夢見る少女の声音で、またある時は虚しい現実を見つめる男の声音で、詩をよむ。あと二行。男の動きが止まる。頭上には黒い傘がぶら下がっている。本を地面に置く。月の住人に頭の糸を引っ張られるかのように、男は静かに立ち上がった。ぼんやりと宙を眺めている。身を開き外套を脱いだ。その瞬間、男は消えた。蒼ざめた月のお姫様の一人舞台、なんにも考えずに白いドレスをひらめかせ舞い踊る。いや、お姫様の周りを、転がっている者たちがいる。溶けて、滲み出すように動く、まるで別世界の、意思を持つ液体。紫の照明が時折彼らを怪しく照らし出す。ふわふわくるくる回っていたお姫様の足取りが急に重くなった。重力の存在を思い出したかのように。足を引きずり座り込んだ。鉛の腕を持ち上げ外套を着る。現れたのはあの男。そろそろと背を地につけ、本を手に取る。息を吸う音が、しんとした世界を震わせた。
「チヨンザイチヨンザイピーフービー
真珠のやうに美しいのさ。」
一切の光が落ちた。
そして次の瞬間、ようやく世界に光と音が一気に帰ってきたのだ。
1ヶ月間を共に過ごした『新編中原中也全集(第1巻)』(中原中也〈大岡昇平ほか=編〉/KADOKAWA)は、もう私の手元にはない。数々の青春の哀しみに寄り添い、優しく照らしてきたあの懐かしい黄土色の本は、これからも永く、たくさんの生に出会い、その魂を震わせていくのだろう。
東京工業大学3年 中川 倫太郎
三月、大学二年の終り
 池袋で一人芝居を上演した。はじめての脚本、はじめての演出、はじめての役者。舞台から観客席を臨む役者のみが目の当たりにできる、500W照明の鋭い光線に貫かれた、はじめての景色。
池袋で一人芝居を上演した。はじめての脚本、はじめての演出、はじめての役者。舞台から観客席を臨む役者のみが目の当たりにできる、500W照明の鋭い光線に貫かれた、はじめての景色。末期患者が自らの死を受け入れるまでの過程を克明に描いた終末期医療の名著『死ぬ瞬間』(E・キューブラー・ロス〈鈴木晶=訳〉/中公文庫)に触発されて作った劇、またどこかでやれたらいいな。
四月、大学三年の始り
 コーヒーにハマった。コーヒーはコーヒーでもエスプレッソが特別いい。平日午後の優雅な空きコマを、僕は大学近くのカフェで過ごすことに決めた。オーナーセレクトの古本が置いてある、ロースタリー併設・ペット同伴の素敵なカフェだ。
コーヒーにハマった。コーヒーはコーヒーでもエスプレッソが特別いい。平日午後の優雅な空きコマを、僕は大学近くのカフェで過ごすことに決めた。オーナーセレクトの古本が置いてある、ロースタリー併設・ペット同伴の素敵なカフェだ。細かく砕かれた深煎りのコーヒー豆をマシンにセットし、轟音と共に高圧で抽出された黒く濃密な液体。本来の香り、酸味、コク、苦味のすべてあざやかなエッセンスが白色陶製のデミタス・カップに注がれて、両手ですっぽりと覆い隠せるほど小さく丸みを帯びたその飲み物は端的で完璧な芸術作品のようだった。
窓から差し込む傾きかけの太陽の下、エスプレッソ片手に短編集『木犀の日』(古井由吉/講談社文芸文庫)を読む。良質で個性的な作品を数多く揃えた(そして文庫本らしからぬ値段で有名な)講談社文芸文庫が僕は好きだ。このレーベルなら信用できる。どの本も総じて面白い。だから作者の名前に縛られずに本を選べる。偶然の巡り合わせがそこにはある。事実『木犀の日』を手に取るまで、僕は古井由吉の名前をぜんぜん知らなかった。
書き出しを読むやいなや「この作家は僕の人生を変えるな」と、そう直感した。味わい深いフルボディの文章はさながらエスプレッソ、硬さの中にやわらかさを秘めた文体、同じ日本語を操っているとは到底思えない。デザートを頼もうか迷ったけれど、この本を読んでいるうちにそんなことすっかり忘れてしまった。
右隣の席では栗毛のトイ・プードルを連れた奥様がアイスティーを飲んでいた。開け放たれたカフェの扉から不意に春風が吹き込む、と、突然、隣の犬が僕の太ももに飛び乗ってきた。犬は吠えもせず、しばらくそのまま膝の上に留まっていた。「ごめんなさい、この子ホント人懐っこくて」そう言って奥様が愛犬を手元にたぐり寄せたあとも、あたたかなかたまりがまだ膝の上で生きているような気がした。
前のページへ

 千葉大学4年生
千葉大学4年生 名古屋大学5年生
名古屋大学5年生 京都大学大学院M2
京都大学大学院M2 東京工業大学3年
東京工業大学3年
